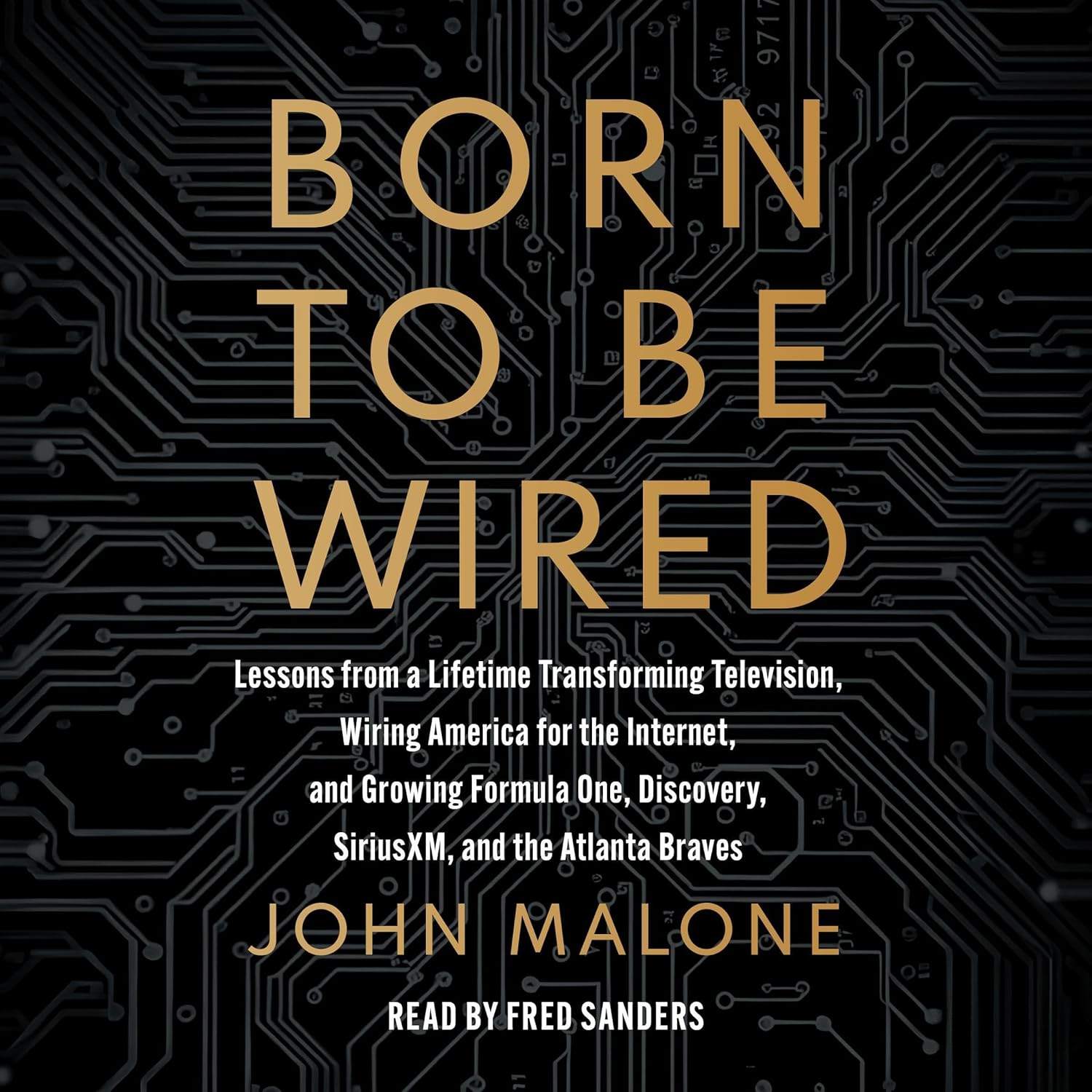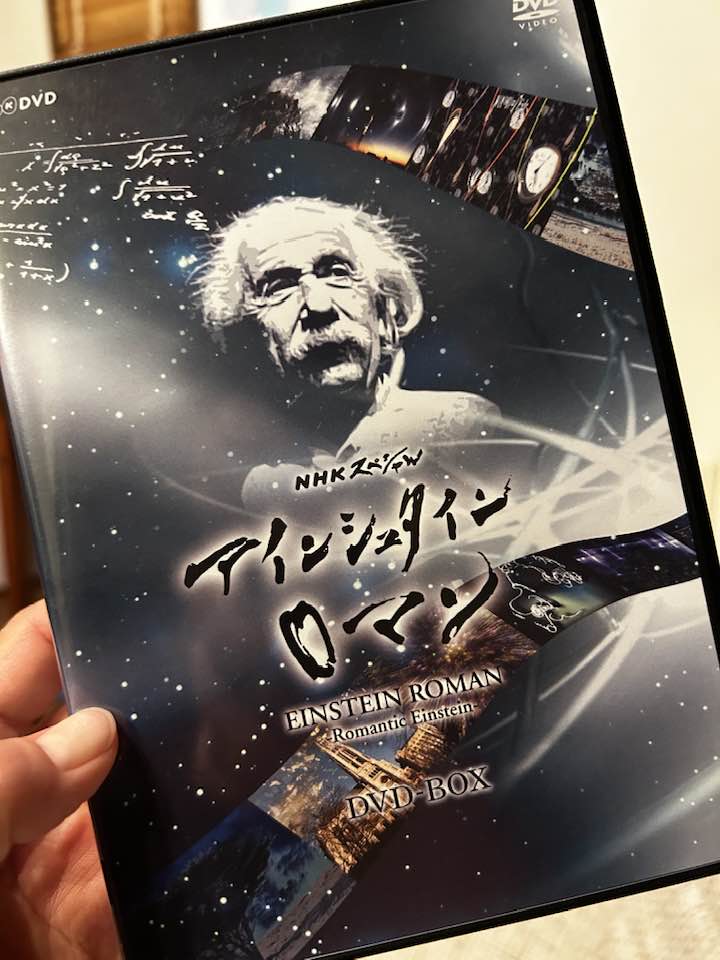【N#208】栄養と健康寿命──内臓脂肪を増やさないための対策
Table of Contents
はじめに
こんにちは!東京・渋谷でロルフィング・セッションを提供し、脳科学を活用して健康寿命を延ばす方法を発信中の大塚英文です。

今回は、健康寿命を支える4つの柱の中から「栄養(Nutrition)」について取り上げたい。参考にするのは、医師であり健康長寿の専門家でもあるPeter Attiaの著書『Outlive: The Science and Art of Longevity』、そして私自身が学んできた知見である。
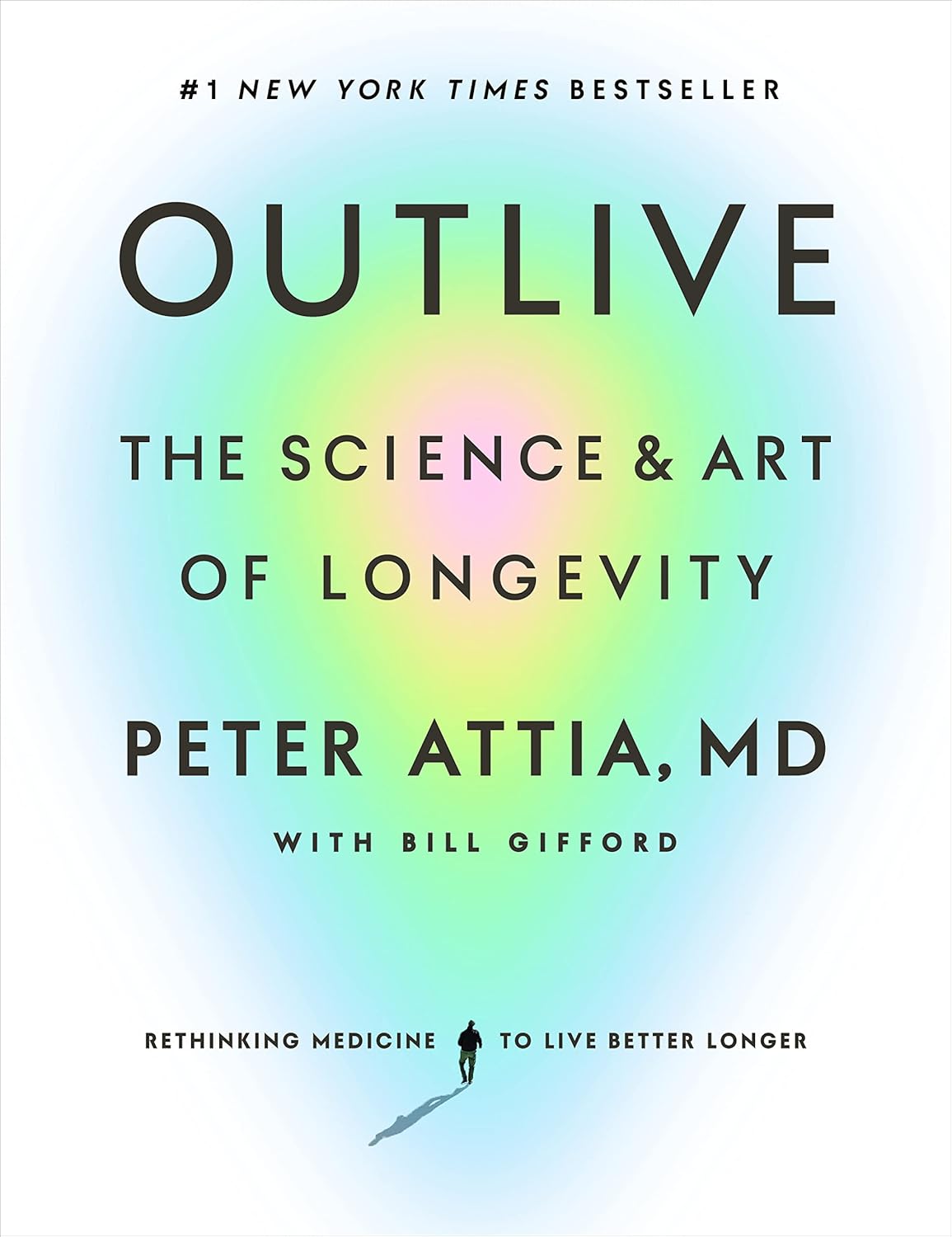
炭水化物と体脂肪の深い関係
炭水化物は、ご飯やパン、麺類、いも類、果物などに多く含まれている。摂取した炭水化物はまずグリコーゲンとして筋肉や肝臓に一時的に蓄えられる。しかし、グリコーゲンは水と一緒に保管されるため容量に限界があり、約1,600kcal分しか保持できない。
そこで余った炭水化物は脂肪へと変換され、体内に蓄えられる。脂肪には以下の2種類がある。
- 皮下脂肪:皮膚の下に蓄積し、ある程度までは比較的「安全」なエネルギー貯蔵庫。
- 内臓脂肪:肝臓や筋肉など臓器の周囲に蓄積し、炎症性サイトカインを分泌。生活習慣病の温床となる。
現代は過食と運動不足により、皮下脂肪の容量を超えた分が内臓脂肪として蓄積しやすい環境にある。
「内臓脂肪」とインスリン抵抗性、脂肪肝、糖尿病との深い関係
皮下脂肪という形で脂肪が保管されている場合は、安全。そうはいうものの、現代は過食の時代。皮下脂肪のキャパを超える形で脂肪が体内に入ってくる。その場合は、筋肉、肝臓を含め、様々な内臓に脂肪が蓄えられる「内臓脂肪」という形になる。
この内臓脂肪は大きな問題になっており、慢性炎症を引き起こす物質(炎症性サイトカイン)を分泌し、様々な疾患の温床につながる。
Peter AttiaのThe Drive(ポッドキャスト)でGerald Shulman博士との対談で初めて知ったことだが、人間は、筋肉から内臓脂肪が蓄積するところからスタート。内臓脂肪が筋肉に蓄積すると、血糖値を下げるホルモンである「インスリン」の効果が発揮できにくくなる(インスリン抵抗性と呼ぶ)。
「インスリン」の効果を発揮するため、更にこのホルモンの分泌量を増やすらしいのだ。
何と、内臓脂肪を増やすホルモンとして一番最強なのがインスリン。次いで、ステロイドホルモンとして知られてる「コルチゾール」、女性ホルモンの「エストロゲン」、男性ホルモンのテストステロン等がある。
余談だが、アトピー性皮膚炎に使われている外用ステロイドは、コルチゾールに似た作用を示すので、ステロイドを長年使っていると、体内に「内臓脂肪」を増やしてしまう。
インスリンの分泌量が増えると、筋肉の内臓脂肪が増加に伴い、肝臓の内臓脂肪が増えてくる。肝臓内の内臓脂肪が3割程度になると脂肪肝と呼ばれ、肝障害、肝炎へと進む。
驚くべきことに、近年アルコールを飲んでいないのに、肝障害(非アルコール性肝障害(NAFLD)と呼ぶ)や肝炎(非アルコール性肝炎(NASH))が報告されていることだ。
インスリン抵抗性(インスリンの分泌量の増加)、NAFLD/NASHは、糖尿病へと進み、心疾患、がん、アルツハイマーへのリスクが高まっていくのだ。
内臓脂肪が引き起こす問題
まとめると、内臓脂肪は単なる「体型の問題」ではなく、次のような疾患リスクに直結する。
- インスリン抵抗性
内臓脂肪が筋肉に蓄積すると、インスリンが効きにくくなり、さらに分泌量が増えるという悪循環に陥る。インスリンそのものが「脂肪を増やす最強のホルモン」でもある。 - 脂肪肝(NAFLD/NASH)
肝臓に脂肪が3割ほど蓄積すると脂肪肝となり、炎症や肝障害へと進む。アルコールを飲まない人でも発症する「非アルコール性脂肪性肝疾患(NAFLD)」や「非アルコール性脂肪性肝炎(NASH)」が増加している。 - 慢性炎症と疾患リスク
内臓脂肪は炎症性サイトカインを放出し、心疾患、糖尿病、がん、アルツハイマー病などのリスクを高める。
このように、皮下脂肪よりも内臓脂肪が危険なのは、全身の代謝と炎症に直接悪影響を及ぼすからである。
内臓脂肪と血糖値の関係
炭水化物を摂ると血糖値が上昇し、それを下げるためにインスリンが分泌される。だが血糖値が大きく変動する食生活を続けると、余分なブドウ糖は中性脂肪に変換され、まず内臓脂肪として蓄積する。
つまり、
血糖値の乱高下 → インスリン分泌増加 → 内臓脂肪蓄積 → インスリン抵抗性 → 生活習慣病リスク
という流れで、悪循環が進んでいくのだ。
だからこそ、「血糖値を測定する」ことは不可欠である。
内臓脂肪と血糖値の測定法
- 体組成計(BIA法)
自宅でも手軽に測れる。電気抵抗から体組成を推定する仕組みで、内臓脂肪レベルも表示される。 - 医療機関でのDEXA測定
骨密度・筋肉量・脂肪量を正確に把握可能。 - エコー検査
肝臓の脂肪量をチェックでき、脂肪肝の有無も診断される。 - 持続血糖測定(CGM)
FreeStyle LibreやDexcomを用いてリアルタイムで血糖値の変動を把握できる。
個人差の大きい血糖値の変化を「見える化」することで、内臓脂肪リスクを未然に防ぐ食習慣を作ることができる。
血糖値測定が決定的に重要な理由
一人ひとり、同じ食品を食べても血糖値の反応は異なる。だからこそ、血糖値測定は「感覚に頼らない栄養管理」の切り札となる。

- 効果:どの食品が血糖値を急上昇させるかを把握でき、内臓脂肪の蓄積を予防できる。
- 予防:高血糖スパイクを抑えることで、中性脂肪の増加・脂肪肝・動脈硬化を回避できる。
- 習慣化:測定結果を日々フィードバックすることで、自然と食事の選択が変わる。
推奨される方法
- FreeStyle Libre 2(リブレ):スキャン式。
- Dexcom G7:リアルタイムにスマホへ送信。精度が高く、Attiaも推奨。
特に重要なのは、最低90日間の装着である。
理由は以下の通り:
- 食習慣は日ごとに変わるため、短期測定では偏りが出る。
- 季節や生活リズムによる変化も含めて把握できる。
- 3か月間続けることで「食べたらこうなる」という学習が進み、行動変容が起きる。
つまり90日間の装着は、単なるデータ収集ではなく、食習慣を身体に定着させるプロセスそのものである。
食事の実践ポイント
Attiaや研究者たちが推奨する実践法は以下の通り。
- 高タンパク質:筋肉維持のために不可欠(体重1kgあたり1.6〜2.2g)。
- 低精製炭水化物:白米や白パンなど血糖値急上昇を避ける。
- 食物繊維を活用:腸内環境を整え、血糖値上昇を緩やかにする。
- 食べる順番を工夫:野菜・タンパク質を先に、炭水化物を後に。
まとめ──血糖値と内臓脂肪を制御する
Peter Attiaの『Outlive』が伝えるのは、血糖値をコントロールし、内臓脂肪を抑えることが健康寿命を守る最大のポイントだということである。
- 炭水化物の摂り方次第で、脂肪の行き先は変わる
- 血糖値が上がりすぎると、内臓脂肪が蓄積し、生活習慣病の温床になる
- 測定(血糖値・体組成)→改善→再測定のサイクルが不可欠
“Don’t just live longer, live better.”
──ただ長く生きるのではなく、より良く生きるために。