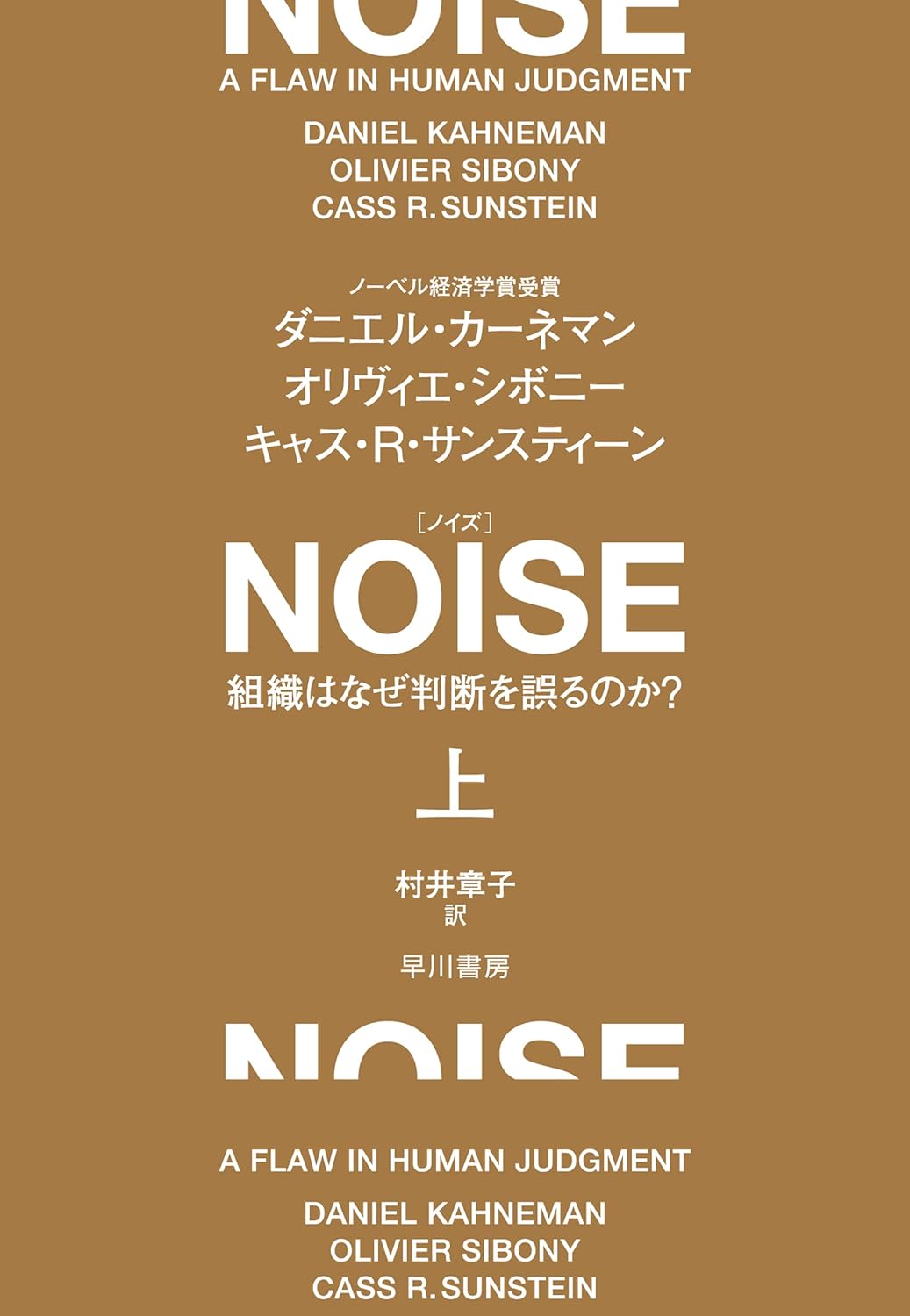【B#243】私の読書の方法──視覚・聴覚・編集の三層構造で世界を読む
Table of Contents
はじめに
こんにちは。渋谷でロルフィング・セッションや脳科学をベースにした講座を提供している大塚英文です。
書物とは?──記憶と想像力を拡大延長されるもの
年間テーマを決めて読書をする意味
私は年間でおよそ200冊近い本を読む。

それも量を積み上げるためではなく、毎年テーマを決めて深掘りし、複数の文脈から立体的に理解するように心がけている。例えば、2025年の年間テーマは100周年を迎えた「量子力学」、そして2023〜2025年の3年テーマは「脳科学」である(詳細は「本をどう選ぶか?〜毎年「テーマ」を決める〜選書の基準」参照)。
こうした読書形式を1995年から継続しており、私にとって読書は単なる趣味ではなく、知的生産の土台であり、自分の思考を作り直し続けるプロセスそのものだ。
メディアは身体の延長である──書物の位置づけ
メディア論の大家マーシャル・マクルーハンは、「人間が開発した技術のすべては、人間の身体機能を拡張するメディアである」と述べた。メディアの発達によって人間の知覚の方法が変わっていくという。
- 時計は体内時計の拡張
- 書かれた文字は目の延長
- ラジオは耳
- 言葉は口
- 万年筆やキーボードは手
- 交通機関は足
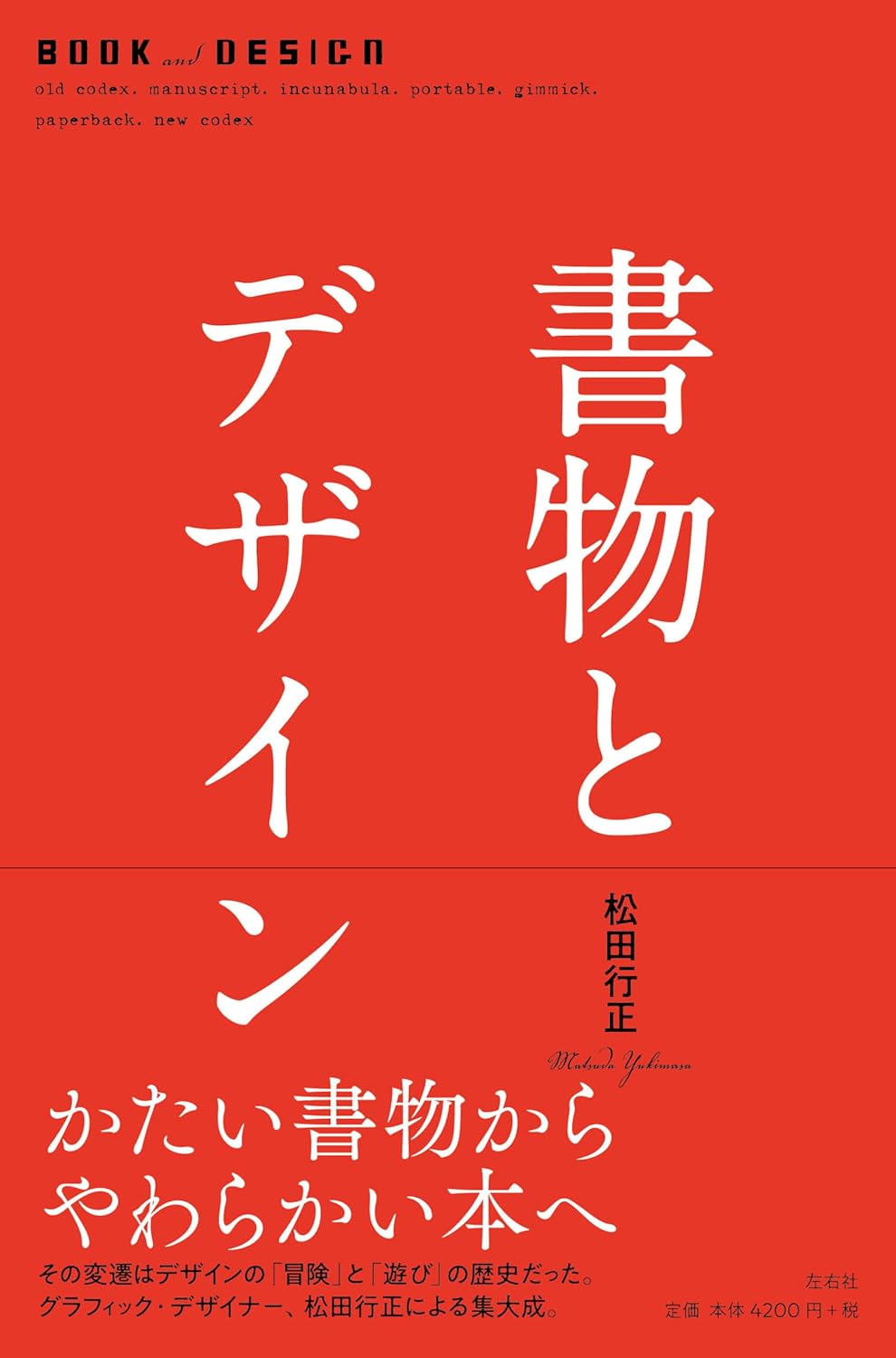
松田行正さんの「書物とデザイン:かたい書物からやわらかい本へ」では、ホルヘ・ルイス・ボルヘスが書物について次のように語っている。
書物は人間が創り出したさまざまな道具類の中で最も驚嘆すべきものです。他の道具はいずれも人間の体の一部が拡張されたものでしかありません。たとえば、望遠鏡や顕微鏡は人間の眼が拡大されたものですし、電話は声が、鋤や剣は腕が延長されたものです。しかし、書物は記憶と想像力が拡大延長されたものだと言う意味で、性格を異にしています(『ボルヘス「語るボルヘス」より』)
この視点から見ると、本をどう読むかは、その人の文化背景、感覚の使い方、人生の問いによって大きく変わる。テーマを決める読書は、新しい視点を手に入れるための手段となりうる。
本のメディアは進化する──紙・電子・音声・生成AI
私の読書習慣も時代とともに変化してきた。紙媒体から始まり、インターネットやスマートフォンの登場によって電子書籍(Kindle、Kinoppy)やオーディオブック(Audible)を使うようになった。
さらに現在では、生成AI(ChatGPT、Gemini)で本の要約を素早く得られるようになり、読書手段は大きく広がった。
和書・洋書・AI(ChatGPT)という三つの入り口を使い分けることで、読書が“インプット”を超え、“編集と思索のプロセス”へと進化している。
ここでは、私がどのように読書と向き合い、和書と洋書をどのように使い分けているのか、その仮説をまとめたい。
日本語の読書は「視覚」──漢字文化が育んだ読み方
日本語の本は、紙や電子本で読む
和書は紙と電子で「見る」ように読む
和書は、基本的に紙か電子書籍で読む。オーディオブックではなく視覚的に読むのは、日本語が「視覚言語」であるという特性が大きい。気に入った本に出会えば紙の質感を求めて買い直す。
また本が増え続けるため、定期的に裁断してスキャンし、PDF化してOCR検索できるようにしている。電子化した書籍は現在約2,500冊ほどになる(詳細は「春と荷物の整理〜波動スピーカーの設置+本の断捨離・電子化を進行中」参照)。
日本語は視覚言語である
日本語は、漢字という表意文字と、ひらがな・カタカナという表音文字の混合体である。
- 漢字:形=意味へ直結する視覚処理
- 仮名:音→文字という音韻処理
漢字の比率が高い文章は「まず形を見る」ことで理解が始まる。視覚的レイアウトや用紙の質感は、私にとって思考の質を高めてくれる。
私にとって和書とは、
「視覚を通じて作者と対話し、新しい知を獲得していく行為」
である。
英語の読書は「聴覚」──音の連続としての言語構造
洋書はAudibleで“耳から理解する”
洋書はほぼAudibleで聴き、内容が良ければChatGPTに要約させ、さらに聴き直す。興味が深まればKindle版も購入し、音声と文字の両方で再読する。
英語は聴覚言語である
アルファベットは音の連続を記号化した「表音文字」であり、理解の鍵は音にある。
- 強弱
- 抑揚
- リズム
これらは英語の理解に不可欠であり、「音→意味」のルートが極めて強い。英語圏でオーディオブック文化が発達したのも自然な流れだ。
私にとって洋書とは、
「耳で世界観を丸ごと受け取る行為」
である。
Audible → ChatGPT 要約 → Audible再読 → Kindle という多層的なループは、内容を身体化するための方法でもある。
日本語と英語の脳内処理の違い──『プルーストとイカ』が示したこと
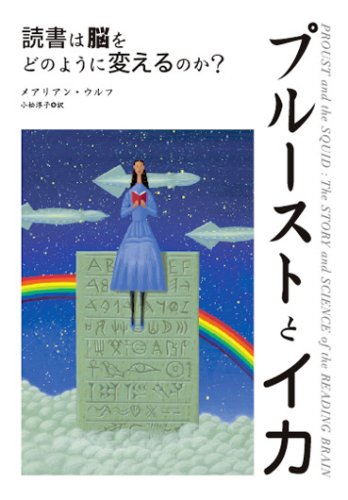
神経科学者メアリアン・ウルフは名著『プルーストとイカ』で、読みとは生得的能力ではなく、文化に合わせて脳が再配線した回路であると述べる。文字体系の違いは脳の使い方に直結する。
英語を読むときに働く脳
英語は最小単位の音「音素」を文字で表す音素文字。このため読解は「綴り→音→意味」という流れで進む。
主に働く領域は:
- 左側頭葉(意味理解)
- 左前頭葉(音韻処理)
- 左後頭側頭部(VWFA:視覚単語形態領域)
いわゆる phonological route(音韻ルート) が中心となる。
日本語を読むときに働く脳
日本語は世界的にも珍しい、表音文字(仮名)と表意文字(漢字)の併用言語。
- 仮名:英語と同じ音韻ルート
- 漢字:形態→意味という視覚ルート
そのため、
左半球だけでなく右半球(視覚・空間処理)も強く働く。
ウルフは「中国語や日本語の読者は、アルファベット使用者より右半球を多く使う」と述べている。
認知科学・脳神経科学の観点からも、日本語は英語より「視覚言語的」だといえる。
ChatGPT は「第三の読書」──編集と思索のプロセス
視覚(日本語)、聴覚(英語)に加え、ChatGPT は「編集と思索の道具」として機能する。
ChatGPT に要約させることで:
- 主要論点が整理され
- 論理構造が可視化され
- 著者の思想の骨格が浮かび上がる
- 自分の理解を検証できる
ChatGPT はまさに
“思考の外部化装置”
である。
ボルヘスが言う「書物は記憶と想像力の拡大延長である」を引き継げば、ChatGPT は「思考そのものを外在化するための装置」と位置づけられるだろう。
RANGE が示した未来──ジェネラリストの時代に読書が必須になる理由
David Epstein の『RANGE(レンジ):知識の「幅」が最強の武器になる』では、
「専門特化よりも、幅広い経験と多様な知識の組み合わせが未来を切り拓く」
と語っている。
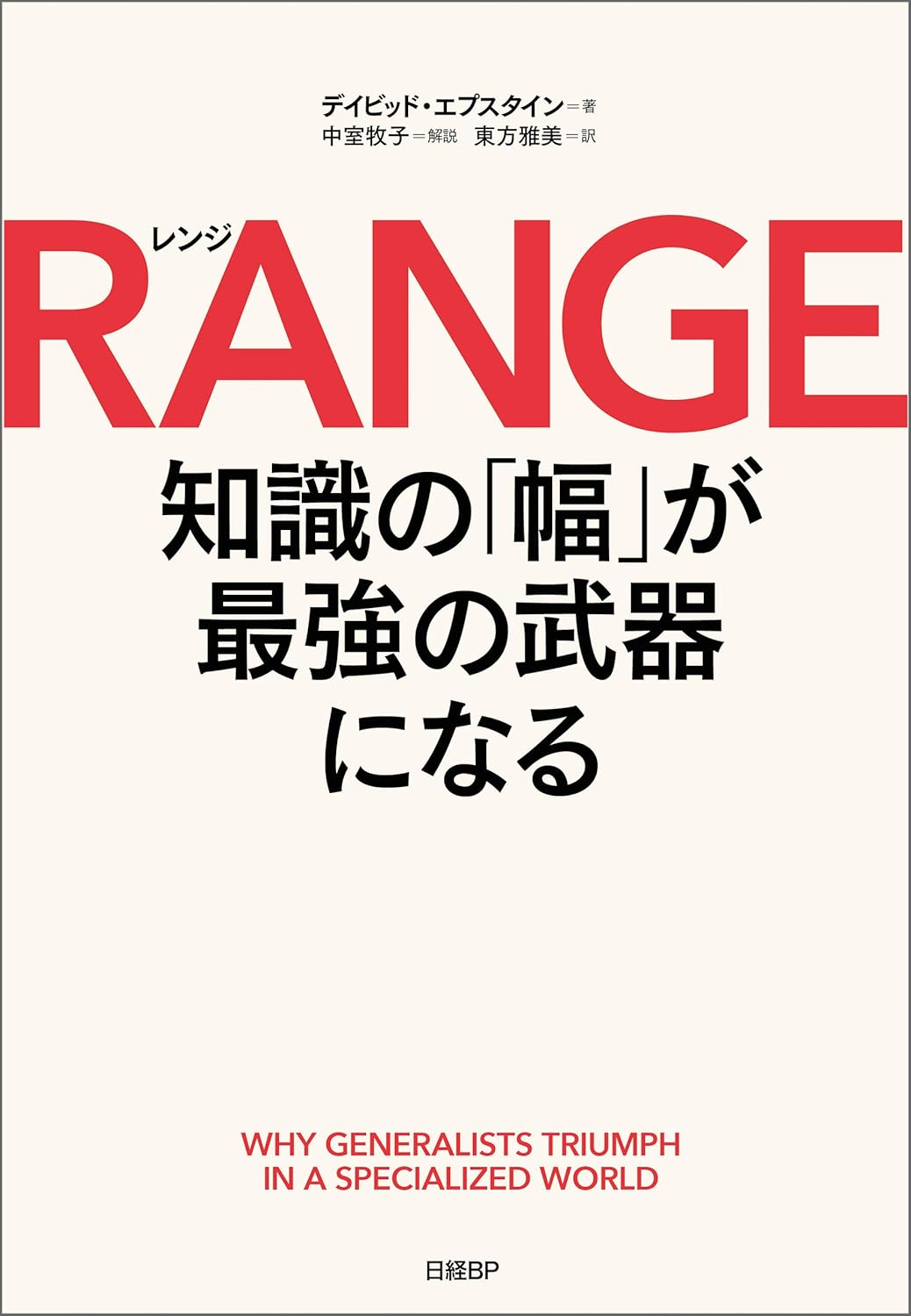
予測不能な時代に価値を持つのは:
- 多分野横断の知
- 異なる文脈を結びつける力
- 異質な概念を組み合わせる創造性
私は年間200冊の読書を通して、
“知の幅 × 深さ”のレンジ
を育てていると感じる。
読書は専門家になるためだけの手段ではなく、知と知を架橋し、新しい視点を創造するための基盤なのだ。
まとめ──読書は感覚の総動員であり、未来を開く技術である
- 日本語は視覚(見る文化)
- 英語は聴覚(聞く文化)
- ChatGPT は編集(思考の外在化)
この三つを使い分けることで、読書は単なる情報収集ではなく、知的生産の方法へと進化する。
ボルヘスが述べたように、本は記憶と想像力を拡張するメディアである。そして現代では、AI がその延長線上に位置づけられ、
読書 → 編集 → 再構造化 → 発信
が誰でも可能になった。
私にとって読書とは、世界の複雑さを読み解き、自分の思考を鍛え、未知に備えるための方法論であり、視覚・聴覚・編集という三層構造の読書は、これからも私の学びを支えていくだろう。
少しでもこの投稿が役立つことを願っています。