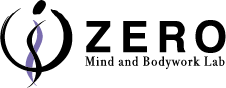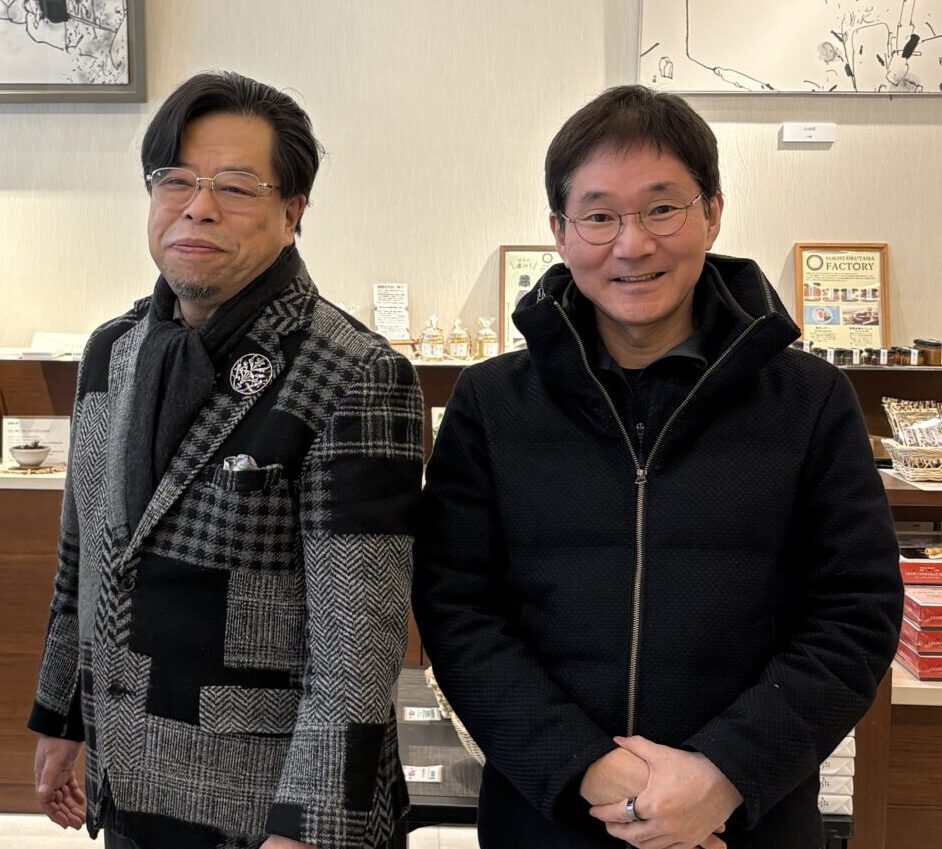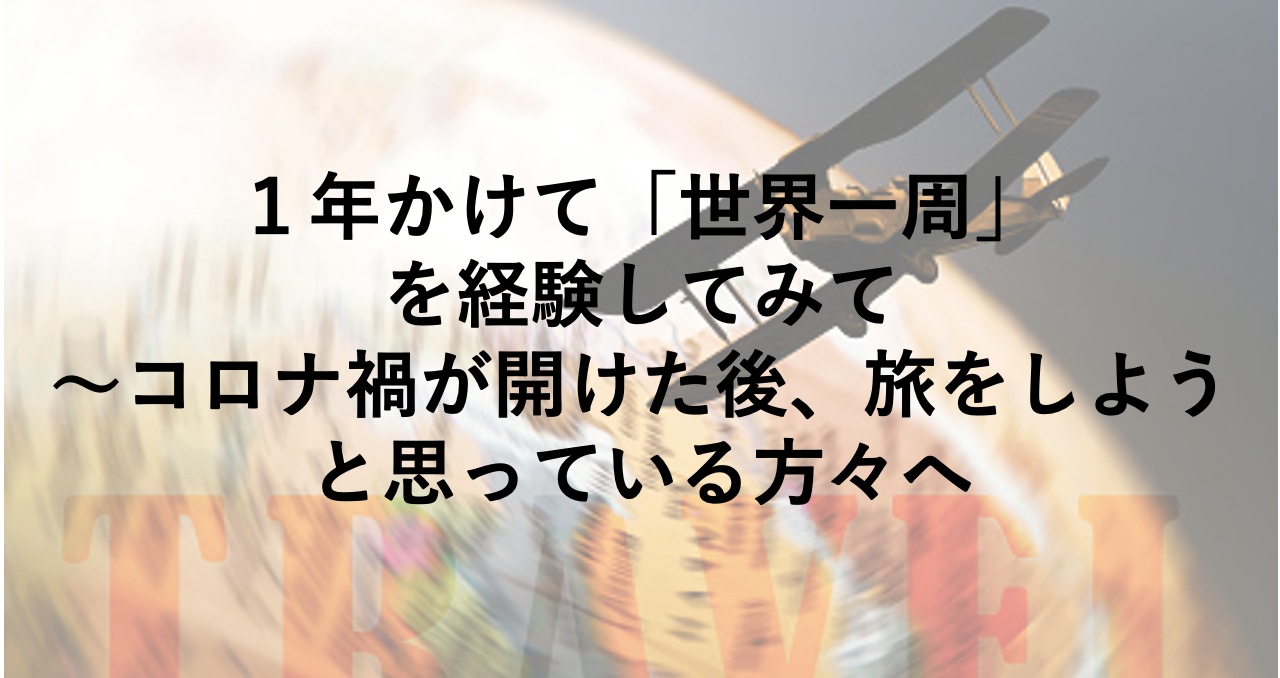【B#253】伊藤憲二『励起』を読んで④──仁科芳雄先生は、日本の物理学界に何をもたらしたか?
Table of Contents
はじめに
こんにちは!東京・渋谷でロルフィング・セッションと脳科学の基づく講座・タロットカードを使ったカウンセリングを提供している大塚英文です。
伊藤憲二さんの「励起──仁科芳雄と日本の現代物理学」は、仁科芳雄先生の伝記であると同時に、20世紀物理学がどのような「知の生態系」のもとで生まれ、維持され、次世代へと受け渡されていったのかを描いた、きわめて射程の長い科学史の書と言える。

この本を読み終えて最も強く感じたのは、日本の量子力学の歩みは、「資金も資源もない中で、いかにして知の生態系を守り、人材を育て続けるか」という、長く静かな戦いだったという点である。
仁科芳雄先生という「越境者」
仁科芳雄先生は、20世紀初頭の物理学において、きわめて稀な立場にあった人物である。
彼は、
- 英国で
- 個人の思考力を極限まで問う文化を見て
- ドイツで
- 研究大学・研究所モデル
- ゼミナールと実験室教育
- 研究を職業として成立させる制度
を体験し
- コペンハーゲンで
- ボーアの研究所における
- 対話・遊び・未完成性を許容する文化
を内側から経験した
数少ない物理学者だった。つまり仁科先生は、三つの異なる「研究組織モデル」すべてを身体化し、身につけた存在だった。
日本に欠けていたもの
一方、仁科が帰国した当時の日本には、近代的な大学制度や研究所は存在していたものの、
- 研究を長期的に支える制度
- 若手が自由に議論できる場
- 失敗や未完成を許容する空気
は、まだ十分に育っていなかった。
日本の学術制度は、
- 国家目的への従属
- 短期的成果への期待
- 序列と権威の強さ
が前面に出やすく、研究はしばしば「正解を早く出す仕事」として理解されていた。これは、量子力学のような直感に反し、回り道を必要とする学問とは、相性が悪い。
理化学研究所という「実験」
仁科が活動の拠点としたのが、理化学研究所である。理研は、ドイツの研究所モデル(とくにカイザー・ヴィルヘルム協会)を参考に設立された、日本では例外的な存在だった。
仁科が理研で目指したのは、
- 大学の講義負担から自由で
- 長期的研究に集中でき
- 若い研究者が集まり
- 世界と直接つながる
研究そのもののための空間である。
仁科研究室の雰囲気
伊藤憲二『励起』が描く仁科研究室の特徴は、単なる組織設計ではない。
そこにあったのは、
- 立場を越えた議論
- 海外研究者との活発な交流
- 若手の自由な発言
- 失敗を咎めない空気
である。
仁科は、自らがコペンハーゲンで体験した「研究所の雰囲気」を、日本で再現しようとしていた。
それは、
- 英国のような過度な緊張でもなく
- ドイツのような硬い制度でもなく
研究を楽しむことを許す空気だった。
日本版「コペンハーゲン」をつくろうとした
仁科研究室では、
- 雑談の延長で議論が始まり
- 結論が出ないまま話が終わり
- それでも思考が前に進む
ということが、日常的に起こっていた。
これは、「効率」や「成果」から見れば、無駄に見えるかもしれない。しかし仁科は、科学研究とは本来そういうものだという確信を持っていた。ここには、明確にコペンハーゲン精神が息づいている。
なぜ、それは難しかったのか
伊藤憲二さんの『励起』が、決して楽観的に描いていないのは、この試みの困難さである。
日本では、
- 国家総動員体制
- 戦時研究への動員
- 戦後の急速な再編
によって、研究は再び目的志向・成果志向へと強く引き戻されていく。
仁科がつくろうとした
雰囲気によって励起される研究文化
は、制度として完全に定着する前に、歴史の大きな力に飲み込まれていった。
日本の量子力学は「貧困の中の創造」だった
伊藤憲二『励起』の中で、とりわけ読み応えがあるのが、仁科芳雄先生と原子爆弾開発計画(いわゆる「二号研究」)との関わりを、冷静かつ具体的に描いている部分である。
ここで明らかになるのは、日本の量子力学が置かれていた、極端な制約条件だ。
- 資金は乏しく
- ウラン資源も枯渇し
- 工業基盤も未成熟
- マンハッタン計画とは比較にならない規模
にもかかわらず、研究は「国家を救う可能性」にすがる形で進められていった。
仁科芳雄と軍――悲劇的な選択
本書は、仁科先生と軍との関係についても、英雄化も断罪もせず、きわめて慎重に描いている。
仁科先生は
- 日本を救いたい
- 科学者としてできることをしたい
という思いから、結果的に「二号研究」へと深く関わっていった。
だが同時に、マンハッタン計画のような国家総力戦とはほど遠い条件下で、このプロジェクトが進められていたことも、本書は丁寧に示している。
ここには、
科学者が国家と関わることの、避けがたい曖昧さと悲劇性
がある。
「二号研究」に見る現場の絆
工学的な意味で言えば、
二号研究は失敗に終わった。
- サイクロトロンの故障
- 資源の枯渇
- 実験の中断
しかし、伊藤憲二が強調するのは、
それでも失われなかったものである。
それは、
- 仁科芳雄
- 朝永振一郎
- 湯川秀樹
といった若き才能たちが、
互いを尊重し、刺激を与え合い、
知的な関係性のネットワークを維持し続けたという事実だ。
絶望的な状況下にあっても、
- 議論は続き
- 思考は止まらず
- 関係性は断たれなかった
ここに、日本の量子力学の本当の核心がある。
それでも残ったもの
それでも、仁科先生の試みは無駄ではなかった。
- 彼のもとから育った研究者たち
- 国際感覚をもった物理学者
- 日本における理論物理・原子核物理の基盤
これらは確実に、日本の科学に影響を残している。
戦時中、日本は「成果」という意味では、何も残せなかったかもしれない。
しかし、仁科が理研で耕し、守り続けた土壌から、戦後まもなく
- 湯川秀樹
- 朝永振一郎
という二人のノーベル賞学者が輩出される。
重要なのは、目に見える制度よりも、見えにくい「態度」である。
- 問いを急がない
- 分からなさに耐える
- 議論を楽しむ
この姿勢こそが、仁科先生が最も伝えたかったものだろう。
『励起』から見た仁科芳雄の意味
伊藤憲二『励起』というタイトルは、ここで再び重みを持つ。
仁科が日本でやろうとしたのは、
- 新しい理論を持ち込むこと
ではなく、 - 研究が自然に励起され続ける状態をつくること
だった。
それは、
- 英国の「緊張」
- ドイツの「制度」
- デンマークの「遊びと対話」
を統合した、きわめて高度で、同時に壊れやすい試みだった。
まとめ──この問いは、今も続いている
伊藤憲二『励起』を通して浮かび上がる仁科芳雄の姿は、過去の偉人ではない。
それは、日本において、研究が励起され続ける条件とは何か
という問いそのものだ。
この問いは、現代の大学、研究所、企業、教育の現場においても、なお未解決のままである。仁科先生が残した最大の遺産は、答えではなく、問いを残したことだったのかもしれない。