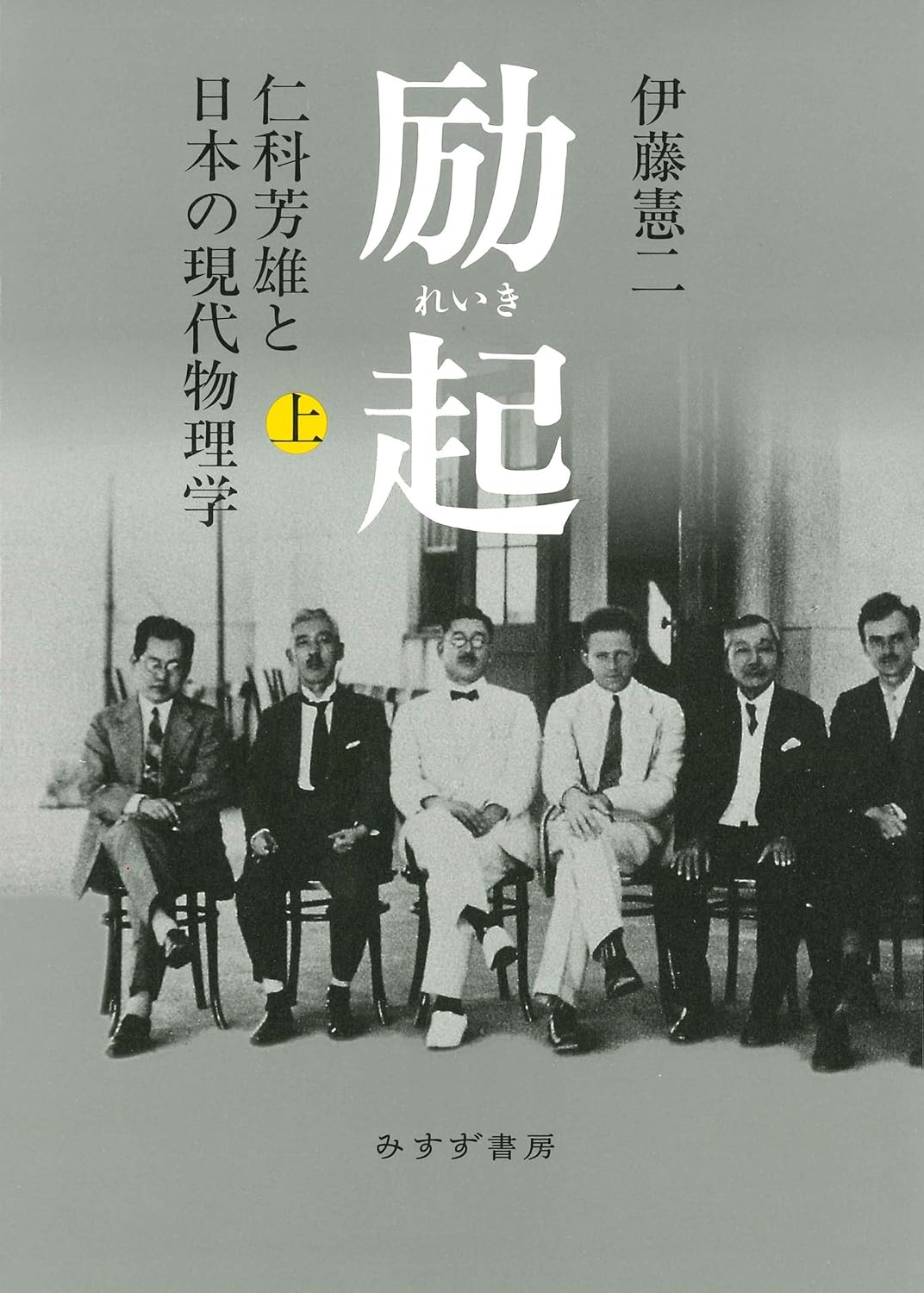【B#236】不測の事態に心を折らない! 困難な時代にこそ必要な 「自分の時計」 で生きる極意と、真の強さの源泉
Table of Contents
はじめに
こんにちは。渋谷でロルフィング・セッションと脳科学をベースにした講座を提供している大塚英文です。
人生の道のりには、時に立ち尽くしてしまうほどの困難や試練が訪れることがある。理不尽や絶望を感じたとき、私たちはどこに心の拠り所を見出し、どのように立ち向かえば良いのか?
今回のブログでは、多くのビジネスパーソンに影響を与え、私も過去に愛読した城山三郎さんの思想を軸に、
城山三郎著『打たれ強く生きる』(新潮文庫)
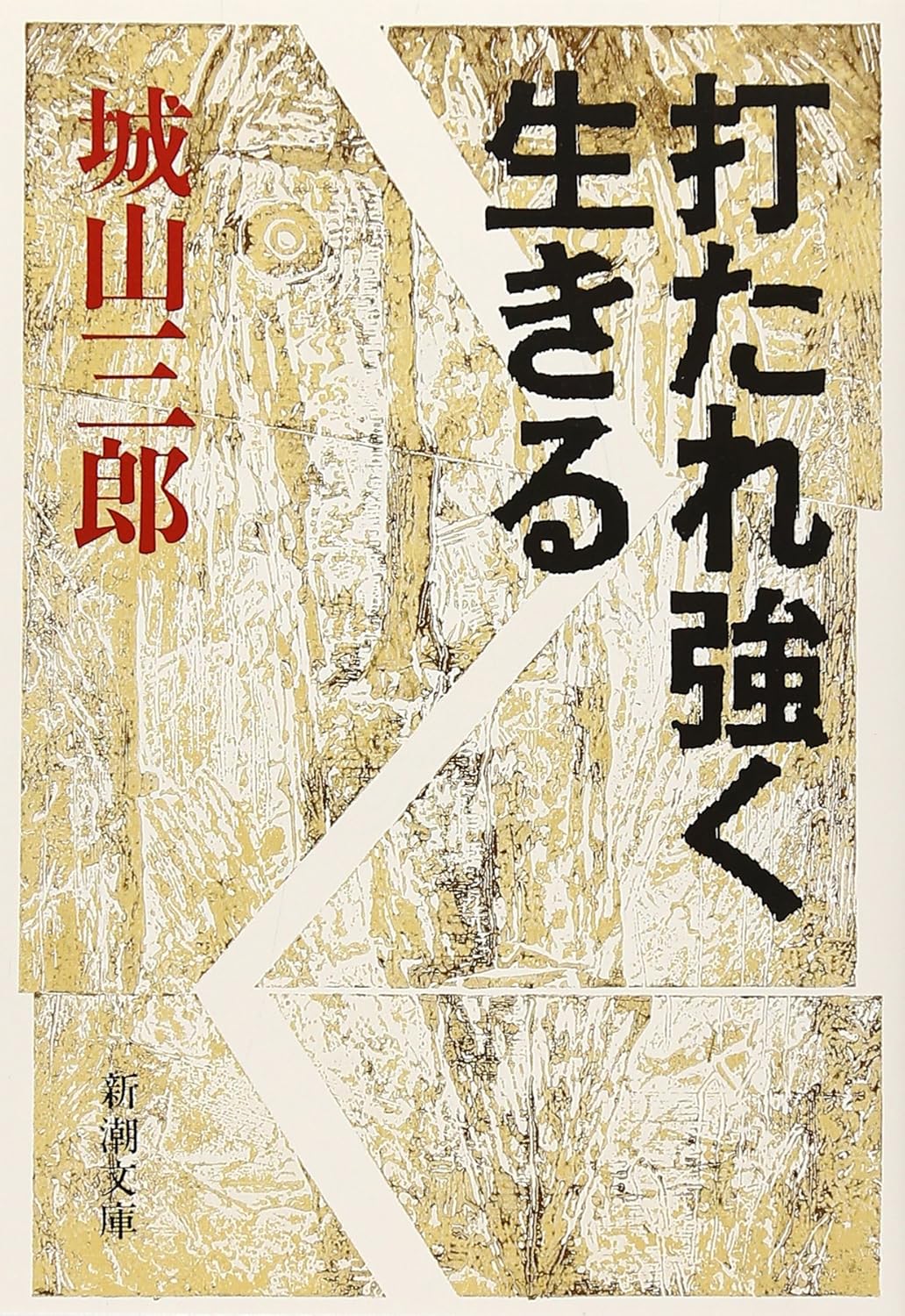
対談集『サラリーマンの一生:管理社会を生き通す』(伊藤肇氏との対談)
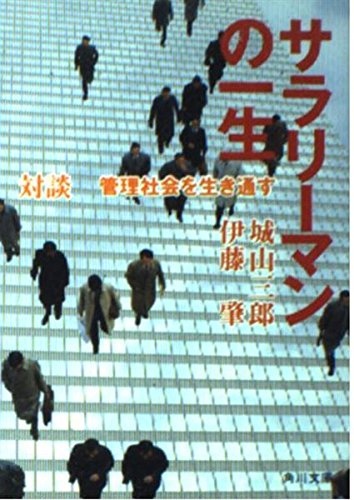
『現代の覚者たち』(致知出版社)
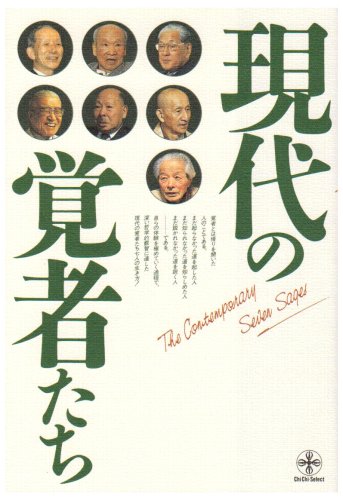
の3冊から、逆境を突破し「打たれ強く生きる」ために、どう乗り越えていくのか?その知恵についてまとめていきたい。
逆境に対する心の構え:達観と自己の確立
逆境に立つと、人は不安や焦燥感から、状況をコントロールしようと必死にもがいてしまいがち。しかし、城山さんの教えは、まず「受け入れる」こと、そして無駄なエネルギーを消費しない心の構えを教えてくれる。
企画院事件を経験した経済評論家の境地
城山さんの『打たれ強く生きる』の中で、特に重みを持つのが、経済評論家であり、後に産経新聞社社長などを務めた稲葉秀三氏(1907-1996)の言葉だ。
稲葉さんは、戦前に国家の重要政策に関わる中枢機関「企画院」に在籍しましたが、当時の軍部に睨まれ、思想犯として検挙される「企画院事件」に連座し投獄されるという、筆舌に尽くしがたい政治的逆境を経験している。
この厳しい体験を乗り越えた人物の言葉だからこそ、以下のフレーズは、単なる楽観論ではない、真の達観を含んでいる。
「もうじたばたしない。あれこれ考えない。平凡なことだが、『成るようにしか成らぬ』と、一切をあきらめ、天に任せた。おかげで、気分だけは楽だった」
これは、努力を放棄する「諦め」ではない。自力ではどうにもならない運命的な事柄に対し、抗うことから生じる無益な苦しみから自らを精神的に解放し、エネルギーの浪費を防ぐ「心の区切り」をつける知恵と言っていいでしょう。
人生の大きな流れに身を委ねることで、かえって次の具体的な行動に全力を注ぐ心のゆとりが生まれる。
「不平等」を前提とし、「自分の時計」で生きる
同じく『打たれ強く生きる』で紹介されている劇団四季の浅利慶太氏の「新入者への掟」は、他者との比較から生じる苦悩を断ち切る鋭い示唆を含んでいる。
- 「この世界は不平等と思え」:人生は理不尽であり、環境や才能に差があるのは当然。最初から不平等を前提とすることで、他人の成功や環境に不平不満を抱く無益な感情を断ち切り、自分自身の目の前の鍛錬と課題に集中することを促す。
- 「自分の時計を持て」:人にはそれぞれ、才能が開花する時期や、真価が問われる時がある。他人のペースや評価軸に振り回されることなく、自分がどういう人間であるかを見極め、自己の人生設計、自己のペースで着実に進むこと。この独立した精神こそが、一時的な逆境に動じない強靭さをもたらす。
人間を支える三つの土台:アチーブメント、インティマシー、セルフの確立
逆境を乗り越えるためには、単に状況に対処するだけでなく、人間としての土台をしっかりと築いておく必要がある。精神的な安定と充実を支える三つの柱として、アチーブメント(達成)、インティマシー(親密性)、セルフ(個)のバランスが重要。
| 柱 | 意味と逆境における役割 | 関連する知恵 |
| セルフ(Self) | 「自分だけの世界(個の世界)」を持つこと。 読書、思索、趣味など、他者に依存しない精神的な領域。逆境で他者との関係が途切れた時も、ここが心の支えとなる。 | 「自分の時計」で生きる |
| インティマシー(Intimacy) | 親しい人との親密な関係(親近性)。 家族、友人、敬愛する師など、自分を支えてくれる人々との関係を大切にすること。 | 人間関係を「財産」とする |
| アチーブメント(Achievement) | 目標達成の感覚(達成)。 仕事での成果、本当にやりたいこと、生きがいなど、人生において何かを成し遂げようとする意志。 | 真剣な姿勢、平凡な反復 |
特に逆境下では、外的要因(アチーブメント)が崩れやすいからこそ、セルフ(自己の内省)とインティマシー(人間関係の財産)の柱が心の強さの土台となる。
本質的な強さを築く知恵:真剣さ、反復、そして人格の形成
『現代の覚者たち』に登場する森信三先生などの先達たちは、目先の成功や華やかな才能よりも、人間としていかに真剣に生きるか、そして平凡な努力の積み重ねこそが偉大さの源泉であると語る。これは、森先生の代表作『修身教授録』の教えとも深く通じるものだ。
能力の優劣を超越する「真剣な人間」
教育者である森信三先生は、その著書『修身教授録』において、人間の真価は能力の多寡ではないと一貫して説いています。これは『現代の覚者たち』の中でも同様に語られています。
天分や素質に心を奪われて嘆くよりも、自己に与えられたものをぎりぎりまで発揮実現することに全力を尽くすことこそ、より大事ではないでしょうか。結局、能力は劣っても、真剣な人間の方が最後の勝利者になるようです。
逆境下で自分の能力の限界に直面したとき、「自分には才能がない」と嘆くのではなく、「今、自分にできること」を、自己の全存在をかけて取り組む「真剣な姿勢」こそが問われる。この真剣さこそが、たとえ結果がすぐに出なくても、周囲の信頼と自己の成長を担保し、最終的な勝利をもたらすと言っていいでしょう。
才能を創り、偉大さの土台となる「平凡な反復」
真の偉大さは、特別な才能ではなく、地味な努力の積み重ねから生まれます。『現代の覚者たち』は、この「平凡さの非凡性」を強調する。
- 「本当に偉大だなと思う人には、みな平凡さがある。平凡に鍛え上げて、偉大にしている。そう思うのです」
- 才能を創る秘訣:「もっとも大切なことは、何度も繰り返してやる、ということです。身に付くまで何度でも、繰り返してやる」
『修身教授録』の教えにもある通り、「本を読んだら必ず実行する」こと。知識を知識で終わらせず、愚直なまでに実行と反復を繰り返すこと。逆境とは、この地道で平凡に見える鍛錬を強いる機会であり、ここを乗り越えた先に、揺るがない自信と、他者からの尊敬を集める確かな人格が形成される。
また、「人を育てる秘訣」として挙げられた「ほめること」も、「やっぱり、自ら鍛えた人でないとだめですね」と続いており、自己鍛錬こそが、他者に良い影響を与える真の魅力の源泉であることを示唆している。
突破口を開く知恵:関係性と「心構え」の力
逆境の渦中では、問題の解決法が見えなくなりがちだが、困難を経験した先達たちは、問題は必ず解決すると断言し、人間的なつながりの重要性を説いている。
問題は必ず片づく。問われるのは「心構え」
伊藤肇氏と城山三郎氏の対談をまとめた『サラリーマンの一生』では、若い世代の悩みに対し、深い洞察をもって力強く断言している。
「君たちだって、今までにいろいろな問題が片づいていなければ、今頃は自殺しているだろう。片づいているからこそこうして生きているのだ」(中略)失恋、病気、家庭のトラブル、仕事上の問題など、どんな難問でも解決され、片づくものだ。しかし、大事なのは、それらの問題に対する取り組み方、心構えだ。
今、目の前にある難問も、過去の困難がそうであったように、必ず解決の時を迎えます。この揺るがない確信を持つことが、まず第一歩だ。
そして、「問題をうまく出す事(=本質を見極める事)が一番大事だ。問題をうまく出せば、それが答えだ」という箴言のように、感情に流されず、落ち着いて問題の本質を見極めようとする「心構え」を持つことが、解決への突破口となる。
人間関係を「財産」とする
孤独になりがちな逆境時こそ、人間関係は不可欠な支えとなる。
サラリーマン社会は、人間関係で仕事をするんだという、そのことを根底から理解しておかないと、(中略)人間関係の財産を大切にすること。こういうことは、サラリーマンとしてというより、人間として成長するために、絶対に不可欠ですね。
仕事の能力や好き嫌いといった表面的な感情で人を選り好みせず、多くの人と誠実に関わり、人間関係を「財産」として築くこと。この財産が、逆境において、情報、助言、そして何より精神的な支えとなってくれる。
まとめ:打たれ強く生きるための5つの柱
城山さんの本や、『現代の覚者たち』の言葉から得られる、逆境を乗り越え「打たれ強く生きる」ための知恵は、人生観と行動原理に根ざした以下の5つの柱に集約されると言っていいでしょう。
- 【受容と解放】 自分の力で変えられないことは「成るようにしかならぬ」と受け入れ、執着を手放す。
- 【自律と集中】 他人と比較せず「自分の時計」で生き、目の前の鍛錬に集中する。
- 【真剣な姿勢】 才能を嘆くより、今与えられた可能性を「真剣」に最大限発揮する。
- 【平凡な反復】 偉大さは特別な才能ではなく、地道な努力を「身に付くまで何度でも繰り返す」ことで創り上げる。
- 【感謝と心構え】 問題は必ず解決すると信じ、人を大切にし、その問題への「心構え」を正す。
困難な状況に直面したとき、今回のブログ記事が少しで参考になれば幸いです!