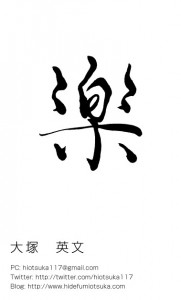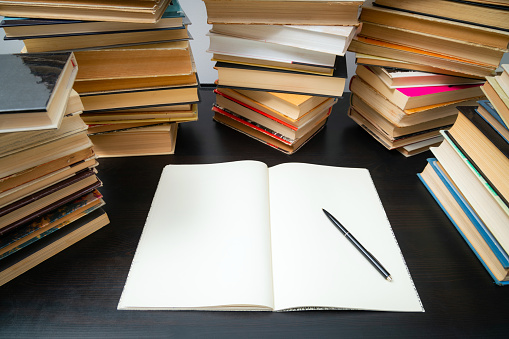【B#235】チャールズ・ダーウィンの「進化論」——ジェントルマン社会が生み出した成果
Table of Contents
はじめに——進化論は“天才の孤独”ではなく、文化と制度の産物だった
こんにちは。渋谷でロルフィング・セッションと脳科学をベースにした講座を提供している大塚英文です。
今回は、生物学で画期的な成果となる「進化論」について、松永俊男著「チャールズ・ダーウィンの生涯:進化論を生んだジェントルマンの社会」を参考に、「進化論」は、英国の文化と制度の産物であったことを中心に紹介していきたい。
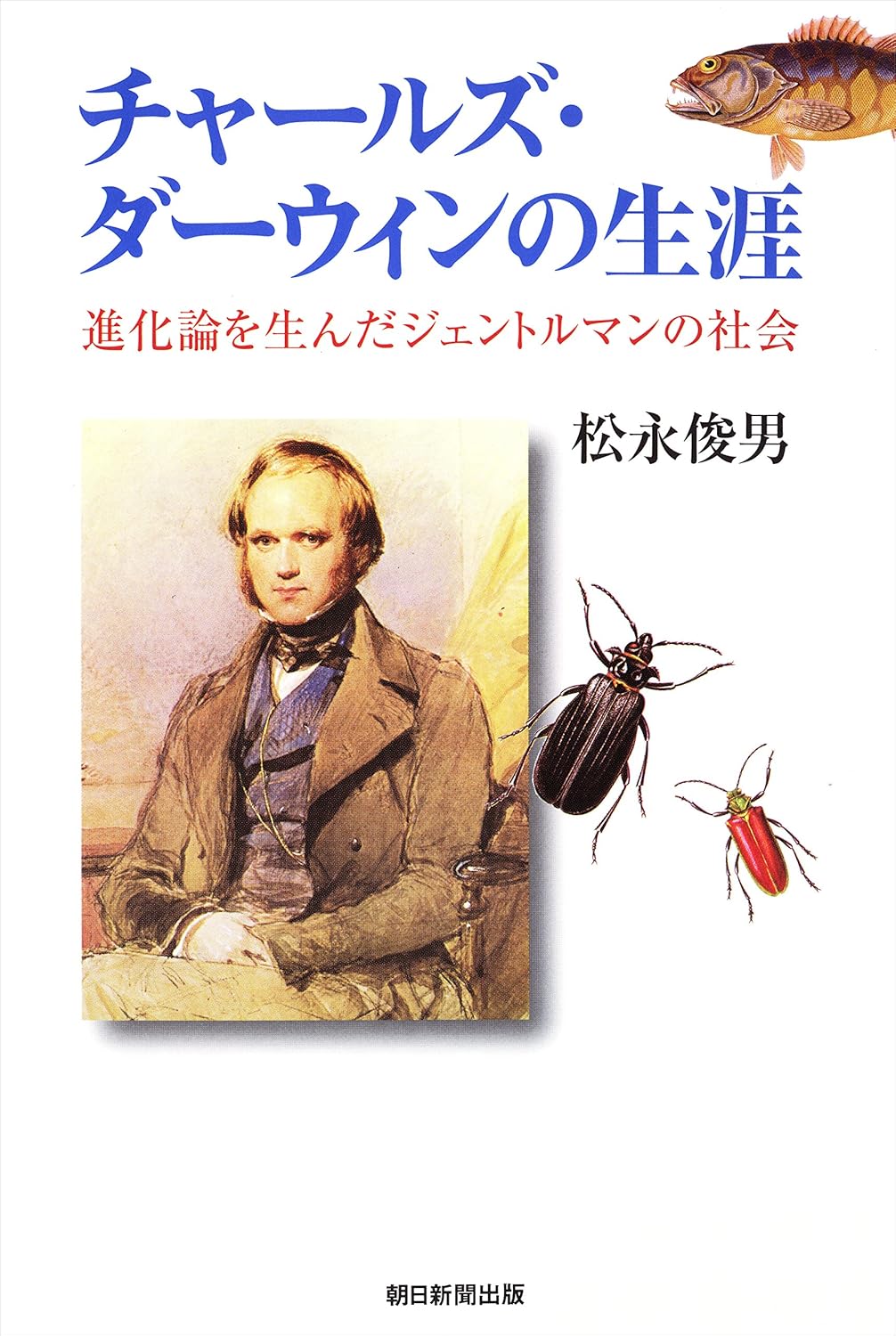
チャールズ・ダーウィンの進化論は、孤高の天才の閃きだけで生まれたわけではない。19世紀、英国という特異な社会構造と文化装置が生み出した「知の結晶」と言える。
実は、ダーウィンを取り巻いていたジェントルマン社会――経済的余裕、社会的信用、道徳的義務感を備えた上層中産階級――が、彼の知的探究を支えた。科学や学問は「職業」ではなく「公共的奉仕」であり、報酬よりも名誉と信頼で駆動される「紳士科学(gentleman science)」の文化がそこにあった。
ダーウィンの思想は、ケンブリッジの学風と人脈、キューガーデンに代表される帝国的知識ネットワーク、王立協会という学術制度、海軍の探検体制、そしてユニタリアンや広教会派に見られる宗教的寛容という基盤の上で成熟した。進化論は、社会の構造と文化の支えがあって初めて生まれた「制度としての知」の成果であった。
ぜひ、一つ一つ、この視点から見ていきたい。
ケンブリッジの学風と人脈——信仰と理性の交差点
ダーウィンは1827年、ケンブリッジ大学クライスト・カレッジに入学し、神学と自然科学を学んだ。当時のケンブリッジには「自然神学(ナチュラル・セオロジー)」という独特の知的伝統があり、神が創造した自然の秩序を理性によって読み解こうとする態度が共有されていた。
ダーウィンはウィリアム・ペイリー『自然神学(Natural Theology)』を耽読し、自然界の精妙な構造の中に「創造の理法」を見る感性を養う。“自然を観察すること自体が神の意志を理解する道である”という信念は、彼の観察や論文をまとめる際に、影響を与えた。
植物学者ジョン・スティーヴンス・ヘンスロー(John Stevens Henslow)との出会いも決定的だった。ヘンスローは野外での実地観察を奨励し、標本採集・分類・記録の厳密さを徹底させた。ダーウィンはその作法を身につけ、のちのビーグル号航海でも克明な記録を残すことになる。
ケンブリッジは、学風と人脈(学閥)が緊密に結びつく共同体でもあった。教授・卒業生・学会・聖職者が互いに推薦・紹介し合い、知的信用の輪を維持する。ダーウィンがビーグル号の自然史担当に選ばれたのも、恩師ヘンスローの推薦による。
ケンブリッジとイングランド教会——広教会派が育てた「ケンブリッジ・ネットワーク」
ダーウィンがケンブリッジに在学していた当時、イギリスの科学界の中核はケンブリッジのフェローたちで、その多くは国教会の聖職者だった。ただし、聖職者が一致して科学を支持していたわけではない。
19世紀のイングランド教会には高教会派・低教会派(福音派)・広教会派の三潮流があった。高教会派は伝統と儀式を重んじ、低教会派は個人の信仰と聖書中心主義を強調し、広教会派は寛容と理性を重視して多様な立場の共存を認めた。
古典研究・歴史学・自然科学に積極的に貢献したのは、ほとんどこの広教会派である。低教会派は科学に無関心で、聖書記述と矛盾する場合には強く抵抗し、高教会派は自然神学そのものに否定的だった。
19世紀初頭、この広教会派の中核がケンブリッジのフェローたちであり、彼らは密接に連絡を取りながら大学改革・宗教・科学の諸問題に当たった。
科学史では、この共同体を「ケンブリッジ・ネットワーク」と呼ぶ。ダーウィンが吸い込んだケンブリッジの空気は、この広教会派的理性主義の影響を強く受け、彼の科学観と倫理観の土台を形づくった。
オックスフォードとケンブリッジ——理性と信仰、理念の対照
オックスフォードは伝統的に人文学と神学の牙城で、古典語教育と聖書解釈を基軸に人格陶冶を重んじた。ここでは知的探究は信仰の補助手段であり、「真理を守る場」であった。
ケンブリッジはニュートン以来の理性・経験主義の拠点として、数学・自然哲学・観察科学を重視する「真理を発見する場」。ダーウィンがケンブリッジを選んだのは偶然ではない。理性を通して自然を理解する気風への親和性が、彼の性格と響き合った。
ジェントルマン階級と科学——「社会的信用」が研究を支えた
ダーウィンはシュロップシャーの名家に生まれ、父ロバートは富裕な医師、母方は陶磁器メーカーのウェッジウッド家。彼は生涯、不労収入によって暮らし、職務や俸給に縛られなかった。
この経済的自由が、長期の観察・記録・実験・思索を可能にした。ロンドン近郊のダウン・ハウスに引きこもるように暮らしながら20年以上を費やし、『種の起源』の構想を練り上げる。彼は「職業学者」というより、真理に奉仕する紳士として生きた。
ビーグル号航海——帝国と科学の協働
1831年、22歳のダーウィンは海軍測量船ビーグル号に乗船する。この航海は、帝国の測量事業と自然史研究が結びついた国家的プロジェクトであった。
しかし実は、艦長ロバート・フィッツロイが若きダーウィンを選んだのは、「話し相手(コンパニオン)」としての役割もあった。当時の英国海軍では、長期航海中の艦長の孤独と精神的圧迫が深刻な問題となっており、自殺する艦長も少なくなかった。ビーグル号の前任艦長プリングルトンも自ら命を絶っている。
フィッツロイ自身も神経質で内省的な性格であり、信仰と科学の狭間で常に葛藤していた。彼は、知的で信頼できる紳士を心の支えとして求め、ケンブリッジのネットワークを通じてダーウィンを推薦されたのである。
ダーウィンはこの「話し相手」としての役割を誠実に果たしつつ、同時に地質・動植物・民族誌を丹念に記録した。その観察の精密さと誠実さは、のちに『種の起源』を支える実証的基盤となる。
そして、信仰に揺れ、孤独に苦しむフィッツロイとの対話こそ、ダーウィンに「自然と神」「法則と目的」をめぐる深い思索を促す精神的鍛錬の場でもあった。
キューガーデンと知識ネットワーク——帝国的植物学の力
ビーグル号からの帰国後、ダーウィンはロンドンの学術ネットワークに加わり、その中心にあったキューガーデン(王立植物園)と深く関わるようになった。キューガーデンは18世紀以来、帝国全土から送られた植物標本を収集・分類する「帝国の植物アーカイブ」として機能しており、世界最大の比較植物学の拠点であった。
この研究施設を率いたのが、ダーウィンの生涯の友人ジョセフ・ダルトン・フッカーである。
フッカーは世界中の博物学者や宣教師と通信を交わし、ダーウィンはそこから得られる膨大な情報を理論構築に活かした。彼らは書簡を通じて「種の可変性」や「地理的分布」を議論し、進化論を思索から実証の科学へと押し上げていった。
キューガーデンは、王立協会やリンネ協会と並ぶ知の制度的中枢でもあり、科学が国家の枠組みの中で組織化されていく象徴でもあった。ダーウィンにとって、ここは単なる植物園ではなく、世界の生命を比較し、法則を見出すための「地球規模の実験室」であった。
この帝国的知識ネットワークがあったからこそ、ダーウィンは個人の観察を超えて、生命をひとつの原理で理解するという壮大な構想を現実の科学として結実させることができたのである。
「プランの一致」と適応——二つの思考の統合としての進化論
19世紀前半の自然研究には二つの潮流があった。
一つは、哲学的・形態学的伝統に根ざす先験的原理から生物を統一的に理解しようとする方向で、リシャール・オーウェンらが唱えた「プランの一致(共通形態)」を重視する立場である。彼らにとって重要なのは環境への適応より、生命に内在する普遍的構造だった。
もう一つは、ペイリー流の適応主義で、自然の精密な構造を「目的に適った設計」として理解し、環境に合致する形態を強調する立場である。
ダーウィンの進化論は、この二つを統合した。すなわち、形態学が見出した「共通プラン」を、歴史的時間のなかで変化しうる秩序として捉え直し、適応主義が注目する「環境適応」をその変化の駆動原理(自然選択)として位置づけた。
固定的プランから生成するプランへ——先験的秩序と経験的適応の橋渡しが、進化論の独創である。これにより、進化論は単なる自然観察の理論を超え、哲学的に自立した生命観へと昇華した。
ユニタリアンと広教会派——宗教的寛容が思想の自由を守った
ダーウィン家とウェッジウッド家は、理性と良心を重んじるユニタリアンの影響を受けていた。国教会内では広教会派が勢力を持ち、信仰と学問の共存を模索。たとえ進化論が創造説を揺るがすものであっても、家族や友人は彼を“異端者”ではなく“誠実な探究者”として支えた。
信仰深い妻エマもまた、夫の科学的誠実さを理解し続けた。宗教と科学を対立させず、理性で調和を図る姿勢こそが、ジェントルマン社会の成熟した知的精神であり、ダーウィンの思想を守る器となった。
さて、最後に核心であるダーウィンの「進化論」について触れたい。
進化論とは何か?
進化論とは「生命は固定されたものではなく、長い時間をかけて変化し、その変化の中に意味や理由がある」という考え方だ。先行する思潮では、生きものは“完成された姿で創られた”と捉えられていた。しかしダーウィンは次のような観察から出発する。
- 違う場所にいる同じ種類の生きものが、微妙に姿を変えている
- その違いは環境との関係で説明できる
- 似ているけれど異なる種には、共通の祖先があるという考えが自然に浮かぶ
こうして、彼は「環境による選択が、時間をかけて生命の多様性を生む」という枠組みをつくった。言い換えれば、生命とは“変化し続けるプロセス”そのものだと考えた。
なぜ、それが革命的だったのか?
進化論が登場した時代、科学・宗教・社会にはこうした前提が存在した。
- 生きものはそのまま変わらずに存在すると考えられていた
- 人間は他の生きものとは本質的に区別されていた
- 世界には神が設計した調和があり、それを変えるものではないと捉えられていた
その中で、ダーウィンの枠組みは次のような転換を提示した。
- 超自然的説明から自然の力へ
生きものの多様さを「神の創造」だけで説明するのではなく、観察可能な自然の仕組み(自然選択)によって説明したこと。 - 人間も自然の連続にあるという視点
人間を“特別”な存在として扱うのではなく、自然の歴史の中に位置づけた点。これは社会・宗教・哲学にとって大きな問いでした。 - 変化こそが生命の本質であるという洞察
「種は固定ではない」「変化し続けるもの」という考え方は、自然科学だけでなく、私たち自身の生き方や認識にも新たな視座を提示しました。
このように、進化論は生物学の枠を超えて、世界観を揺さぶった「革命的な着想」だったと言える。
キリスト教との関係――なぜ“対立”とも“対話”とも言えるのか?
進化論が提示した世界観は、当時のキリスト教的世界観と交差し、時には緊張を生んだ。キリスト教的世界観では、
- 生きものは一度創造されてから変わらない
- 人間は神に似せて創られた特別な存在
- 世界は神の意図によって秩序立てられている
といった前提があった。
一方、進化論は、
- 生きものは時間とともに変化する
- 人間も他の生きものと同じ自然の一部である
- 種の分化・適応というプロセスが世界を形づくる
という視点を提示する。結果として、教会・神学者・一般市民の中には「人間の尊厳」「神の創造」という概念が揺らぐように感じた人も少なくない。
ただし注目すべきは、ダーウィン自身が“科学と信仰を敵対させる”ことを目的としていたわけではない点だ。彼はもともと牧師志望であり、信仰を完全に否定する姿勢をとっていたわけではありません。むしろ、科学的探究と宗教的探求が“共存できる場”として発展していく可能性を示していたとも言える。
そして、ケンブリッジにおいて信仰と学問を対立させずに育む「広教会派」の伝統が、彼の体系化を支える文化的土壌だったことも見逃せない。
おわりに——「知のエコシステム」が思想を育てる
このように進化論は、ケンブリッジの学風、人脈と師弟関係、ジェントルマン階級の倫理と経済的自由、キューガーデンの国際ネットワーク、宗教的寛容という文化的背景が重なり合い、ゆっくりと熟成した。
さらにその核心には、「プランの一致」と「適応」という二つの思考を統合する哲学的胆力があった。ダーウィンは自然界を固定的秩序ではなく生成する秩序として見た。その視線の先に、19世紀の科学と哲学を架橋する本当の創造がある。
ダーウィンの生涯は、学問と文化、信仰と理性、個人と共同体が交差するところにこそ、新しい世界観が生まれることを示していると思う。