【B#228】2025年・ノーベル医学生理学賞・坂口志文教授が受賞
Table of Contents
はじめに
こんにちは。渋谷でロルフィング・セッションと脳科学をベースにした講座を提供している大塚英文です。
今年(2025年)のノーベル生理学・医学賞は、大阪大学の坂口志文特任教授に決まったことがニュースで話題になっている。
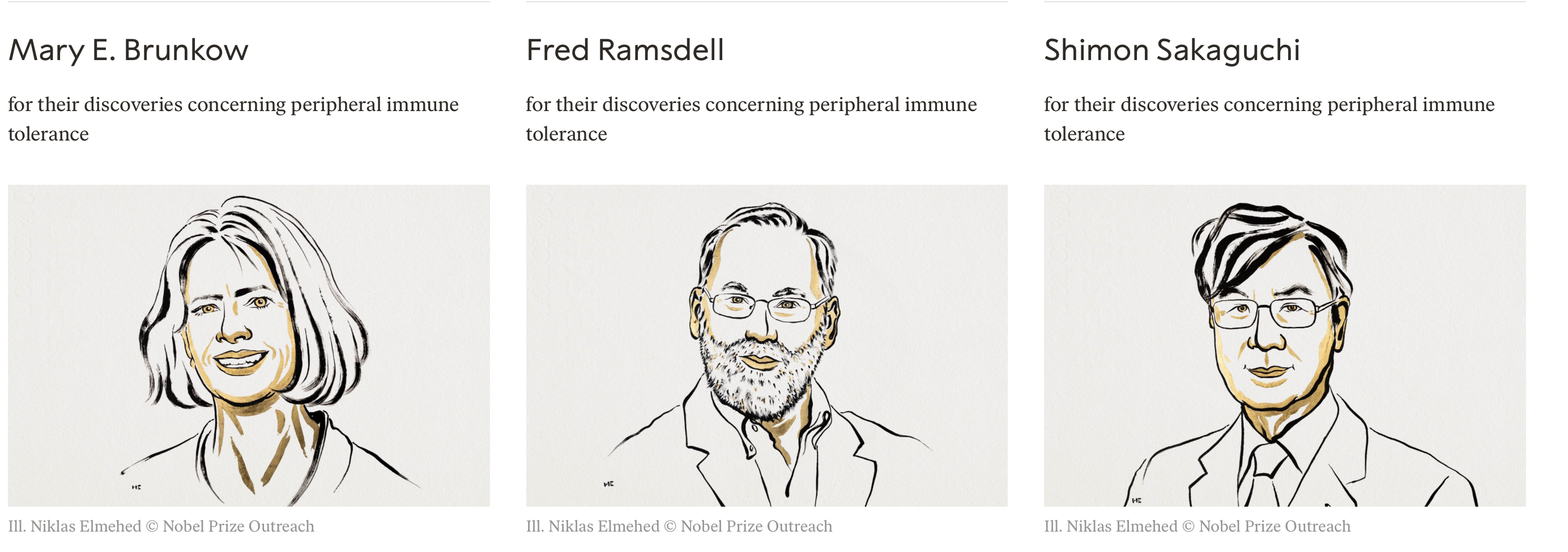
免疫学とのご縁ー博士課程の時のテーマ
私は、1997年4月から2001年3月の4年間、東京大学大学院医学系研究科の免疫学教室の博士課程に在籍していた。当時の指導教官は、谷口維紹教授(現、東京大学名誉教授)。その前の教室の主任が今は亡き多田富雄教授だった。
多田先生は、科学者のみならず日本文化にも造詣が深い方で、科学と哲学の接点と言える「免疫の意味論」の本も出しており、私も何度も読んだ記憶があった。
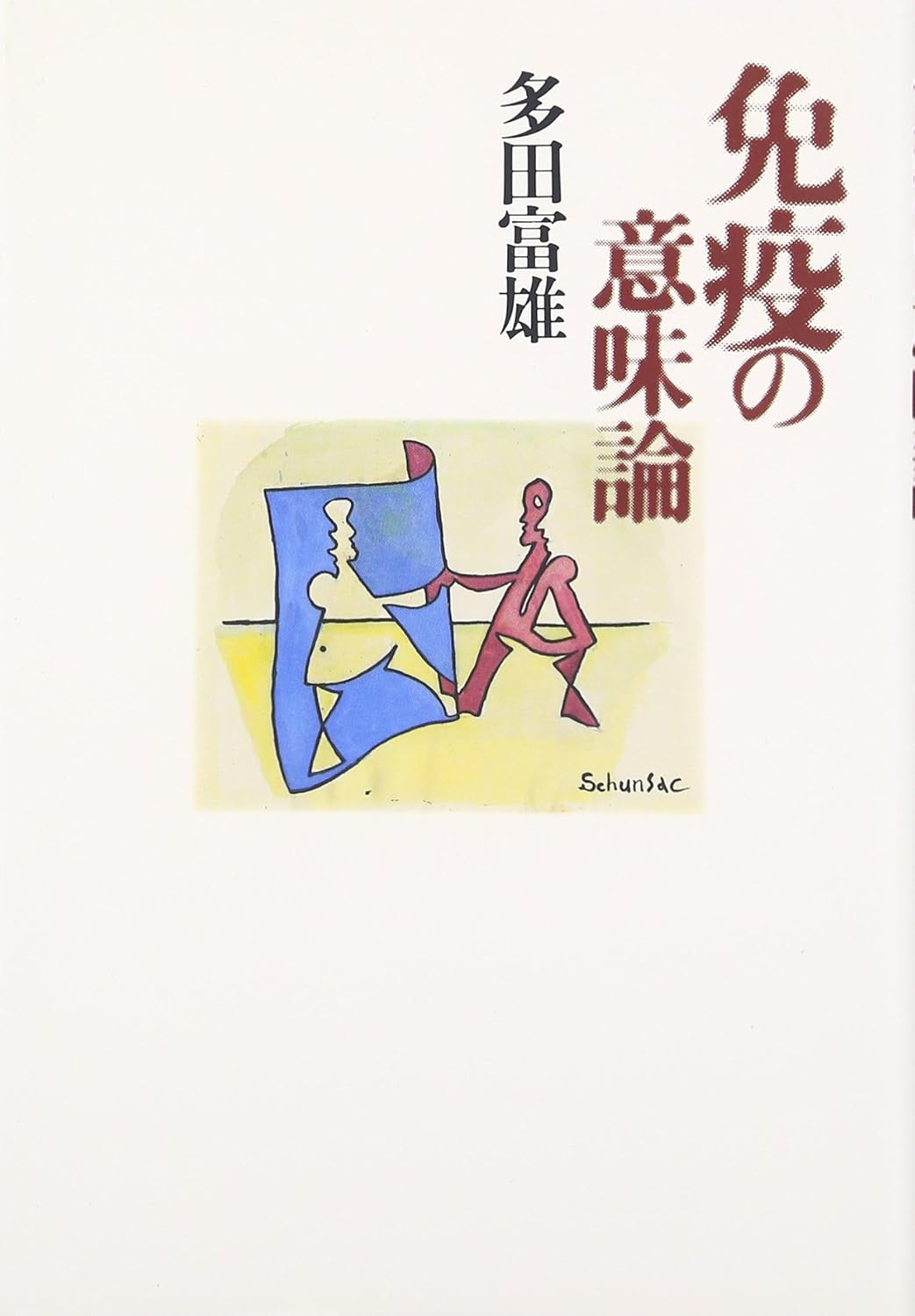
話題が脱線するが、多田先生とお会いした時、所属した研究室主催の石坂公成先生の講演会が行われていた。石坂先生は、長年米国でご活躍された研究者で、アレルギーを引き起こすIgEの発見者として知られている。
多田先生の師匠にあたる方だけではなく、炎症サイトカイン(IL-6)の発見者、岸本忠三先生や、私の博士審査でお世話になった高津聖志教授等、錚々たる弟子を育てている。
人材をどのように育てているのか?石坂先生は、「我々の歩いた道」という本にまとめている。別のブログ記事で紹介しているので、ご興味のある方、チェックしてください。
今回は、岸本忠三著、中嶋彰著の「現代免疫物語・BEYOND・免疫が挑むがんと難病(ブルーバックス)」を参考に、坂口先生がどのようなプロセスで、発見に至ったのか?についてまとめたい。
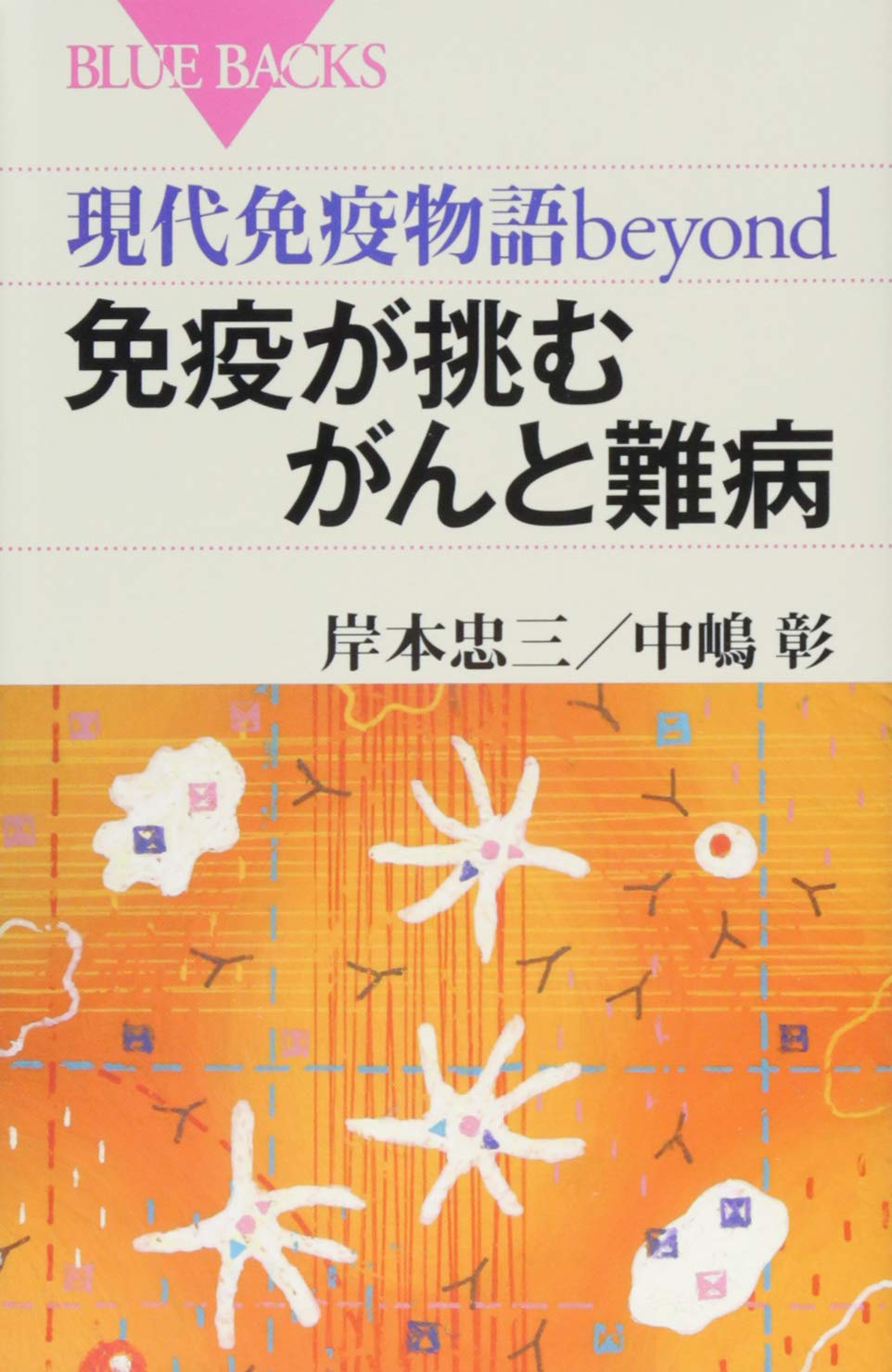
抑制性T細胞の栄光から挫折へ
坂口先生の制御性T細胞の歴史は、多田先生やエール大学のリチャード・ガーションによって発表された抑制性T細胞(サプレッサーT細胞)から始まる。
ところが、IgE抗体を分泌するマウスで実験すると、異物を注入してもIgEは一時的に増えるだけで、すぐ減ってしまった。さらに、X線を当てたり胸腺を取り除いたりすると、逆にIgEが異常に増えるという不可解な結果が出た。
ある朝、多田は風呂に入っているときに「もしかして、免疫を抑える細胞を壊してしまったのでは?」とひらめきました。すぐに実験を行い、胸腺を摘出したマウスに正常なマウスの胸腺を移植したところ、IgEの量が大きく減った。この結果から、多田は「免疫の働きを抑える細胞」が存在すると確信させる。
1971年、ワシントンでの国際免疫学会で彼はこの細胞を「抑制性T細胞(サプレッサーT細胞)」と名づけて発表。世界中の研究者に衝撃を与え、大きな注目を浴びた。抑制性T細胞=CD8陽性T細胞という前提で研究を進めていたが、残念ながら、当時の技術では免疫抑制の仕組みを正確に捉えることができなかったのである。
やがて、抑制性T細胞は下火に。この「幻の仮説」を胸に秘め、後にそれを現実の発見へとつなげたのが坂口先生だった。
制御性T細胞は、否定された理論からの出発
1970年代後半、坂口先生は、京都大学大学院を中退し、愛知県がんセンター研究所に研究員として参加した。とはいえ、正式なポストはなく、無給の研究生という立場だった。
当時、免疫学の主流は「外敵を攻撃する免疫の仕組み」──つまり、T細胞やB細胞による活性化機構の研究であった。多田先生がかつて提唱した「免疫を抑える細胞(抑制性T細胞)」の仮説は、再現性の問題からすでに学界で“否定された理論”とされていた。
坂口先生がこの分野を再び手がけることは、当時の常識からすれば“研究者生命を賭けるような行為”と言える。
実験のきっかけ ― 胸腺摘出マウスの異常反応
坂口先生が注目したのは、胸腺を摘出したマウスに見られる異常な炎症反応だった。
通常、胸腺はT細胞の教育を担う臓器であり、そこを失うと免疫が弱まるはずである。ところが実際には、逆にマウスの体内で自己免疫的な炎症反応が起きる。
このパラドックスから、坂口先生は次のように考えた。
「胸腺には、免疫を活性化する細胞だけでなく、それを抑える細胞も存在しているのではないか。」
つまり、胸腺を失うことで免疫のブレーキ役が欠け、免疫系が暴走している──。この仮説こそが、後の「制御性T細胞(Regulatory T cell, Treg)」発見の原点と言える。
海外の居場所を転々としながら、定職を得ることなく、博士研究員として制御性T細胞の性質を明らかにすることを追求していくことになる。
実験の突破口 ― CD4陽性T細胞の一部に抑制能を発見
坂口先生は、マウスの胸腺や脾臓からCD4陽性T細胞を分離し、その一部をさらに分類して実験を行った。
結果、CD4陽性T細胞の中でもCD25(IL-2受容体α鎖)を持つごく一部の細胞が、他のT細胞の活性化を抑える働きを示すことを確認した。
余談になるが、私の博士の研究テーマは、T細胞の免疫に関わるIL-2の研究。制御性T細胞の指標は、IL-2の受容体が関係する(CD25、IL-2受容体α)ということもあり、当時の坂口先生の論文は読み、フォローしていた。
この細胞を除去すると、マウスは自己免疫疾患を発症し、逆にこの細胞を戻すと症状が沈静化したのだ。
坂口先生はこの瞬間、
「免疫には、アクセル(活性化)とブレーキ(抑制)の両方が存在する」という確信を得た。
という。
当時の論文は国内外で大きな注目を集めたが、本人はポストも名声もなく、依然として無給のまま研究を続けていた。
坂口先生は、
「真実は、地位よりも長く残る」
という信念を胸に、データの再現性を何度も確認し続けた。
「幻の研究者」と呼ばれた時代
坂口先生の名前は、海外では論文で知られていたが、本人が学会に姿を見せることはほとんどなかった。そのため欧米の研究者の間では、彼は“Phantom Researcher(幻の研究者)”と呼ばれていたらしい。
愛知がんセンター時代こそが、制御性T細胞(Regulatory T Cell, Treg)の存在を初めて明確に示した科学史的転換点であった。
京都大学への招聘と確立期
1995年、43歳で東京都老人総合研究所の免疫病理部門長に就任。この職は、坂口先生にとって初の安定した定職だった。
ここで、愛知がんセンター時代に掴んだ仮説をより体系的に検証する研究環境を得た。免疫抑制機構の存在を再現性ある実験系で示すために、マウスモデルと細胞分離技術を改良し、CD4⁺CD25⁺T細胞が免疫制御の中心にあることを明確にした。
更に、FOXP3遺伝子の発見によって、この細胞が明確なアイデンティティを持つことが証明され、制御性T細胞は現代免疫学の中核概念となった。
まとめ
今回は、坂口教授のノーベル賞受賞もあり、私の大学院生時代のことを思い出したので、その話を含め、ご紹介させていただいた。
少しでもこの投稿が役立つことを願っています。






