【B#221】依存症をめぐる真実──Gabor Matéの『In the Realm of Hungry Ghosts』
Table of Contents
はじめに
こんにちは、渋谷でロルフィング・セッションや脳科学をベースにしたコーチングを提供している大塚英文です。
カナダ人医師のGabor Maté(ガボール・マテ)の本 In the Realm of Hungry Ghosts: Close Encounters with Addiction を読み、依存症について従来の理解を超える新たな考え方を知ることができた。そこで、今回は、マテの本を中心に、依存症についての考え方を紹介したい。
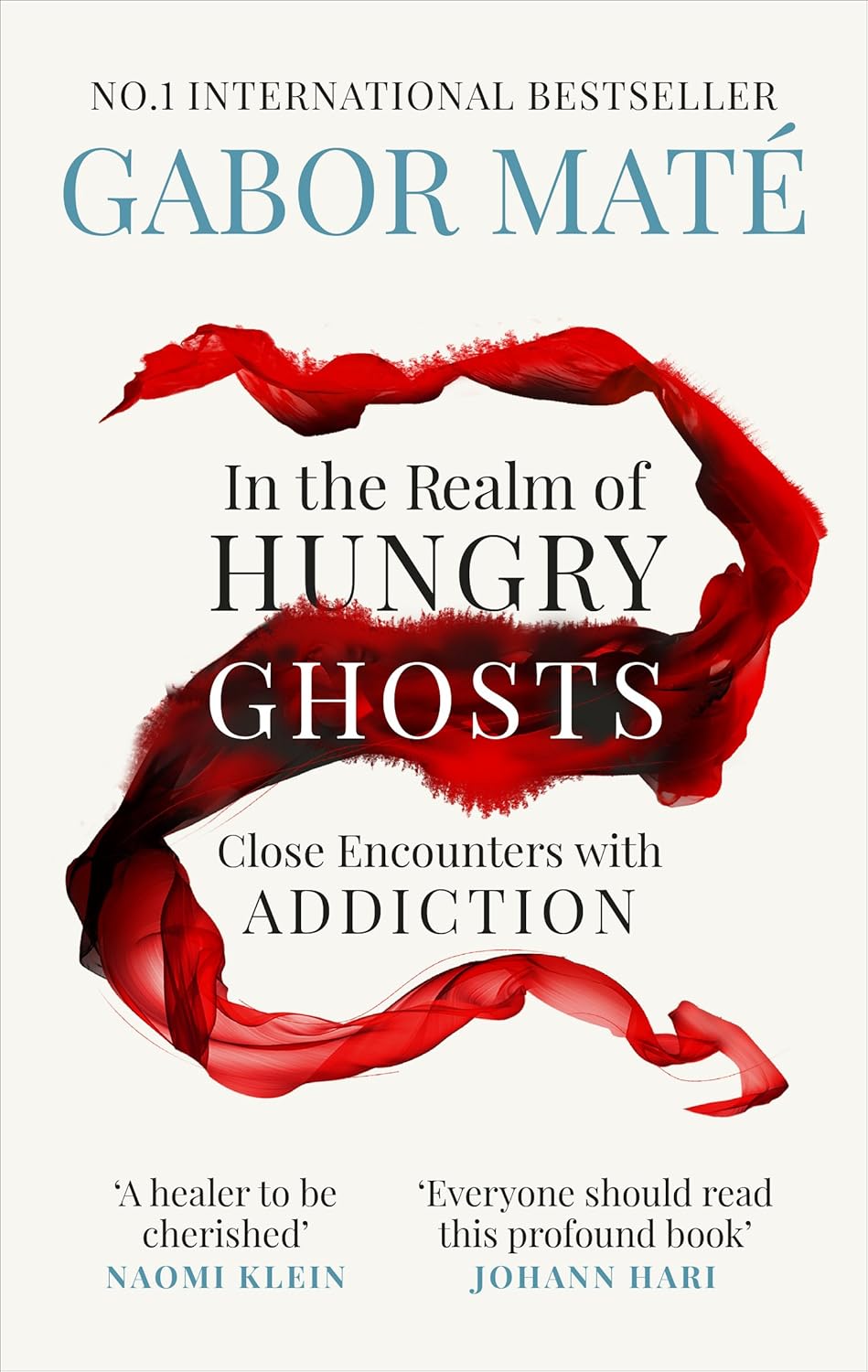
バンクーバーのダウンタウン・イーストサイドから
この本の舞台は、カナダ・バンクーバーの「ダウンタウン・イーストサイド」と呼ばれる地域である。ここは北米でも最も深刻な薬物依存とホームレスの問題を抱える場所の一つであり、マテは長年にわたりこの地域で依存症患者を診てきた。
医師としての臨床経験、そして自らも仕事や購買衝動への依存傾向を抱えていた当事者としての実感が、今回紹介する本の内容を支えている。
彼は冒頭で次のように述べる。
“Addiction is not a choice anybody makes; it’s not a moral failure. It’s not an ethical lapse. It’s not a weakness of character. It’s not a failure of will. It’s a response to human suffering.”
(依存は誰かが選ぶものではない。それは道徳的な失敗でも、意志の弱さでもない。それは人間の苦しみに対する応答なのである。)
「空腹の亡霊(Hungry Ghosts)」とは何か?
タイトルの「Hungry Ghosts(餓鬼)」とは、仏教における存在である。大きな胃を持ちながら喉が針の穴ほどに細く、決して満たされることのない亡霊である。マテは依存症患者をこの比喩で描く。彼らは薬物やアルコール、ギャンブルや買い物などを通して「欠けたもの」を埋めようとするが、決して充足することはない。
“All addictions, whether to drugs or to behaviors, serve the same purpose: they distract from pain, they soothe suffering, and they provide a temporary sense of control.”
(あらゆる依存は、薬物であれ行動であれ、同じ目的を果たしている──それは痛みから気をそらし、苦しみを和らげ、一時的なコントロール感を与えることだ。)
患者の事例──孤独と痛みの背景にあるもの
マテは本書で、依存症の背後にある「人生の物語」を数多く紹介している。その中から印象的な二つを取り上げたい。
コカインに依存する女性・ジュリー(仮名)
ジュリーは30代前半の女性で、路上での生活を余儀なくされていた。幼少期、母親はアルコール依存症であり、父親からは度重なる虐待を受けていた。安心できる居場所を持てなかった彼女にとって、コカインは「唯一、心を落ち着けることができる手段」だった。
“For Julie, the drug was not the problem but the solution—until it stopped working.”
(ジュリーにとって薬物は問題ではなく解決策だった──それが効かなくなるまでは。)
この言葉は、薬物依存を単なる「悪い選択」ではなく「苦しみに耐えるための工夫」として理解すべきことを示している。
ヘロイン依存の男性・ジョー(仮名)
ジョーは40代で、長年ヘロインを注射し続けていた。彼の語るところによれば、10歳のときに母親を交通事故で亡くし、その悲しみを抱えたまま育った。誰もその痛みに寄り添わず、孤独の中で彼は早くからアルコールに依存し、やがてヘロインへと移行した。
ジョーは医師にこう語った。
“When the heroin hits, it’s like being held in my mother’s arms again.”
(ヘロインが効くと、まるで母の腕に抱かれているように感じるんだ。)
この告白は、依存が「快楽の追求」ではなく「失われた愛着の代替」であることを鮮烈に物語っている。
依存症の根源──幼少期のトラウマと愛着の欠如
マテの核心的な主張は、依存症は「脳の病気」であると同時に「関係性の病」であるという点である。幼少期に安心できる愛着関係を得られなかった子どもは、感情の自己調整に必要な神経回路を十分に発達させられない
そのために大人になってからも慢性的な空虚感やストレスに脆弱となり、薬物や行動への依存に陥りやすくなる。
彼は次のように語る。
“The origins of addiction are always to be found in the lived experience of the child, not in heredity.”
(依存の起源は常に子どもの生きられた経験の中にあり、遺伝にあるのではない。)
これはボウルビィの愛着理論とも響き合う視点であり、依存症を単なる「自己責任」として扱う従来の社会的理解を根底から揺さぶる。
治療と回復の道
マテは、依存症からの回復には単なる禁断症状の管理や薬物の遮断だけでは不十分であると述べる。重要なのは「人間関係を通じて安心を取り戻すこと」であり、そこから神経可塑性による癒しが始まる。
彼が提案する具体的な方向性は以下である。
- 安全な関係性の再構築
医師・カウンセラー・家族との間に信頼を築くことで、依存を生んだ孤立を和らげる。 - トラウマに向き合う心理療法
幼少期の痛みを理解し直し、言葉と感覚を通して統合していく。 - ハームリダクション(被害低減)
「薬をやめろ」と突き放すのではなく、安全な注射所や医療的サポートを提供することで、命を守りながら回復の可能性を開く。 - 身体を取り戻す実践
マインドフルネス、ヨガ、ボディワークなど、身体感覚を回復させる手段が、情動調整を助ける。
マテは、依存症者を「壊れた人」とは見なさない。彼にとって依存は、「生き延びるための最良の選択」であり、そこから回復へと道を拓くことができるものである。
“The question is never ‘Why the addiction?’ but always ‘Why the pain?’”
(問うべきは「なぜ依存なのか?」ではなく、「なぜ痛みがあるのか?」である。)
おわりに
In the Realm of Hungry Ghosts は、依存症を「犯罪」や「意志の弱さ」として切り捨てる社会的偏見を超え、人間の苦しみと愛着の断絶に根ざした現象として描き直す書である。バンクーバーの現場からの生々しい声、そしてマテ自身の自己開示が、本書に揺るぎないリアリティを与えている。
依存症とは「空腹の亡霊」に取り憑かれることではなく、かつて失われたつながりを取り戻すための苦闘である。そしてその回復は、孤立ではなく関係性の中でこそ可能になる。本書はそのことを深い洞察と compassion をもって語りかけている。






