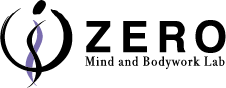【N#9】有機農業の歴史〜化学肥料、農薬、地力低下(欧米)、公害問題(日本)
有機農業(オーガニック)が自然で、遺伝子組換え食品(Genetic Modified Organism、GMO)は不自然だという意見をよく聞く。
世界的にもオーガニック・ブームで、世界一周の旅でヨーロッパ諸国を訪れた際、オーガニックから作られた食品専門の店が多数あったのに驚いた記憶がある(「オーガニック専門店」参照)。

渋谷のサロン・ZEROで地粉茶会を提供しているが(「食事は何でできているのか?〜小麦を中心に」参照)、素材も可能な限り、オーガニックのものを使うようにしている。
さて、改めて
「オーガニックとは何か?」
を考えた際、なかなか答えるのが難しい自分がいる。
そこで、本コラムでは、オーガニックと化学肥料について取り上げ、それぞれの違いについてまとめてみたい。

まずは「オーガニック」。
オーガニック=Organicは、生命によって作り出す物質=オーガニックとして知られており、生命に頼らない無機と分けて考えるとわかりやすい。19世紀に有機物質の一つである、尿素を人工的に作り出せることがわかって以来、有機化合物は、生命に頼らず人工的に作られることもわかってきた。そのため、無機と有機の境界は曖昧だが、
「生物によって作り出される物質」=「オーガニック」
とみて良さそうだ。
日本では、
「有機農業の推進に関する法律」(平成18年12月に制定)に、
「化学的に合成された肥料及び農薬を使用しないこと、並びに遺伝子組換え技術を利用しないことを基本として、農業生産に由来する環境への負荷をできる限り低減した農業生産の方法を用いて行われる農業」
をオーガニックと定めている。
つまり、
「環境に優しい、化学肥料、農薬、遺伝子組み換え技術を使わない」
作物のことをオーガニックといって間違いなさそうだ。

植物は、肥料として、窒素、カリウム、リン、カルシウム、マグネシウムを含め17種類の元素が栄養として必須だということを化学で学ぶが、肥料に必要な物質は化学工業や天然石から作り出すことができる。この種類の肥料は化学肥料と呼ばれる。
化学肥料は、水に溶けやすく、植物にも吸収されやすいので扱いやすい。一方で、栄養素が流れやすいために、絶えず肥料をつけ足す必要がある。
意外と、化学肥料の歴史は浅い。
19世紀から20世紀にかけて石油を中心とした化学工業が発達する前は、如何にして窒素を肥料に確保することが課題だった。植物を成長させるためには、大量の窒素が必要だからだ。
大気中の80%は窒素で占めているが、窒素は安定な物質なため、植物は直接使うことができない。そこで、マメ科植物の根粒菌の力を使って、マメ科の植物に住み着き、細菌と植物との共同作業を通じて、大気中の窒素を利用できる(窒素固定という)方法が取られた。
しかし、この手法だと、農作物の単位面積当たりの収穫量に限界がある。

そこで、化学工業を使って窒素固定できる技術が開発された。
主なものとして、20世紀初頭、ドイツ人のフリッツ・ハーバーとカール・ボッシュにより、大気中の窒素と化石燃料(石炭、石油等)由来の水素からアンモニアを化学の力で作り出すことに成功したハーバー・ボッシュ法がある。当時、ドイツは化学工業の最先端をいっていたが、もともと痩せた土地だったため化学肥料の研究が進んだというのが大きい。
ポイントは、化石燃料が使われていること。石炭や石油産業と共に、農業は発達していることを理解することが大切だ。参考に、トラクター、グリーンハウス、農作物の移動に際しても石油が消費されている。
このような、化学肥料を使うことで、単位面積当たりの農作物の収穫量が飛躍的に増加。扱いが易しいので、瞬く間に、世界的に普及した。

有機肥料は、動・植物を材料に作られる。有機肥料は、土の微生物に徐々に分解され、その後植物に吸収されるため、時間がかかるが、土に蓄積されやすい特徴を持つ。一方で、完熟していない有機肥料を使うと、悪臭、ガス発生、害虫などがでてくることもある。

有機肥料については、マイケル・ポーランの「雑食動物のジレンマ(Omnivore’s Dilemma)」に詳しいが、同書によると、
1940年代、イギリス人のAlbert Howardは、インドの伝統農法から有機物を土に返す堆肥づくりを長年にわたり研究。その頃から欧米では、化学肥料によって地力減退が問題になってきたので、持続可能な農業の方法の一つとして、「オーガニック」に注目して紹介した。
同じ頃、アメリカ人のJ. I. Rodaleが雑誌「Organic Gardening and Farming」を創刊し、オーガニックの情報を発信。1969年、「Whole Earth Catalog」に同雑誌が取り上げられることで、菜食主義者のヒッピーたちに熱烈に支持され、普及していった。
その頃、化学肥料が地力低下や環境への影響、のちに述べる農薬の安全性の問題から、反戦運動と結びついたタイミングがあったことが大きい。

そして、農薬。
日本には農薬取締法があり、
「農作物を害する菌、線虫、だに、昆虫、ねずみその他の動植物又はウイルスの防除に用いられる殺菌剤、殺虫剤その他の薬剤及び農作物等の生理機能の増進又は抑制に用いられる成長促進剤、発芽抑制剤その他の薬剤をいう」
を農薬として定めている。
農作物は害虫に悩まされる歴史でもあった。天然物質(例、除虫菊)や無機物を使って害虫駆除をしていたが、化学工業の発達に伴い、化学の力を借りた農薬が開発されるようになる。
1938年、ガイギー社のパウル・ヘルマン・ミュラーらにより、有機塩素化合物の一つであるDDTに防虫効果があることが判明。コストがかからず、大量に安価に作ることができるので、世界的に普及した。第二次世界大戦後の日本でも、チフス、シラミ等の防疫対策にも使われた。
しかし、DDTについては、発がん性の指摘や、自然界で分解されにくいことから環境への悪影響が懸念され、使用中止になる。参考にマラリア対策として一部の発展途上国で現在でも使われることがある)
農薬は軍事産業と結びつくことが多いことから(DDTはベトナム戦争でも使用)、ベトナム反戦運動と結びつき、農薬に頼らない農作物作りの意識が高まっていった。
一方で、日本の場合は、50年代から、公害問題が次から次へと発生。
化学物質の健康への影響が懸念。農薬や化学肥料に頼らない安全な農作物を求める声が叫ばれ、化学物質に頼らないオーガニックへの意識が高まった。

さて、日本国内で「有機農産物」として出荷し、販売していくためには、JAS規格による検査が必要となる(実は、「有機農業の推進に関する法律」の前に規格が作られた)。
例えば、
1)堆肥等で土作りを行い、種まき又は植付前の2年以上 化学合成肥料及び農薬の不使用を基本として栽培
2)種子や苗は、原則、有機のものを使用
3)組換えDNA技術の利用や放射線照射を行わない
4)一般製品との混合、薬品等からの汚染がないよう管理
といったことが、認定に定められている。
驚いたのは、農薬にもJAS規格があることだ。農産物に重大な損害が生ずる危険があり、農薬の使用以外には効果的な防除ができないケースの場合には、有機農産物の生産をする中でも使うことのできる農薬が定められている。実に、約40種類が知られている(「有機農産物の日本農林規格」、別表2参照)。
このように日本では有機栽培に一部の農薬を使うことができるため、
「有機栽培」は必ずしも「無農薬栽培」とは限らない。

さて、オーガニックの普及度を見ると日本は予想以上に低い。
例えば、農林水産省の調査(「平成30年4月「有機農業の事情」の報告書」参照))によると、
1)日本では、有機農業の面積割合は0.2%に過ぎない(イタリア:14.5%、ドイツ:7.5%、フランス:5.5%)。
2)日本のオーガニックの市場規模は、1,500億円(欧州:3.7兆円、米国:4.7兆円)
等。
欧米は継続的に農作物を得るため、日本は公害問題への対処で消費者からの要望で安全な農作物が求められることも普及率に影響を与えている可能性がある。
駆け足で、オーガニックについて紹介した。遺伝子組み換え作物については別途紹介したい。