【B#224】ジェラスフリーに生きるとは何か〜ソーシャルメディアの時代に揺れる嫉妬心との向き合い方
Table of Contents
はじめに
こんにちは、渋谷でロルフィング・セッションや脳科学をベースにした講座を提供している大塚英文です。
今回ご紹介したい一冊は、清川永里子さんの「人生がうまくいく人のジェラスフリーな生き方: 妬みを手放し、自分の幸せに気づく感情の整理術 」だ。感情の中であまり注目されてこなかった「嫉妬」を正面から扱い、その乗り越え方を提示している点が興味深かった。
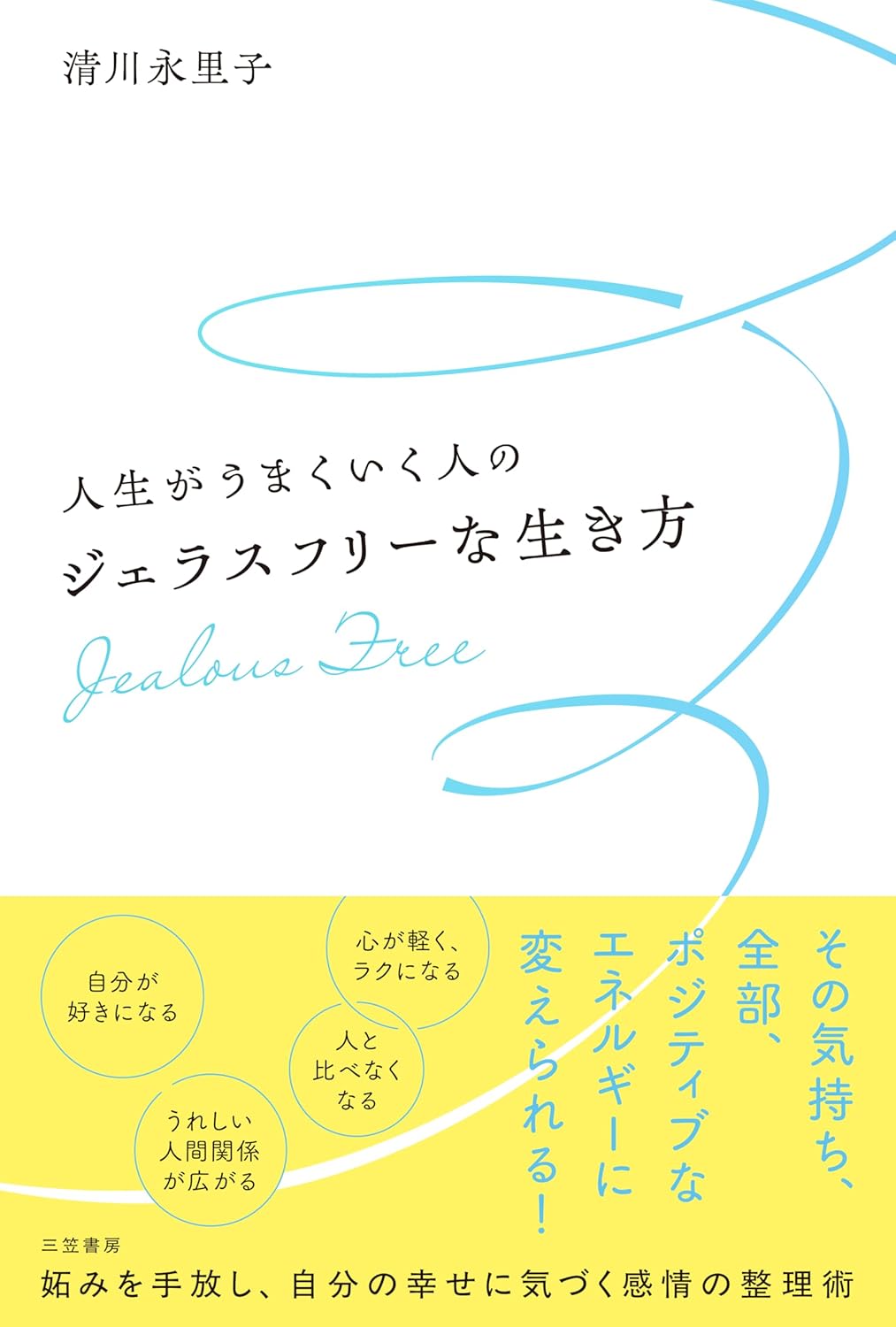
そこで、今回はこの本を通じて、妬みの心について考えてみたい。
ソーシャルメディア全盛の時代、人生の満足度は低下している?
ソーシャルメディア(Facebook、X(旧ツイッター)、Instagram、Tik-Tok)で、誰もが自分を発信できる時代。便利な一方で、私たちは日常的に他人の成功や旅行、恋愛、ライフスタイルを目にし、知らず知らず比較させられる状況に置かれる。
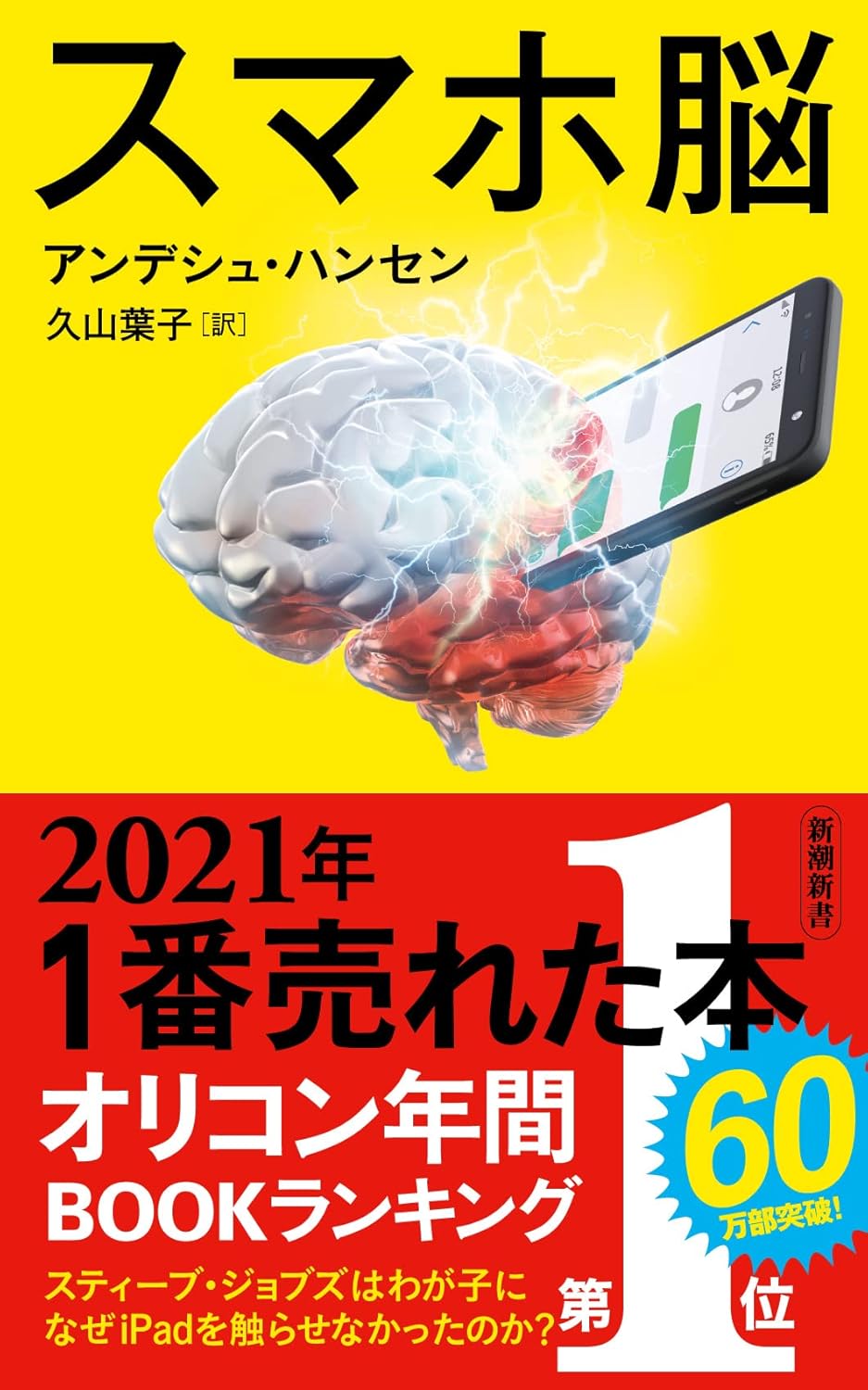
アンデシュ・ハンセンの「スマホ脳」では、SNSを通じた比較の弊害について次のように指摘している。
SNSを通じて常に周りと比較することが、自信を無くさせているのではないか。まさにそうなんだ。Facebookとツイッターのユーザーの3分の2が「自分なんかダメだ」と感じている。何をやってもダメだーだって、自分よりも賢い人や成功している人がいると言う情報を常に差し出されているのだから。特に、見かけは。
10代を含む若者1500人を対象とした調査では、7割が「インスタグラムのせいで自分の容姿に対するイメージが悪くなった」と感じている。20代が対象の別の調査では、半数近くが「SNSのせいで自分は魅力的ではないと感じるようになった。
このように「比較」を余儀なくされる。これこそ「嫉妬心」が芽生えるのだ。
「妬み」は他人との比較から始まる
今回紹介する本の著者は、
「妬みは自分を誰かと「比べる」ことから始まります」
と指摘した上で、
「アメリカの社会心理学者フェスティンガー(1919年〜1989年)は、もともと人間には自分の能力を正当に評価したいという動機があり、それを満たすために人と比較するといっています。まだ、比べる相手は、自分と似た人が選ばれやすい傾向にあるともいってます」
の時に「妬み」が生じると指摘している。
そして、この比較に関しては、
- 上方比較:自分より望ましい状態にある人と比較する
- 下方比較:自分よりも下だと感じられる人と比較する
の2種類があり、妬みで苦しくなると、著者の経験(私もそうだが)、人は上方比較していることが多いと感じるそうだ。
では、どのように「妬み」の感情について向き合ったらいいのか?そして「妬み(Jealous、ジェラス)」から自由になる=ジェラスフリーの生き方をしていくために、どのようにすればいいのか?
日常的にできることを本では紹介している。
ジェラス・フリーの心の整え方
妬まないメンタルに必要なこととして、10項目を挙げているが、その中でも
- まあいいかの精神を持っている(心の切り替えが上手い)
- 心の安全地帯を持っている(悩んでいる時に、聞いてくれる人がいるか)
- 打ち込める何かがある(オタク気質は人のことを気にしている暇がない)
- 持ち物に自分だけのこだわりがある(身につけるものに自分がご機嫌でいられる)
このような意外と見落としがちな習慣が「妬まない」心の整え方に役立つと言うことは、非常に面白く思った。
軸を持って生きると、人に振り回されなくなる
この本の中で最も印象的な箇所は、「軸をもって生きる」と指摘した箇所だった。その軸を持つと周囲の意見に振り回されることがなくなるからだ。
具体的には、
- 自分はどう生きたいのか
- どういう人間になりたいのか
- 自分の考える最善とは何なのか
この3つを明確にすること。これらを明確になっていると、人に何を言われても「あなたの考えはそうなんですね、でも、私の考えと生き方は違う」と振り回されることがなくなるという。
いつでも、戻れる自分の軸を言語化し、明確にすること。ジェラス・フリーの生き方の一つの大きな秘訣を見た感じがする。
キリスト教で「愛」の反対は、「憎しみ」ではなく「妬み」
実は「妬み」の感情で、最も印象的に語った一冊の本がある。土居健郎著・渡部昇一著の「いじめと妬み: 戦後民主主義の落とし子(現「いじめ」の構造)」だ。

平成のいじめ問題を背景に、過度な平等主義が嫉妬心を助長することを指摘している。その本の中で、興味深ったのは、キリスト教の「嫉妬」に対する考え方だ。
キリスト教では、「愛の反対は憎しみではなく妬みである」と著者の一人渡部昇一さんが指摘している。妬みは人間存在の根源的な感情であり、聖書の中でもカインとアベルの物語をはじめ数多く描かれてきた。キリスト教は妬みを「罪」として厳しく戒め、信仰や共同体生活を通してその破壊的力を制御してきたらしい。
愛の反対は、妬み。清川さんの本を読んでいると、この視点がより理解できたと感じる。
まとめ
ソーシャルメディアが身近になった現代、私たちは日々「比較」にさらされ、嫉妬心を抱きやすい環境に生きている。けれども、嫉妬は単なる負の感情ではなく、「自分が何を欲しているのか」を映し出す鏡でもある。
嫉妬を正面から受け止め、
- 「まあいいか」の精神で切り替える
- 安心できる関係や打ち込める活動を持つ
- 自分の軸を明確にする
こうした実践を重ねることで、嫉妬に縛られず、ジェラスフリーに生きることができる。
「愛の反対は憎しみではなく妬みである」という言葉の重みを胸に、嫉妬を敵にせず、自分を知るためのサインとして受け止めてみてはいかがでしょうか。
ぜひ「妬み」について深掘りしたい方には、本をお勧めしたい。






