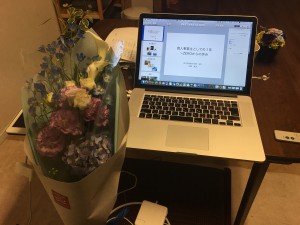【B#222】ウィーン精神と横断的知の交差点──エリック・カンデル『The Age of Insight』を読む
Table of Contents
はじめに
こんにちは、渋谷でロルフィング・セッションや脳科学をベースにしたコーチングを提供している大塚英文です。
19世紀末から20世紀初頭のウィーンは、ハプスブルク家が支配するオーストリア=ハンガリー帝国の首都であり、ヨーロッパ有数の文化的交差点だった。
私も、10年前(2014年7月〜2015年6月)世界一周したとき、旧オーストリア・ハンガリー帝国の都市(ウィーン、ブタペスト、プラハ)を訪れ、その街の雰囲気に魅了された。
旧帝国内にはドイツ系、ハンガリー系、スラブ系、ユダヤ系など多様な民族・宗教が共存し、その複雑な政治的・社会的緊張が「アイデンティティとは何か」「人間とは何か」という根源的な問いを人々に突きつけられたのでしょう。
一方で、宮廷の庇護とブルジョワ階級の台頭により、芸術・音楽・文学・科学が活発に発展。こうした多層的背景のもとに形成された独自の文化的雰囲気を「ウィーン精神(Viennese Modernism)」と呼ばれた。
このウィーン精神の大きな特徴は、知的サークル(ドイツ語で「Kreis(クライス)」)にあった。芸術家・科学者・哲学者・文学者がコーヒーハウスやサロンに集い、専門の垣根を越えて議論を交わしたことで、学問が過度に専門分化するのを防ぎ、横断的かつ創造的に発展することを可能にしたのである。
ウィーン出身のノーベル賞受賞神経科学者エリック・R・カンデル博士の著書 The Age of Insight (邦訳:「芸術・無意識・脳」)は、この「ウィーン精神」を軸に、芸術と科学の革新を鮮やかに描き出している。
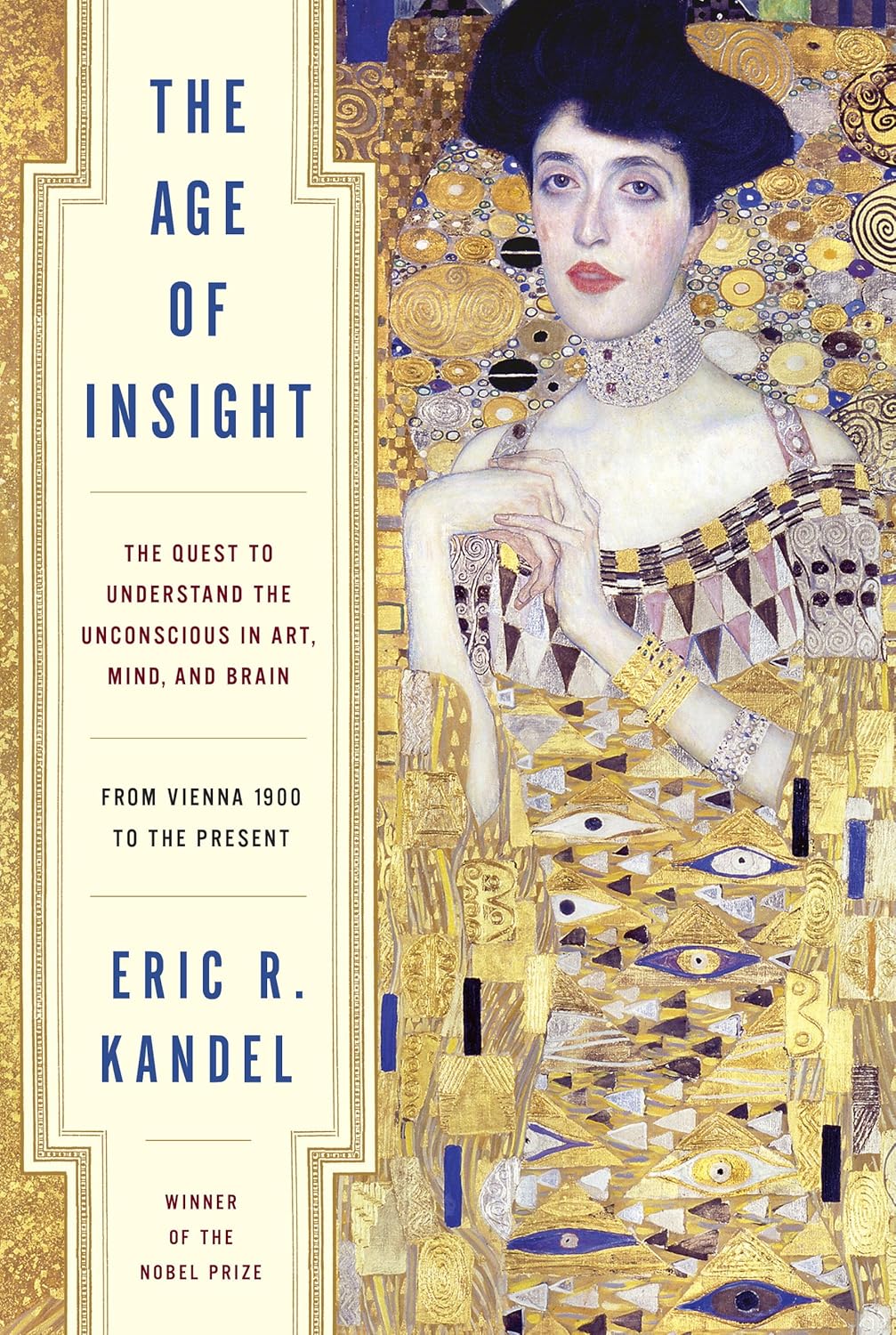
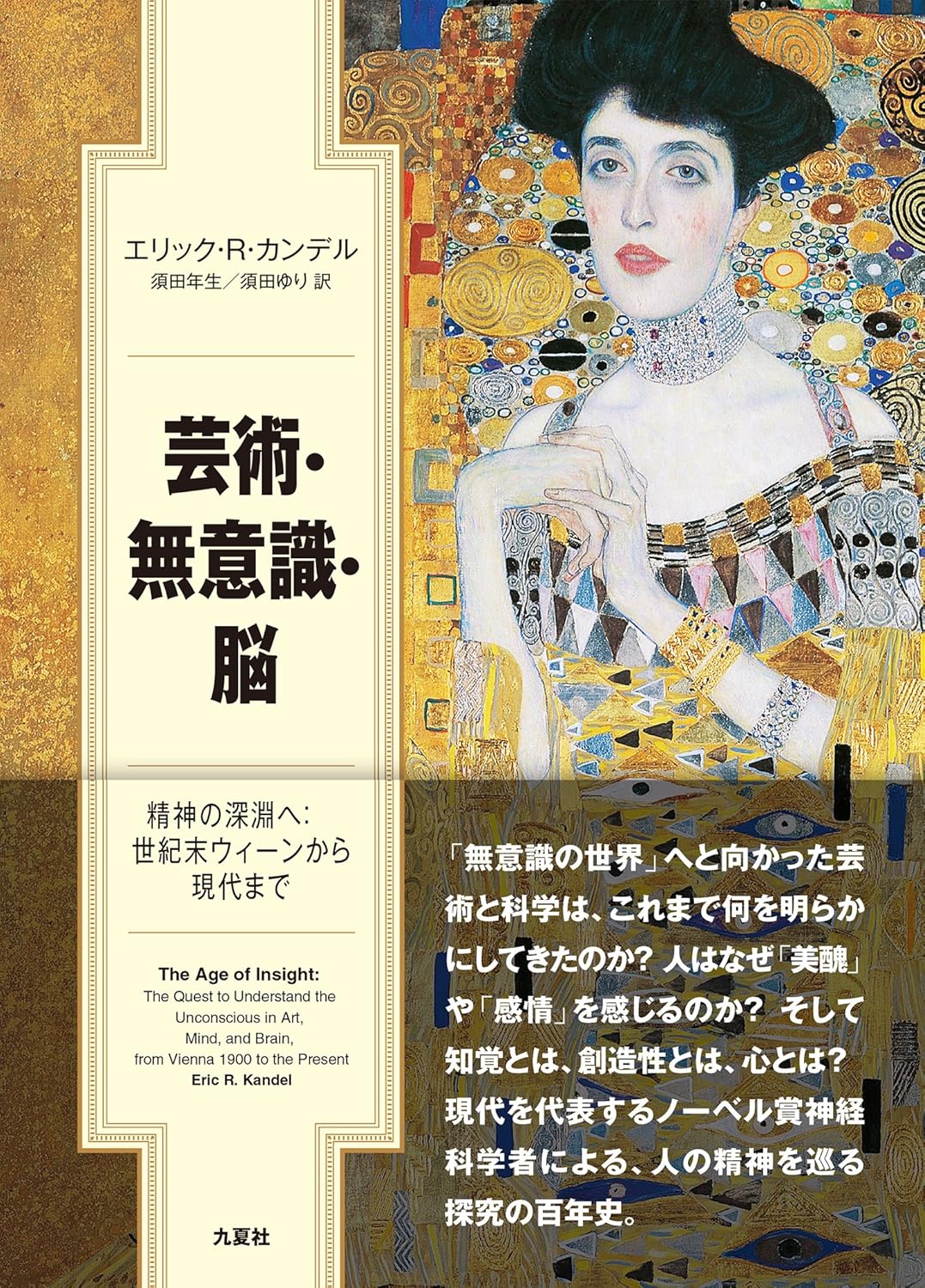
今回は、この本の内容を中心にご紹介させていただきたい。
クリムトとフロイト──無意識をめぐる対話
グスタフ・クリムトの装飾的で官能的な絵画は、人間の深層心理を探るフロイトの精神分析と呼応した。両者に共通していたのは、「表面的な美や理性を超えて、人間の無意識に迫る」という姿勢にある。
エゴン・シーレやオスカー・ココシュカもまた、人間の不安や欲望を赤裸々に描き出し、芸術を通じて「心の深層」を表現する試みを行った。
科学と哲学──相対性理論とウィーン学派
同じ時代に、アインシュタインは相対性理論によって「時間と空間の絶対性」を揺るがした。これは単なる物理学の理論ではなく、人間が世界をどのように理解するかという哲学的パラダイムをも揺さぶる革新だった。
アインシュタインと知的サークル
鈴木理著の『分子生物学の誕生』によれば、若き日のアインシュタインはETH(スイス連邦工科大学)の学生時代、多様な政治的・民族的背景をもつ学生に囲まれていた。スラブ系の同級生ミレヴァ・マリッチは彼の最初の妻となり、後にドイツへの移住を拒んだことでも知られる。
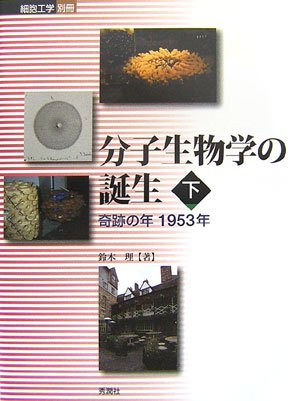
ベルン特許局時代には、哲学科のモーリス・ソロヴェーヌ、数学科のコンラート・ハビヒトとともに「アカデミー・オリンピア」を結成し、マッハやボルツマンの論文を読み議論を重ねた。このようなサークル(「クライス」)活動は、後の特殊相対性理論に至る重要な知的刺激となった。
ヨーロッパ各地に存在した「クライス」の中でも最も影響力をもったのが、ウィーン大学のシュリックを中心としたウィーン学派である。彼らは論理実証主義を掲げ、数学・物理学・論理学を基盤に学問を統一的に再編成することを目指した。
1921年、アインシュタインがプラハを再訪した際、後任教授でありウィーン学派の一員でもあったフィリップ・フランクとともにコーヒーハウスを巡り、その文化的雰囲気を楽しんだことも知られている。
マッハの影響
アインシュタインは直接的にウィーン学派のメンバーではなかったが、エルンスト・マッハの著作を青年期から熱心に読み、絶対的な時間・空間観を疑う視点を得ていた。
マッハ的経験主義と懐疑精神が、相対性理論を生むための知的土壌を与えたと言える。後にウィーン学派はアインシュタインの理論を哲学的に支持し、論理実証主義を展開していった。
ゴンブリッチの役割──芸術と知覚の科学化
エルンスト・H・ゴンブリッチ(Art and Illusion の著者)は、ウィーン精神を継承しつつ、芸術を「人間の知覚と認知のプロセス」として捉え直した。彼は「芸術とは外界を模倣するのではなく、知覚の習慣と期待を操作するものだ」と述べ、芸術表現を科学的知覚論の一部として分析した。
カンデルはこの視点を神経科学と結びつけ、本では、脳の働きと芸術体験の関係を明らかにした。
脳科学とアートの未来
カンデルは、現代の神経科学を通じて「人間が芸術をどのように体験するのか」を解説する。クリムトの作品を鑑賞する時、単に形や色を認識するのではなく、記憶や感情、無意識的連想が呼び起こされる。ゴンブリッチの「知覚の科学」とカンデルの「神経科学的解明」は、この点で響き合う。
おわりに
The Age of Insight は、ハプスブルク帝国の多様な文化的基盤と知的サークルの伝統から生まれた「ウィーン精神」を背景に、芸術と科学の豊かな対話を描き出す。そこには、クリムトの官能的な絵画、フロイトの無意識の探究、アインシュタインの理論とマッハの影響、ウィトゲンシュタインの哲学、そしてゴンブリッチの知覚論が重層的に絡み合っている。
ウィーンの知的サークルが示すように、芸術も科学も「専門の垣根を越えて交わる場」があってこそ、人間とは何かを深く探求できる。芸術と科学を切り離さず、人間理解のために統合する──その挑戦が今もなお続いていることを、この本は教えてくれる。