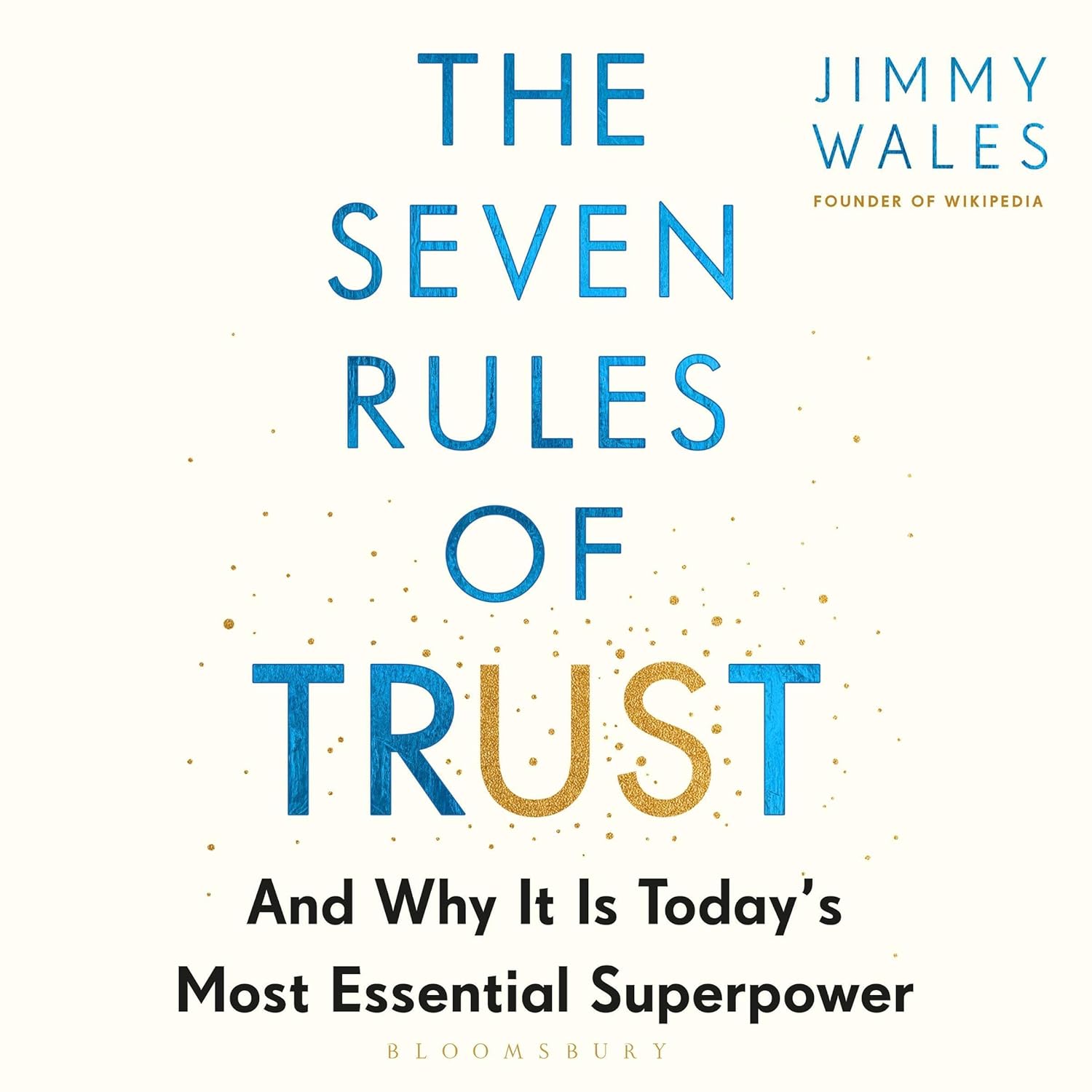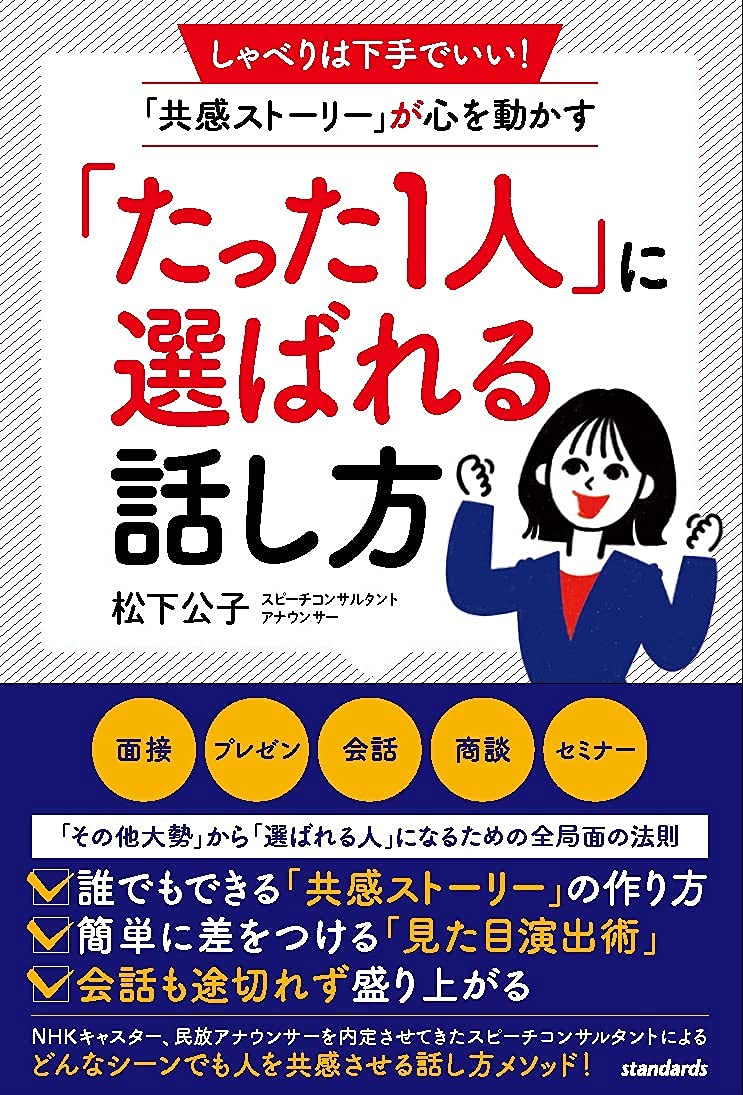【B#212】共感から始まる世界──山口一郎・野中郁次郎『直観の経営』に学ぶ現象学のエッセンス
Table of Contents
はじめに
こんにちは。渋谷でロルフィング・セッションや脳科学ベースの講座を提供している大塚英文です。
2025年に読んだ本の中でも、とりわけ印象深かった一冊が、山口一郎さんと野中郁次郎さんによる共著『直観の経営──共感の哲学で読み解く動体経営論』である。
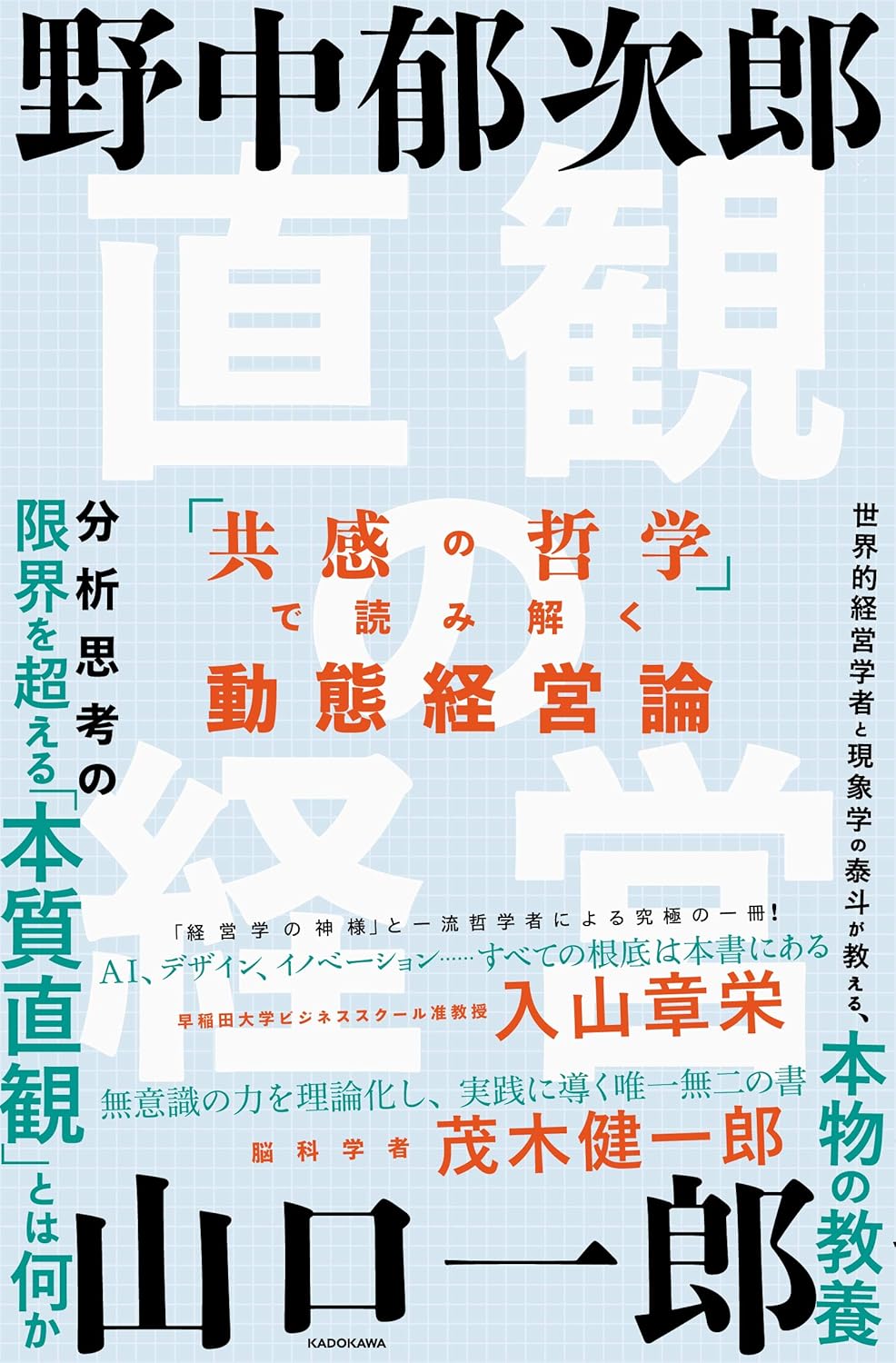
以前のブログ記事で、経営理論との接点や暗黙知の知識創造についてまとめたが、今回はその続編として、現象学の哲学的な視点そのものに焦点を当てて掘り下げてみたい。
「共感」の哲学から世界は始まる
現象学とは、「世界がいかに私たちに現れるか(phenomena)」を問う哲学である。エトムント・フッサール(Edmund Husserl)によって体系化され、モーリス・メルロー=ポンティ(Maurice Merleau-Ponty)によって身体や感覚の観点からさらに深められた。
この思想は、客観世界を前提にするのではなく、主観的経験の側から世界を見つめ直す。
たとえば、赤ちゃんがこの世界をどうやって理解するのかを考えてみよう。赤ちゃんにとって、世界は最初から「確かなもの」としてあるわけではない。むしろ、誰かとの「あたたかさ」や「肌の感触」「声のトーン」といった共感の経験を通じて、「この世界は信頼できる」と感じることから始まる。
これは、フッサールが『ヨーロッパ諸学の危機と超越論的現象学』で語った「主観から世界が立ち上がる」という構造にも通じる。すなわち、客観から主観は生み出せないが、主観から客観は生み出すことができるという逆転の発想である。
「時間的契機」とは何か?
現象学における「時間的契機(temporal moment)」とは、時間を単なる「過去・現在・未来」という直線的な流れとしてではなく、「経験の中でどのように現れているか」という観点から捉えたときの、時間の“構成要素”としての働きを指す。
私たちの意識は、今だけを感じているのではない。たとえばメロディーを聴いているとき、今鳴っている音だけではなく、すでに鳴った音(過去)やこれから鳴るだろう音(未来)を含んだ“全体”を聴いている。
つまり、時間とは、「今」だけでは成立せず、「過去」「現在」「未来」が一体となって経験の厚みを構成しているのである。
フッサールはこの時間の構造を、以下の三つの時間的契機として理論化した。
- 過去把持(retention)
- 現在(primal impression)
- 未来予持(protention)
三つの時間的契機──過去・現在・未来の重なり
過去把持とは?
今この瞬間に現れている経験に対して、すぐ直前の出来事が“背景”として残り続けている状態。たとえば、音楽を聴いているとき、前の音が完全に消えることなく、今の音と結びついて旋律としてまとまる。この「聞き取り済みの過去」が現在に保持されているのが過去把持である。
現在とは?
点としての「今」ではなく、過去の余韻を保持しつつ、次に起こることを予感しているという、厚みのある「今」。現象学では、過去と未来が重なり合って構成される“持続の現在”を重視する。
未来予持とは?
次に何が起こるかを先取りして構え、予期している意識の働き。会話の中で相手の言葉の続きを自然に予想する、リズムに合わせて体を動かすといった経験が該当する。
この三つの契機は、個別にバラバラではなく、絶えず流動的に連続し、現在という経験のなかに同時に含まれている。
時間構造の例──電車と野球の「今」
山口・野中の両氏は、この時間構造を理解するために次のような例を紹介している。
電車の急ブレーキ
電車が急に止まったとき、「なぜ止まったのか?」という問いが浮かぶが、そのとき私たちは、直前の加速・減速やアナウンスといった背景情報を無意識に保持している。これは過去把持が現在の経験に混ざっていることを示している。
野球の打者
プロ野球のバッターは、ボールが届く前にバットを振り始めている。これは未来を予期しているからこそできる直観的な行動である。完全にボールを見てからでは間に合わない。予持があるからこそ、動きが“今”に間に合う。
このように、私たちの行動や判断は、常に過去と未来が織り込まれた時間の中で行われている。
志向性と本質直観
現象学では、「意識は常に何かを意識する」性質、すなわち志向性が基本的な前提である。私たちはただ反応するのではなく、常に「意味」を志向して世界に向かっている。
その意味で、感覚とは「受け身な反応」ではなく、「世界との関係性において意味を立ち上げる活動」である。
たとえば、誰かの涙を見て胸が締めつけられるように感じるとき、それは単なる視覚的刺激ではなく、意味のある出来事として共に感じているのである。これがメルロ=ポンティのいう「感覚の本質は共感にある」ということだ。
受動的意識と能動的意識──私の選択はどこから始まるのか?
フッサールは、意識の成り立ちを「受動的意識(passive synthesis)」と「能動的意識(active synthesis)」に分けて論じた。
- 受動的意識:意図せず与えられた感覚や意味のまとまり。音楽の旋律や誰かの表情、風景の印象など。
- 能動的意識:私が意図的に行う判断や解釈、行動の選択。
脳科学者ベンジャミン・リベットの実験では、意識的に「手を動かそう」と思う前に、すでに脳内では運動準備が始まっていたという結果が得られている。つまり、自由意志による行動のように思えても、その多くは受動的な構造の中から自然に立ち上がってくる。
現象学と経営──感じる経営へ
『直観の経営』は、経営を「感じて動くこと」として捉え直す提案である。計画やKPI、数値といった三人称の枠組みに頼るのではなく、現場の身体感覚や直観、関係性に根ざした意思決定を重視する。
感じる力が経営の中核となるというこの視点は、ロルフィングやコーチングの実践とも共鳴する。共感、直観、動きは、一人称と二人称の関係から立ち上がる経験であり、そこにこそ意味と創造性の源がある。
おわりに──世界は共感から立ち上がる
世界はすでにそこにあるのではなく、「私」と「あなた」の関係の中で生成されている。そしてその中心にあるのが、共感という働きである。
『直観の経営』は、現象学・共感・身体性といったテーマを、組織やリーダーシップの文脈と見事に結びつけている。知識は頭の中で生まれるのではない。世界とどう関わるかという感覚の質によって立ち上がる。
以前のブログ記事では、アメリカ海兵隊やトヨタ、ホンダなどの事例を交えて、より実践的に紹介しているので、ぜひあわせてご覧いただきたい。