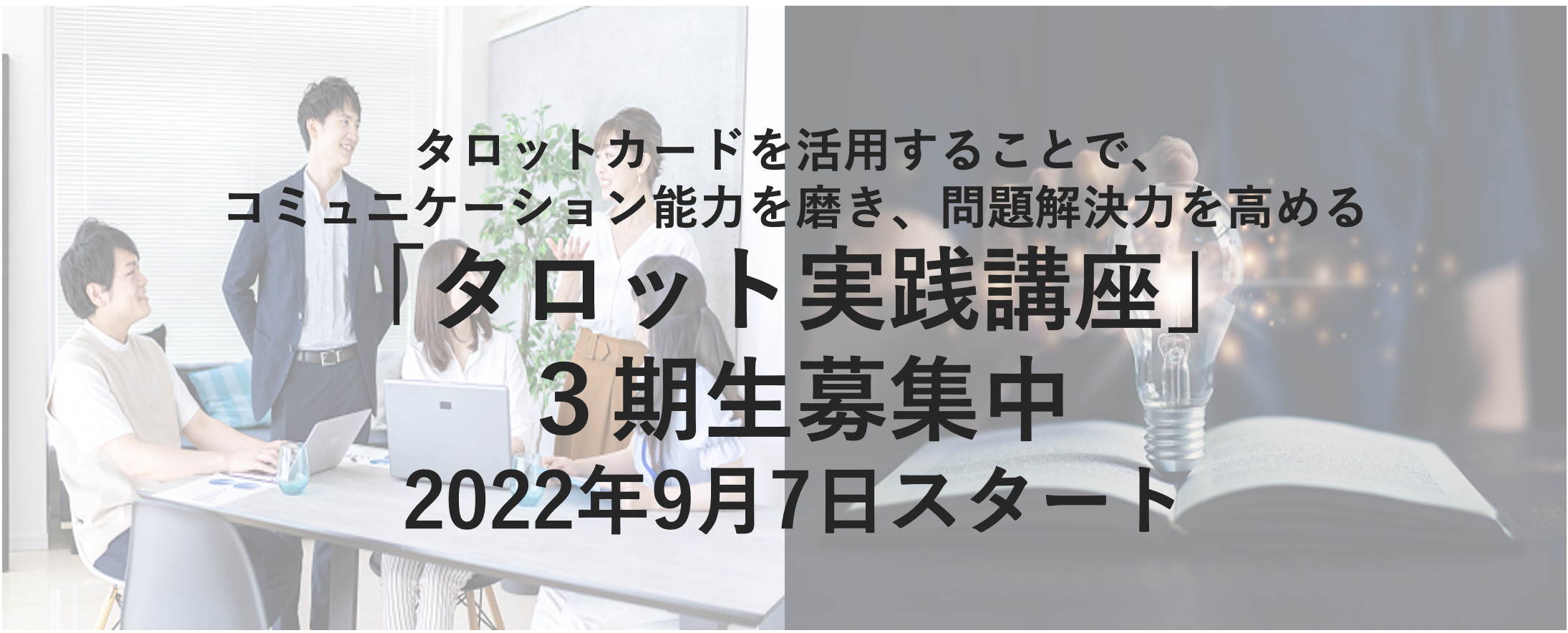【B#207】現象学と経営──共感・関係性・感覚から知識創造を捉え直す
Table of Contents
はじめに
こんにちは、渋谷でロルフィング・セッションと脳科学に基づいた講座を提供している大塚英文です。
2025年に読んだ中で、特に印象的だった本のひとつが、野中郁次郎さんと山口一郎さんの共著『直観の経営──共感の哲学で読み解く動体経営論』だった。
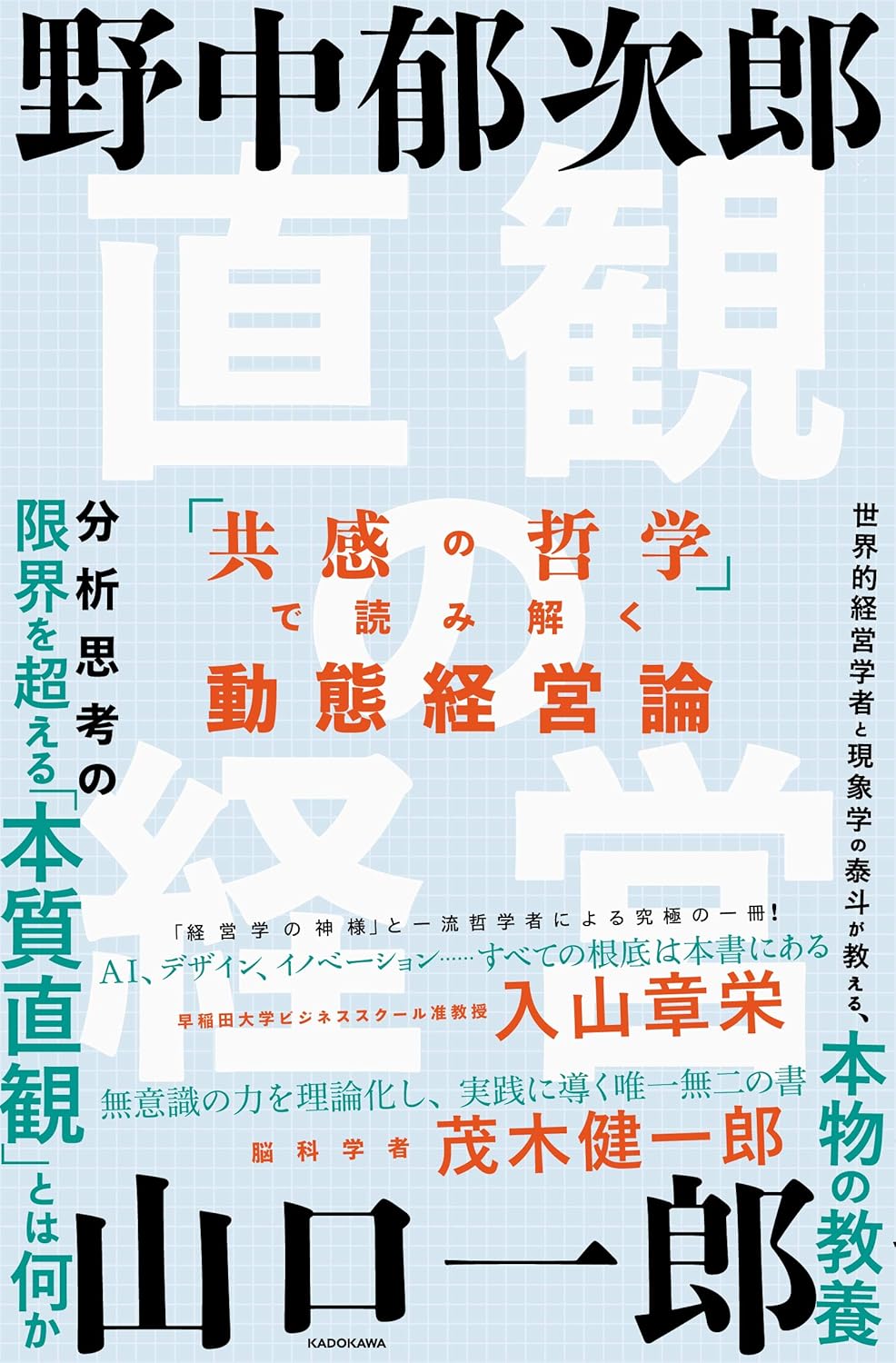
現象学と会社経営との接点
なぜ、面白かったか?というと、難解でなかなか捉えきれない「現象学(Phenomenology)」を噛み砕いてわかりやすく説明しているのみならず、会社経営を例え話で語っていることだ。
しかも、この本は、経営や組織論において常識とされてきた「計画」「分析」「KPI重視」といった合理主義的アプローチを根底から問い直し、現象学・共感・身体性・暗黙知を軸とした“知の動態論”へと新たな視点へと我々を誘ってくれている。
本記事では、「現象学とは何か?」「共感と知識創造はいかに結びつくのか?」「感覚・言語・概念はどのように働くのか?」を中心に、本書で取り上げられているアメリカ海兵隊・京セラ・トヨタ・ホンダの事例も交えながら、より実践的に理解を深めてみたい。
現象学とは何か?──“感じている世界”から始まる認識論
現象学とは、「主観」と「世界」との関係性に注目し、その交点において“意味がいかに生成されるか”を探る哲学的アプローチである。20世紀初頭、エトムント・フッサールによって体系化されたこの思索は、「世界を客観的に分析する」態度とは異なり、「私という主体が、どのように世界に出会い、経験し、意味づけているのか」を問い直す。
たとえば、ある部屋に入って「寒い」と感じたとする。その感覚は、温度という客観的データではなく、空間の中に身体をもって存在するという主観的経験=関係性そのものに根ざしている。私たちは世界にただ向き合うのではなく、世界との関わりの中で意味を編み出している。
現象学は、こうした“生きた経験”における意味を作り出すのプロセスこそが、知の出発点であると主張する。
感覚=共感である──メルロ=ポンティの身体的知覚論
フッサールの弟子筋にあたるモーリス・メルロ=ポンティは、現象学を「身体」へと開いた。彼はこう述べている。
「感覚の本質は共感にある(La sensation est essentiellement empathie)」
これは、感覚とは単に刺激を受け取るものではなく、他者や世界と“共に感じる”運動そのものであることを意味している。
たとえば、人が涙を流しているのを見たとき、自分の胸が締め付けられるような感覚を覚えることがある。このような身体レベルでの共鳴こそが“共感”の本質であり、私たちはその共感的な基盤の上に言語や論理を築いているのである。
概念・言語とは何か?──感覚を輪郭づける道具
私たちは日常的に「考える」とき、言葉や概念を用いる。しかし現象学の立場では、言葉や概念は“最初にあるもの”ではなく、むしろ「感覚・経験の流れを切り取り、固定するための装置」として捉えられる。
言語は“伝える”ための道具である前に、共に世界を捉えるための“型”である。メルロ=ポンティにとって、言葉とは「身体が意味を形づくる運動」なのであり、世界はまず“身体で感じられ”、そののち“言葉になる”のだ。
知識は論理から生まれるのではなく、感覚の世界に身を置くこと=共感的に存在することから始まる。これが、暗黙知と知識創造をつなぐ重要な鍵である。
暗黙知と直観──知識はどこから生まれるのか?
野中郁次郎氏が提唱する「知識創造理論(SECIモデル)」では、暗黙知→形式知への変換プロセスが中心である。本書では、その出発点として「共感」「感覚」「直観」といった、従来の経営学では扱われにくかった領域が重視されている。
暗黙知とは、明文化・数値化されていない、身体的・経験的・情動的な知である。たとえば、ベテラン整備士が機械の異常を「音」で察知するような知覚。あるいは、職人が材料に触れた瞬間に“良し悪し”を判断する感覚。これらは論理的に説明できないが、確かに働いている知のかたちである。
こうした直観的知覚は、組織の中で共感と対話を通して共有されてはじめて、知識としての価値を持ちはじめる。
事例1:アメリカ海兵隊──「判断」を現場に預ける組織知
本書で紹介される事例のひとつが、アメリカ海兵隊である。海兵隊では、作戦中の現場判断をトップダウンではなく、最前線の兵士一人ひとりの“直観と状況判断”に委ねる文化が確立されている。
これは「分散型の直観的意思決定」であり、極限状態での意思決定には、即時的な感覚と関係性の認識が不可欠であるという前提に立っている。ここでは、「形式知による計画」よりも、「身体で感じ、共感によって共有された状況認識」にこそ、勝機があるとされている。
まさに「感覚の本質は共感にある」というメルロ=ポンティの哲学が、実践の中に根を下ろしている例である。
事例2:京セラ──アメーバ経営と関係性の知
京セラの「アメーバ経営」は、野中郁次郎氏が高く評価している知識創造型組織の代表例である。この経営手法では、数人単位の小集団(アメーバ)が、自律的に行動し、現場での対話と試行錯誤を重ねることで経営の単位となる。
重要なのは、ここでの知識が「上から与えられるもの」ではなく、現場にいる者同士の“関係性”の中から生まれているという点である。メンバー同士が互いの判断・感覚・目的を共有し、「共に感じ」「共に動く」ことで、暗黙知が浮上し、組織全体の意思決定力が高まっていく。
事例3:トヨタの現場──“見る”ではなく“感じる”現場力
トヨタ生産方式においては、「現地・現物」「五感で捉える」「カンバン方式」など、身体的な経験を重視する知の文化が根づいている。
たとえば、「なぜ5回問う(なぜなぜ5回)」という改善プロセスは、単なるロジックではなく、現場に“身を置き”、そこで起きていることを“感じ取り”、問題の本質を体感的に理解するための問いである。
トヨタの現場では、マニュアルに書かれた「正解」よりも、その場の人間が“肌感覚”で判断し、共に考え、動くことが重視されている。これも、現象学的・共感的な知の実践例として非常に示唆深い。
事例4:ホンダ──「三現主義」と“手を動かす知”
ホンダの創業精神に根づいているのが、「三現主義(現場・現物・現実)」である。これはトヨタにも通じるが、ホンダでは特に「自分で見て、自分で手を動かして、自分で考える」という実践知の姿勢が徹底されている。
本田宗一郎は「失敗からしか学べない」と語り、実際に技術者が手で部品を削り、自らの手応えから「何かがおかしい」と直感するような暗黙知を重視した。そこでは感覚・経験・共感に支えられた現場的判断が、エンジニアリングの創造性の源泉となっている。
ホンダの製品開発がユニークで革新的であり続ける背景には、このような身体知に基づく判断を信頼する文化がある。これもまた、直観の経営の優れた実践例である。
デカルト的世界観との違い──「分離」から「あいだ」へ
近代的な思考、特にデカルト的な認識論では、**「心と身体」「主観と客観」「自分と他人」**が切り離されている。だが現象学では、すべての経験は関係性の中にある。
知識とは、データでも分析でもない。それは「つながり」のなかでしか生まれない。だからこそ、「共感」や「身体性」が不可欠なのである。これは、ロルフィングやコーチングにおける“触れる”“感じる”“共にいる”という在り方とも重なり合う。
結論──“共感する身体”から始める知識創造
『直観の経営』は、共感と現象学の視点から「知ること」「感じること」「つながること」を再定義している。それは単なる経営戦略の話ではない。私たちの身体、感覚、関係性に根ざした知の哲学である。
アメリカ海兵隊、京セラ、トヨタ、ホンダといった事例は、いずれも「共感する身体」がいかに実践的な知の源泉であるかを示している。本書が描く“動体経営論”とは、混沌と不確実性のなかで生きる現代のリーダーや実践者にとって、極めてリアルで、実践的な知のあり方であると感じている。
知識は頭の中で生まれるのではない。それは、「世界とどう関わるか」という感覚の“質”によって立ち上がると言っていい。