【B#205】“普通”が人を病ませるとき──Gabor Matéの「The Myth of Normal」から学ぶ
Table of Contents
はじめに
こんにちは、渋谷でロルフィングと脳科学ベースの講座・セッションを提供している大塚英文です。
今回は、Gabor Maté著 The Myth of Normal: Trauma, Illness, and Healing in a Toxic Cultureの内容ついてご紹介させていただきたい。
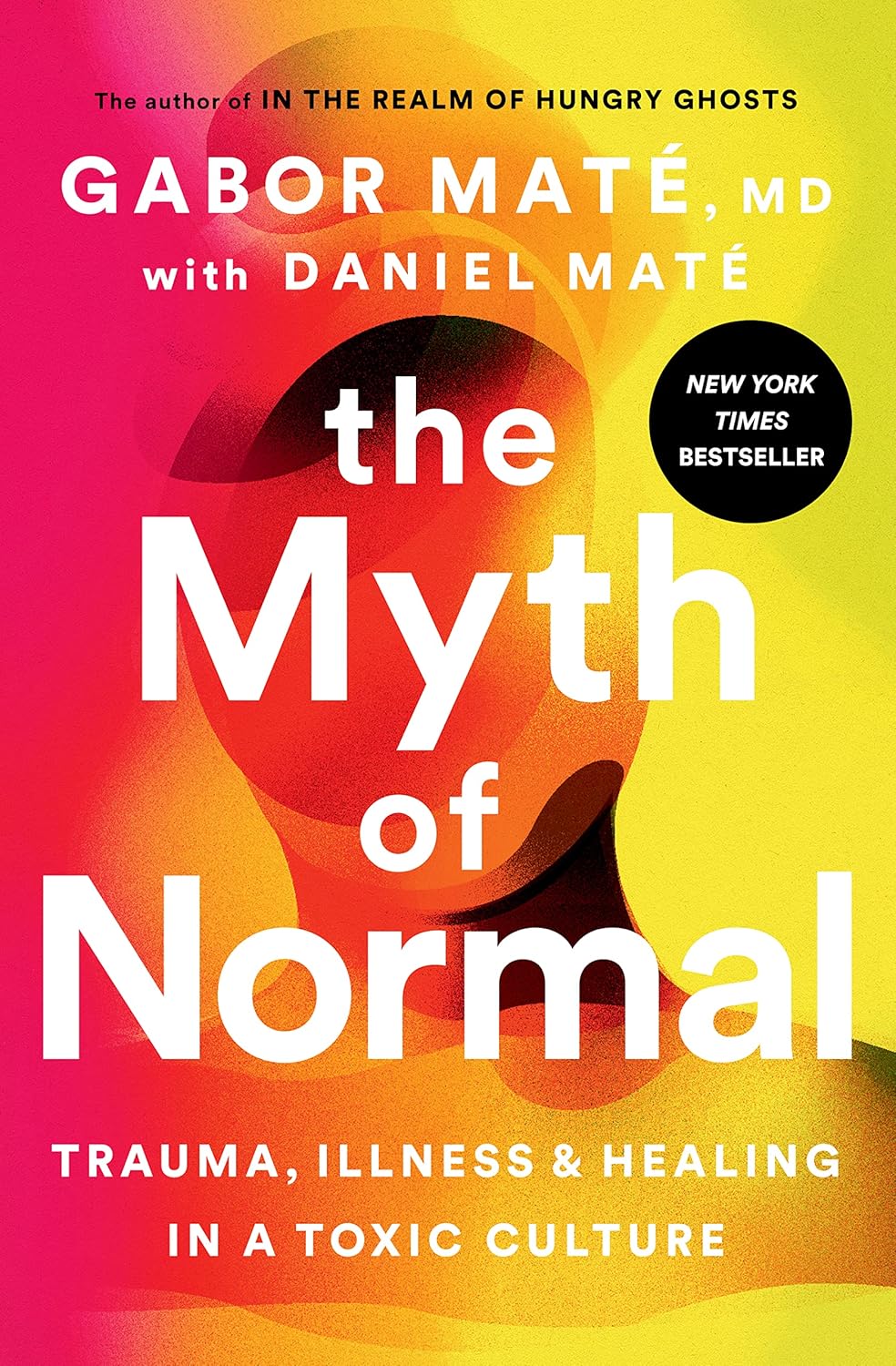
「健康」や「正常」とは誰が決めるのか?
「「普通に働き、普通に感情をコントロールし、普通の家庭を築く」──こうした“普通”という概念は、現代社会において人々が目指す理想とされがちである。しかし、Gabor Maté は、この「普通」という考え方自体に疑問を投げかけている。
“In a society that is fundamentally abnormal, the concept of ‘normal’ is itself a lie.”
「そもそも異常な社会において、“普通”という考え自体が嘘なのである。」
現代社会は、成果主義や競争、感情の抑制を重んじる構造の中にある。そのような環境で生き延びるために人は、自分の本当の気持ちや体の感覚を押し込め、「普通らしく」ふるまおうとする。その結果として、心身のバランスが崩れ、不調や病気となって現れる場合があるというのが、Maté の問題提起である。
「Normal(正常)」という神話
人はしばしば「怒ってはいけない」「弱さを見せてはいけない」「いい人でいなければならない」と思い込み、それを「成熟した大人のふるまい」と捉えている。しかし、そのような価値観に無理に適応し続けることで、内面的な緊張やストレスが積み重なり、心や体に不調をもたらすことがある。
“What we call ‘normal’ is in fact the exaggerated stress of striving to meet expectations that are themselves pathological.”
「“普通”とされている状態は、実のところ、病的な期待に応えようとする過剰なストレスにすぎない。」
つまり、「普通であろうとする努力」そのものが、健康を損なう要因となっている可能性があるということである。
病気は体だけの問題ではない
私たちは病気を、「体のどこかが壊れたこと」として捉える傾向がある。しかし、Maté は、病気の背景には「心の状態」「人間関係」「社会環境」といった広い要素が関係していると主張する。
この考え方は、「生物・心理・社会モデル」と呼ばれており、以下の三つの視点で病気を捉えるものである。
生物的な側面:体の反応
ストレスが続くと、体は「コルチゾール」と呼ばれるホルモンを出し続ける。この状態が長く続くと、免疫力が下がり、眠れなくなり、内臓の働きにも影響が出る。長期的には、がんや自己免疫疾患といった深刻な病につながることもある。
心理的な側面:感情を抑えるクセ
慢性的な病気を持つ人には、「怒りを我慢する」「いつも人に合わせる」「自分の気持ちより相手を優先する」といった共通の傾向が見られる。こうした性格的な特徴は、実は子どもの頃に身につけた「安全に生きるためのクセ」であり、大人になってもそれを手放せず、結果としてストレスが積み重なるのである。
社会的な側面:文化の影響
成果を上げることが評価され、感情を見せることが「弱さ」とされるような文化の中では、人は自然な感情を抑え、自分の体の声を聞くことを忘れてしまう。Maté は、こうした文化そのものが「毒性のある社会(toxic culture)」であると指摘している。
トラウマと慢性病のつながり
Maté は、多くの慢性病の背景に「トラウマ」があると語る。ここで言うトラウマとは、大きな事故や虐待だけを指すのではない。
“Trauma is not what happens to you. Trauma is what happens inside you as a result of what happens to you.”
「トラウマとは、何が起きたかではなく、それによって“内側で何が起きたか”である。」
つまり、トラウマとは、自分の感情を切り離し、「感じないようにして生きる」ために身につけた反応である。そしてこの反応が長期間続くことで、体にさまざまな不調が現れるという。させる。結果として炎症、自己免疫、代謝異常、精神身体症(心身症)といった形で身体化する可能性が高まる。
トラウマはどのようにして形成されるのか?以下のように整理すると理解できると思う。
- 切断(Disconnection):身体感覚・情動・欲求・他者との結びつきが断たれる。
- 防衛的適応(Adaptive Response):痛みから守る短期戦略が長期には不健康要因となる。
- 凍結された時間(Frozen Present):過去体験の生理反応が現在でも再活性化する。
- 意識外記憶(Implicit Memory):言語化不能でも身体反応として残存する。
- 孤立と恥(Shame & Isolation):「自分だけがおかしい」という自己物語を形成する。
トラウマに関する5つの誤解(Five Myths about Trauma)
Maté は、トラウマを正しく理解するためには、まず「トラウマに関する5つの誤解」を解く必要があると述べている。
誤解①:トラウマとは「起きた出来事」のこと
Myth 1: Trauma is what happened to you.
実際には、出来事そのものではなく、それにどう反応したかがトラウマである。
誤解②:トラウマは特別な人だけが経験する
Myth 2: Trauma is rare and exceptional.
トラウマは誰にでも起こりうる普遍的なものであり、特別なことではない。
誤解③:トラウマは“悪い出来事”によってのみ起きる
Myth 3: Trauma only comes from bad things happening.
「あるはずのものがなかった経験」──たとえば、愛されなかった、守られなかったといった体験も、深いトラウマになりうる。
誤解④:トラウマは過去のもので、今は関係ない
Myth 4: Trauma is in the past.
トラウマは、今この瞬間の感じ方や行動、体の状態に影響を与え続けている。
誤解⑤:トラウマは心の弱さや病気の証拠
Myth 5: Trauma is a weakness or mental illness.
トラウマは「弱さ」ではなく、つらい状況の中で生き延びるために身につけた知恵である。
“Trauma is not a flaw or weakness. It’s a coping strategy that worked in the past, but now keeps us stuck.”
「トラウマは欠陥ではない。それは過去に役に立った“生き延びる方法”なのだ。
真の癒しとは何か?
Matéは治療(cure)と癒し(healing)を区別する。治療が症状軽減・機能回復を指す狭義の医療行為であるのに対し、癒しとは存在全体の統合として捉える。
“Healing is not the absence of symptoms, but the presence of wholeness.”
「癒しとは、症状がないことではなく、“自分らしさ”が戻ってくることである。」
Maté は、「癒し」を以下のようなプロセスとして語っている。
- 再接続(Reconnection):身体感覚・情動・自己受容に再び触れる。
- 境界と“No”の回復:自己を守るの意識が免疫機能にも反映する可能性。
- 関係的安全(Relational Safety):共感的他者との出会いが神経系の再調整を促進する。
- ソマティック実践:身体経路から凍結反応を解凍する(呼吸法、ボディワーク、トラウマインフォームド・タッチ等)。
トラウマ統合のプロセス概観
参考に、トラウマの統合は、下記のプロセスを通じて、人は少しずつ、本来の自分を取り戻していくことができる。
- 安全な場づくり(内的・対人的)。
- 感情と身体感覚の追跡(追体験ではなくチューニング)。
- 意味づけの再構築(恥から自己共感へ)
- 日常での自己境界・選択行動のリハビリテーション
「Normal」から「Whole」へ──この本が投げかける転換
『The Myth of Normal』は、病いを以下のような新たな捉え方を紹介している。
| 従来の見方 | Matéが促す見方 |
|---|---|
| 病気=身体の故障 | 病気=生存適応の長期的な副作用 |
| 正常=社会規範への適応 | 正常=しばしば不健康な文化的な適応である |
| 健康=症状がないこと | 健康=自己・身体・他者・環境との関係性の統合である |
| トラウマ=一部の人の稀な経験 | トラウマ=文化的に広がる普遍現象である |
結びに──「普通」に合わせることが、健康を遠ざけていないか?
『The Myth of Normal』は、私たちにいくつかの問いを投げかけている。
- 「普通であろう」とすることで、何を犠牲にしてきたか?
- 今感じている不調は、本当に“自分のせい”なのか?
- その痛みは、「もっと本当の自分に戻ってほしい」という、体からの声ではないか?
“Illness is not a mistake. It’s a message.”
「病気は間違いではない。それは、何かを見直すべき時だというメッセージである。」この本は、体の不調を「排除すべき敵」ではなく、「自分を取り戻すためのきっかけ」として見直す視点を与えてくれる一冊である。ぜひ、トラウマにご興味を持つ方、手に取ってみてください!






