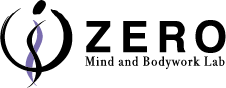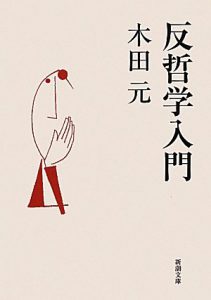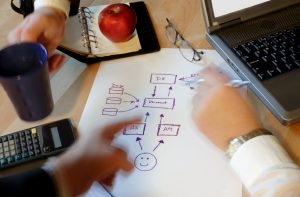【B#73】哲学(2)〜西洋哲学における「主観」「客観」の意味とその関係
欧米には根底に流れる思考の方法=世界観というものがある。
その世界観を追うものを彼らは「哲学」という学問を通じて体系化されている。
前回の本コラム(「超自然的原理と反哲学〜西洋独特な哲学はどのようにして生まれたのか?」参照)では、
西洋の哲学の独自性というのは、何からの超自然的原理を設定し、それを参照しながら、存在するものの全体を見るといった思考様式を持っていること。その流れはプラトンからヘーゲルまで脈々と続いていることを簡単に紹介した。
今回は、その延長上に「主観的」・「客観的」という西洋の思考様式があること、そしてそれが近代に入ってから思考方式として入ってきたことも書きたい。
「客観的に考える」というのは、今では当たり前で、サイエンスのみならず、ビジネスにおいてもロジカル・シンキング、医療の現場ではエビデンス(証拠)が大事だという形に現れている。
しかしながら、それは昔から当たり前だったというとそうではなく、近代に入ってから確立した考え方である。それは、キリスト教が中心だった中世からサイエンスや「人間理性」が中心となる近代に移行する際に出てきたものだ。
大辞林によると、
「主観」=「その一人一人のものの見方」
「客観」=「当事者ではなく、第三者の立場で観察し、考えること。また、その考え」
と書かれている。
「主観的」「客観的」という考えが生まれたのは、ルネ・デカルト(René Descartes、1596年〜1650年、以下デカルト)からイマヌエル・カント(Immanuel Kant、1724年〜1804年、以下カント)にかけて近代哲学が確立した頃だ。
木田元さん(以下木田さん)の「反哲学入門」によると、デカルトは「方法序説」で「理性」という考えをキリスト教との関係で以下のように位置付けた。
木田さんの文章を引用したい。
「一般にキリスト教の世界創造論では、・・・世界は神によって創造されたものであり、従って、世界には最高の理性(Ratio)としての神の意図が摂理(ratio=理性的法則)として支配している。
一方で神は、世界創造の仕上げとして、自らに似せて人間を創造し、それに理性(ratio)を与えた。従って、人間の理性は人間のうちにありながらも神の理性の出張所か派出所のようなものである。
その理性に神によって植えつけられた生得概念は、世界創造の設計図ともいうべき神の諸概念の不完全な部分写しのようなものだということになる。従って、人間の理性(以下人間理性)に生得的な概念と、世界を貫く理性法則とは、神を媒介として対応し合っている。
人間が生得概念をうまく使えさえすれば、世界を底のそこまで成り立たせている理性法則を正しく認識することができるはずである」
そして、
「認識できるもの」=「真に存在するもの」
と
「理性(ここでは、人間理性)には、自然の中で真に存在するものを認識し、決定力する」
ことが明確になっていった。
当然、このような「人間理性」は、自然を超えて存在するものなので、プラトンやキリスト教でいう「神」の超自然的原理の思考の文脈の中で理解することができる。
最終的に「人間理性」が近代哲学の柱となり、キリスト教の「神(又は神的理性)」の中世哲学に変わる超自然的原理の思考方式となる。
ガリレオ・ガリレイ(Galileo Galilei、1564年〜1642年)は、
「自然という書物は数学的記号で書かれている」
と世界を表現。キリスト教とは相容れないこの考えを、デカルトを通じて、哲学的な裏づけが得られるようになる。
その結果、キリスト教の影響を受けない形でサイエンスが発展していくような道筋ができてくる。
デカルトは、
「人間理性」=「基体(Substantia、ラテン語)」
と表現。基体の働きを「主観(subiectum)」(「下(sub)に投げ出されたもの(iectum)」のラテン語の由来)と呼んだ。
一方で、
「主観」によって認識される対象を「客観(obiectum、ラテン語)(「向こう(ob)に投げ出されたもの(iectum)」=「心に投影された事物の姿」のラテン語由来)」と呼んだ。
すなわち、
デカルトの時に
主観、客観は、
「主観」=「存在するために他の何ものをも必要としない、それ自体で存在するもの」(→今でいう客観)
「客観」=「感覚の働きに向き合う。心に投影されたりするもの、事物の事象内容」(→今でいう主観)
と、「主観」と「客観」が今でいう逆の意味で使われていたことになる。
それがデカルトからカントまでの間に、今の「主観」「客観」という意味で使われるようになった。
竹田青嗣さんの「現象学入門」によると、
中世のキリスト教以前の世界では、神の教えを人々は教会から受け取り、自分で合理的に考える必要がなかった。
しかし、「人間理性」が意識されるようになってから、キリスト教の神学の知識ではなく、人間の理性は世界に対する知識を「客観的」に考えることによって「正しく」捉えることができるという確信が生まれるようになった。
例えば、
サイエンスでは、仮説を立てて、実験を繰り返すことで確かめるという方法をとるが、
「仮説」=「主観」
「実験を繰り返して得られる確証」=「客観」
という形で主観的と客観的との関係による思考が確立されたように。
ただ、ここには問題が出てくる。
デカルトは神が人間に託して理性を与えているいうことが前提で、「主観」や「客観」が成り立つ。
もし「神」の存在が証明されない場合には、この論理は破綻していくことになる。そういった視点からも、主観と客観ということは考えておく必要がある。その課題について哲学者はどう立ち向かったのか?現象学やメルロ=ポンティの思想を理解していく上で、鍵となる主観と客観については「「客観」から「主観」を迫れるのか?〜直接経験から身体図式へ」に取り上げた。
ご興味のある方、ぜひチェックください。