【B#242】RANGE(レンジ)──知識の「幅」が、人生と組織を強くする
Table of Contents
はじめに
こんにちは。渋谷でロルフィング・セッションや脳科学ベースの講座を提供している大塚英文です。
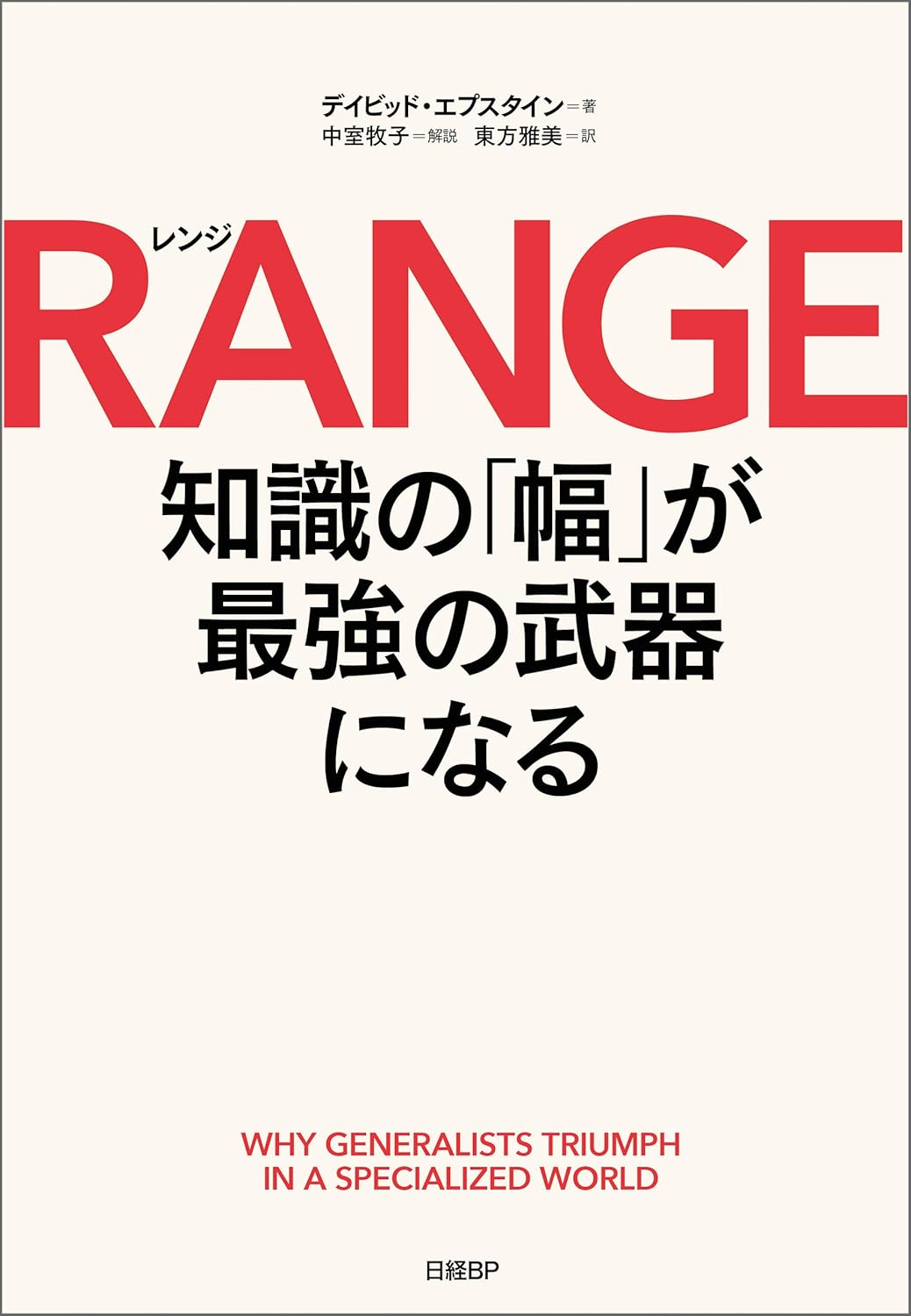
デイヴィッド・エプスタイン著『RANGE(レンジ)──知識の幅が最強の武器になる』を手に取った。組織における専門家とジェネラリストの役割について、興味深いことが書かれており、今回、この本をベースに、専門家とジェネラリストについて考えてみたい。
それはこれまで私たちが信じてきた
「効率こそ正義」
「専門性こそ成功への道」
「早く始め、集中すれば勝てる」
という価値観が必ずしも正しいわけではない、ことの理解が深まった。
本書には、
“遠回りやムダに見える経験こそが、長期的には最大の財産になる”
の記載がある。
キャリア形成、教育、スポーツ、企業組織…あらゆる領域において、“幅”を持つことの重要性を改めて考えさせられた。ここでは本書の要点を、私自身の視点も交えながらまとめていく。
「1万時間」「グリット」「早期教育」は本当に“正解”なのか?
キャリアや自己成長の文脈で語られるとき、
・1万時間の法則
・グリット(やり抜く力)
・早期専門教育
といった概念は強い影響力を持っている。
これらが人々を惹きつける理由は、「効率が良い」「ムダがない」「最短距離で成功できる」というメッセージが明確だからのように思う。
RANGE が指摘する早期特化する問題点として、
- 「深さ」だけで勝てる世界ではなくなっている
- 若いうちは適性が変わる
- 強みを決めつけると、視野が狭くなる
- 予期せぬ環境変化に弱い(VUCA耐性が低い)
- 異分野の経験が不足し、創造性が伸びない
しかも、『RANGE』が示す事実は、驚くほど対照的な視点を紹介している。
環境が安定し、予想できるような環境(Kind Environment)では“専門型”が強い。
しかし予想できない状況(Wicked Environment)には“幅を持つ人”が圧倒的に強い。
しかも、これは勘ではなく、さまざまな分野の研究や実例から導かれた結論なのだ。
タイガー・ウッズ vs ロジャー・フェデラー:対照的な成長パターン
タイガー・ウッズ:早期専門型の象徴
・生後9か月でゴルフクラブ
・2歳でテレビ出演
・徹底した英才教育
「一点突破・絶対的専門型」の象徴とも言える存在。
ロジャー・フェデラー:幅広い身体経験が創造性を育てた
・サッカー
・スキー
・バスケットボール
・水泳
・卓球
などを幼少期に並行して経験し、テニスに集中したのは比較的遅い時期からだった。
母親がテニスコーチにもかかわらず、無理に専門化を迫らず、“遊びながら幅広く身体を使う”時期が長かったことが興味深い。
結果、フェデラーのプレーには
・即興性
・柔軟性
・創造性
が豊かに現れているという。
これはまさに「幅」=RANGE の力と言っていい。
ダーウィン:寄り道の多さが“革命的発想”を生んだ
進化論を生み出したチャールズ・ダーウィンも典型的な“遠回り型”の人物と言っていい(詳細は「チャールズ・ダーウィンの「進化論」——ジェントルマン社会が生み出した成果」参照)。
ダーウィンは、ケンブリッジで医学や神学を学びながら、
・昆虫採集
・鳥類観察
・鉱物・地質学
・狩猟
・標本づくり
・自然誌の読書
など、学問とは関係のないように見える寄り道をしていた。
これらの経験が、ビーグル号航海で一気に統合され、「自然選択」という人類史上でも指折りの「進化論」の概念誕生
へとつながっていく。
寄り道が多かったからこそ、ダーウィンにしか見えない仮説が生まれた。
これはレンジの本質を最も象徴する事例と言っていい。
任天堂・横井軍平:ムダな遊びが世界を変える
ゲームボーイ、ゲーム&ウォッチを生み出した横井軍平。任天堂を“世界一の遊びの会社”に押し上げた人物だ。
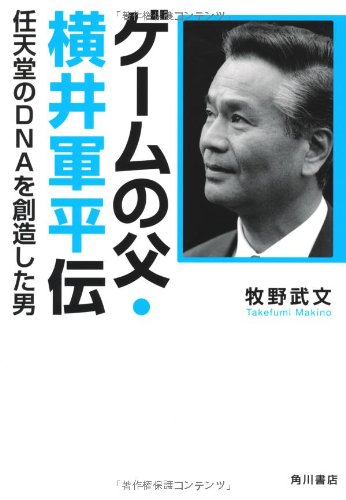
「枯れた技術の水平思考」の言葉を作ったのは、任天堂の開発部に1965年から1996年まで籍を置いていた横井さんだった。牧野武文さんの「ゲームの父・横井軍平伝ー任天堂のDNAを創造した男」によると、横井さんは「枯れた技術の水平思考」を以下のように表現している。
ものを考えるときに、世界に一つしかない、世界で初めてというものをつくのが、私の哲学です。それはどうしてかというと、競合がない、競争がないからです。
この意味は、最先端の技術を追いかけるのではなく、使い古されて、価格も安くなっているちょうど古い技術を、一歩引いたところから水平思考をしてみる。すると別の使い道が見えてくる。それは世界に一つしかない商品になるだろう。
横井さんは、その背景を別の言葉で以下のように表現している
技術者というのは自分の技術をひけらかしたいものですから、すごい最先端技術を使うということを夢に描いてしまいます。それは商品作りにおいて大きな間違いとなる。売れない商品、高い商品ができてしまう。
私がいつもいうのは、「その技術が枯れるのを待つ」ということです。つまり、技術が普及すると、どんどん値段が下がってきます。そこが狙い目です。
横井さんには、
・ものづくりが好き
・鉄道模型に夢中
・外車への興味だけではなく、自分で車をいじる
・テープレコーダーを買って、車のスピーカーに接続、世界初のカーステレオを作る
等、「ものを作ってイタズラに使う」という考え方があった。
これがのちに、横井さんが開発する様々な玩具は全てイタズラに使えるもの、ものづくりで人をびっくりさせたい、それが玩具、ゲーム&ウォッチ、ゲームボーイへとつながっていく。
このように、
遊びの経験が、無数のアイデアの源泉となっていた。
横井軍平ほど“ムダの価値”を体現した人はいないかもしれない。
企業組織でも「幅のある人」が必要とされる理由
RANGEの考え方は個人だけでなく、企業組織にも深く関わる。
多くの企業では
・スペシャリスト(専門家)
・ジェネラリスト(幅広く理解する人)
が存在し、それぞれの役割は明確に異なる。
スペシャリストの強み
・深い専門知識
・特定領域で高いパフォーマンス
・精密で複雑な作業を正確に行える
化学者・エンジニア・外科医など、専門性が直接価値に結びつく領域では不可欠です。
ジェネラリストの強み
・複数の情報を俯瞰して統合できる
・部門横断の調整役
・予期せぬ問題に柔軟に対応
・新規事業や戦略設計に向いている
不確実性が高く、状況が変化しやすい環境では、ジェネラリストの方が強さを発揮します。
RANGEが明らかにした事実
企業研究でも、
「予測困難な市場ほどジェネラリストが活躍する」
というデータが示されています。
理由はシンプルで、専門領域のパターンが当てはまらない未知の問題に対して、専門家はむしろ弱くなるためだ。
チェスの世界:専門家ほど“予測不能な問題”に弱くなる
『RANGE』で印象的だったのが、チェスの実験の事例を紹介していたことだった。
- チェスのグランドマスターは、過去の膨大な対局パターンを記憶している。
- しかし「ランダムに並べた盤面」を見せると、一般人とほぼ同じレベルまで能力が下がる
ことが分かった。
つまり、専門家は、パターンが崩れた瞬間に力を失うということです。
これは企業経営やキャリアの世界、さらには現代社会全体にも当てはまります。
VUCA(変動性・不確実性・複雑性・曖昧性)の時代では、「過去の成功パターン」が通用しない場面が増えているため、幅を持つ人間=ジェネラリスト的な知性の価値が高まっている。
“幅”は深さの敵ではない。深さを支える土台である
専門家の価値はもちろん重要。しかし、専門性は“二階建ての構造”を持っている。
- 一階部分:幅広い経験、さまざまな視点
- 二階部分:高度な専門性
専門性を真に活かすためには、「幅」という土台が不可欠だと『RANGE』は教えてくれる。
専門家ほど、別分野の知識に触れるべき理由がここにある。
私自身のキャリアにも「レンジ」があった
振り返ると、私自身のキャリアも“寄り道だらけ”だった。
- 生命科学(免疫学)の研究
- 製薬企業でのマネジメント
- 世界一周の旅
- ヨガ
- コーチング(CTI)
- ロルフィング
- 神経科学・発達心理
- タロット、身体知、東洋思想
一見バラバラに見える経験が、現在のRolfing × 脳科学 × コーチング という統合的なアプローチに結実している。もし早い段階で“専門”に縛られていたら、このような組み合わせは生まれなかった。
まとめ:非効率こそ、あなたの独自性を育てる
『RANGE(レンジ)』の最大のメッセージは非常にシンプルだ。
- 早く専門化した人は、予想できるルーチンが求められる仕事には強い
- しかし、予想できない状況に置かれた時には“幅を持つ人”が勝つ
- そして、予期せぬ変化にはジェネラリストが強い
- 経験の「ムダ」に見える部分が、創造性の源泉になる
- すべての寄り道が、未来につながる
遠回りした分だけ、見える景色が違う。
ムダな経験と思えたものが、未来の創造性を形づくる。
幅のある人生は、しなやかで、強い。
『RANGE』は、そんな勇気を与えてくれる一冊でした。






