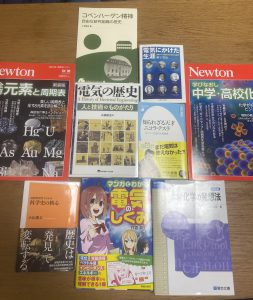【B#230】「古代ゲノム研究の人類学からみる、我々はいつから人間なのか」のセミナーを拝聴して
Table of Contents
はじめに
こんにちは。渋谷でロルフィング・セッションと脳科学をベースにした講座を提供している大塚英文です。
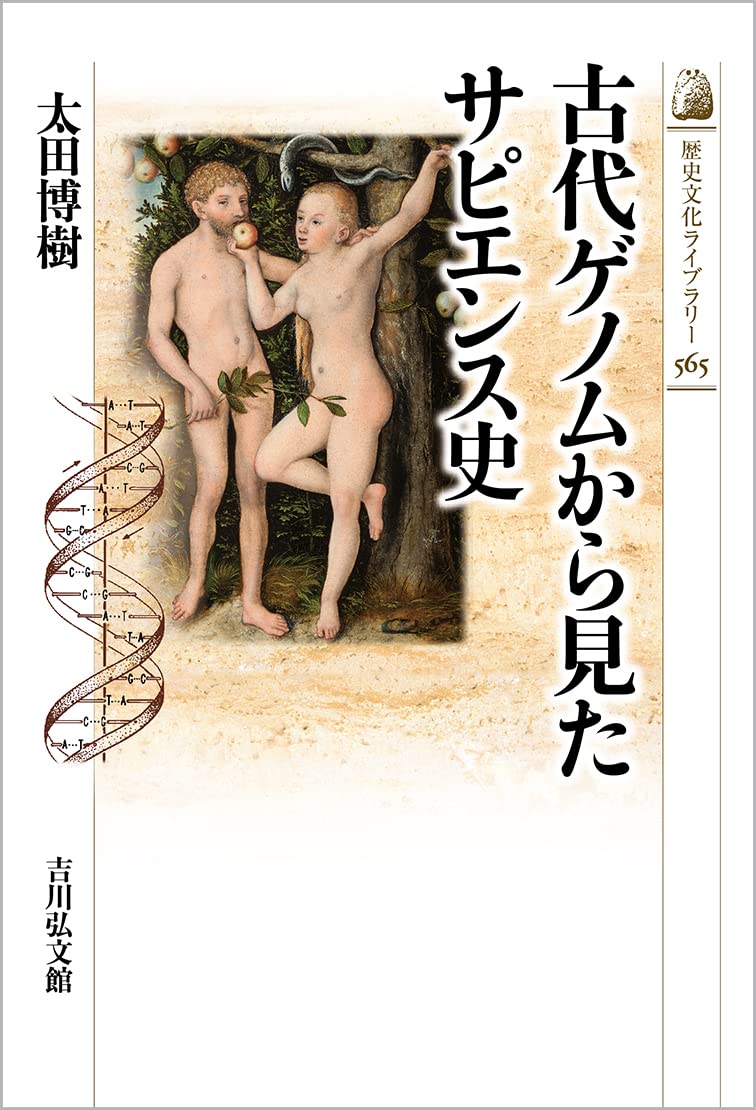
2025年10月15日(水)の午後6時半から都内で安川新一郎さん主催で行われたセミナー(BRAIN WORKOUT EXTENSION)に参加した。テーマは、人類学。過去5年、いろいろな本にあたって興味を持っている分野で、今回初めて専門家のお話を聞く貴重な機会となった。
今回は、どのようにしてこのセミナーと出会ったか?今回のテーマである人類学の私自身、何に興味を持っているのか?そして、セミナーの内容で何が面白かったのか?を中心にまとめていきたい。
BRAIN WORKOUTとの出会い
2025年9月21日、都内で開催されたアインシュタインのドキュメンタリー動画(NHKスペシャル・アインシュタイン・ロマン)の上映会に参加した。そこで、安川新一郎さんと出会った。安川さんの私塾の参加者が大半だったのだが、一人一人が素晴らしい質問を投げかけていた。
安川さんの本が間違いなく面白いのではないか、と感じ、すぐに「BRAIN WORKOUT」を手に取って拝読。人類の脳の進化を「6つのモード」に整理し直し、知能のアップグレードを語っている点、脳科学の本を10冊読んでいる感覚があった。
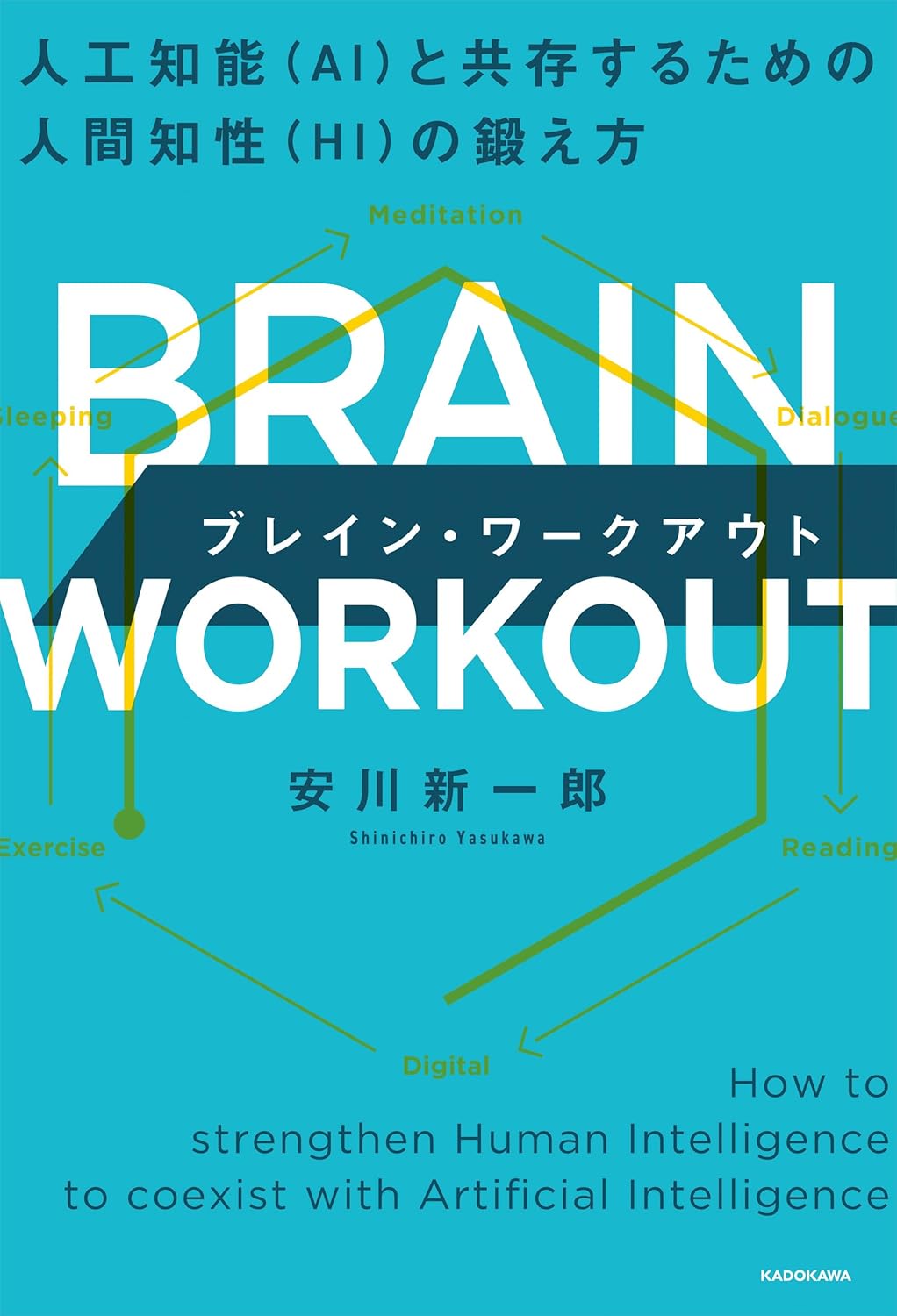
安川さんの中で、2025年10月15日(水)から、BRAIN WORKOUTをテーマにした全6回・月1回のセミナーを開催することについて、ご案内いただいた。
このセミナーは、BRAIN WORKOUTで取り上げた各テーマ(運動、睡眠、瞑想、対話、読書、デジタル)に各界の有識者を招いて行うというものだ。
幸運だったのは、直前にご案内だったにもかかわらず、初回の日程が空いていたことだった。そこで、当日を迎えた。テーマは人類学。東京大学大学院理学研究科生物科学専攻ゲノム人類学研究室の太田博樹教授を招いた講演会で、題名は「古代ゲノム研究の人類学からみる、我々はいつから人間なのか」。
以下、セミナーの内容を中心にまとめたいと思っているが、その前、私自身が人類学の興味を持っているのか?から始まり、太田先生の本の紹介、DNAシークエンサーの歴史、そして最後にセミナーの内容へと進めていきたい。
「サピエンス全史」と人類学とは何か?
私は、ユヴァル・ノア・ハラリ(Yuval Noah Harari)の「サピエンス全史 文明の構造と人類の幸福」を原書で繰り返し読んでいく中、
「人間は、どこから来て、いかにして現在に至ったのか」
について、科学的(人類学)な視点から、どこまでサピエンスについて明らかになっているのか?調べたいという気持ちになった(以下、人間のことを「サピエンス」という用語を使って語っていきたい)
背景となったのは、2001年3月、大学院で博士号(PhD)を取得(専門分野が分子免疫学)していたことだった。私が過去に研究室で使っていた分子生物学的な手法が、人類学に取り入れられて、教科書が書き換えられていく時代を迎えているのだ。
一方で、フィールドワークを通じて、文化的な側面を研究する文化人類学にも興味があったので、昨年(2024年)には人類学をテーマに、多面的な領域を集中的に本を読む機会を作った。
人類学の考え方は、15世紀の大航海時代から始まる。西洋人が、新世界の人たちという「他人」と出会うことで、人間とは何か?を考えるようになる。すなわち、現地に住み、生の人間を観察。現地の言語を覚えて、調査するという「フィールドワーク」を使ってアプローチするということ。
人類学の「anthropology」は、人間(anthropos)、学(logy)に由来。人間について研究するという意味を持つ。英国では、人類学を「自然人類学」「先史考古学」「社会人類学」の3つに分かれる。
人類の外見を科学的にに解析する手法を取り入るのが「自然人類学」、遺跡から出た土器、動物の骨、植物の種子などを通じて世界を語るのが「先史考古学」、社会の諸民族を比較して解析するのが「社会人類学」。英国の社会人類学は、伝統的に家族、親族、婚姻等、集団に重点が置かれるという。
一方で、米国では「社会人類学」を「文化人類学」と呼び、上記の3つに加え「言語人類学」が加わる。フランスでは、社会人類学や文化人類学を「民族学(ethnologie)」、日本では「民俗学(forklore)」などが加わる。
大雑把に人類学を見ると、ハード面からのアプローチ(自然人類学、先史考古学)、後者は、ソフト面からのアプローチ(社会人類学、民俗学、民族学)と見て良さそうだ。
さて、今回、太田先生とは初対面になる。事前に、研究内容を知りたいと思ったので「古代DNAから見たサピエンス史」を手に取ってから臨むことにした。以下、簡単ではあるが、太田先生の本の内容を紹介したい。
「古代ゲノムから見たサピエンス史」(太田博樹先生の本)
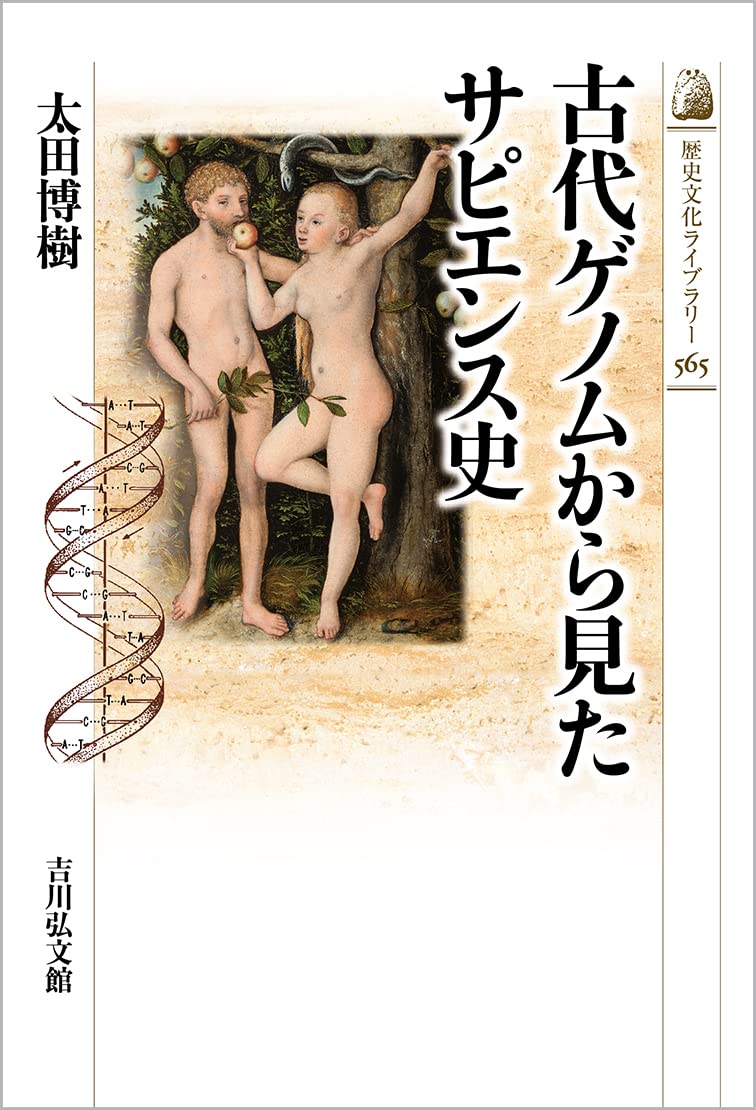
古代ゲノム学の誕生
この本は、化石や形態学でしか語ることのできなかった人類学が、分子生物学の解析技術が大幅に進んだことで、古代DNA(ancient DNA)=古代ゲノム学の誕生したこと。そして、考古学的な知見と結びつくと、サピエンスの歴史がどのように見えるのか?に迫った一冊になっている。
最新の成果を取り上げているが、分子時計、DNAの構造、ゲノム、遺伝子といった基礎用語をしっかりと説明した上で、ネアンデルタール人、デニソワ人の全ゲノム配列の解明及び成果の意義。なぜ、縄文人のプロジェクトを立ち上げたのか?専門的な部分もあるが、一般の方が読んでも理解が深まる内容になっている。
マックスプランク研究所の組織文化
個人的には、太田先生が、2022年のノーベル医学・生理学賞を受賞したマックス・プランク協会・進化人類学研究所(以下、エヴァ)のスバンテ・ペーボ(Svante Pääbo)教授の研究室に2年間留学したという体験を本にしているところが面白かった。その体験記。
本に研究室の雰囲気についてまとまっているので、一部引用したい。
ドイツにある大学は、全て国立大学であるが、マックスプランク研究所は、いかなる大学からも独立している。スクラップ・アンド・ビルド方式といって、成長めざましい研究分野には、巨額な投資をし、また成果の出ない研究所は、迅速に潰してしまうか、縮小し、将来性のある別の分野と合併させ、新しい研究所を創設する。
ペーボ教授が属していたマックスプランク研究所は、上記の組織の文化の元で古代ゲノム学が発展させていく。太田先生によると、マックスプランク研究所の予算が協会全体として年間二兆円を越える予算がつく。参考に、現代の日本の研究体制の規模では想像できない金額だ。
しかも、若い研究者を「幹部候補」として、育成する仕組みが確立されている。例えば、エヴァでは、大学院生やポスドクも、一人に一つの居室が与えられている。驚くべきことに、大学院生の実験には、それをサポートする技術者が、少なくとも一名、付いていたという。
私も院生の経験があるが、日本では、大学院生が学費を支払い、奨学金を得ることも狭き門で、たいて大人数で一つの部屋を居室で研究することが強いられるのだ。エヴァに集まってくる若者たちは、失敗のリスクをかえりみず、素晴らしい環境で研究に没頭できるのだ。
マックスプランク研究所と似たような雰囲気があるのは、理化学研究所だ(詳しくは「「科学の楽園」の理化学研究所〜どのように創造的な組織を作るか?〜科学と産業の融合の事例」参照)。しかしながら、同研究所では、スクラップ・アンド・ビルド方式は採用していない。
本では、その他に、チンパンジーと人間の違いをゲノム情報だけではなく、環境によって情報が変わるというエピジェニテックスの視点も紹介。今まで拝読した人類学(古代ゲノム学)から見たサピエンスの歴史の中で、同書が一番わかりやすかった本だった。ぜひ、この分野にご興味のある方、チェックいただきたい。
さて、太田先生のセミナーの内容に移る前に、DNAの解析技術の発展について語りたい。2003年にヒトゲノム計画(HGP)を終えた後、解析技術がどのように発展していったかだ。この技術抜きにして、古代DNA学の発展を語ることができないからだ。
ヒトゲノム計画+ゲノム解析技術の発展とイノベーション
ヒトゲノム計画の完了(2003年)
2003年、米国衛生研究所(National Institute of Health、NIH)の傘下にある国立ヒトゲノム研究所(NHGRI)の主導のもと、ヒトゲノム計画(Human Genome Project, HGP)が完了した。ヒトの全DNA配列(30億塩基対)を解読、約13年と30億ドルが費やされた。
当時使われた技術は「サンガー法」と呼ばれる古典的なDNA解析法(DNAシークエンサー(sequencer)、フレデリック・サンガーが開発し、1980年にノーベル賞受賞)で、一本一本のDNAを蛍光色素で標識し、電気泳動で読み取る方法。精密ではあるものの、莫大な費用と時間がかかった。
HGPの成功は「生命の設計図を解読した」という歴史的快挙といって良かったが、同時にコスト的に「誰もが自分のゲノムを読める時代はまだ遠い」ことを示していた。
$1000 Genome Projectの登場(2004年〜2014年)
HGP完了からわずか1年後、NHGRIは、次なる挑戦を掲げる。2004年、「$1000 Genome Project」──すなわち、1人のゲノムを1000ドルで解読する技術を開発するという大胆な研究プログラムだった(2014年に終了)。
このプログラムは、当時としては非現実的な目標だった。ここに、米国の国力の凄さを感じるのだが、NIHは高リスク・高インパクト研究への資金を供給。イノベーションを大学やスタートアップ企業に技術開発を委ねることにした。
さらに、「コスト/ゲノム」データを継続的に公開し、業界の進歩を見える化。これは「ムーンショット(大いなる飛躍)」を科学的に牽引する上で重要な政策的仕組みだったと言える。
2005年頃から、従来のサンガー法に代わる画期的な技術が登場する。それが次世代シーケンサー(Next Generation Sequencer: NGS)だった。NIHのビジョン、ベンチャーの野心、そして研究者たちの粘り強い努力が、20年で「30億ドル→1000ドル」という奇跡を生み出していく。
腸内細菌叢、個別化医療と人類学への応用
このコスト削減により、簡単に低コストで効率良くゲノム配列を解読することができるようになった。そこで、人の腸内細菌叢、個別化医療などのイノベーションにつながっていく。予想外だったのが、今回のテーマとなった古代DNA学への応用だった。
ペーボ教授は、ネアンデルタール人の全ゲノム配列を解明した。ネアンデルタール人の化石から、独自のDNAの抽出法を独自に確立し、その発展の上で解明したのだが、DNAシークエンサーのコストダウンが果たした役割も大きい。
前置きが長くなってしまったが、これらの事前知識を元に、今回のセミナーの内容をまとめたい。
「古代ゲノム研究の人類学からみる、我々はいつから人間なのか」(今回のセミナーの内容)
安川さんのテーマプレゼンテーションから始まり、人工知能と人間の違いはどこにあるのか?最新ロボットを例(Figure 03)にYoutube動画をシェアしながら、紹介。この動画は衝撃的すぎて、ロボットの未来がどうなるのか?ChatGPTと結びつくとどうなるのか?近い未来を感じさせる内容だった。
安川さんは、太田先生のプレゼンに入る前に、
- 人間はどこから人間なのか?
- 日本人はどこまで日本人なのか?
- 人類は一夫一妻は本当か?
の3つの問題意識を提起。この視点で太田先生の話を聞くことができたので、非常にわかりやすく内容が入ってきた。
人間はどこから人間なのか?
太田先生は、古代ゲノムの研究を通じて、人の進化を研究している。先述のゲノムの解読技術の発展はどのように進んだのか?を説明しつつも、ネアンデルタール人、デニソワ人の全ゲノム解読からみたサピエンスとの違いを紹介。
更に、類人猿(テナカザル、オランウータン、ゴリラ、チンパンジー)との違いを通じて人間とは何か?を説明した。
面白かったのは、
- サピエンスは、人に教えることができる、チンパンジーは、人に教えることができない
- 人類の起源は、チンパンジーから分岐した700万年前のこと
- ヒトの起源は、ネアンデルタール人からサピエンスが分岐した30-10万年前のこと
- ヒトは類人猿と違うのは、犬歯がないこと、性差わかりにくくなっていること
等、わかりやすくサピエンスと他の生物の違いを定義し、説明したことだった。
チンパンジーとサピエンスのゲノムの違いは、1.4%に過ぎない。この違いは、ゲノムの情報だけでは理解できない。環境によってゲノムの変化(DNAのメチル化、蛋白質(ヒストン)のアセチル化)により遺伝子のON/OFFになるというエピジェネティックスの手法も人類学に入ってきていることも語っていた。
しかしながら、人間はどこまで人間なのか?学問の発展とともにわかりにくくなっている現状についても指摘している。これからの研究の発展に期待したい。
日本人はどこまで日本人なのか?
太田先生の研究室では縄文人のプロジェクトを進めている。課題は、日本は酸性土壌、温暖湿潤の気候のため、本土(本州、四国、九州)では骨そのものが残りにくい。一方で、貝塚や、沖縄半島の石灰岩の岩場や洞窟はアルカリ性。人骨が残りやすいという。
古代の日本人の研究では、ミトコンドリアDNA(母系遺伝)や一部のマーカー遺伝子が使われてきた。これらは情報量が少なく限界もあった。
太田先生の研究室では、伊川津貝塚から見つかった化石から、縄文人のゲノム配列を読むことに成功。何と、解析を進めていくと、ラオス・マレーシアで発見されたホアビニアン文化人と多くの遺伝的バリエーションを共有していたらしい。
今後、縄文人や渡来人がどのようにして日本に押し寄せてきたのか?解明されていけば日本人の期限が明らかになってくるのではないかと思う。
人類は一夫一妻は本当か?
一夫一妻については、オランウータン(シングルマザー)、ゴリラ(一夫多妻)、チンパンジー・ボノボ(多夫多妻)について語っており、サピエンスについては、一夫一妻ではなく、「恒常的な性的受容性」という興味深い表現で説明していた。

人類学者のエマニュエル・トッドは、「我々はどこから来て、今どこにいるのか? アングロサクソンがなぜ覇権を握ったか」で、各国の家族構造と教育、そしてその歴史的影響を整理しているが、古代ゲノム学から見た視点ではなく、太田先生の話は、これを相補するような印象を受けた。
午後6時半から開始し、終わったのが午後9時。懇親会会場に移ってから、2時間。あっという間に時間が過ぎ、太田先生と色々と情報交換もできた。
まとめ
今回は、安川さんからのご紹介で、人類学をテーマとした、セミナーの第1回に参加した模様についてご紹介させていただいた。
人間とは何か?人類学(古代ゲノム学)の視点から、今まで知らなかったことが多く、学びも深かった。
このような貴重なセミナーに誘っていただいた安川さん、運営スタッフの皆様、ありがとうございました!そして、太田先生。素晴らしいプレゼンに感謝しています。