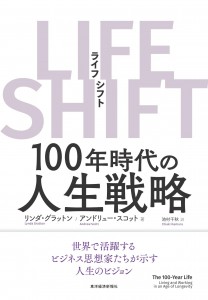【N#212】老化研究の新しい地平──リチャード・ミラー博士とITP(マウス老化モデル)の挑戦
Table of Contents
はじめに
こんにちは、渋谷でロルフィング・セッションや脳科学をベースにした講座を提供している大塚英文です。
私は、如何にして健康寿命を延ばしていけるか?興味を持って欧米の情報を収集しているが、中でもDr Peter Attia(ピーター・アッティア)のポッドキャスト(The Drive)は、有用な情報が多く学びも深い。

健康寿命を知るためには「老化とは何か」。どのようにすれば、それを「遅らせる」ことができるのか?について知る必要があると思う。
私が注目しているプロジェクトの一つに、ミシガン大学のリチャード・ミラー博士(Richard A. Miller, M.D., Ph.D.、以下ミラー博士)が率いるInterventions Testing Program(ITP)(日本語訳:介入試験プログラム)がある。そして、ITPは、マウスを使った老化研究プロジェクトのことだ。
なぜ、このようなプロジェクトが立ち上がったのか?どのようなことが明らかになってきたのか?を中心に、下記のポッドキャストの内容を参考にまとめたい。
ヘイフリック仮説がもたらした誤解
1960年代、レナード・ヘイフリック(Leonard Hayflick)は「正常ヒト細胞は約50回で分裂を止める」という現象を報告した。これが「ヘイフリック限界(Hayflick limit)」と呼ばれた。参考に、分裂が止まった細胞のことをsenescence cell(老化した細胞)という。
後に、エリザベス・ブラックバーン(Elizabeth Helen Blackburn)博士らにより、テロメアの短縮によってsenecence(老化)は起きると考えられるようになった。
しかし、ミラー博士は、この考え方が老化研究を大きく誤らせたと指摘している。
“Hayflick decided that was akin to aging and that he had found a way to study aging in culture — Now that’s nuts. It’s nothing like aging in the slightest.”
「ヘイフリックは、培養細胞の分裂停止を老化のモデルと考えた。だがそれは全くの誤りであり、老化とは似ても似つかない」とミラーは語る。
ミラー博士によれば、培養細胞の分裂停止は単なる現象の一つにすぎず、個体全体の老化メカニズムを説明するものではない。残念なことに、多くの研究者がこの「細胞レベルの老化」に夢中になり、「老化=テロメア短縮」という思考の枠組みにはまってしまったという。
“The limitation of growth—the Hayflick limit—was actually due to the shortening of telomeres… It’s important and true, but people convinced themselves that telomeres were something to do with aging too.”
「分裂制限は確かにテロメアの短縮によるものだ。だが、そのことから“テロメアこそ老化の原因”と信じ込んでしまったのは誤りである。」
ミラー博士はこのような誤解を「老化研究の最初の大きな迷路」と評している。
「老化は遅らせられない」という思い込みとの決別
ミラー博士が老化研究において最も重視したのは、
「老化は単一のプロセスなのか、それとも無数の独立した過程の集合なのか」
という問いである。
彼は明確に前者――すなわち「老化は統一的な制御メカニズムを持つプロセス」であると主張した。
“Very few people, even among professional aging researchers, would check the box that said, ‘yeah, there’s a single aging process.’ And until you check that box, the notion that you could interrupt the process makes no sense.”
「老化を一つの統一的プロセスだと考える研究者はほとんどいなかった。しかし、それを認めなければ、老化を“遅らせる”という発想自体が成り立たない。」
この考え方が、後にITPを設計する上での思想的基盤となっていく。老化は一つの原因で説明できるものでなく、複雑だが、その“速度”を制御する共通の生物学的プロセスが存在するという立場である。
“I don’t really care what causes aging. What I care about is ‘what is the process that can postpone all the different aspects of aging?’”
「私は老化の“原因”には興味がない。知りたいのは、老化のあらゆる側面をまとめて遅らせることができる生物学的プロセスである。」
ITP誕生の背景
2003年、アメリカ国立老化研究所(NIA)のハーバー・ワーナー(Huber Warner)が主導し、ミラー、ナンシー・ナドン(Nancy Nadon)、アーラン・リチャードソン(Arian Richardson)らが協議を重ねた結果、「薬剤が本当に寿命を延ばすかどうかを厳密に検証する」国家プロジェクトが立ち上がった。
それが、Interventions Testing Program(ITP)である。
ミラー博士はこの設立をこう振り返る。
“The goal of the ITP is to develop a fundamentally sound way of testing one question: Does this drug extend mouse lifespan?”
「ITPの目的は、極めて単純かつ根本的な問い――“この薬はマウスの寿命を延ばすのか?”――を、科学的に確実に答える枠組みを作ることであった。」
ITPの4原則
ITPの設計思想は、再現性と客観性を極限まで高めることにあった。
統計的パワーの確保
雌雄各50匹、対照群は倍の100匹。寿命延長が8〜10%であっても、80〜90%の確率で検出できる設計である。
> “We want enough mice that if a drug extends lifespan by 8% or 10%, we’ll pick it up 80% or 90% of the time.”
> 「寿命を8〜10%延ばす薬があれば、80〜90%の確率で検出できるだけのマウス数を確保する。」
三拠点での同時レプリケーション
ミシガン大学(ミラー博士)、テキサス大学サンアントニオ校、ジャクソン研究所の3施設で同じ手順(プロトコル)で試験を実施。
> “Doing it at all three sites not only gives us power, but also tells us if the effect is reproducible.”
> 「3つの施設で同時に行うことで、統計的パワーが得られるだけでなく、結果の再現性を確かめることができる。」
遺伝的にヘテロなHET3マウスを使用
近交系マウスではなく、4系統を交配したHET3マウスを採用。個体ごとに遺伝的に異なるが、半分の遺伝子を共有するという設計である。
> “Each one of those children is genetically unique, but each will share half of its genes with all the others.”
> 「すべての子マウスは遺伝的にユニークでありながら、互いに半分の遺伝子を共有している。」
外部提案を受け入れるオープンシステム
誰でも候補化合物を提案できる体制が整えられている。
> “Anybody can make a suggestion for a molecule that may have some longevity properties.”
> 「長寿効果をもつかもしれない化合物であれば、誰でも提案できる。」
近交系マウスを使わない理由
興味深いのは、HET3のマウスを使うことだ。
通常、実験室で使ってるマウスの大半は、近交系マウス。近交系マウスとは、20世代以上にわたり近親交配(兄弟姉妹交配など)を繰り返したマウスのこと。遺伝的に均一であるため、実験の再現性が高いのが特徴となる。
近交系マウスの例には、多くの研究で用いられるC57BL/6(私が博士課程の頃、大変お世話になったマウスだ!)、免疫でよく使われるBALB/c、そして心血管研究や薬理学で利用されるDBA/2等がある。
近交系マウスを使う弊害について、ミラー博士は以下のように語っている。
“About 90 % of the work in aging with mice (and actually all of medical research with mice) uses a single inbred genotype — black 6 mice — where there’s no variation from mouse to mouse in their genetics as well as being inbred which means they have bizarre peculiarities like blindness and deafness, etc.”
日本語に訳すと、一般的に使われてきた近交系マウス(前述の C57BL/6 、通称「ブラック6」)は遺伝的に均一であり、盲目や難聴などヒトには存在しない遺伝的特性を示すことが多い。このため、薬剤試験の結果が系統特有の遺伝的背景に依存してしまう危険があると。
ITPではこの問題を回避するため、4系統の異なる近交系マウスを交配して作るHET3マウスを採用している。
これにより、各マウスが遺伝的にユニークでありながら、互いに50%の遺伝子を共有するという「制御された多様性」を実現している。
“Each one of those children is genetically unique, but each will share half of its genes with all the others.”
「すべての子マウスは遺伝的にユニークでありながら、互いに半分の遺伝子を共有している。」
ミラーはこの設計意図を次のように説明している。
“About 90% of the work in aging uses a single inbred genotype—black 6 mice—where there’s no variation. The impetus for developing a genetically heterogeneous stock was to not trick ourselves into picking a drug that only worked on one strain.”
「老化研究の約90%は、遺伝的に均一なブラック6マウスで行われてきた。だが、そうした単一系統では“そのマウスにしか効かない薬”を見抜けず、誤った結論を導く危険がある。そこで遺伝的に多様な系統を導入したのだ。」
HET3マウスは、ヒト集団に近い遺伝的ばらつきを持つことで、結果の一般化可能性(external validity)を大幅に高めることにつながる。
そのため、HET3で有効性が示された薬は「より広い遺伝的背景をもつ生物にも通用する可能性が高い」と評価されている。
ITPが明らかにした成果
アスピリンとNDGA(初回コホート)
最初のコホート研究では、アスピリンとNDGA(ノルジヒドログアイアレチン酸)が雄マウスで寿命延長を示した。三拠点すべてで再現され、ITP設計の妥当性を証明した。
“Nordihydroguaiaretic acid (NDGA) worked at all 3 sites (although only in males).”
「NDGAは三つの施設すべてで寿命延長効果を示した(ただし雄マウスのみ)。」
ラパマイシンの衝撃
2009年に発表されたラパマイシン(Rapamycin)研究(Nature誌)では、高齢期(600日齢)開始でも寿命を延ばすことが明らかになった。mTOR経路の制御が老化速度を変えうることを初めて哺乳類で実証した意義は極めて大きい。
アカルボースと17-α-エストラジオール
糖代謝抑制薬アカルボースと17-α-E2は、雄マウスで顕著な寿命延長を示した。
この結果は、性ホルモンの違いが老化の速度に影響することを示唆している。
メトホルミンの複雑な結果
一方、驚きなのは、糖尿病薬メトホルミン(Metformin)だ。メトホルミン単独では明確な寿命延長は見られなかった。しかし他の研究では低用量での延命効果が報告されており、投与時期・用量・系統差が重要な変数であることを示している。
老化研究の「正しい問い」
ミラー博士が繰り返し強調するのは、研究の出発点となる問いそのものである。
“If you don’t ask the right question, you are guaranteed to flail. If you ask the right question, you may still flail, but at least you start on the other guy’s 20-yard line.”
「正しい問いを立てなければ、必ず迷走する。正しい問いを立てれば、たとえ苦戦しても、すでに相手の20ヤードラインから試合を始めているようなものだ。」
つまり、老化研究の核心とは「何が老化を起こすのか?」ではなく、
「どうすれば老化をまとめて遅らせられるのか?」という問いに置き換えることでもある。
まとめ
- ヘイフリック仮説は、細胞分裂の限界を老化と混同した点で研究を誤らせた。
- ITPは、統計的厳密性・多施設再現性・遺伝的多様性を備えたマウスをモデル動物として使った、唯一の老化介入プログラムである。
- アスピリン、NDGA、ラパマイシン、アカルボースなどの結果が、「老化は可塑的である」という事実を実証した。
- 老化研究の出発点は、「原因探し」ではなく「遅延可能性の探求」である。
ITPの研究成果は非常に興味深く、これからもぜひ追っていきたいと思っている。