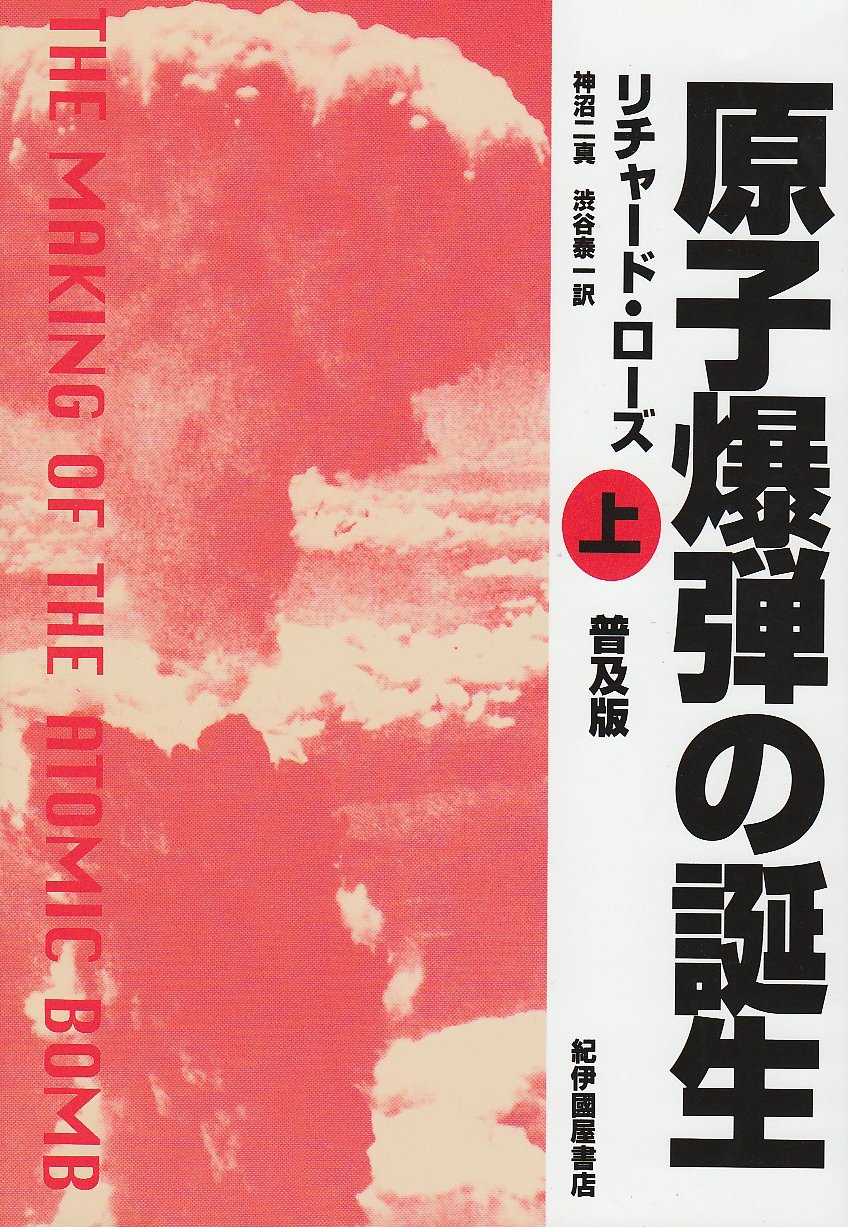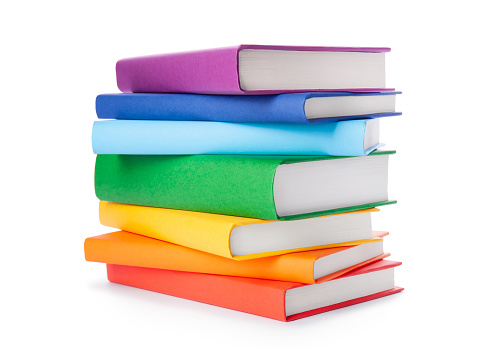【N#192】睡眠こそ最強の“脳トレ”──レム・ノンレム、神経伝達物質、そして生活習慣から考える
Table of Contents
はじめに
こんにちは。渋谷でロルフィング・セッションと脳科学に基づいた講座を提供している大塚英文です。

みなさんは、最近よく眠れていますか?
「しっかり寝ないと…」と分かっていても、寝つきが悪い、夜中に目が覚める、朝起きてもスッキリしない──そんな悩みを抱える方は多いのではないでしょうか?
実は、睡眠はただの「休息」ではなく、脳と身体の“回復・学習・整理”のための極めて能動的な時間です。最新の脳科学は、睡眠が記憶の定着、感情の安定、身体の修復、さらには社会性や創造性にも影響することを明らかにしています。
今回は、睡眠のメカニズムと、今日から実践できる生活習慣の工夫、そして「暑くて眠れない夜」の対策まで、脳科学をベースに解説します。
覚醒と睡眠の違い──「起きている」とは何か?
「覚醒」とは、単に目が覚めている状態ではなく、脳が外界の情報を選択的に処理し、行動に向かう“準備ができた状態”のことである。
- 脳幹にある「網様体(RAS)」という神経ネットワークが大脳皮質を活性化させる
- アセチルコリン、ノルアドレナリン、ドーパミン、ヒスタミン、セロトニンといった神経伝達物質が覚醒を支えている
- とくにアセチルコリンは「注意」や「集中」を生み出す鍵
対して、睡眠は脳の「視索前野(しさくぜんや)」が働き、GABAという抑制系の神経伝達物質を使って、覚醒状態をシャットダウンする。脳は“自ら”休息を作り出しているのである。
2種類の睡眠──レムとノンレム、それぞれの役割
睡眠は90分周期で「ノンレム睡眠(深い眠り)」と「レム睡眠(浅く夢を見る眠り)」が交互に繰り返される(レム(REM)は、Rapid Eye Movement(素早い目の動き)の略)。
ノンレム睡眠(Non-REM)
- 睡眠の前半に多く現れる
- 視床が感覚情報を遮断し、大脳皮質が沈静化
- 成長ホルモンが分泌され、身体の修復が促進
- 睡眠紡錘波(すいみんぼうすいは)が出現し、運動記憶やスキル学習の定着が起こる(ピアノ演奏やスポーツ動作など)
レム睡眠(REM)
- 睡眠の後半に増加
- 脳波は覚醒時と同様の活動状態になり、夢を見やすい
- アセチルコリンが優位になり、創造性・感情処理・長期記憶の統合が行われる
- 同時に、身体は“麻痺”状態となり、夢の内容を行動に移せないようになっている(安全装置)
ポイント:
ノンレムで「情報を整理」し、レムで「記憶と感情を統合」する。この2段階が“脳の片付け”に不可欠である。
ホルモンと神経伝達物質──眠気の正体
睡眠を導くには、複数のホルモンと神経物質が複雑に関与している。
セロトニンとメラトニン
- 朝に日光を浴びるとセロトニンが分泌される
- セロトニンは夕方から「メラトニン」に変換される
- メラトニンは深部体温を下げ、入眠を促進
夜のスマホや蛍光灯はメラトニンの分泌を止めてしまう
アデノシンとカフェイン
- 起きている時間が長くなると、脳内にアデノシンが蓄積され「眠気」が高まる
- カフェインはアデノシン受容体に“偽装”して結合し、一時的に眠気をブロック
カフェインの半減期は約6時間。午後の摂取には注意が必要である
睡眠を深める生活習慣──朝から夜までの整え方
良い睡眠は「夜」ではなく「朝」から始まる。体内時計と自律神経を味方につける生活が重要である。
● 朝にすべきこと
- 起床後90分以内に朝日を浴びる
- 冷水と温水の交互シャワー
- カフェイン摂取は起床から90分後以降にする
● 夜にすべきこと
- 就寝90分前の入浴(40℃前後)で体温を一時的に上げ、放熱を促す
- 寝室の温度は**18〜20℃**が理想
- 顔や手足を布団の外に出すことで放熱しやすくなる
- 顔を冷たい水で洗うことも放熱に効果的
中核温と熱放散の仕組み──なぜ“手足を温める”と眠くなるのか?
深部体温(中核温)が下がることが、入眠の引き金になる。その鍵を握るのが「放熱」のメカニズムである。
● 中核温とは?
- 脳や内臓など、身体の中枢部の温度(およそ37℃前後)
- 睡眠時には自然に低下し、入眠を助ける
- 起床の90〜120分前が最も低くなる
● AVA(動静脈吻合)とは?
- 動脈と静脈が直接つながる特殊な血管構造
- 手のひら、足の裏、額などに集中
- 血流が豊富で、効率的な放熱装置として働く
手足を温めることでAVAが開き、体表から熱が逃げ、中核温が下がる
● 夏の夜におすすめの対策
- 就寝前にぬるめのお風呂
- 手足を布団の外に出す
- 顔を洗って蒸発熱を利用する
- 寝室の温度はやや低め(18〜20℃)
冷やすより、「温めて放熱させる」ことが眠気を呼ぶコツである
まとめ──眠りながら、脳と身体は進化している
睡眠とは、ただ「休む」のではなく、
- 情報を整理し、記憶を定着させ
- 感情を統合し、ストレスを回復し
- 身体を修復し、成長ホルモンを分泌する
という極めて能動的な再構築の時間である。
質の高い睡眠を得るためには、「ホルモン」「体温」「光」「覚醒物質」といった複雑なリズムを生活習慣の中で整える必要がある。とくに、AVAを活用した熱放散や体温調節の知恵は、夏の夜に眠れない現代人にとって大きな助けになるだろう。
睡眠は、最も効率的で、最も根本的な脳のメンテナンスである。
参考文献
- マシュー・ウォーカー『睡眠こそ最強の解決策である』
- 『Sleep Sleep Sleep』(サンマーク出版)
- 櫻井武『睡眠の科学』『食欲の科学』(ブルーバックス)
- 佐々木努編著『もっとよくわかる!食と栄養のサイエンス』(羊土社)
- Huberman Lab Podcast #4, #101, Gina Poe回