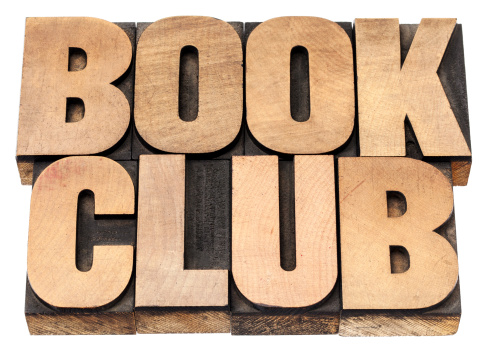【N#191】水が足りていない?──熱中症対策・疲労回復・高齢化・糖質制限にも関係する「水分補給」の重要性
Table of Contents
はじめに
こんにちは!東京・渋谷でロルフィング・セッションと脳科学に基づいた講座を提供している大塚英文です。
以前の投稿で、「塩分と高血圧の本当の関係」について、James DiNicolantonio博士の著書『The Salt Fix』をもとに紹介した。塩分が過度に悪者扱いされてきた背景や、塩分不足がむしろ現代人の健康に悪影響を及ぼしている可能性について触れた。

今回は続編として、「水分補給の重要性」について、以下の視点から整理したい。
- なぜ「糖質制限」をすると水不足になるのか?
- 熱中症対策にはなぜ「水+塩分」が必要なのか?
- 水分補給のタイミングと量とは?
- 高齢になると水不足になる理由と保水力の低下とは?
- 実践のためのポイントとは?
現代人は、糖質制限や加工食品の多用などの影響に加え、年齢を重ねるにつれて「水分が不足している」ことに気づかないまま生活しているケースが多い。
特に高齢者は、体内の水分量そのものが減少し、口渇感も鈍くなることから、慢性的な脱水状態に陥りやすい。水をしっかり「摂る」ことだけでなく、「保持する=保水する」力が低下することも忘れてはならない。
なぜ水分が重要なのか?──脳、筋肉、腸内細菌の働きに直結する
人体の約60〜70%は水分で構成されている。特に筋肉、脳、血液、腸内環境の維持において、水は不可欠である。睡眠中には約200〜500mLの汗が自然に失われ、起床後には排尿によってさらなる水分が排出される。したがって、朝の時点で多くの人が軽い脱水状態にあると言える。
また、年齢とともに体内の水分量は減少し、以下のように変化する。
- 新生児:75%
- 成人男性:60〜65%
- 高齢者(70歳以上):50〜55%
これはつまり、高齢になると、若い頃に比べて水の“貯金”が少ない状態で生きているということである。その上、喉の渇きを感じにくくなるため、知らないうちに脱水が進んでしまう。
さらに、腸内に棲む2〜3kgにも及ぶ腸内細菌の働きも、水不足によって低下する。水は、体内のすべての機能の潤滑油である。
糖質制限はなぜ水不足を招くのか?
糖質には、水を身体に保持する「保水性」がある。炭水化物を摂取すると、体内でグリコーゲンと結びつき水分を保持する。一方で、糖質制限を行うと、この保水機能が低下し、腎臓からナトリウムやカリウムなどの電解質とともに水分が排出されやすくなる。
さらに、加工食品を避ける傾向もあり、自然と水分摂取が減少する。結果として、体内の水と電解質のバランスが崩れ、脱水状態が慢性化する危険性がある。
特に糖質制限を行っている高齢者では、「食事量そのものが少ない」「塩分が控えめ」「体内の保水力が落ちている」など、さまざまな要因が重なるため注意が必要である。
水を飲んでも吸収されない?──塩分との関係
水を飲んでも「すぐに尿として排出される」と感じたことはないだろうか。これは体内のナトリウム濃度が十分でないと、保水できずに水分が保持されないためである。
体液は一定のナトリウム濃度を保とうとする恒常性(ホメオスタシス)を持つ。ナトリウムが不足していると、いくら水を摂っても尿として排出されやすい。水分を「吸収し保持する」ためには、塩分(ナトリウムとミネラル)の同時補給が必要である。
この「保水力」は、年齢とともに低下する。したがって、高齢者こそ「水だけでなく、良質な塩(天然ミネラルを含むもの)」とセットでの補給を意識すべきである。
水分補給のタイミングと量──10時間ルールと体内時計
水分補給には「タイミング」と「持続性」が求められる。
- 起床直後:睡眠中の発汗と排尿による水分損失を補うため、400〜800mLの水を推奨
- 10時間以内にこまめに摂取:腎臓の活動は体内時計の支配を受けており、夜間は休息モードに入るため、日中に集中的に補給することが重要
- 目安量:体重1kgあたり2mLを15分おきに摂取(例:60kgの人で10時間に約2L)
特に高齢者は、「喉が渇いたと感じる前に飲む」ことが重要である。自覚がなくても、体内では水分不足が進行している可能性がある。
熱中症対策──汗とナトリウムの損失に注目
夏場に運動や入浴をした際には、大量の発汗が生じる。汗1kgあたりに含まれるナトリウムは約5gとされており、これは通常の1日摂取量に匹敵する数値である。
そのため、熱中症対策としては「水のみ」では不十分であり、塩分(特に天然ミネラルを含む塩)との同時摂取が必須である。
また、就寝中の発汗や、入浴時の水分損失も意外と見落とされがちである。寝ている間の汗は夏冬問わず350mL、入浴時は500mLに及ぶことがある。これらを補うためにも、日常的な塩入りの水分補給が不可欠である。
ストレスと水・塩の関係──副腎ホルモンとのつながり
ストレスが高まると、副腎から分泌されるコルチゾールが、皮膚などに貯蔵されたナトリウムを血中に移動させる。これは身体にとって「塩分が足りていない」信号であり、結果として疲労感、集中力低下、不安感などの症状が表れやすくなる。
このような状態では、適切な塩分補給がストレス軽減に貢献する可能性がある。
実践のポイント──日常でできる「水+塩」習慣の工夫
脳活講座で紹介した内容から、次のような実践ポイントを日々の生活に取り入れるとよい。
- 朝起きたらまず塩水
コップ1杯(200〜300mL)の水に、天然塩をひとつまみ(約0.5g)入れて飲む。空腹時は吸収率が高く、腸への刺激も与えられる。 - 午前中を中心に意識的に水分補給
10時間以内に集中的に補給することで、腎臓の活動リズムに沿った効率的な排出と保水が期待できる。 - 「口が乾く前に」飲む習慣
特に高齢者は喉の渇きを感じにくいため、定期的に15分ごとに少量ずつ飲む意識を持つとよい。 - ミネラル補給には天然塩を活用
精製塩ではなく、海塩・岩塩・ぬちまーす・クリスタルソルトなどを使用することで、マグネシウムやカリウムも補える。 - 入浴や運動後は経口補水液や手作り塩水
水1Lに天然塩2g、レモン汁適量、必要に応じて少量のハチミツを加えるなどして、電解質と水分の再補給を行う。 - 夏場は水筒に塩水を用意
外出時に持ち歩くことで、熱中症の予防とパフォーマンス維持に効果がある。
まとめ──「水+塩」が健康の基本
水分補給は「水だけ」では不十分であり、塩分とのセットで初めて保水機能が発揮される。とりわけ高齢者にとっては、水の「補給」と「保持」の両方を意識することが、健康を守るうえで極めて重要である。
以下の点に注意して、日常生活を見直してほしい。
- 高齢になるほど、体内の水分量が減る
- 糖質制限中は脱水リスクが高まる
- 水を摂るなら塩も忘れずに
- 朝の水分補給と「10時間以内ルール」を習慣化
- 夏場・運動後・サウナ後は塩水や経口補水液が有効
- ミネラル豊富な天然塩の使用を推奨
- 実践的な工夫で、こまめな補給と保水力の維持を目指す
水と塩──シンプルだが極めて本質的なテーマである。この情報が、日々の体調管理や健康意識の向上に役立てば幸いである。