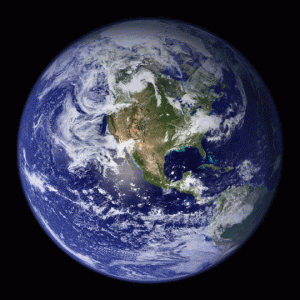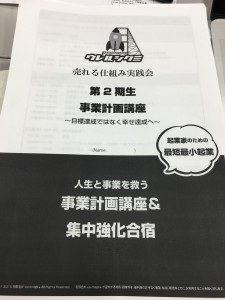【B#211】判断のブレがもたらす見えない危険──ダニエル・カーネマンらの「NOISE」から学ぶ
Table of Contents
はじめに
こんにちは。渋谷でロルフィング・セッションと脳科学ベースの講座を提供している大塚英文です。
私たちは日々、多くの判断を下している。診断を下す医師、評価を行う上司、判決を出す裁判官──それぞれが「正しい」と信じて判断を下す。しかし、その判断が日によって、あるいは人によって大きくブレているとしたらどうだろうか?
今回紹介するのは、ダニエル・カーネマン(Daniel Kahneman)、オリヴィエ・シボニー(Olivier Sibony)、キャス・サンスティーン(Cass R. Sunstein)による著書『Noise: A Flaw in Human Judgment(ノイズ──組織はなぜ判断を誤るのか?)』である。
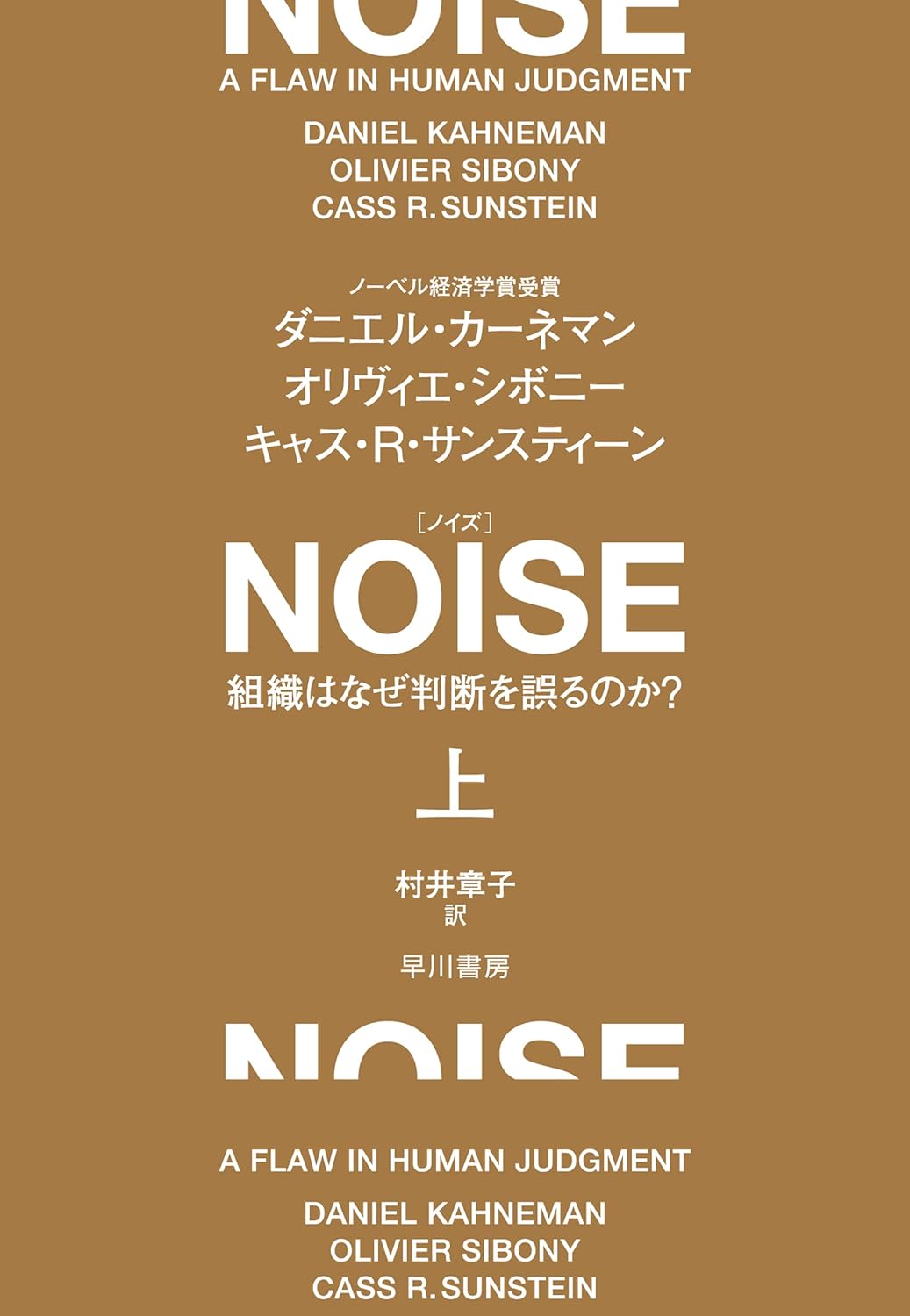
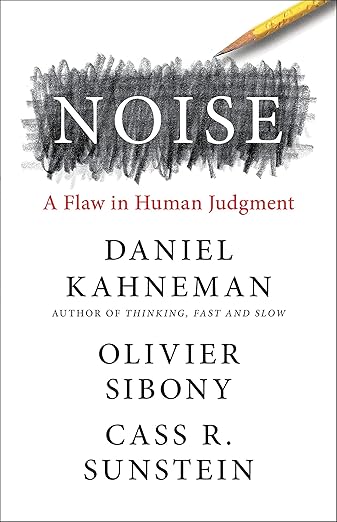
以前ブログで取り上げた、ダニエル・カーネマンの本『ファスト&スロー』が明らかにした「バイアス(bias)」とは異なるもう一つの判断エラーである「ノイズ(noise)」に光を当てた一冊である。
バイアス(Bias)とノイズ(Noise)の違い
まず、混同されがちな2つの概念を明確にしておく。
| 概念 | 日本語訳 | 意味 | 例 |
|---|---|---|---|
| バイアス(bias) | 系統的偏り | 判断の方向性が一貫して誤っていること | いつも高めに評価する癖 |
| ノイズ(noise) | 偶発的なブレ | 同じ条件でも判断がバラついてしまうこと | 曜日や天候で評価が変わる |
バイアスは「的の一点からずれて同じ方向に外れる」こと、ノイズは「ばらばらな方向にブレている」ことにたとえられる。どちらも意思決定をゆがめるが、ノイズの存在は見えにくく、軽視されやすい。
『NOISE』の主要な構成
第1部:ノイズとは何か?(Part 1: Finding Noise)──判断のバラつきに、なぜ気づけないのか?
本章では、ノイズ(noise)という現象が実際の意思決定プロセスにどのように現れるかを紹介している。
たとえば、同じ犯罪に対して、異なる裁判官が「6か月の刑」と「5年の刑」を言い渡すケースがある。このような判断の一貫性のなさ(judgment variability)が「ノイズ」である。
主な概念(Key Concepts)
- System Noise(システム・ノイズ):組織内で同じような案件に対して異なる判断が出ること
- Occasion Noise(偶発ノイズ):その日の気分・天気・タイミングなどにより変化する判断
- Level Noise(水準ノイズ):評価の厳しさや甘さの傾向が人によって異なること
ケーススタディ(Case Study)
大手保険会社で同じ事故案件を異なる担当者に査定させたところ、平均で20%近くも金額がブレていた。これがノイズの典型例である。
第2部:判断の構造(Part 2: The Machinery of Judgment)──「判断」とは何か?を分解する
本章では、人間の判断がどのように構成されているのかを分析する。カーネマンらは判断を「ノイズの影響を受けるシステム」と捉え、個人差や状況の影響を定量化しようと試みている。
主な概念(Key Concepts)
- Intuition(直感):しばしば頼りにされるが、ノイズを多く含む
- Pattern Recognition(パターン認識):一貫したパターンではなく、バラついた判断の温床にもなりうる
- Judgment Decomposition(判断の分解):複雑な判断を要素に分けることでノイズを抑制できる
注目ポイント:
直感(intuition)に頼る判断は、「確信はあるが間違っている」ことが非常に多く、ノイズの温床となる。つまり、自信と正確性は一致しない。
第3部:ノイズの測定とコスト(Part 3: Measuring Noise)──見えないブレが、どれだけ損失を生むのか?
本章では、ノイズを定量的に測る方法と、ノイズがもたらす「見えない損失」について述べられている。
主な概念(Key Concepts)
- Noise Audit(ノイズ監査):組織内の判断のバラつきを測定する方法
- Decision Hygiene(意思決定の衛生管理):ノイズを減らすための方法論
ケーススタディ(Case Study)
企業の人事評価では、評価者ごとにスコアのバラつきが激しく、昇進・報酬・離職率に深刻な不平等を生んでいた。ノイズ監査により評価基準の見直しが行われ、ばらつきが40%削減された。
第4部:ノイズを減らす技術(Part 4: Improving Judgment)──判断の質をどうすれば上げられるのか?
カーネマンらは、「ノイズをなくすことはできないが、減らすことはできる」と述べ、具体的な方法論を提案している。
主な技法(Practical Techniques)
- Structured Judgment(構造化された判断)
感覚や印象に頼らず、複数の要素ごとにスコアを付けて合算する。 - Independent Assessments(独立した評価)
チームで話し合う前に、まず全員が個別に意見を記録することでバイアスやノイズを防ぐ。 - Aggregation(集約)
個人の判断を複数集めて平均を取ることで、全体のノイズを抑えられる(“wisdom of the crowd”効果)。
第5部:倫理と判断(Part 5: Taking Responsibility)──誰がノイズの責任を取るのか?
ノイズがもたらす不公平は、本人や組織だけでなく、社会全体に影響を与える。
本章では、倫理的観点からも「ノイズの軽減」が重要であると説いている。
主な論点(Key Topics)
- Accountability(説明責任):ばらついた判断には説明責任が伴うべき
- Fairness(公平性):ノイズは人間の尊厳や正義に反する
- Justice(正義):裁判、診断、雇用など、正義の根幹が揺らぐ可能性がある
『ファスト&スロー』との違い
本書『ノイズ』は、カーネマンの代表作『ファスト&スロー』の“続編”のように読まれがちだが、焦点を当てているテーマは明確に違う。
『ファスト&スロー』が取り上げたのは「バイアス(系統的な偏り)」であり、判断が一貫して間違う構造だった。一方『ノイズ』は、「バラつきそのもの」に注目している。つまり、同じ情報をもとにしても判断が揺れるという“見えにくい誤差”に警鐘を鳴らしているのである。
両者を比較することで、現代の意思決定に潜むリスクをより立体的に捉えることができる。
| 比較項目 | 『ファスト&スロー』 | 『ノイズ』 |
|---|---|---|
| 主眼 | 認知バイアス(bias) | 判断のばらつき(noise) |
| 対象 | 思考の“方向性の偏り” | 思考の“ばらつきと不一致” |
| 解決策 | バイアスへの気づきと熟慮 | 構造化と衛生管理による削減 |
| 例 | 「いつも偏って同じ間違いをする」 | 「人によって判断がバラバラ」 |
まとめ
『ノイズ』は、私たちが思っている以上に判断が「ブレている」こと、そしてそのブレが社会のあらゆる場面に影響を与えていることを教えてくれる。本書の核心は、「ノイズは“見えにくい間違い”だからこそ、より深刻である」という警告である。
だからこそ、「正しそうに見える判断」に対してこそ、見えないノイズの存在に敏感であることが必要なのだ。