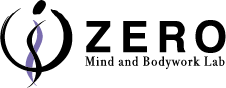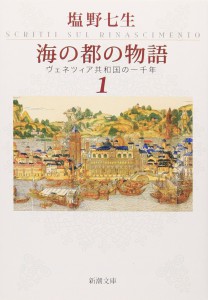【B#251】伊藤憲二『励起』を読んで②──ドイツはどのようにして「研究という文化」を生み出したのか
Table of Contents
はじめに
こんにちは!東京・渋谷でロルフィング・セッションと脳科学の基づく講座・タロットカードを使ったカウンセリングを提供している大塚英文です。
「励起──仁科芳雄と日本の現代物理学」との出会い
2025年、量子力学をテーマとした本を読んできたが、中でも、伊藤憲二さんの「励起──仁科芳雄と日本の現代物理学」という素晴らしい本と出会い、年末に1000ページ近くの文量をあっという間に読み終えることができた。

この本は、仁科芳雄の伝記であると同時に、20世紀物理学を生み出した各国の「知を生み出す組織」を比較する書でもある。前回は、英国を取り上げた。今回は、ドイツを取り上げることにする。ドイツの研究大学・研究所モデルは、研究を個人の才能ではなく、社会制度として成立させた点で、際立っている。
今回も、この本を参考にドイツの研究環境についてまとめたい。
統一なきドイツが生んだ文化競争
19世紀初頭まで、ドイツは単一の国家ではなかった。1815年に成立したドイツ連邦は、約35の連邦国家が緩やかにつながった政治体であり、中央集権的な国家が成立するのは、1871年、プロイセン国王を皇帝とするドイツ帝国の誕生を待たねばならない。
さらに、ドイツとオーストリア=ハンガリー帝国を含む中央ヨーロッパには、広大なドイツ語圏が形成され、巨大な人口と多様な都市・地域が存在していた。
重要なのは、この分散した政治構造のもとで、各連邦国家が「文化の高さ」で競い合っていたことである。軍事力や経済力で覇を競うことが難しい小国家にとって、大学や学問は、国家の知的水準と文化的威信を示す最重要の装置だったといっていい。
統一以前に訪れた精神文化の黄金時代
その結果、ドイツ語圏では、国家統一から遠い18世紀後半の段階で、すでに文学・哲学の黄金時代が到来する。
- ヨハン・ヴォルフガング・フォン・ゲーテ
- フリードリヒ・シラー
- イマヌエル・カント
学問とは実用のための技術ではなく、人格そのものを形成する営みだという考え方が、広く共有されていた。
この精神的土壌が、後の自然科学の制度化を可能にした。
ベルリン大学とフンボルト理念
この流れを制度として結晶化させたのが、1810年創設のベルリン大学である。その設計思想を与えたのが、プロイセン教育行政の中心人物であり、言語学者でもあったヴィルヘルム・フォン・フンボルトである。
フンボルトの大学理念の核心は、研究と教育の統一にあった。
大学教師は、もはや単なる知識の伝達者ではなく、研究者である。学生もまた、単なる学習者ではなく、研究に参与する存在である。学生は自ら研究を行い、教授はそれを導き、支援する。
大学とは、完成された知を教える場ではなく、知が生成されつつある現場と捉えることができる。
この考え方は、新人文主義の延長線上にある。古代ギリシャ・ローマの古典を学び、思考を鍛えることで、
人格を内側から統治するという思想が、自然科学にもそのまま適用された点に、ドイツの特異性がある。
ゼミナール制度──研究の予行演習としての教育
この理念を日常的な教育制度として具現化したのが、ゼミナール制度である。ゼミナールでは、少人数の学生が原典や最新研究を読み、発表し、議論し、教授がそれを指導する。
ここで行われているのは、理解度の確認ではない。研究そのものの予行演習である。問いを立て、先行研究を読み、自分の解釈を示し、批判に耐える。研究は、最初から共同的で公開的な営みとして始まる。
これは、試験と序列による個人選抜を軸としたケンブリッジの数学トライボス文化とは、根本的に異なる。
ギーセン大学とリービッヒ──実験室教育の革命
この研究志向の教育が、自然科学において決定的な形をとったのが、ギーセン大学における化学教育である。その中心人物が、ユストゥス・フォン・リービッヒであった。リービッヒ以前、大学における実験は、教授が演示し、学生はそれを見るという形式が主流だった。
リービッヒはこれを根底から変えた。学生一人ひとりに作業台を与え、自ら試薬を扱い、失敗を含めて実験の全過程を経験させたのである。この実験室は、授業の補助ではなく、研究と教育が完全に一致する場だった。
実験室=研究者養成装置
リービッヒの実験室からは、数多くの化学者が育ち、その弟子たちはヨーロッパ各地、さらにはアメリカへと広がっていった。
重要なのは、この教育が化学にとどまらなかった点である。
- 仮説と結果の往復
- 実験ノートの書き方
- 装置の改良
- 再現性への徹底した意識
これらは、そのまま物理学・生理学・工学へと移植可能だった。
19世紀後半以降、物理学は精密な装置と訓練された研究者を必要とする学問へと変化していく。その人的基盤は、化学実験室教育によって先に準備されていたのである。
ゼミナール × 実験室が生んだドイツ型研究者
ここで、ドイツ型研究文化の構造がはっきりする。
- ゼミナール
→ 思考し、議論し、批判に耐える知性を育てる - 実験室
→ 手を動かし、失敗し、再現性を身につける
この二つが結合することで、
理論も理解し
実験も実行でき
研究を職業として継続できる人材
が、個人の天才性に依存せず、安定的に生み出された。
研究所モデルへ──大学の外側へ
この大学文化の上に重ねられたのが、大学の外側に設けられた研究専用機関である。その象徴が、カイザー・ヴィルヘルム協会(現在のマックス・プランク協会)である。教育義務を負わず、長期的・基礎的研究に専念できる研究所は、研究そのものを職業として成立させた。
ドイツの物理学は「一つの中心」を持たなかった
ここまで見てきたように、ドイツの研究文化の本質は分散性にある。
英国のように「ケンブリッジ」という単一の象徴的中心が存在するのではなく、ドイツでは複数の都市・大学が、それぞれ異なる役割を担いながら、全体として物理学を前進させていた。
その代表的な三拠点が、
- ゲッティンゲン
- ベルリン
- ミュンヘン
である。
これらは同じ「ドイツの大学」ではあっても、研究の性格・文化・人材の集まり方が明確に異なっていた。
ゲッティンゲン ―― 数学と理論物理の震源地
ゲッティンゲン大学は、19世紀後半から20世紀初頭にかけて、世界最高水準の数学・理論物理の中心地となった。
ここでは、
- 数学
- 数理物理
- 理論物理
が、ほとんど区別なく結びついていた。
この環境を象徴する人物として、
- ダフィット・ヒルベルト
- フェリックス・クライン
がいる。
彼らのもとで形成されたのは、理論的厳密さを最優先する研究文化である。20世紀に入ると、量子力学の形成期において、ゲッティンゲンは決定的な役割を果たす。
- マックス・ボルン
- ヴェルナー・ハイゼンベルク
が集い、行列力学が生まれたのは、この地である。
特徴(ゲッティンゲン)
- 数学的形式化を極限まで推し進める
- 抽象性・一般性を重視
- 理論物理の「最前線」を担う
- 実験よりも理論が主導
ゲッティンゲンは、理論が最も高く励起された場所だったと言える。
ベルリン ―― 国家と結びついた研究の中心
ベルリン大学は、フンボルト理念を体現する大学として出発したが、19世紀後半以降は、国家の中枢と結びついた研究拠点となっていく。
ベルリンの特徴は、
研究が常に
- 国家
- 行政
- 研究所
- アカデミー
と接続されていた点にある。
この環境で活躍した代表的人物が、
- マックス・プランク
- アルバート・アインシュタイン
である。
プランクは、量子論の創始者であると同時に、研究制度を代表する人物でもあった。
彼は、
- プロイセン科学アカデミー
- カイザー・ヴィルヘルム協会
と深く関わり、研究を国家的事業として運営する立場にあった。
特徴(ベルリン)
- フンボルト理念の制度的中心
- 国家と研究の強い結合
- 理論と実験のバランス
- 学問の「正統性」を担保する役割
ベルリンは、ドイツ科学の制度的心臓部だった。
ミュンヘン ―― 理論と実験を媒介する教育拠点
ミュンヘン大学およびミュンヘン工科大学を中心とするミュンヘンは、ゲッティンゲンやベルリンとは異なる性格を持っていた。
ここで決定的な役割を果たしたのが、
- アルノルト・ゾンマーフェルト
である。
ゾンマーフェルトは、理論物理学者でありながら、教育者として比類ない影響力を持っていた。
彼のゼミナールからは、
- ヴォルフガング・パウリ
- ペーター・デバイ
- ハンス・ベーテ
など、20世紀物理学を担う人材が次々と育っていく。
特徴(ミュンヘン)
- 理論と実験の橋渡し
- ゼミナール教育の完成形
- 人材育成に特化
- 国際的ネットワークの形成
ミュンヘンは、理論を「使える研究者」に変換する場だった。
三拠点の違いを一言で言えば
整理すると、三つの拠点は次のように位置づけられる。
- ゲッティンゲン
→ 理論を極限まで抽象化する場所 - ベルリン
→ 研究を制度として統合・正当化する場所 - ミュンヘン
→ 理論と実験を結び、人材を育てる場所
この分業構造こそが、
ドイツ物理学の持続的な強さの源泉だった。
まとめ:「励起」とは、研究が日常として循環する状態である
伊藤憲二『励起』を通して見えてくるドイツの姿は、天才のひらめきや爆発的発見ではない。
- ゼミナールで考え続け
- 実験室で手を動かし続け
- 研究が日常として回り続ける
その結果、学問全体が高いエネルギー準位=励起状態を保ち続ける。仁科芳雄先生が、ドイツで見たのは、天才の瞬間ではなく、知が自然に生成され続ける社会的装置だったのだろう。
最後に、ニールス・ボーアのコペンハーゲン研究所とコペンハーゲン精神について取り上げたい。