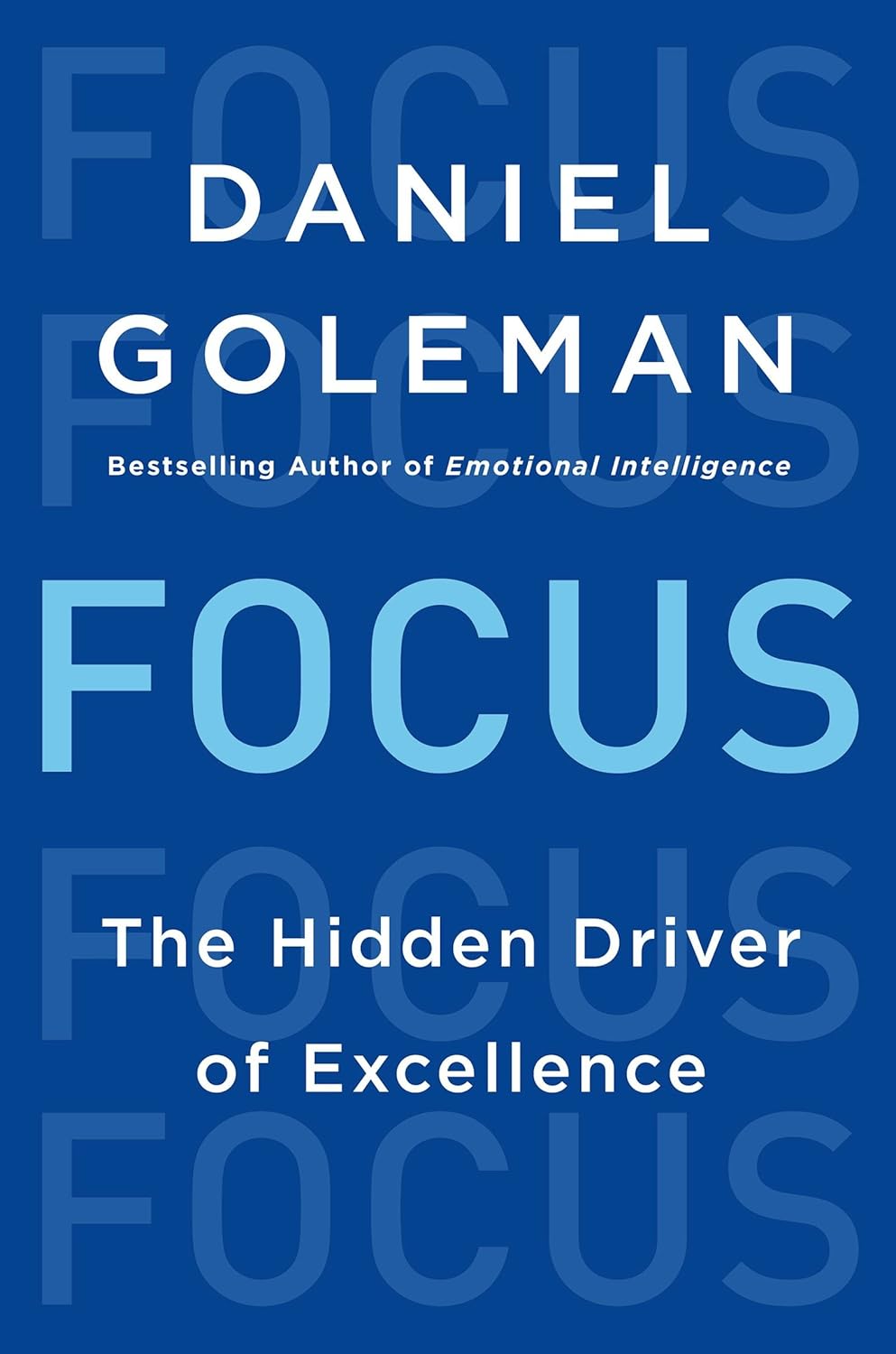【B#237】日本の大学院・講座制度はどう生まれたのか?〜中山茂『帝国大学の誕生』を拝読して
Table of Contents
はじめに
こんにちは。渋谷でロルフィング・セッションと脳科学をベースにした講座を提供している大塚英文です。
私は過去に、大学院や企業に所属し、研究・開発に勤しんでいた。このような経緯があり、大学や企業の組織で、創造性を発揮するには、どんな仕組みが適切なのか?興味を持ってブログにまとめている。
以前にも、
1)英国のジェントルマン階級の支援の下、チャールズ・ダーウィンの進化論が誕生したこと。
2)コペンハーゲン精神、ドイツのゼミナール制度の下、量子力学が誕生したこと。
3)研究者の自由度、最新設備の導入、人的交流、研究者の厚遇の下、理化学研究所が誕生したこと。
4)国家プロジェクトとして、異なる専門分野を統合・課題解決に向けた原爆開発の「マンハッタン計画」。
等について、まとめてきた。
今回は、我が国、日本が、どのような経緯で大学・大学院を作ったのか?考えてみたい。
中山茂氏の不朽の名作『帝国大学の誕生』は、近代日本が西洋から科学技術を輸入する際、ドイツ、米国、フランスの制度を「いいとこ取り」しながらも、結果として「変革が難しい」硬直した大学システムを作り上げてしまった経緯を鮮やかに解き明かしている。
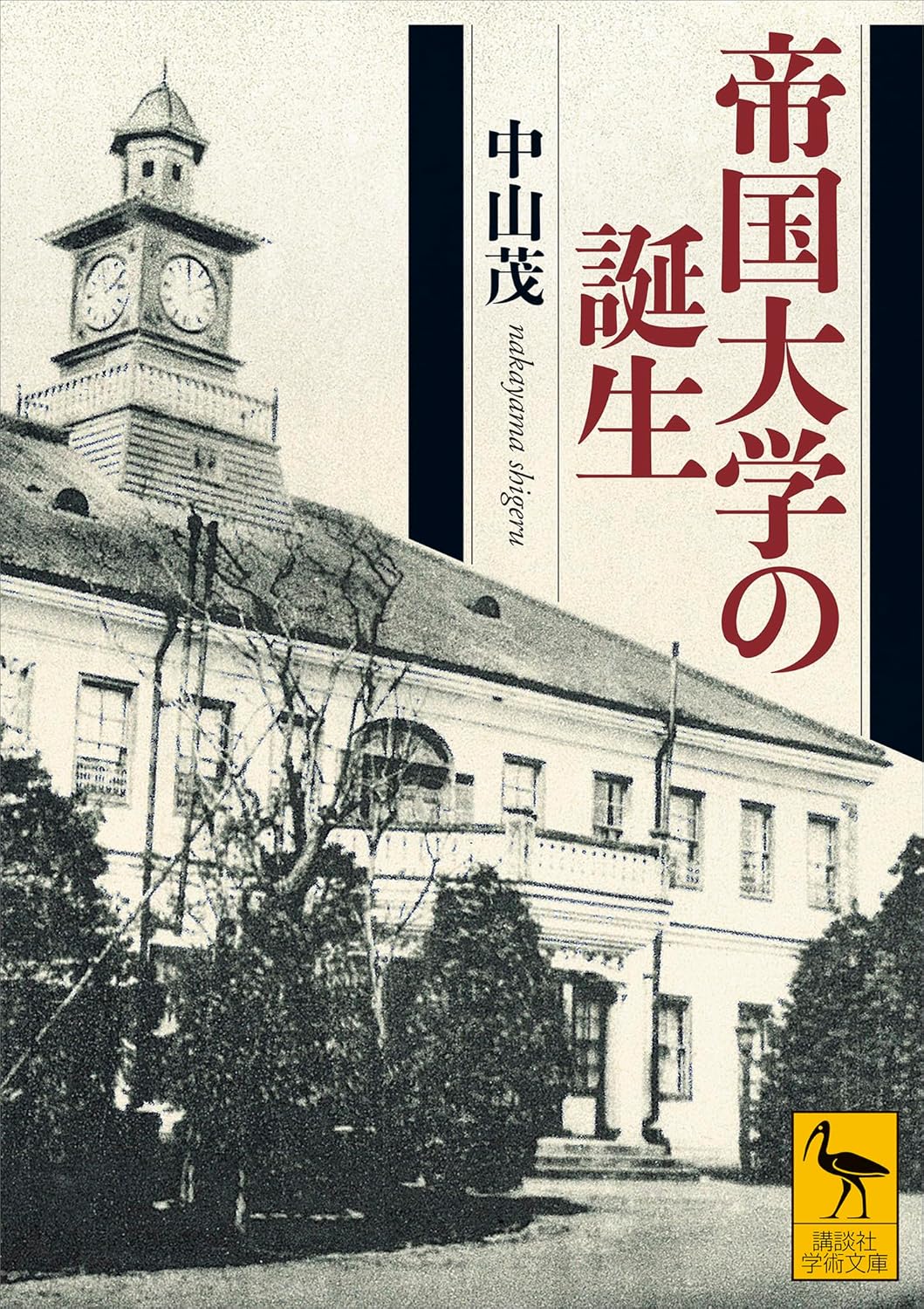
今回のブログでは、中山茂氏の著作『帝国大学の誕生』を参考に、日本が近代化の過程で参考にした欧米の大学制度の構造と、日本が独自に選択した大学院、講座制の功罪について、その誕生の経緯を追っている。
この歴史を深掘りすることで、私は、現代日本の研究力低下や組織文化の硬直性を理解する鍵が、この「帝国大学誕生の秘密」に隠されていると強く確信しているからだ。
欧州中世大学の伝統:討論が生んだ学問のスタイル
欧州中世大学の伝統:討論が生んだ学問のスタイル
近代の研究型大学が生まれる母体となった西洋の中世大学には、現代のような筆記試験(ペーパーテスト)がなかった。これは、当時は紙が貴重であり、大勢の学生に一斉に試験を行うことが困難だったためだ。
- 討論による能力評価: その代わり、西洋のスコラ学は論理や修辞を重視したため、学生の能力のテストはすべて討論の形で行われました。これは、試験というよりも弁論の試合に近いものだった。
- 論理を磨く学位試験: 学位取得の際には、学生は自らの論旨を並み居る先輩の博士(教授)たちの攻撃(質問)から守り通して、初めて学位を与えられた。この方式は、表現形式に制約はあったものの、学生が自らの論理を徹底的に磨き上げ、自らの専門とするテーマを深く掘り下げる方向に導いた。
- 受け継がれる慣行: 今日でも西洋の大学の学位試験に口頭試問が慣行となっているのは、この中世以来の伝統を守っているからだ。この「討論と論理重視」の精神は、後のドイツ型大学の教授と学生の関係にも深く影響を与えた。
中国・科挙制度の影響:中央集権的なエリート選抜
一方、東洋では、中国の科挙制度が数百年間にわたって国家官僚を選抜する仕組みとして機能した。
- フランスへの影響: ヨーロッパの啓蒙主義者たちは、家柄ではなく能力によって官僚を選抜する科挙の中央集権的で平等な選抜思想に強い関心を持った。フランスは、ナポレオンが確立した官僚的なシステムの中で、この国家による統一的な試験に基づくエリート選抜の思想を強く取り入れた。
- 日本への影響(身分の流動性): 明治日本は、このフランス経由の「中央集権的な選抜システム」を採用することで、旧来の身分制度から能力主義に基づくエリートへの道を開き、身分の流動性を持たせる装置としても利用した。これにより、帝国大学は富国強兵のためのエリートを効率的・画一的に育成・選抜する強い性格を持つことになったと言っていい。
ドイツ型大学の理念:フンボルトの革新と「研究と教育の統一」
近代ヨーロッパにおける研究型大学の原型は、19世紀初頭のプロイセンに誕生したベルリン大学(フンボルト大学)にある。
ヴィルヘルム・フォン・フンボルトの役割
教育行政家であったヴィルヘルム・フォン・フンボルト(Wilhelm von Humboldt)は、「研究と教育の統一」という革新的な理念に基づき、ベルリン大学を設立した。彼は、大学を自由な学問探求の場と位置づけ、教授の自由な研究活動そのものを最高度の教育と見なしていた。
地方分権と自由な選択が生んだ競争原理
ドイツの大学の強さを支えた構造的な要因の一つが、統一国家成立以前の地方分権にあった。
- 国家の成立と大学: ヨーロッパの多くの名門大学、特にドイツの大学は、プロイセンやバイエルンといった領邦国家が、まだ統一国家(ドイツ帝国)となる前に、地方の権力と威信をかけて設立・育成された。
- 地方分権のメリット: ドイツは多数の領邦国家に分かれていたため、各領邦が自国の威信をかけて独自の大学を設立・育成した。この競争原理により、各大学は特色ある研究分野を伸ばし、学問の多様性が生まれた。
- 学生の選択権: ドイツの学生には、どの大学でどの教授の講義を聴くかを比較的自由に選ぶ権利があった。この「学生の選択」は、大学の講義と研究水準に対する市場原理として機能し、大学のレベルを自律的に引き上げることに貢献した。
私講師(Privatdozent)制度:競争と実力主義
フンボルトの理念を支え、徹底した実力主義を体現したのが私講師(Privatdozent)制度。これは、博士号取得者が大学の承認を得て無給で講義を行い、学生の聴講料と研究実績によって将来の教授職を目指すという、厳しい競争の仕組みだった。
カイザー・ヴィルヘルム協会の誕生:研究の専門化
20世紀に入ると、教育機関としての大学では対応しきれない大規模研究のニーズに応えるため、カイザー・ヴィルヘルム協会(現在のマックス・プランク協会)が設立された。これは、大学の教育義務から切り離された、純粋な研究のみを目的とする機関として機能することになる。
カイザー・ヴィルヘルム協会については「「古代ゲノム研究の人類学からみる、我々はいつから人間なのか」のセミナーを拝聴して」に詳しくまとめているので、ご興味のある方、チェックください。
英国の「アカデミー」と研究面での遅れ:ダーウィンの時代背景
英国の大学(オックスフォード、ケンブリッジ)は、伝統的なカレッジ制による紳士的教養に重きを置き、近代的な専門研究への転換がドイツに比べて遅れていた(詳しくは「チャールズ・ダーウィンの「進化論」——ジェントルマン社会が生み出した成果」をご参照ください)。
なぜ英国はドイツに遅れてしまったのか?
- 「紳士の教養」への偏重: 大学の主な目的が紳士的教養と人間形成に置かれ、専門的な近代科学の研究よりも古典的なリベラルアーツが重視されました。
- 『種の起源』で知られるチャールズ・ダーウィンがケンブリッジ大学に在籍した19世紀初頭、彼が学んだのは神学であり、自然科学は主要な正規科目ではなかった。ダーウィンが熱中したのは、正規のカリキュラム外であった植物学や地質学の個人的な探求だった。
- 研究活動の外部化: 専門的な科学研究の多くは、大学内部ではなく、王立協会(アカデミー)などの外部の私的な学術団体に依存していたため、大学自体が研究機関として組織化されるのが遅れた。
日本の判断: 実学と組織的な研究を急務とする明治日本にとって、非効率でありエリート育成のスピードに合わない英国の大学モデルは、採用が見送られた。
フランス・米国の要素と日本の選択
米国型大学の進化:専門教育としての「大学院」
米国は、ドイツ型の研究志向を取り入れつつ、学部(カレッジ)教育とは明確に区別された「大学院(Graduate School)」を創設した。これは、教育と研究の場を組織的に分離し、高度な専門人材を養成する道筋を確立したと言われている。
フランスからの影響:国家主導の中央集権的・官僚的な統制
日本が大学運営の「骨格」として最も参考にしたのは、フランスの教育制度が持つ中央集権的で官僚的なシステムだ。
- 日本の大学の特異性: ドイツの大学が国家が成立する前に地方の競争で生まれたのに対し、日本の帝国大学は明治という統一国家の成立後に、国家主導で設立された。このため、当初から国家の目的に強く奉仕する性格を持っていた。
- 「官立」の性格と国家管理: フランスの大学は国家の機関として厳しく統制され、教育・研究は国家目標に奉仕する側面が強かった。これは、富国強兵のためのエリート養成を急ぐ日本の国策に合致した。
- 文部省による厳格な統制: 帝国大学は文部省の厳格な管轄下に置かれ、教員も官吏とされた。これは、ドイツの大学に見られたような大学の自治や自由な競争とは異なり、中央政府の強い指導のもとで運営される基盤となった。
日本の核心的選択:大学院と講座制
結果として、帝国大学は、フンボルトのドイツ(研究重視・教授中心主義)、米国(独立した大学院)、そしてフランス(官僚統制)という多国籍な要素をハイブリッドさせた独自のモデルとなった。
- 講座制の採用(ゼミナール式の模倣): ドイツのゼミナール式(ゼミ)での研究指導を模倣し、教授一人を頂点とする講座を最小単位とするシステムを採用した。
- 予算(経費)の紐付け: この講座制は、研究費や運営のための予算(経費)が講座単位で付与される構造であったため、教授の権限を絶対的なものとし、研究リソースの獲得と配分を固定化した。
- 講座制の一長一短:
- 一長(メリット): 教授の強力なリーダーシップのもとで、特定の専門分野の研究を深く掘り下げて発展させることができる。
- 一短(デメリット): 教授の権限が強すぎるあまり、講座が蛸壺化し、閉鎖的で硬直的な組織となり、学際的な研究が生まれにくい構造を生み出した。
- 帝国大学拡張の要因: この講座は、教授と研究室の独立した単位であるため、研究需要の拡大や教授ポストの要求に応じて自己増殖的に増えていく傾向があった。これが、最終的に東京から札幌、京城(ソウル)まで、9つの帝国大学へと全国的に大学を増やしていく原動力の一つとなった。
制度の硬直化と変革の難しさ
中山茂氏は、この一度確立された日本の大学システムが、自己保全機能を強く持ち、外部からの圧力なしに変革が極めて難しいことを指摘している。
ドイツで見られたような大学間の自由な競争や学生による自由な選択といった外部からの圧力が不足していた分、日本の大学制度は硬直化しやすい構造を持ったと言える。
まとめ
中山茂氏の『帝国大学の誕生』は、近代日本の大学制度が、国家の目標達成を最優先とする中で、ドイツの研究力と米国の大学院を形式的に導入しつつも、フランス的な中央集権的な統制と硬直的な講座制で固められた歴史して見ることができる。
- 日本の選択の功罪: 帝国大学は、短期間で国家に必要なエリートを養成し、日本の近代化に大きく貢献した。しかし、その代償として、ドイツのような地方や学生による競争原理を欠き、国家主導の硬直したシステムを内在させてしまった。
- 変革の難しさの根源: 一度確立された講座制などの制度は、自己保全機能を持ち、外部からの圧力や市場原理が働かないため、「一旦できると変革が難しい」という日本の大学特有の構造的な壁を築いてしまった。
この歴史的経緯こそが、現代の日本の大学が、国際競争力や柔軟な組織運営といった課題に直面し続けている根本原因の一つとして捉えることができるのではないかと思う。
少しでも、この投稿が役立つことを願っています。