【B#233】変化の時代に必要な「意図的な冷静さ」──『Deliberate Calm』を読む
Table of Contents
はじめに
こんにちは。渋谷でロルフィング・セッションと脳科学をベースにした講座を提供している大塚英文です。
私たちが生きる現代社会は、かつてないほど不確実で、複雑で、急速に変化している。気候変動、テクノロジーの進化、経済の変動、そして社会の分断──これらの変化は、私たちに絶えず「適応する力」を求めている。
しかし、皮肉なことに、変化が最も求められる瞬間にこそ、人は過去のやり方にしがみついてしまう。
それは人間の脳と身体が生存のために作られたメカニズムゆえである。危険を察知すると、扁桃体が作動し、防衛反応が優先される。だが、この反応的なモードにとどまる限り、私たちは新しい状況に学び、創造的に応じることができない。
『Deliberate Calm: How to Learn and Lead in a Volatile World』(Jacqueline Brassey, Aaron De Smet, Michiel Kruyt著、未邦訳)は、このような時代において「反応ではなく、意図的に選択する冷静さ」をいかに育むかを示している。
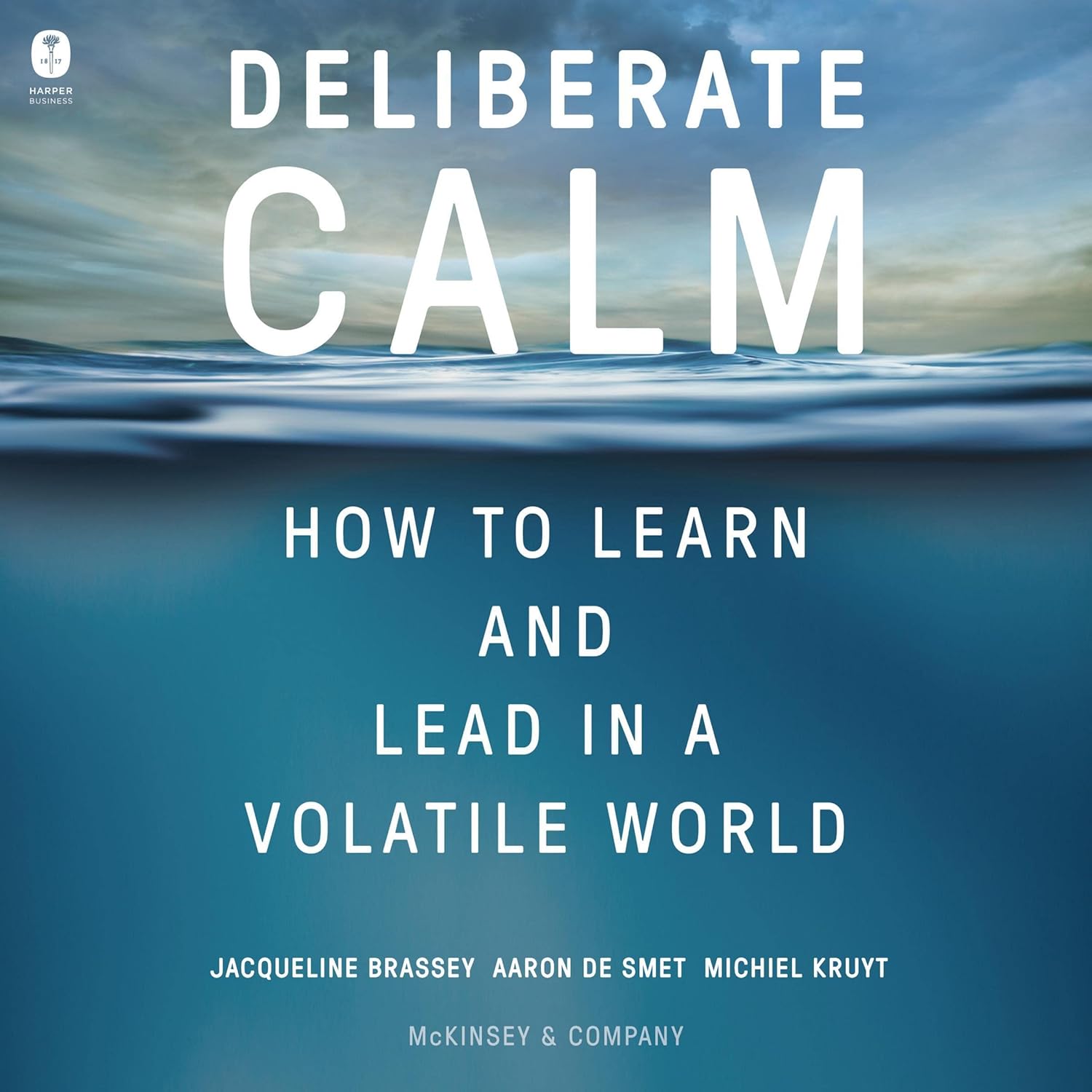
2025年に出会った脳科学の本で最も印象に残ったものだった。しかも、心理学・神経科学・発達理論を統合させた内容になっており、「冷静さは訓練可能なスキルである」ということを学んだ一冊となった。しかも、コンサル業界の人たちによってまとめられた本というのに意義があると思っている。
そこで、今回は、この本を中心に、なぜ、冷静さがスキルとして学べるのか?を中心にまとめたい。
適応性パラドックス──変化を妨げる無意識の罠
この本の核心の一つが、「適応性パラドックス(Adaptability Paradox)」である。それは、次のような逆説で表される。
「変化に最も適応しなければならないときほど、人は過去の成功体験に頼り、柔軟性を失う。」
このパラドックスが生じるのは、人間の神経系が「安全」を最優先にしているためである。脅威を感じると、交感神経が活性化し、筋肉が緊張し、視野が狭まり、創造的思考が働かなくなる。
こうした防衛的反応は、生存の観点では合理的だが、現代の複雑な社会課題においてはむしろ逆効果となる。
私たちが今問われているのは、「危険を避ける能力」ではなく、「不確実性の中でも開かれ続ける能力」である。
創造モード(Learning Mode)と防衛モード(Protection Mode)──神経系の二つの働き
本書では、人の意識状態を二つのモードに分類して説明している。
| モード | 主な特徴 | 脳・神経の状態 |
|---|---|---|
| 防衛モード(Protection Mode) | 危険を避け、過去のやり方に固執する。焦り・怒り・回避反応が強くなる。 | 扁桃体が優位。交感神経が緊張し、ストレスホルモンが分泌される。 |
| 創造モード(Learning / Creation Mode) | 落ち着いた注意のもと、好奇心や柔軟性が高まる。新しい行動を試す意欲が生まれる。 | 前頭前野が活性化し、副交感神経が働く。呼吸が深く、全身が協調的に機能。 |
防衛モードに陥ると、思考・感情・行動が「反応的」になり、学習や共感の能力が著しく低下する。
一方、創造モードでは、感情を制御しながら環境を広い視野で捉えることができる。ここで重要なのが、自分がどちらのモードにいるかを自覚できる能力である。
デュアル・アウェアネス──「二重の気づき」がもたらす自由
著者たちは、このモードの切り替えを支える中核スキルとして「デュアル・アウェアネス(Dual Awareness)」を提唱する。
それは、外界(状況・他者・出来事)と内界(感情・思考・身体感覚)の両方を、同時に観察できる心の状態である。
精神科医ヴィクトール・フランクルの有名な言葉を引くなら、
“Between stimulus and response, there is a space.
In that space lies our power to choose our response.”
刺激と反応のあいだには「空間」がある。その空間の中に、私たちが選択する力がある。
この「空間」に気づけることが、まさにデュアル・アウェアネスである。
身体の緊張や心のざわめきを観察し、外側で起きている出来事との間に「一呼吸の余白」をつくる。すると、私たちは自動的な反応ではなく、意図的な選択を行う自由を取り戻す。
ゾーンの理論──FamiliarとAdaptiveの境界を越える
この本では、人の行動と学習を「ゾーン(Zone)」という比喩で説明している。
- Familiar Zone(慣れのゾーン):安心感があり、既知のやり方で対処できる領域。
- Adaptive Zone(適応のゾーン):未知で不安を伴うが、真の学習と変容が起こる領域。
人は本能的にFamiliar Zoneに留まろうとするが、変化の本質は常にその外側にある。
適応のゾーンに一歩踏み出したときこそ、デュアル・アウェアネスが試される。
心拍数が上がり、思考が硬直する――その瞬間にこそ、呼吸を整え、自分を観察し、創造モードへ戻す訓練が必要である。
この移行の瞬間を意識的に扱えるようになると、未知への恐れは好奇心に変わり、変化そのものが学びの源泉となる。
意図的な冷静さを育てる3つのステップ
- 気づく(Awareness)
自分が防衛モードに入りつつあることを認識する。身体のこわばり、息苦しさ、怒りや焦りの感覚に気づくことが第一歩である。 - 間をつくる(Pause and Breathe)
反応を止め、一呼吸おく。深い呼吸によって神経系を再調整し、前頭前野の働きを取り戻す。 - 選択する(Choose Intentionally)
恐れからではなく、目的と価値観に基づいて行動を選ぶ。これが「意図的な冷静さ(Deliberate Calm)」の実践である。
この3つのプロセスは単なるメンタルテクニックではなく、「神経可塑性(Neuroplasticity)」を通じて脳と身体を再教育する方法である。繰り返すことで、反応パターンそのものが変化していく。
私自身の実践への示唆
本書を通じて強く感じたのは、「身体感覚への気づき」こそが防衛モードから抜け出す鍵であるということだ。
ロルフィングやコーチングのセッションでは、クライアントが身体の緊張を観察し、呼吸と共に“今ここ”に戻る練習を繰り返す。これはまさに、デュアル・アウェアネスの訓練である。
身体は、心よりも正直である。身体が発するサインを丁寧に感じ取ることによって、思考や感情に支配される前に、自分を再調整できる。
例えば、セッション中にクライアントが「今、呼吸が深くなった」と気づく瞬間。それは、創造モードへの転換が起きたサインである。
コーチングの現場でも同じである。クライアントの反応的な言動を「変えよう」とするのではなく、まず「その瞬間に何が起きているのか」を共に観察するところから始まる。
この“共に気づく”というプロセス自体が、Deliberate Calmの理論を体現している。
さらに興味深いのは、本書が示す理論が、神経科学と発達心理学の橋渡しになっている点である。
防衛モードから創造モードへ、FamiliarからAdaptiveへ──この移行は、脳の構造変化(可塑性)と意識の成長段階(成人発達理論)を同時に含んでいる。
私の実践では、これを身体と対話する形で扱うことで、より深い統合が起きるのを実感している。
おわりに──冷静さは生まれつきではなく、選び取るもの
「冷静さ」は性格ではなく、訓練によって育てられるスキルである。
本書が強調する“Deliberate(意図的な)”という言葉には、深い意味がある。
それは、ただ落ち着くことではなく、「混乱の中で意識的に落ち着きを選び取る」という能動的行為を指す。
現代は、外的な変化が止むことのない時代である。だからこそ、私たちが育てるべきは、外を変える力よりも、内を整える力である。
その力の中心にあるのが、デュアル・アウェアネス──内と外を同時に感じ取り、反応ではなく選択によって生きる知恵である。
この本を通して学んだ「意図的な冷静さ」は、単なるリーダーシップスキルを超え、身体の知性・心の成熟・人間の成長を統合する道であると感じる。






