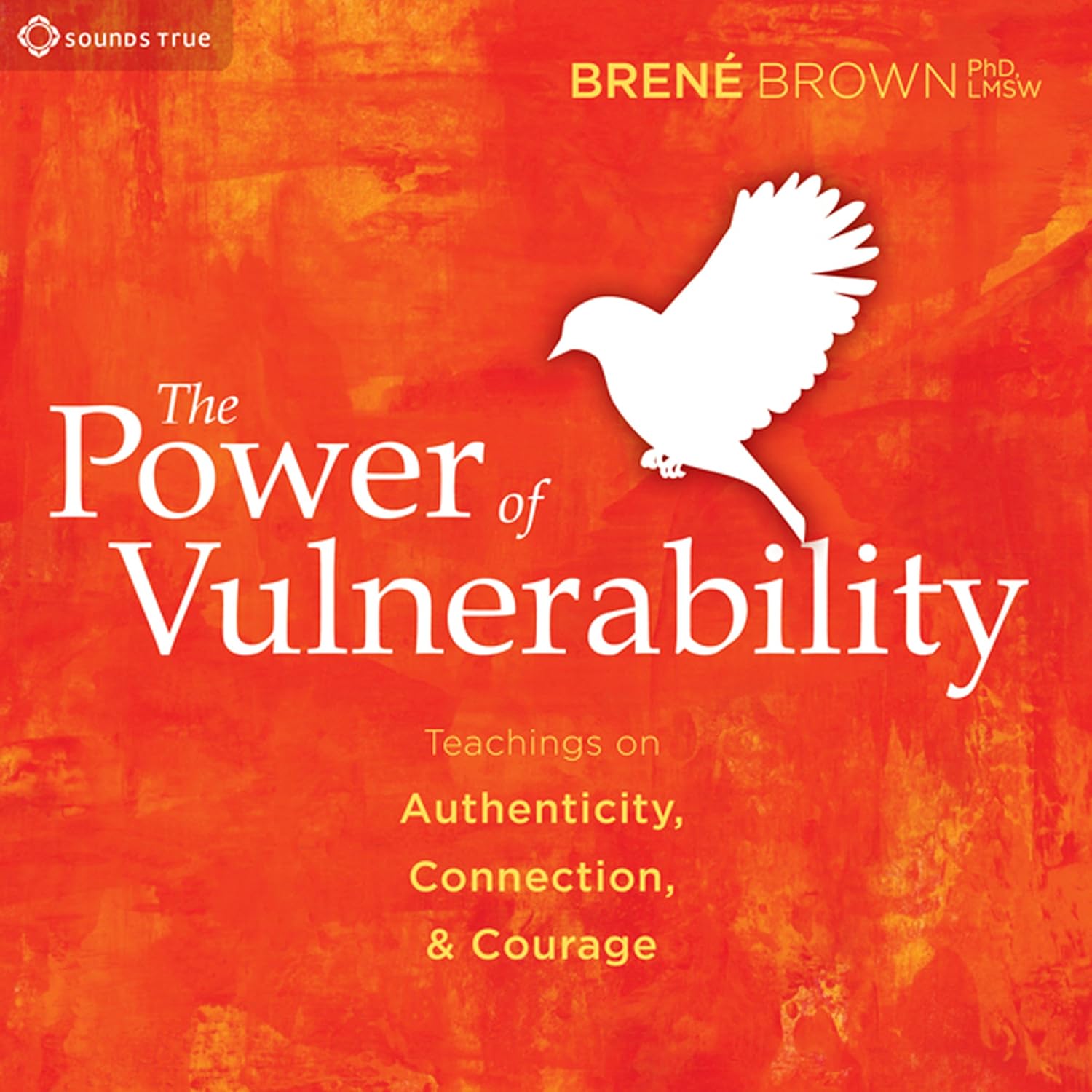【B#231】老化をめぐる「エネルギー感知システム」──AMPK・ラパマイシン・カロリー制限・メトホルミン
Table of Contents
はじめに
こんにちは。渋谷でロルフィング・セッションと脳科学をベースにした講座を提供している大塚英文です。
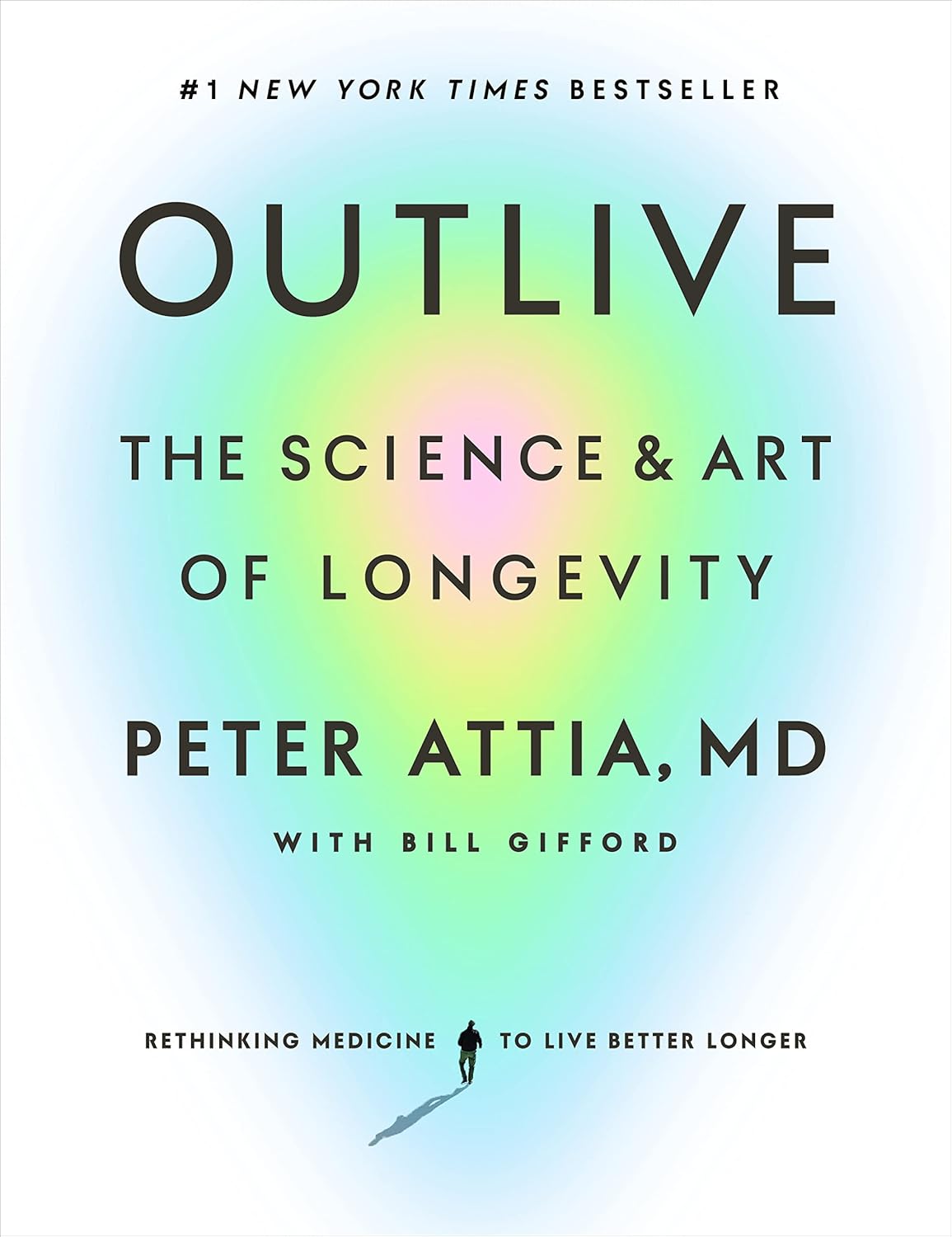
今回も、Peter Attiaの著書『Outlive: The Science and Art of Longevity』をもとに、AMPK、ラパマイシン、カロリー制限、メトホルミンという4つのキーワードから、「老化を制御する〜健康長寿の実現」の科学の最前線を紹介する。
カロリー制限が教えてくれること
長寿研究の世界で、最も古くから注目されてきたテーマの一つが「カロリー制限(Caloric Restriction)」だ。
「カロリー制限」とは、必要最低限の栄養を保ちながら摂取カロリーを減らすことを指す。最初の発見は1930年代、ウィスコンシン大学の栄養学者クライブ・マッケイ(Clive McCay)が、ラットに通常より30〜40%少ない食事を与えると、寿命が40%延びたという報告をしたことに始まる。
以来、酵母、線虫、ショウジョウバエ、マウス、サルなど多くの種で、
「カロリー制限による寿命延長」が確認されてきた。
重要なのは、単に「痩せること」や「断食」とは異なり、栄養バランスを保ちながらカロリーのみを減らすこと。
参考に、ヒトにおいては、動物実験のような「極端なカロリー制限」は必ずしも現実的ではない。以下のような課題がある。
- 長期的な筋肉量・骨密度の低下リスク
- 免疫力の低下、寒さへの耐性減少
- 栄養不足によるホルモンバランスの崩壊
実際、ラットやサルの研究でも、過剰な制限では寿命延長効果が見られないことがある。そこで近年注目されているのが、カロリー制限の「様」な作用機序を考えて、それに似たような作用を期待する方法だ。
カロリー制限の作用機序を見ていく。
栄養摂取量を減らすと、細胞は「燃料不足」を感知する。この状態になると、細胞はストレス耐性を高め、代謝を効率化する。その反応の中心にあるのが、AMPK(AMP-activated Protein Kinase)とmTOR(mechanistic Target of Rapamycin)という二つの経路だ。
以下、この2つの経路と、関わりの深いオートファジーについて見ていきたい。
AMPK ― 代謝の「燃料警報システム」
AMPKは、細胞のエネルギー残量を監視するセンサーのような酵素として、車のガソリン警告ランプが点灯するように、AMPKは「燃料が足りない」と感知するとスイッチが入る。
細胞は、AMPKのシグナルが入ると、省エネモードに切り替わり、次のような反応を起こす。
- ミトコンドリアが新たに作られる=新生(mitochondrial biogenesis)を促進し、エネルギー効率を上げる。
- 肝臓での糖新生や脂肪分解を促して、燃料を確保する。
- mTOR(成長・合成を司る経路)を抑制し、オートファジー(自食作用)を活性化する。
AMPKは、断食や運動の際にも活性化する。「食事制限」や「運動」は、どちらもAMPKを通じて細胞のリフレッシュを促している。
オートファジー ― 細胞の自己修復システム
オートファジーとは、細胞が古くなったタンパク質や損傷した構造を分解・再利用する仕組みだ。日本人研究者の大隅良典教授が解明し、ノーベル賞を受賞したことで日本で話題となった。
オートファジーとは、「自己食作用」と訳される。細胞が古くなったタンパク質や損傷したミトコンドリアなどを分解し、再利用する仕組みとして知られている。
この作用が適切に働くことで、
- 細胞内の「ゴミ(タンパク質凝集体)」を除去し、
- 酸化ストレスを軽減し、
- エネルギー効率を最適化します。
神経変性疾患(アルツハイマー病・パーキンソン病)では、このオートファジー機能が低下していることが知られている
興味深いのは、このオートファジーを食事制限・断食・運動・ラパマイシン(rapamycin)などで再び活性化(AMPKの活性化やmTORの抑制)できるという点だ。
ラパマイシン ― mTORを制御して寿命を延ばす薬
ラパマイシンは、もともと、臓器移植後の拒絶反応を防ぐための免疫抑制剤として使われている。発見の経緯を含め、以前ブログにまとめた。近年、動物実験では寿命を延ばし、健康寿命(healthspan)を改善効果が認められている(「老化研究の新しい地平──リチャード・ミラー博士とITP(マウス老化モデル)の挑戦」参照)
効果の鍵を握るのが、mTOR経路の抑制だ。mTORは細胞の成長と合成を促すシグナル経路だが、過剰に活性化すると老化が進行する。ラパマイシンはこのmTORを一時的に抑えることで、細胞を「修復と再生のモード」に切り替える。
以下のようにまとめることができる。
- mTORオン → 細胞成長、合成、増殖
- mTORオフ → オートファジー、修復、ストレス耐性向上
老化とは、多くの場合、mTORが慢性的にオンの状態とも言える。この過剰な成長シグナルが、がん・糖尿病・動脈硬化など「老化関連疾患」を促進すると考えられている。
興味深いのは、投与のリズムによって効果がまったく異なる点だ。
- 連日投与 → mTORの2つの複合体(mTORC1とmTORC2)をともに抑制し、免疫抑制の作用が強まる。
- 週1回などの周期的投与(cyclic dosing) → 主にmTORC1を抑制し、むしろ免疫機能を高めることがある。
2014年のノバルティス社の研究では、ラパマイシンの類縁体「エベロリムス(everolimus)」を高齢者に週1回投与したところ、インフルエンザワクチンへの抗体応答が向上した。
つまり、ラパマイシンは「免疫抑制剤」ではなく、投与方法によっては免疫を調整し、若返らせる薬になりうるのだ。
Dog Aging Project ― 犬の老化を食い止める実験
ワシントン大学のMatt Kaeberleinは、ラパマイシンをペット犬に投与してその影響を調べる「Dog Aging Project」を進めている。犬はヒトと同じ環境で生活し、同じように老化するため、老化研究の優れたモデルとされている。
なぜ「犬」なのか? — モデルとしての強み
- 犬はヒトと同じように家庭環境で生活し、医療ケアを受けており、環境的条件がヒトに近い。
- 犬の寿命はヒトより短いため、「老化」という時間を圧縮して観察できる。つまり、ヒトで数十年要する現象を、犬では比較的短期間で追える可能性がある。
- 品種・体格・遺伝的背景が大きく異なる犬種が多数存在し、「変異」が大きいため、遺伝・環境・ライフスタイルの影響を捉えやすい。
- 犬はヒトと同じ環境下で老化性疾患(心疾患・腫瘍・関節疾患など)を発症する機会があり、ヒトに対しもデータを適用しやすい。
予備研究では、ラパマイシンが心臓機能の改善や慢性炎症の減少をもたらすことが確認され「臓器の若返り」さえも示唆されている。
この研究の本試験には600匹以上の犬が参加しており、結果は2026年に発表予定だそうだ。
メトホルミン ― 糖尿病薬から「長寿薬」へ
もう一つ注目されている薬が、糖尿病治療薬のメトホルミン(metformin)。長年の臨床データから、メトホルミンを服用している糖尿病患者は、がん発症率が低く、場合によっては非糖尿病者よりも長寿であることが報告されている。
この観察を踏まえ、Nir Barzilaiが主導する「TAME試験(Targeting Aging with Metformin)」が進行中だ。
この試験では、「老化」そのものを測定するのではなく、老化関連疾患(がん・心疾患・認知症など)の発症時期が遅れるかどうかを評価する。
もし有効性が確認されれば、老化そのものを医療の対象とするという画期的な一歩になる。
Medicine 3.0 ― 「病気を治す」から「健康を維持する」時代へ
Peter Attiaは、こうした研究を「Medicine 3.0」と呼んでいる。それは、病気を発症してから治療する従来の医学(Medicine 2.0)とは異なり、病気になる前に介入し、健康寿命を最大化する医療のことだ。
AMPK、mTOR、ラパマイシン、メトホルミン──
これらは単なる薬や酵素の話ではなく、
「エネルギーの感知」と「修復のスイッチ」という、人間の生物学の根本を示している。
まとめ
| 機構/薬剤 | 主な標的 | 作用方向 | 主な効果 |
|---|---|---|---|
| カロリー制限 | 栄養センサー全般 | 栄養不足を模倣 | AMPK活性化、mTOR抑制、オートファジー促進 |
| AMPK | エネルギー感知酵素 | 低栄養状態で活性化 | ミトコンドリア新生、脂肪燃焼、修復促進 |
| ラパマイシン | mTORC1 | 成長シグナル抑制 | オートファジー促進、炎症抑制、免疫調整 |
| メトホルミン | AMPK間接活性化 | 糖代謝調整 | インスリン感受性改善、加齢関連疾患予防 |
これらすべてに共通するのは、「細胞がエネルギー不足をどう感じ、どう回復するか」という点。老化を単なる時間の経過ではなく、「細胞の情報処理の偏り」と捉える視点。それこそが、Attiaが目指す「長く、より良く生きる」ための科学的アプローチだと言える。
この投稿が少しでも役立つことを願っています。