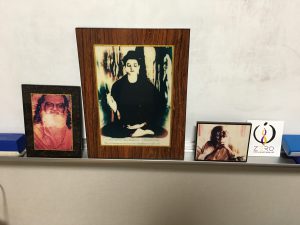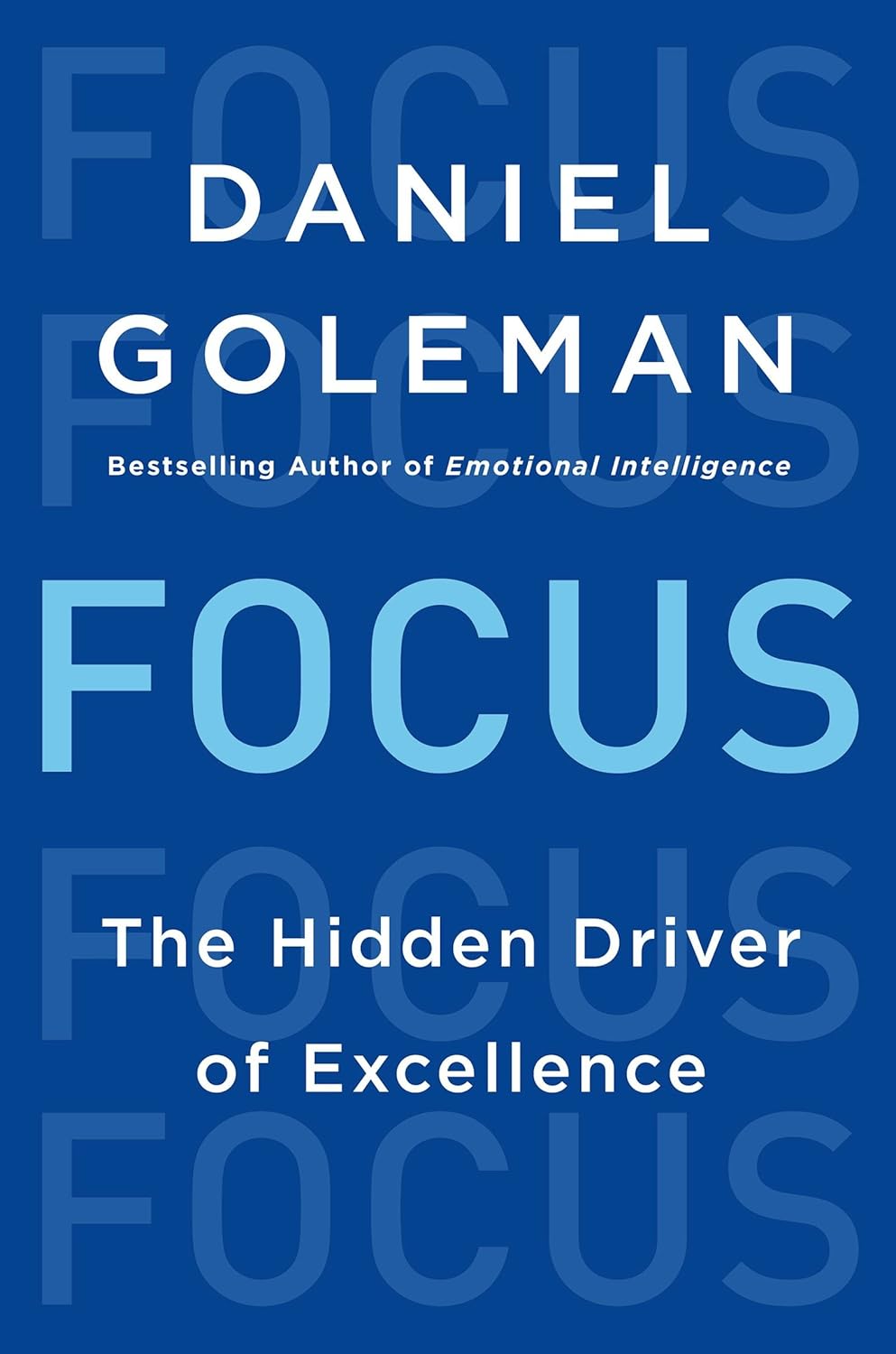【B#227】太平洋の火山が生んだ長寿の鍵──ラパマイシン(Rapamycin)の物語
Table of Contents
はじめに
こんにちは。渋谷でロルフィング・セッションと脳科学をベースにした講座を提供している大塚英文です。

私は普段より、健康寿命をどのように延ばすのか?についての情報を発信している。そこで参考にしているのは、Peter AttiaのOutlive – The Science & Art of Longevityという本だ。2023年に出版されてから、繰り返し繰り返し読んでる。
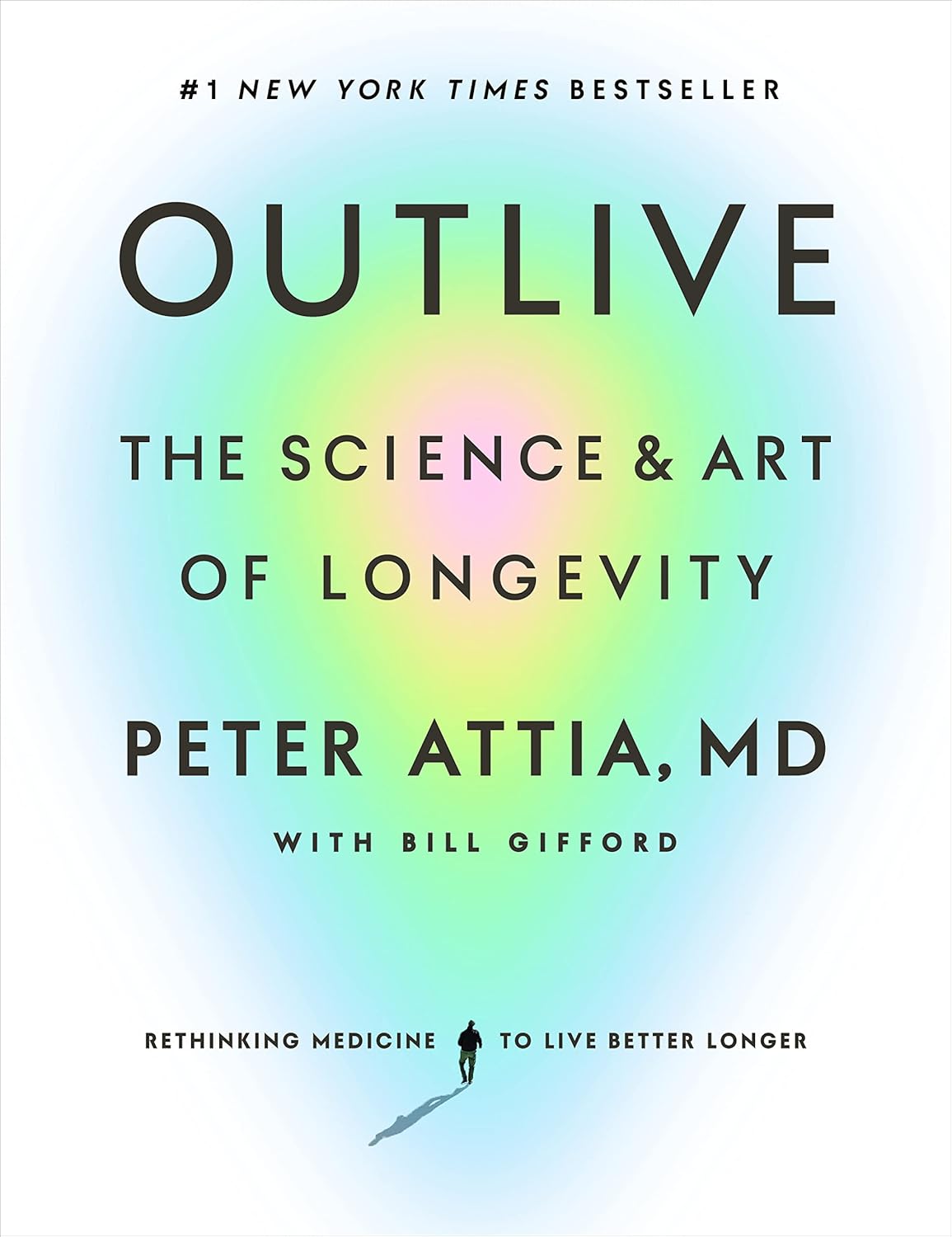
今年(2025年)の9月25日に邦訳(ピーター・アッティア著「OUTLIVE(アウトリブ) 人はどこまで生きられるのか 健康長寿の限界を超える科学的戦略」)が出たので、ご興味のある方はぜひ手に取っていただきたいと思っている一冊だ。
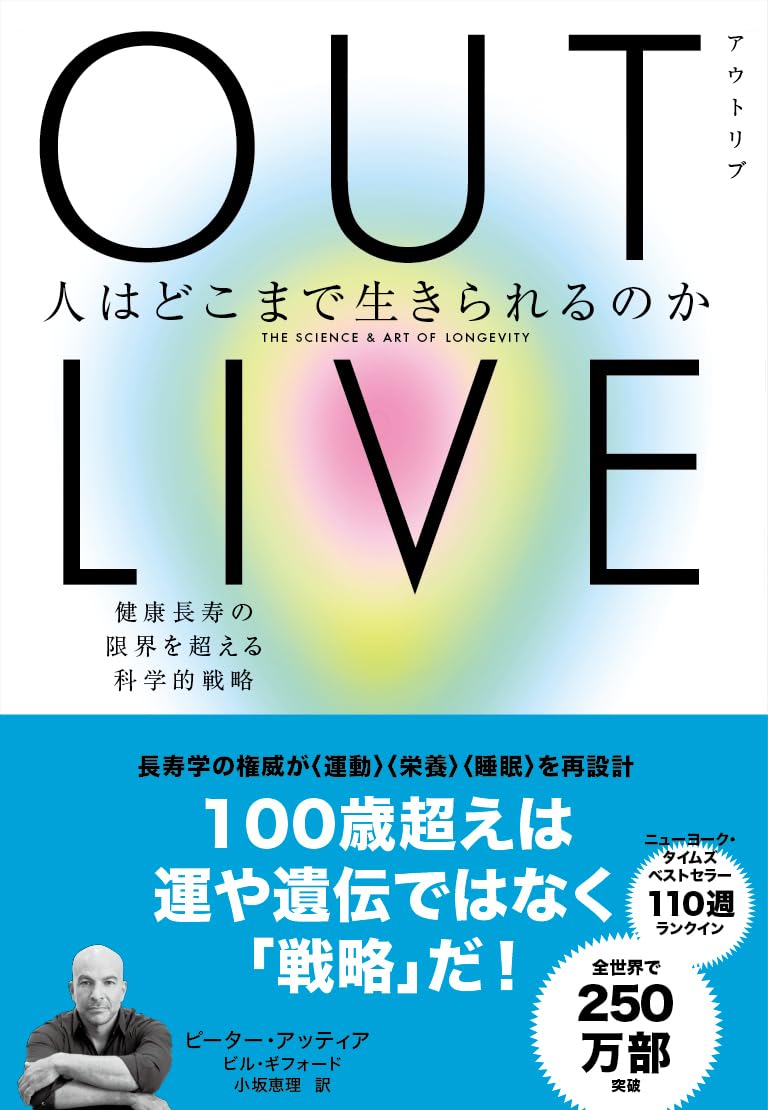
この本には健康長寿に関してさまざまな情報が掲載されているが、個人的に面白かったのが、臓器移植後の免疫抑制薬として使われている「ラパマイシン(Rapamycin)」だ。近年、ラパマイシンは老化を進めるのを遅らせるというデータが出ており、注目されている。
この分子がどのように発見され、老化にかかわるようになったのか?物語として面白いので、Peter Attiaの本を参考にまとめてみたい。
イースター島の巨大な死火山から物語が始まる
太平洋の南米にある孤島、ラパ・ヌイ(イースター島、現地ではこのように呼ばれている)の南西部には、ラノ・カウ(Rano Kau)という巨大な死火山がある。
火口の中心には、1 マイルほどの湿地の湖が広がり、地元の人々の間では「病に苦しむ者が火口に降り、一夜を過ごせば癒やされる」と信じられてきた。火山の胎内には、何か特別な“生命の力”が宿る──そう語り継がれてきたのである。
Peter Attiaは『Outlive』の中でこう書く。
“This is where the story of rapamycin begins.”
「ラパマイシンの物語は、ここから始まる。」
1964年、医療探検隊が島にやって来た
1964年の終わり、カナダ・ハリファックスから1隻の海軍艦艇が、はるか南太平洋の孤島を目指して出航した。
この航海こそが、Medical Expedition to Easter Island(METEI)──イースター島医療探検隊である。
探検の目的は、当時の島民の健康状態を調べ、医療支援を行うことだった。チリ政府が島に空港建設を計画しており、「外界との接触が始まる前の状態を記録しておく」ことが急務だったのである。
医学者たちは、栄養状態や感染症、遺伝的特徴などを調査し、同時に島の土壌・植物・微生物のサンプルも採取することになった。
彼らが採取した土の中に、火山湖のほとりで採れた瓶があった。それが、のちに「ラパマイシン」と呼ばれる物質を含む土だった。
彼らもまた、島民が語る“癒やしの火口”の伝説を耳にしていたという。偶然にも──いや、自然の導きによって──その土の中には、生命の老化を左右する微生物が眠っていたのだ。
モントリオールの研究室で見つかった“奇妙な物質”
数年後、カナダ・モントリオールにあるAyerst Research Laboratoriesの生化学者、スレン・セーガル(Suren Sehgal)のもとに、イースター島の土壌サンプルが届いた。
セーガルは、その中に「強力な抗真菌作用をもつ未知の物質」が存在することを発見する。土壌中の放線菌 Streptomyces hygroscopicus が産生する物質であった。彼はその化合物を分離・培養し、「Rapamycin」と名づける。
“Rapa”は島の名Rapa Nuiから、“mycin”は抗生物質を意味する接尾語である。
当初、彼が期待したのは「水虫の特効薬」だった。実際、近所の女性にこの物質を含む軟膏を試したところ、皮疹が瞬く間に治ったという。だが、ラパマイシンの真の可能性は、はるかに大きかった。
科学者の執念──冷凍庫に眠った瓶
1970年代初頭、Ayerst社は経営統合によりモントリオールの研究所を閉鎖した。経営陣は、セーガルに「すべての試料を破棄せよ」と命じる。
彼は命令に背いた。ひと瓶のラパマイシンをこっそり研究所から持ち出し、自宅の冷凍庫に隠して保存した。
息子のアジャイ(Ajai)によれば、
「アイスクリームを取り出そうと冷凍庫を開けると、“DO NOT EAT”と書かれた謎の容器があった」という。
数年後、セーガルがアメリカ・プリンストンに転勤すると、瓶も一緒に引っ越した。
1987年、製薬大手Wyeth(現ファイザー)がAyerstを買収したとき、新しい上司に「何か面白いテーマはあるか?」と尋ねられ、
彼は再び冷凍庫からその瓶を取り出した。そこから、ラパマイシンの第二の人生が始まったのである。
ラパマイシンの“力”──免疫から長寿へ
1999年、ラパマイシン(一般名シロリムス)は、アメリカFDAにより臓器移植患者の免疫抑制薬として承認された。免疫反応を抑えることで、移植臓器が拒絶されるのを防ぐ。
さらに、その特性を応用して冠動脈ステントの再閉塞防止薬としても使われるようになった。
その後も“ヒット”は続く。
2007年には、ラパマイシン類似化合物のエベロリムス(everolimus)が腎臓がん治療薬として承認され、
この分子の多面的な応用が明らかになっていく。
Wyeth社は、イースター島のラノ・カウ火口近くに記念碑を建て、この発見を称えた。しかし、Attiaが島を訪れたとき、碑はすでに盗まれており、跡形もなかったらしい。
mTORという“スイッチ”
ラパマイシンがなぜ多様な作用を持つのか──その鍵を解いたのが、分子生物学者デヴィッド・サバティーニ(David Sabatini)博士だった。
彼は、セーガルから渡された論文コピーを手に、細胞内でラパマイシンが作用する標的を追い続けた。
その結果、ラパマイシンが直接作用するタンパク複合体を発見した。
それがmTOR(mechanistic Target of Rapamycin)である。
mTORは、細胞が成長モードに入るか、あるいは節約・修復モードに入るかを決める“指揮官”のような存在だ。
栄養やアミノ酸が豊富なときは活性化し、細胞はタンパク合成・分裂・繁殖を進める。
逆に栄養が乏しいときには、mTORが抑制され、細胞はオートファジー(自己分解)によって老廃物を掃除し、
代謝を節約しながら生き延びる。
Attiaはこの仕組みをこう表現する。
“mTOR basically has a finger in every major process in the cell.”
「mTORは、細胞内のあらゆる主要プロセスに指をかけている。」
ラパマイシンはこのmTORを一時的に“休ませる”ことで、細胞を修復と再生のフェーズへ導く。つまりそれは、生命のエネルギー配分を切り替えるスイッチとなるらしいのだ。
老化を遅らせる薬
2009年、『ニューヨーク・タイムズ』の小さな記事が世界を驚かせた。
「抗生物質、マウスの老化を遅らせる(Antibiotic Delayed Aging in Mice)」──
ここで言う“抗生物質”こそがラパマイシンであった。
別のブログの記事で紹介したが、アメリカ国立老化研究所(NIA)主導で行われているのが、Interventions Testing Program(ITP、介入試験プログラム)だ。ITPは、老化の仕組みを解明するプログラムの一環だが、そこで使われるマウスに対して、ラパマイシンを投与した結果、メスで13%、オスで9%長く生きたのだ。
一見、平凡なニュース。しかし、内容は驚異的であった。
マウスが「老年期」に入ってから──つまり生後600日(人間でいえば60歳前後)にラパマイシンを投与しても、残りの寿命がオスで28%、メスで38%延びたというのである。
Attiaはこう記している。
“It was the equivalent of a pill that could make a sixty-year-old woman live to the age of ninety-five.”
「それは、60歳の女性を95歳まで生かす薬に匹敵する効果だった。」
この研究は科学誌『Nature』に発表され、論文の著者らは、「ラパマイシンは、がんによる死を遅らせる、あるいは老化機構そのものを遅らせることで寿命を延ばした可能性がある」
と述べている。
ここで重要なのは、ラパマイシンが哺乳類の寿命を延ばした“初めての化合物”だったという点である。しかも、結果は偶然ではなかった。
この実験は、ITPの取り決めに基づいて、3つの独立した研究チーム・3つの異なる研究所で、合計1,901匹の遺伝的に多様なマウスを用いて実施され、すべての研究で一貫した成果が得られた。
さらに、その後、複数の研究機関によって再現実験でも同様の結果が確認された。
Attiaはこの点を強調する。
“The results had been consistent across the board… Even better, other labs quickly and readily reproduced these results, which is a relative rarity.”
「結果はすべての実験で一致し、さらに他の研究室でも容易に再現された──それは科学界では非常に稀なことである。」
再現できなかった“奇跡のサプリ”たち
ラパマイシンの発見は、科学の再現性という観点でも特筆すべきである。多くの“話題の長寿成分”が再現に失敗した中で、唯一確実な結果を示したのがラパマイシンだった。
2006年、赤ワインの皮に含まれるレスベラトロールが肥満マウスの寿命を延ばしたという研究が発表され、
メディアは「ワインを飲めば長生きできる」と騒いだ。
だが、後続の研究では再現されず、アメリカ国立老化研究所(NIA)が実施した厳密な再試験でも、寿命延長効果は認められなかった。
同様に、話題を呼んだニコチンアミドリボシド(NR)も、正常マウスでは寿命延長を示さなかった。つまり、マウスやヒトにおいて、サプリメントが寿命を延ばした確実な証拠は存在しないのである。
一方で、ラパマイシンに関しては、2009年以降の研究が次々とその効果を裏づけている。酵母、ショウジョウバエ、線虫などの多様な生物種においても、mTORの活性を抑えることで寿命が延びることが確認された。
“Thus, a reasonable person could conclude that there was something good about turning down mTOR, at least temporarily.”
「少なくとも一時的にmTORを抑えることには、何らかの生物学的な利点がある──そう結論づけるのが妥当だろう。」
mTORが教える“成長と再生”のバランス
ラパマイシンの根底にあるメカニズムは、前述のmTORである。
mTORは、栄養・エネルギー・成長因子などの情報を統合し、細胞が「成長モード」で新たなタンパク質を合成するか、あるいは「修復モード」でオートファジーを促進するかを決定する。
Attiaは、mTORを次のように比喩している。
“To some extent, mTOR is like the general contractor for the cell.”
「mTORは、細胞の“ゼネラル・コントラクター(総合請負人)”のような存在だ。」
栄養が豊富であれば、細胞は分裂を繰り返し、成長と繁殖にエネルギーを注ぐ。一方、栄養が乏しい環境では、mTORが抑制され、細胞は“再生と省エネ”のモードに入る。このバランスこそが、生命の時間をどのように使うかを決める鍵になる可能性がある。
ラパマイシンは、このスイッチを意図的に切り替える薬だ。細胞に「少し休め」と伝えることで、代謝の再調整と修復の時間をつくる。その結果、老化の進行を遅らせ、健康寿命を延ばす可能性が生まれるのだ。
まとめ──自然と進化が残した“知恵”
ラパマイシンの物語は、火山の伝説、偶然の発見、科学者の執念、そして進化の叡智が交錯する壮大な生命史である。
太平洋の孤島の土から見つかった分子が、
酵母からヒトに至るまで、生命の普遍的メカニズムを制御する鍵であるという事実。
それは、進化が何億年にもわたって受け継いできた「生きる力」と「休む力」のバランスを象徴している。
Attiaは、ラパマイシンを単なる“長寿薬”としてではなく、「生命の仕組みを理解するための光」と捉えている。
“Rapamycin is not a fountain of youth, but a flashlight that shows us how aging works.”
「ラパマイシンは若返りの泉ではない。老化の仕組みを照らす懐中電灯なのだ。」
私たちが学ぶべきは、薬そのものよりも、自然の中に潜む“時間の使い方”の智慧なのかもしれない。生命とは、常に成長と再生のあいだで揺らぎながら、進化し続ける存在であるとも言えるのではないかと思う。