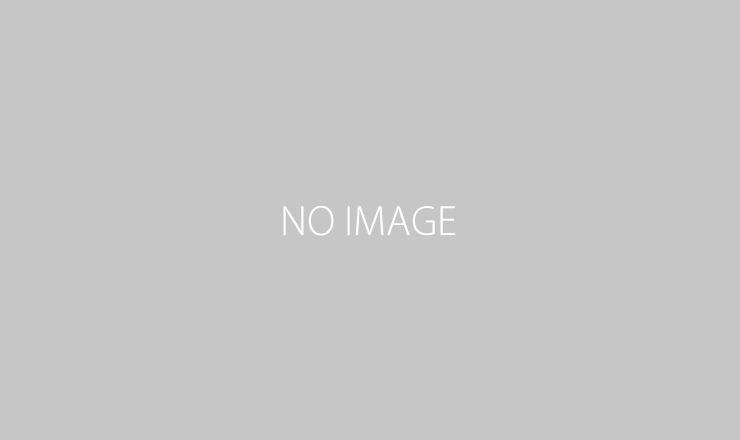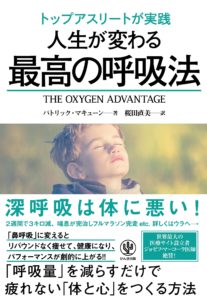【B#225】自分の古典を持つことの大切さ ― 『知的生活の方法』から学ぶ
Table of Contents
はじめに
こんにちは、渋谷でロルフィング・セッションや脳科学をベースにした講座を提供している大塚英文です。
私自身、これまで多くの本と出会い、そして手放してきた。仕事や人生の転機のたびに、必ず本から大きなヒントを得てきたように思う。そのなかで、何度も繰り返し読み返し、自分の土台を作ってくれた本がいくつかある。
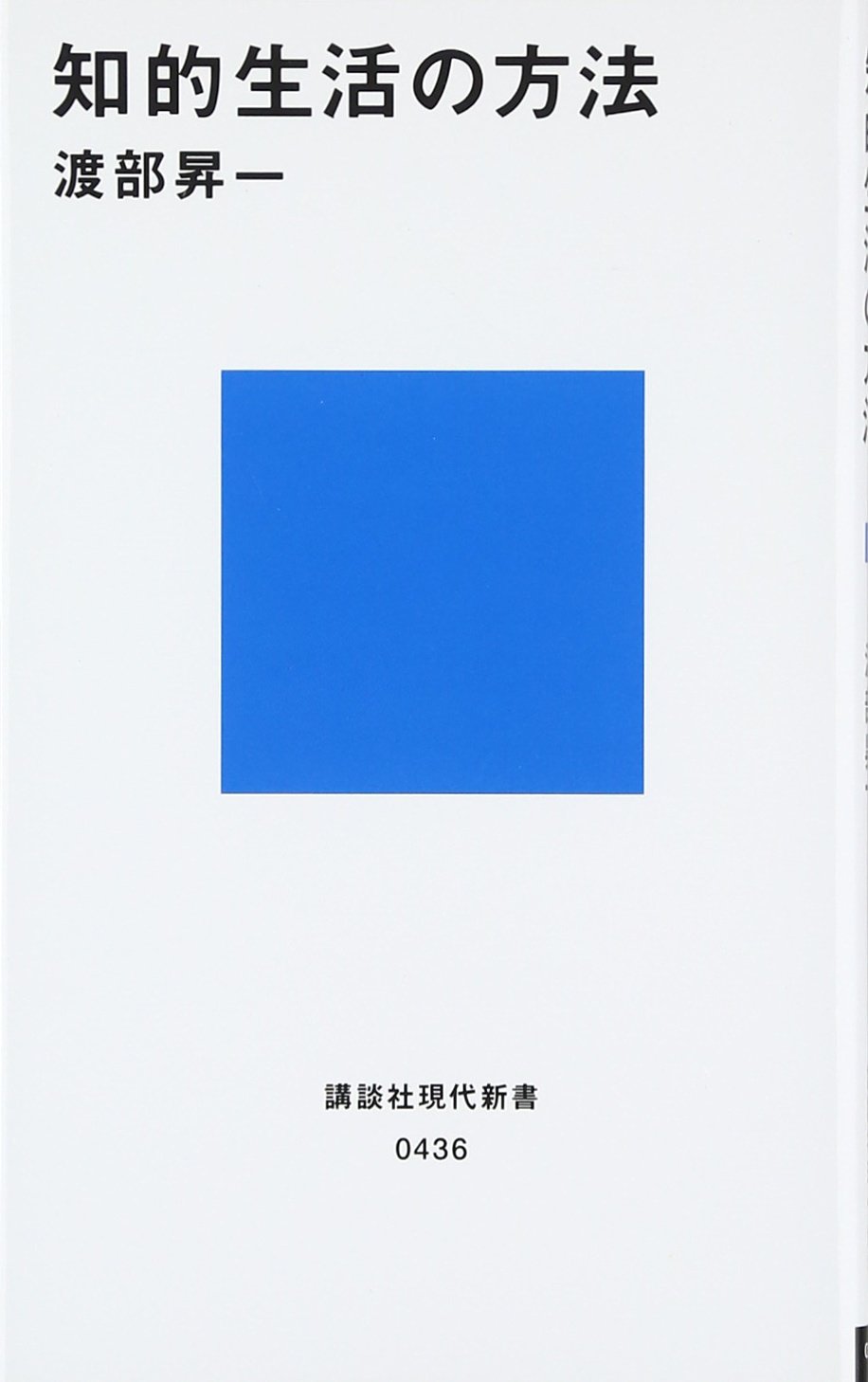
最近改めて読み直したのが、渡部昇一先生の名著『知的生活の方法』である。この本には、単なる「知識を増やすための読書法」ではなく、知的に生きるための姿勢が貫かれている。その中心にあるのが「自分の古典を持つこと」と「知的正直であること」の大切さである。
繰り返し読むことがもたらす力
渡部先生は、繰り返し本を読むことの意義を次のように述べている。
「このように繰り返して読むということの意味はどういうことなんだろうか。それは筋を知っているのにさらに繰り返して読むということであるから、注意が内容の細かい所、面白い叙述の仕方にだんだん及んでいゆくということになるであろう。これはおそらく読書の質を高めるために必須の条件と言ってもよいと思う」
物語の筋を追うだけではなく、再読を通じて細部や理念に目が向く。まさに、反復が読書の質を高めるということである。
自分の古典を持つということ
さらに渡部先生は問いかける。
「あなたは繰り返して読む本を何冊ぐらい持っているだろうか。それはどんな本だろうか。それがわかれば、あなたがどんな人かよくわかる。しかしあなたの古典がないならば、あなたはいくら本を広く、多く読んでも私は読書家とは考えたくない」
ここで言う「古典」とは、歴史に残る普遍的な名著という意味にとどまらず、自分にとっての古典を指している。何度も読み返し、そのときの自分に新しい気づきをもたらしてくれる一冊。そこには、自分の知的な趣味や人となりが反映されている。
私にとっての「古典」:洋書・和書のリスト
私自身も、人生の節目ごとに繰り返し手に取り続けている本がある。例えば、私自身の洋書(英語)と和書の古典を挙げてみると、発売日順に並べると、以下のようなリストができる。
洋書(発売日順)
- Dale Carnegie – How to Win Friends and Influence People (1936年)(邦訳:デール・カーネギー著『人を動かす』)
- Robert Pirsig – Zen and the Art of Motorcycle Maintenance (1974年)(邦訳:ロバート・パーシグ著:『禅とオートバイ修理技術: 価値の探究』)
- Richard P. Feynman – Surely You’re Joking Mr. Feynman! (1985年)(邦訳:リチャード・ファインマン著:『ご冗談でしょう、ファインマンさん』)
- Peter F. Drucker – New Realities (1989年)(邦訳:ピーター・ドラッカー著:『新しい現実』)
- Steven R. Covey – 7 Habits of Highly Effective People (1989年)(邦訳:スティーブン・R・コヴィー著:『7つの習慣』)
- Deepak Chopra – The Seven Spiritual Laws of Success (1994年)(邦訳:ディーパック・チョプラ著:『富と成功をもたらす7つの法則』)
- Michael Pollan – Omnivore’s Dilemma (2007年)(邦訳:マイケル・ポーラン著:『雑食動物のジレンマ』)
- Ed Catmull and Amy Wallace- Creativity, Inc. Overcoming the Unseen Forces that Stand in the Way of True Inspiration (2014年)(邦訳:エド・キャットムル著『ピクサー流・創造する力』)
- Yuval Noah Harari – Homo Deus (2015年)(邦訳:ユヴァル・ノア・ハラリ著:『ホモ・デウス:テクノロジーとサピエンスの未来』)
- Peter Attia, Bill Gifford – Outlive, The Science and Art of Longevity (2023年)(邦訳:ピーター・アッティア著:『OUTLIVE(アウトリブ) 人はどこまで生きられるのか: 健康長寿の限界を超える科学的戦略』)
和書(発売日順)
- 岡本太郎著:『今日の芸術』(1963年)
- 渡部昇一著:『知的生活の方法』(1976年)
- 塩野七生著:『海と都の物語』(1980年)
- 伊藤肇著『人間的魅力の研究』(1980年)
- 塚本哲也著:『我が青春のハプスブルグ・皇妃エリザベートとその時代』(1996年)
- 中村天風著:『運命を拓く』(1998年)
- 稲盛和夫著:『生き方』(2004年)
- 木田元著:『反哲学入門』(2007年)
- 森信三著・他:『現代の覚者たち』(2011年)
- 内藤廣著:『内藤廣と若者たち : 人生をめぐる一八の対話』(2011年)
興味深いことに、これらの「私の古典」には共通点がある。
- 読むたびに毎回違った発見や気づきをもたらしてくれること
- 文章のリズムが良く、すんなりと自分の中に入ること
- 自分の書く文章に大きな影響を与えてきたこと
この三つの要素があるからこそ、私は何度でも繰り返し読み返し、学び直すことができるのである。
まとめ
流行の本や情報を追うことも必要だが、それ以上に「自分の古典」を持つことは、知的生活を長期的に支える土台となる。
繰り返し読むことによって、脳の回路が変わり、趣味が形成され、理念を感じ取る力が磨かれていく。そうしてこそ、私たちは「知的正直さ」を持って自分の道を歩むことができるのである。
あなたにとっての「古典」は何であろうか。ぜひ、折に触れて読み返すことで、自分だけの知的な宝物を育ててほしいと願っている。