【B#220】ADHDをめぐる新しい視点──Gabor Maté『Scattered Minds』を読み終えて
Table of Contents
はじめに
こんにちは、渋谷でロルフィング・セッションや脳科学をベースにした講座・コーチングを提供している大塚英文です。
今回は、カナダの医師ガボール・マテ(Gabor Maté)の著作 Scattered Minds について取り上げる。この本は、著者自身がADHD(Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder、注意欠如・多動症)を抱えていた体験を出発点に、多岐わたってADHDを紹介しており、私自身、ADHDの理解が深まった。
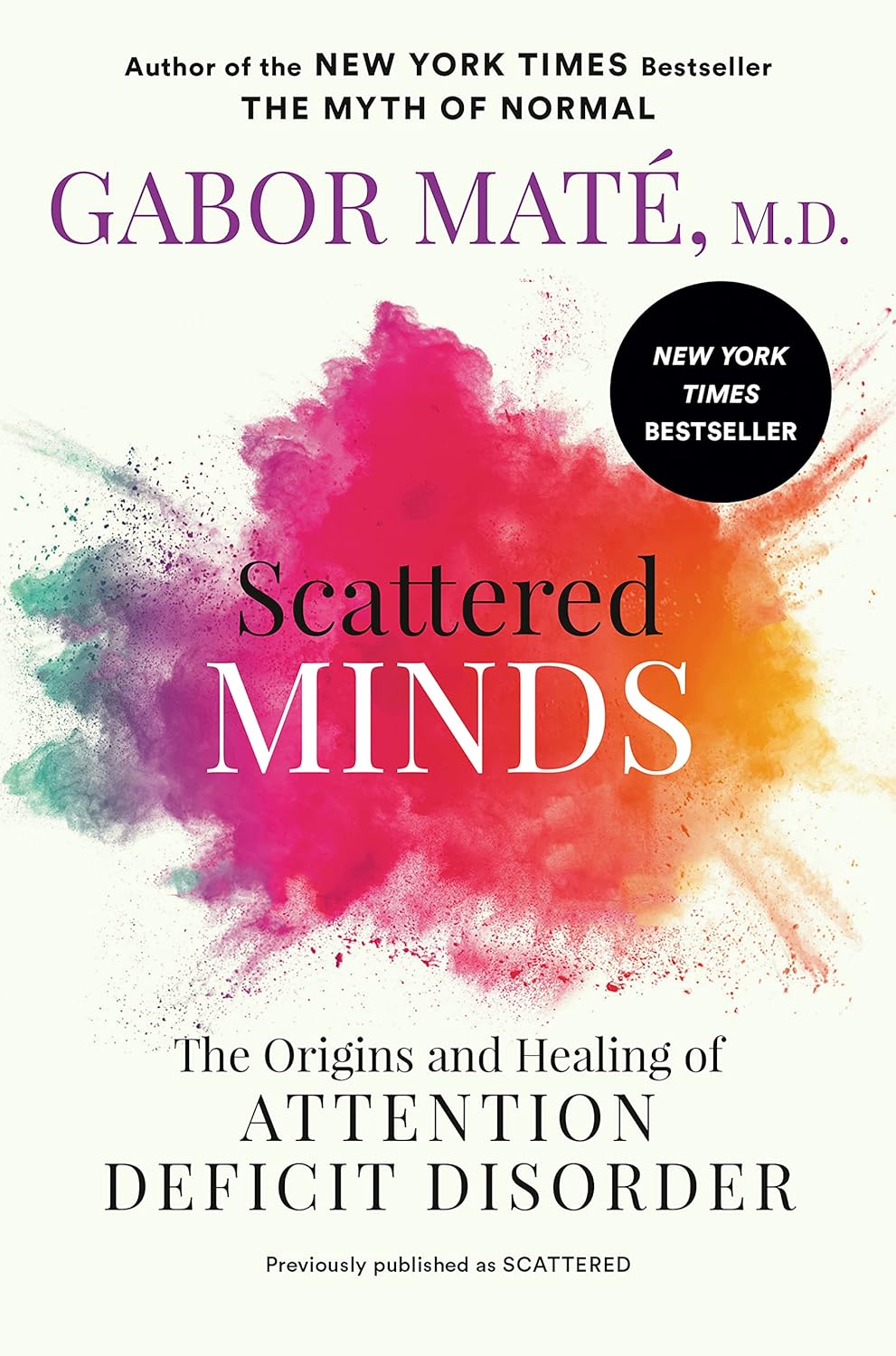
参考に、ADHDについては、過去に、治療薬(精神刺激薬)という視点から「ADHDの診断基準、アデロール、リタリン、コンサータ、認知行動療法」で取り上げたので、ご興味のある方は、チェックください。
今回は、マテの視点からADHDを紹介したい。
著者自身の生い立ちと体験
マテは1944年、ナチス占領下のブダペストで生まれた。ユダヤ人であった彼の家族は迫害に直面し、父親は強制労働に送られ、母親は日々の恐怖と飢えの中で赤ん坊を育てなければならなかった。母親は愛情深く子どもを抱いたが、同時に常に恐怖と緊張を抱えており、その情動状態は幼いマテに深く刻み込まれた。
同じ家庭に生まれながら、兄は比較的落ち着いた性格であったのに対し、マテ自身は注意が散漫で衝動的であった。この対比は、遺伝子がすべてを決めるのではなく、親との関わり方や安心感の度合いが子どもの神経発達に決定的な影響を与えることを物語っているという。
マテはこう書いている。
“The ADD mind is not a defective mind, but a mind developed in response to difficult circumstances.”
(ADHDの心は「欠陥のある心」ではなく、困難な状況に応答する中で形成された心なのである。)
この視点は、ADHDを持つ人やその家族に深い理解と慰めを与えるのではないかと思う。
ADHDは「遺伝病」ではなく、環境への適応
従来、ADHDは強く遺伝に依存する疾患と考えられてきた。しかし、マテは、遺伝子はあくまで「可能性の枠組み」を提供するに過ぎず、実際にADHDとして現れるかどうかは、幼少期の環境ストレスと親子関係の質に大きく左右されるという。
幼児は、恐怖や緊張に満ちた環境で感情を抱えきれないとき、注意を散らすことで生き延びようとする。感情の重荷から身を守るために「気づかないこと」を選び、その結果として「注意が外に飛ぶ」パターンが形成される。これが後に「注意欠如」と呼ばれる特性へとつながっていく。
マテは次のように述べている。
“What we call a disorder is actually a coping mechanism, a survival strategy in the face of unbearable stress.”
(私たちが「障害」と呼んでいるものは、実際には耐えがたいストレスに直面したときの対処メカニズムであり、生存戦略なのである。)
ここに、ADHDを「固定的な疾患」ではなく「環境に適応する過程で形成された神経パターン」という新たな視点で捉えることができる。
愛着理論との接点──情動調整と注意の発達
マテは、ADHDの根底には「情動の自己調整」と「注意のコントロール」の未発達があると指摘する。この点はジョン・ボウルビィ(John Bowlby)の愛着理論(Attachment Theory)と深く響き合う。
乳児は母親や養育者との安定した愛着を通じて、感情を落ち着け、自律神経を安定させる方法を学ぶ。しかし母親自身が強いストレスを抱え、情動的に不安定な場合、その安定は子どもに伝わらない。すると子どもは「自己調整する能力」と「注意を持続する能力」を十分に発達させることができず、後にADHDの症状となる。
マテは書いている。
“The circuitry of attention and self-regulation develops only in the presence of a calm, attuned caregiver.”
(注意と自己調整の回路は、落ち着いて共鳴してくれる養育者の存在があって初めて発達するのである。)
この言葉は、ADHDを理解する上で愛着関係の重要性を如実に物語っている。
治療と展望──神経可塑性を生かす道
では、ADHDに対してどのような治療や支援が可能なのか。マテは薬物療法の短期的な効果を認めつつ、それを唯一の解決策とすることに警鐘を鳴らす。彼が重視するのは、環境と経験を通じた脳の再統合である。
その方法は多岐にわたる。
- 心理療法と自己理解
幼少期の傷つきを理解し、自分が「壊れている」のではなく「生き延びるために適応したのだ」と再解釈すること。 - 安全な人間関係
安心できるパートナーやコミュニティとの関係を築き、神経系に安定の体験を与えること。 - マインドフルネスと瞑想
注意を「今ここ」に根付かせる練習は、散漫な心を穏やかに統合する助けとなる。 - 身体的アプローチ(ボディワーク、運動、呼吸法)
身体感覚を通じて神経系を落ち着け、情動調整の基盤を取り戻すこと。 - 教育的サポート
子どもの個性を尊重した学習環境を整え、成功体験を積み重ねること。
マテは未来に希望を見出している。
“Healing is possible because the brain is not fixed; it is shaped by experience throughout life.”
(癒しは可能である。なぜなら脳は固定的なものではなく、生涯を通じて経験によって形づくられるからである。)
神経可塑性という科学的事実が、ADHDを持つ人々に「変わる可能性」を保証するのである。
おわりに
Scattered Minds は、ADHDを「遺伝的な疾患」として単純に説明するのではなく、愛着・環境・神経発達の文脈で理解することを提案する書である。著者自身の苦悩と洞察を背景にした語りは説得力を持ち、ADHDを持つ人々や家族に新たな視点と希望を与えてくれる。
ADHDとは「壊れた脳」ではなく、「環境に適応した脳」である。そしてその脳は、再び経験と関係性を通じて変化し得る。マテの言葉は、この可能性を私たちに思い出させる。




