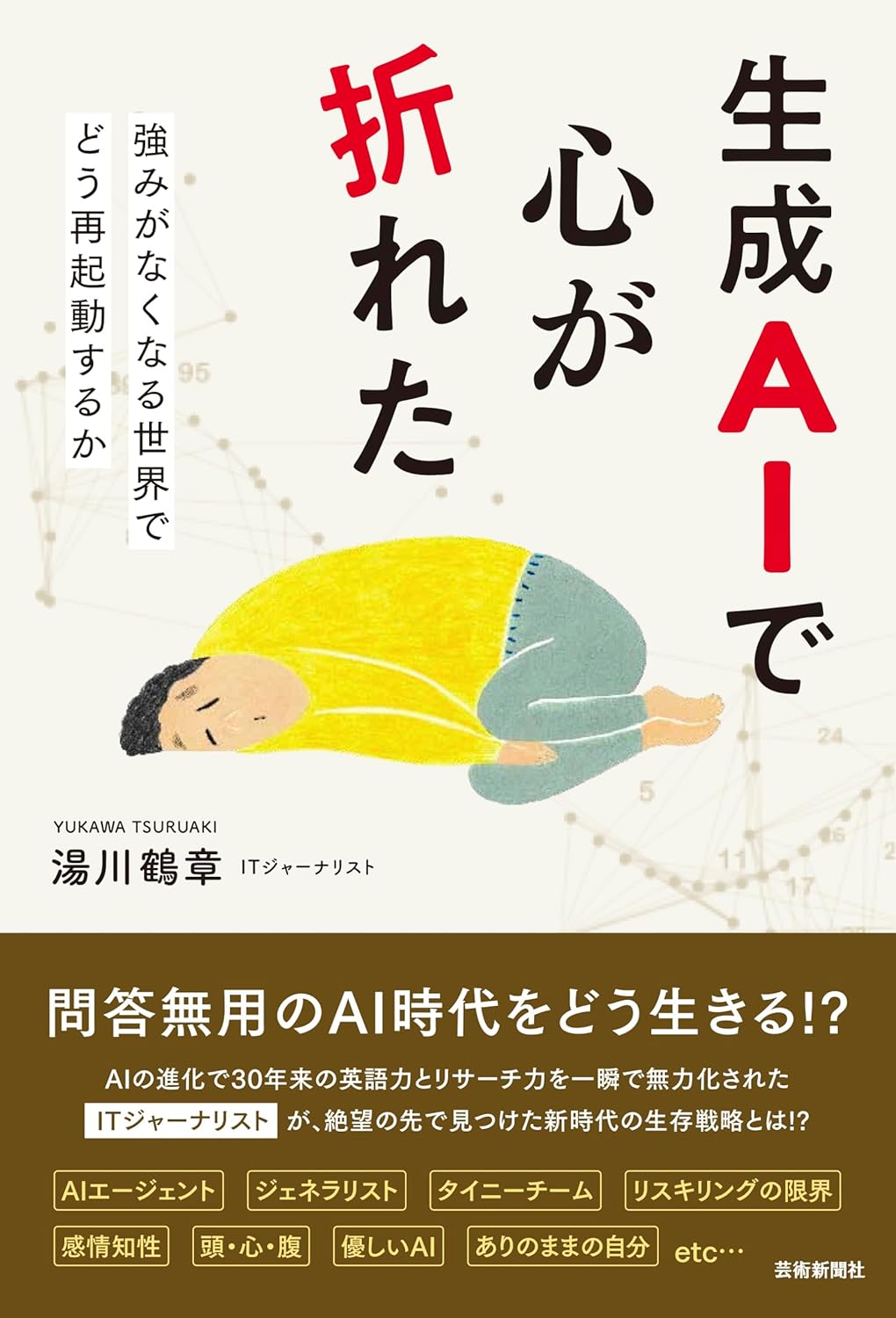【N#210】認知症とはどのような病気か──「人生後半の最大のリスク」をどう軽減するか?
Table of Contents
はじめに
こんにちは。渋谷でロルフィング・セッションや脳科学をベースにした講座を提供している大塚英文です。
最近、伊古田俊夫先生の著書『認知症とはどのような病気か 脳の構造としくみから全体像を理解する』を読み、認知症の理解が深めることができた。健康寿命を全うする上で、認知症は脳卒中と並び知ることが重要だと思う。
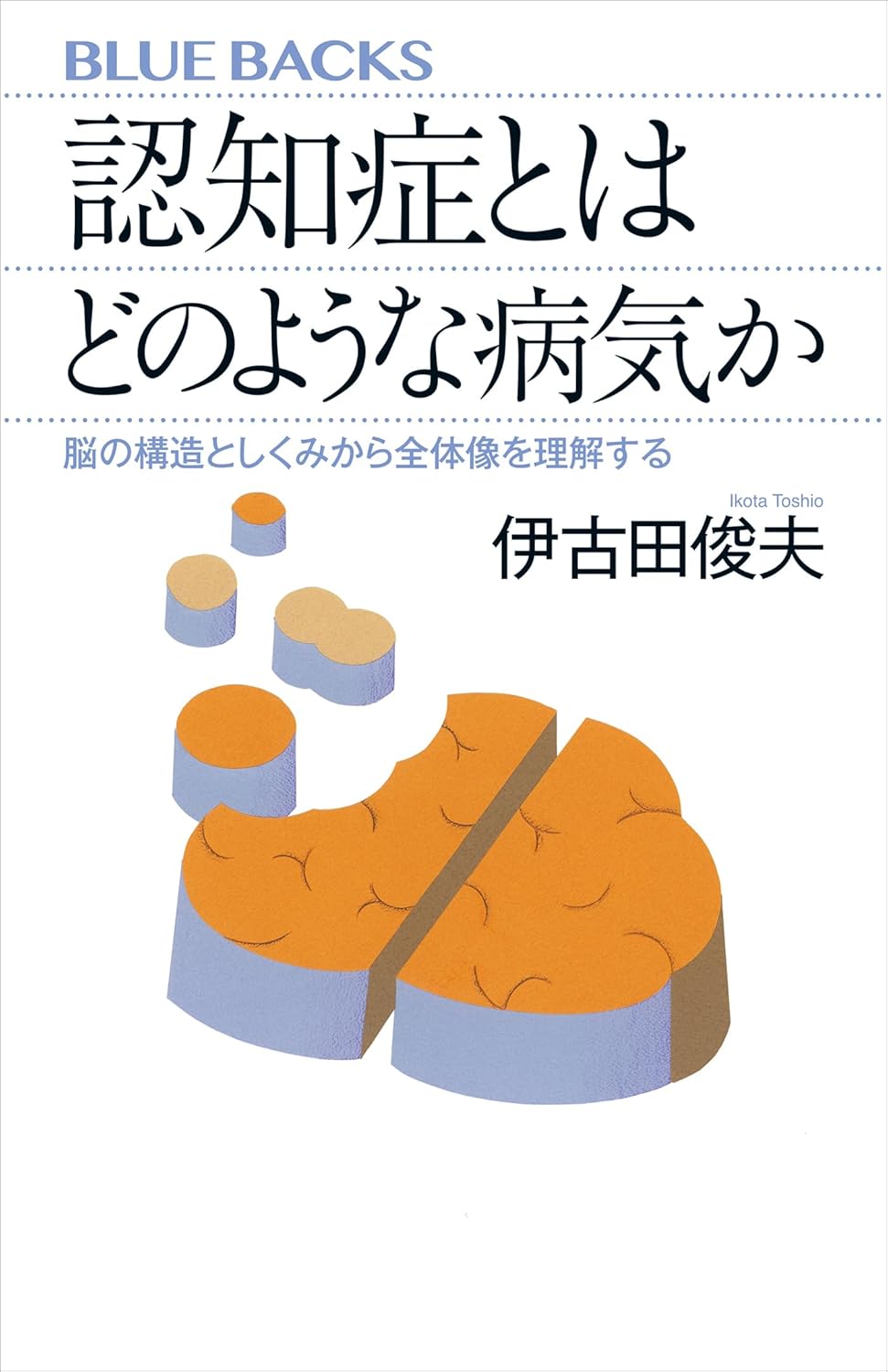
そこで、今回は、この本から得た知見と、Peter Attia氏の『Outlive』が提示する予防戦略を組み合わせて、健康寿命を延ばすために必要な「認知症の正しい理解」を整理してみたい。
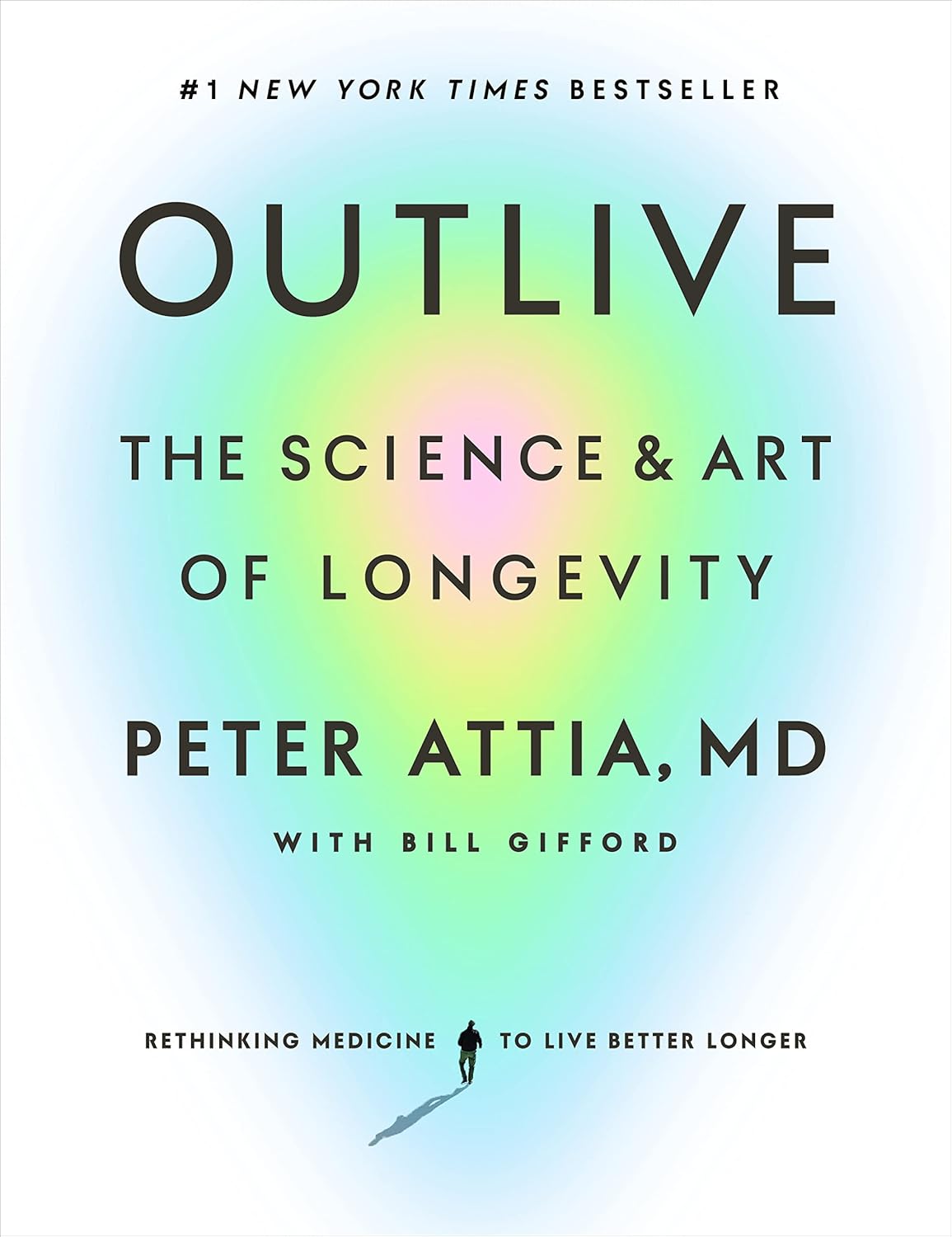
認知症と脳卒中の違いとは?
まず誤解されやすいのは「認知症」と「脳卒中(脳梗塞や脳出血)」の関係である。
- 脳卒中は、脳の血管が詰まる・破れるといった「急性の発作」であり、発症直後から運動麻痺や言語障害などが明確に現れる。
- 認知症は、アルツハイマー病や血管障害などの影響で「脳の機能が徐々に低下する状態」を指す。進行はゆっくりで、記憶障害や判断力低下などが段階的に積み重なる。
両者は全く別の病気だが、脳卒中は血管性認知症の原因となり得るため、互いに深い関連を持つ。したがって「脳卒中を防ぐことは認知症を防ぐことにもつながる」と言える。
なぜ、健康寿命のために認知症の知識が必要なのか?
健康寿命を考える上で、認知症の知識は欠かせない。その理由は大きく三つある。
- 介護の最大要因だから
認知症は要介護の主要原因の一つであり、発症すれば本人の生活の質(QOL、Quality of Life)だけでなく、家族・社会の負担が大きい。 - 予防と対策の余地があるから
認知症は不可避の老化現象ではなく、生活習慣や環境改善でリスクを減らすことができる。特に血管性認知症や可逆性認知症は、予防や治療で改善の可能性がある。 - 正しい診断が生活を変えるから
タイプごとに症状や治療法は異なる。誤った理解は不必要な不安を生む一方、正しい知識は「できること」を明確にし、健康寿命を支える力となる。
なぜ、認知症のタイプを知る必要があるのか?
認知症は単一の病気ではなく、原因も症状も異なる複数の疾患の総称である。タイプを知ることには以下の意義がある。
- 治療法や対応が異なる
- アルツハイマー病では進行抑制薬が使えるが、前頭側頭型では効果が乏しい。
- レビー小体型では抗精神病薬が禁忌になる場合がある。
→「正しい診断」が、その後の治療とケアの質を大きく左右する。
- 予防のアプローチが異なる
- 血管性認知症では生活習慣病の管理が最大の予防策。
- 睡眠や代謝異常が関与するタイプでは生活習慣改善がカギになる。
- 可逆性の可能性がある
- ビタミンB12欠乏や正常圧水頭症、慢性硬膜下血腫は適切な治療で改善が期待できる。
→「治る認知症」を見逃さないためにもタイプの理解は不可欠である。
- ビタミンB12欠乏や正常圧水頭症、慢性硬膜下血腫は適切な治療で改善が期待できる。
認知症の種類を知ることは、恐怖心を煽るのではなく、正しい対処と希望の余地を見出すために重要なのである。
認知症の種類(主要タイプの特徴)
伊古田先生の本では、以下のようなタイプが取り上げられている。
1. アルツハイマー病(AD)
- 症状:記憶障害から始まり、見当識障害・判断力低下へ進行。
- 病態仮説:アミロイドβやタウたんぱくの異常蓄積が主説だが、炎症や代謝異常など多因子の関与も注目されている。
- 治療:コリンエステラーゼ阻害薬やNMDA受容体拮抗薬で進行を遅らせるが、根本治療は確立していない。
2. 血管性認知症(VaD)
- 特徴:脳血管障害による“まだら認知症”。段階的に悪化することが多い。
- 予防:高血圧・糖尿病・脂質異常の管理が直接予防につながる。
3. レビー小体型認知症(DLB)
- 特徴:幻視、注意の変動、パーキンソニズム。
- 注意点:抗精神病薬に対する過敏性があり、薬剤選択が難しい。
4. 前頭側頭型認知症(FTD)
- 特徴:50〜60代の若年発症も多く、人格・行動の変化や言語障害が目立つ。
- 対応:薬物効果は乏しく、環境調整とケアが中心。
5. 可逆性認知症(重要な鑑別)
- 例:ビタミンB12欠乏、甲状腺機能低下、正常圧水頭症、慢性硬膜下血腫、アルコール関連障害など。
- 特徴:適切な治療で改善する可能性がある。誤診を避けるための丁寧な鑑別が不可欠である。
予防と治療の現状
伊古田先生によると、以下のような予防策と治療方針が重要になるという。
- 予防:運動・食生活・知的活動・社会参加・睡眠の質が鍵。
- 治療:薬物療法は進行抑制が中心。非薬物療法として音楽療法、回想法、身体活動などが有効。
- 重要点:認知症は「不可逆の老化」ではなく、生活習慣と環境の改善によって進行を遅らせたり、発症を防げる余地がある。
Peter Attiaの『Outlive』が示す予防戦略
一方で、健康寿命を全うする上で、網羅的に扱ったPeter Attia氏は『Outlive』では、認知症を「人生後半の最大のリスク」の一つと捉え、予防は行動にかかっていると強調する。
具体的には以下の5点である。
- 有酸素運動(VO₂MAXの向上)
- VO₂MAXは認知症リスクを下げる強力な指標。
- 脳血流を維持することが神経保護につながる。
- 筋力とバランスの維持
- 筋肉量とバランスは転倒リスクを減らし、間接的に認知症予防に寄与。
- スクワットやデッドリフトなど大筋群を鍛える運動を推奨。
- 睡眠の最適化
- 深睡眠時にアミロイドβが脳から排出される。
- 睡眠時無呼吸は大きなリスク因子であり、治療が必須。
- 血糖コントロールと代謝の安定
- インスリン抵抗性は「3型糖尿病」とも呼ばれるアルツハイマーのリスク因子。
- CGM(持続血糖測定)で自分の血糖変動を知ることが推奨される。
- 情動とストレスのマネジメント
- 慢性的なストレスは認知症リスクを高める。
- 瞑想・呼吸法・心理的レジリエンスの構築が予防の一部である。
健康寿命との関係
- 伊古田先生の視点:認知症は多様であり、必ずしも避けられない運命ではない。正しい理解と鑑別が生活の質を守る。
- Peter Attiaの視点:認知症予防は「日常の行動変容」によって実現可能であり、運動・睡眠・代謝・ストレス管理がカギとなる。
両者を組み合わせると、認知症は「恐怖の対象」ではなく、科学と生活習慣の知恵でリスクを減らし、健康寿命を延ばせる課題として捉え直すことができると言える。
まとめ
- 認知症と脳卒中は異なる病気だが、血管障害を介して深く関連する。
- 健康寿命を全うするためには、認知症の知識が不可欠であり、その理由は「介護の最大要因」「予防可能性」「正しい診断が生活を変える」の3点である。
- さらに、認知症のタイプを知ることは、治療・予防・改善可能性の判断に直結する。
- 伊古田俊夫氏の著書からは、認知症を冷静に理解する姿勢を学べる。
- Peter Attia氏は、『Outlive』で予防医学の観点から「行動によるリスク低減」を具体的に提示する。
- 健康寿命を守るためには、正しい理解と日常の実践の両輪が欠かせない。