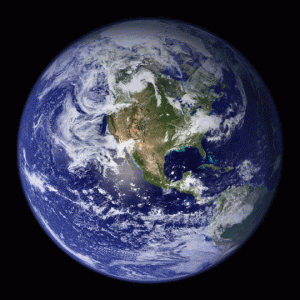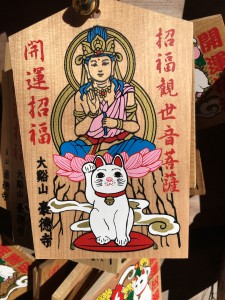【N#207】睡眠──健康寿命を支える見えない柱
Table of Contents
はじめに
こんにちは。渋谷でロルフィング・セッションと脳科学をベースにした講座を提供している大塚英文です。

過去の記事では、Peter Attiaの健康寿命戦略の全体像を紹介した上で、前回は、運動の重要性についてまとめた。今回、生命力の根幹を支える睡眠に焦点を当てる。睡眠については「睡眠こそ最強の“脳トレ”」に書いたが、本記事は、健康寿命の視点からまとめたい。
睡眠の質が健康寿命に与える影響
研究によれば、慢性的な睡眠不足や質の低下は、認知症、糖尿病、心血管疾患、うつ病、免疫低下など、多くの慢性疾患のリスクを高める。逆に、適切な睡眠は以下の点で健康寿命を支える。
- 認知機能の維持(アルツハイマー病予防)
- 筋肉・骨・関節の修復(転倒・骨折リスク低減)
- 免疫力の維持(感染症やがんの予防)
- 血糖値とホルモンバランスの安定(代謝疾患予防)
- 感情の安定(社会的活動の維持)
ノンレム睡眠とレム睡眠の役割
睡眠は大きくノンレム睡眠(Non-REM Sleep)とレム睡眠(REM Sleep)に分けられ、約90分周期で交互に訪れる。
- ノンレム睡眠(深い眠り)
脳と身体の物理的な修復期であり、特に睡眠前半に多く現れる。成長ホルモン分泌のピークとなり、免疫強化や筋肉・骨・組織の修復、事実やスキルの記憶固定に関与する。 - レム睡眠(浅い眠り)
「Rapid Eye Movement(急速眼球運動)」の略で、まぶたの下で眼球が素早く動くことから名づけられた。脳は覚醒に近い活動をしながら筋肉は弛緩し、感情や記憶の整理、創造性の発揮、夢の生成に関与する。
ノンレム睡眠が不足すれば免疫・代謝・認知機能が低下し、レム睡眠が不足すれば感情コントロールや創造性に悪影響が出る。
疲労と眠気の違い
疲労(Fatigue)は筋肉や神経系の消耗によるパフォーマンス低下であり、眠気(Sleepiness)は脳の覚醒度が低下して睡眠欲求が高まった状態である。
強い精神的ストレスやカフェインの摂取により「疲れているのに眠れない」状態が起こり得る。逆に、日中ほとんど活動していなくても、情報過多で脳が疲弊すると強い眠気を感じることがある。
光とルクス──体内時計のリセット
光の強さはルクス(lux)で表され、体内時計やメラトニン分泌に大きな影響を与える。
- 晴天の屋外(直射日光):100,000ルクス前後
- 曇天の屋外:5,000〜20,000ルクス
- コンビニ店内:約1,500ルクス
- スーパー店内:約500〜1,000ルクス
- 野球場ナイター照明:約1,000ルクス
- 室内の一般照明:約300〜500ルクス
- 月光(満月):0.1〜0.3ルクス
朝は2,000ルクス以上の光を浴びることで体内時計がリセットされ、夜間のメラトニン分泌が促される。逆に就寝前は500ルクス以下に落とし、寝る1時間前からはスマートフォンやパソコンのブルーライトを避けることが望ましい。
ブルーライトとは何か?
ブルーライトは、可視光線の中で波長が380〜500ナノメートルの青色光を指す。特にスマートフォン、パソコン、タブレット、LED照明から多く発せられる。
この波長の光は、網膜の視細胞から視交叉上核(体内時計の中枢)に強い刺激を送り、メラトニン分泌を抑制する作用がある。
重要なのは、ブルーライトは日中には必要不可欠であるという点である。午前から日中にかけてブルーライトを十分に浴びることで、覚醒度が高まり、集中力・判断力・気分の安定が得られる。また、体内時計の同調が進み、夜間の自然な眠気が訪れやすくなる。
一方で、夜間に浴びるブルーライトは体内時計を後ろにずらし、入眠を遅らせたり、ノンレム睡眠を浅くする原因になる。そのため、夜はブルーライトカット機能や暖色照明の使用が推奨される。
深部体温と入眠
中核温と熱放散の仕組み──なぜ“手足を温める”と眠くなるのか?
深部体温(中核温)が下がることが、入眠の引き金になる。その鍵を握るのが「放熱」のメカニズムである。
- 中核温とは
脳や内臓など、身体の中枢部の温度でおよそ37℃前後を保つ。睡眠時には自然に低下し、入眠を助ける。起床の90〜120分前が最も低くなる。 - AVA(動静脈吻合)とは
動脈と静脈が直接つながる特殊な血管構造で、手のひら、足の裏、額などに集中している。血流が豊富で効率的な放熱装置として働く。手足を温めることでAVAが開き、体表から熱が逃げ、中核温が下がる。
このため、就寝90分前の入浴(40℃で約15分)や、サウナと水風呂の交代浴は、一時的に深部体温を上昇させ、その後の反動で急降下させることで、自然な眠りを誘発する。
サウナと睡眠
サウナ後は副交感神経優位となり、ノンレム睡眠の割合が増える傾向がある。高温サウナだけでなく、ミストサウナやぬるめの長湯でも同様の効果が期待できる。就寝直前ではなく、1.5〜2時間前に行うと深部体温の低下と重なりやすい。
日中活動と夜の睡眠
日中の軽〜中強度運動(ウォーキングやヨガ、軽い筋トレ)は、夜の睡眠を深める。激しい運動は就寝3時間前までに終えることが望ましい。
休養の工夫
休養は夜の睡眠だけではなく、日中の回復習慣も含まれる。
- アクティブレスト:軽いストレッチや散歩で血流を促す
- マインドフルレスト:瞑想、呼吸法、自然音を聴く
- ソーシャルレスト:安心できる人との交流で心理的安全を得る
こうした休養を日中に取り入れることで、夜の睡眠がより深まりやすくなる。
測定と改善
OURA Ring、Apple Watch、WHOOPなどを用いて、ノンレム/レム比率や入眠潜時を測定し、光・温度・食事・運動のタイミングを調整する。
「測定 → 改善 → 再測定」のサイクルを回すことで、自分に最適な睡眠パターンを確立できる。
まとめ
睡眠は自然に任せるものではなく、戦略的に最適化できる健康資産である。
朝の光で体内時計を整え、深部体温の変化を利用して入眠を促し、休養の多様性を確保することで、健康寿命の基盤が強化される。睡眠への投資は、未来の自分への確実な投資であるといっていい。