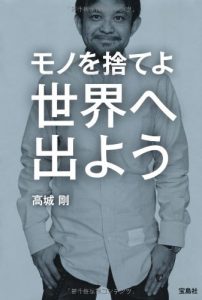【B#187】物理学はどこで迷子になったのか?〜『The Trouble with Physics』とリー・スモーリンの問い
Table of Contents
はじめに
東京・渋谷でロルフィング・セッションと脳科学から栄養・睡眠・マインドの脳活(脳科学活用)講座を提供している大塚英文です。
現代の理論物理学では、超ひも理論は支配的な地位を占めているらしい。すべての素粒子を「一次元の振動するひも」として統一的に記述するこの理論は、かつて多くの物理学者を魅了した。一方で、批判も多い。
リー・スモーリン(Lee Smolin)は、自身の著書『The Trouble with Physics(邦題:迷走する物理学)』の中で、超ひも理論が物理学を袋小路に追い込んでいるのではないかという根本的な問いを投げかけている。
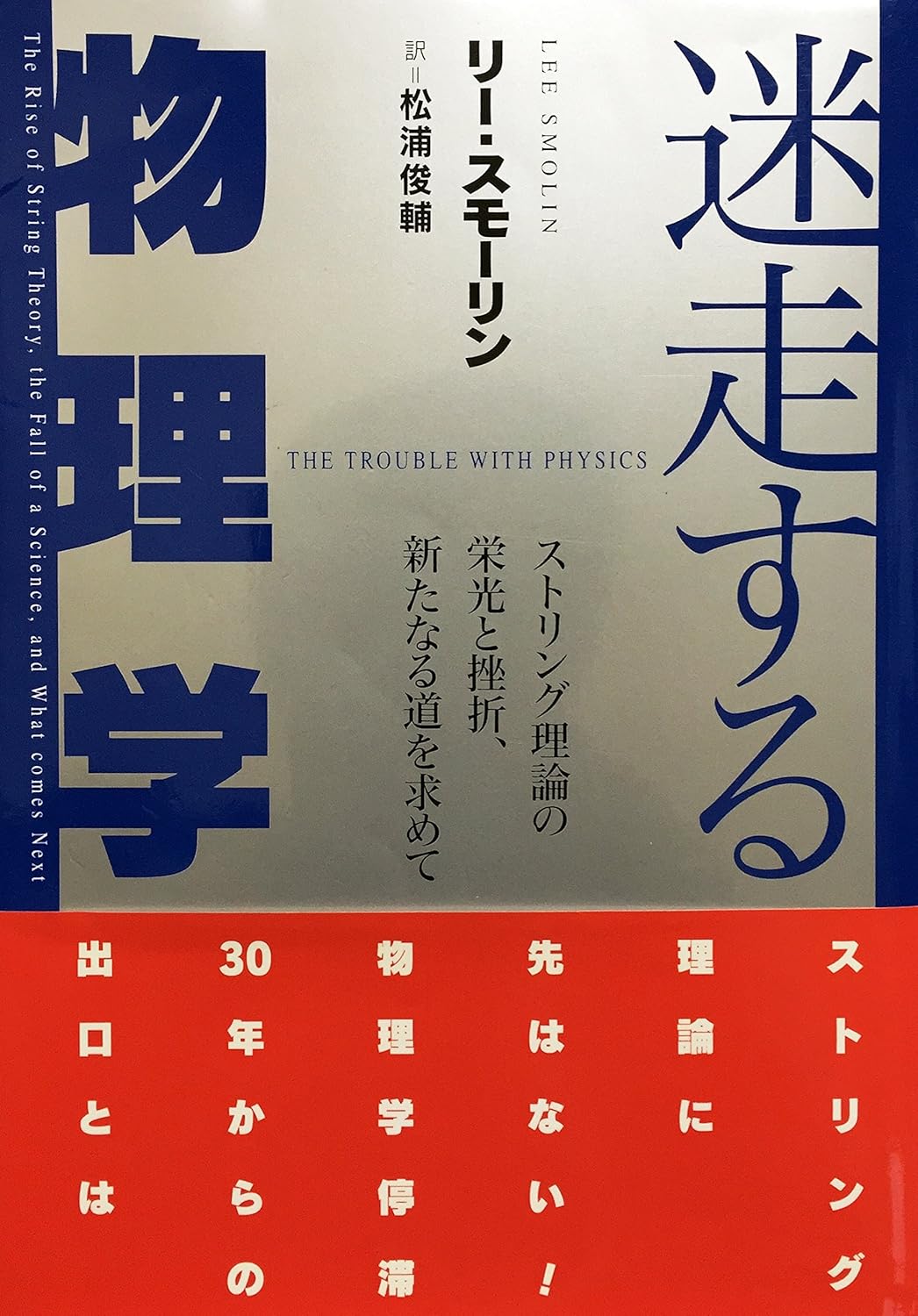
今回は、スモーリンの主張を整理し、彼と親交のあった科学哲学者ポール・ファイヤアーベント(Paul Karl Feyerabend)、ループ量子重力理論の共同提唱者であるカルロ・ロヴェッリとの思想的つながり、エリック・ワインスタインの批判的視点を加えながら、理論物理学が直面している構造的問題について迫っていきたい。
超ひも理論の問題点
超ひも理論は、自然界のすべての力──電磁気力、弱い力、強い力、そして重力──を一つのフレームで統合しようとする壮大な理論である。興味深いことに、スモーリンは、その野心的な構想が、いくつかの根本的な問題により頓挫していると指摘する。
実験で検証できない
「超ひも理論は、現在あるいは近い将来の実験で検証可能な予測を一つも示していない(String theory has failed to make any predictions that are testable by current or near-future experiments.)」とスモーリンは語る。
この理論は、極端に小さなプランクスケールでの現象を扱っており、現在の実験技術では検証が不可能である。そのため、ポパーの意味における反証可能性(falsifiability)を満たさず、科学理論としての健全性を欠いているとのことだ。
解が多すぎて予測ができない
超ひも理論には約 10^500 個もの「解」が存在するとされるが、その中から我々の宇宙に対応する唯一の解を選び出す手がかりがない。「ランドスケープ問題」によって、理論の予測力は著しく損なわれ、科学の名の下にあらゆる観測結果を“説明”するだけの後付けの枠組みに陥っている。
学界の閉鎖性
スモーリンがとりわけ憂慮しているのは、物理学界の社会構造である。超ひも理論が圧倒的な支配力を持ち、他のアプローチ──とりわけループ量子重力のような代替理論──が資金的にも制度的にも不利な立場に置かれていることを危惧している。
「本当の問題は、超ひも理論そのものではなく、それを取り巻く科学界の社会構造だ(The real problem is not string theory itself but the sociology of science that surrounds it.)」という彼の言葉は、理論的な対立以上に、制度的な歪みに対する警鐘になっている。
ファイヤアーベントとの思想的共鳴
スモーリンがこのような立場に立つ背景には、科学哲学者ポール・ファイヤアーベントとの交流が一つのきっかけとなっている。ファイヤアーベントは著書『方法への反逆(Against Method)』において、「いかなる普遍的な科学的方法も存在せず、異端や多様性こそが科学を健全に保つ」と述べた。
スモーリンもまた、科学の進歩には一つの理論や枠組みに固執しない柔軟性が必要であると主張し、特定の理論が独占的に扱われることへの警戒感を強く示している。
ループ量子重力理論とは何か?
超ひも理論に代わる選択肢としてスモーリン自身が研究を主導してきたのが、ループ量子重力理論(Loop Quantum Gravity, LQG)である。これはアインシュタインの一般相対性理論の枠組みを保ちながら、その時空構造を量子化しようとする試みである。
共同研究者カルロ・ロヴェッリとともに、LQGは超ひも理論とは異なる、背景独立型の量子重力理論として発展してきた。
時空の量子化
LQGでは、空間と時間は連続体ではなく、スピンネットワークと呼ばれる離散的構造によって構成されている。これは、時空そのものに「原子」のような最小単位があるという考え方である。
「ループ量子重力理論は、空間と時間が固定された舞台ではなく、それ自体が動的で量子化されているという考えに基づいている(LQG is based on the idea that space and time are not a fixed stage, but themselves dynamic and quantized.)」とスモーリンは述べる。
実験可能性と予測
LQGは、ブラックホールのエントロピー計算やビッグバン特異点の回避(ビッグバウンス)、さらには宇宙マイクロ波背景放射への痕跡など、間接的ながらも検証可能な予測を持つ。これは、理論が科学的検証に開かれていることを意味し、スモーリンが評価する重要な点である。
ロヴェッリと「関係性の物理学」
カルロ・ロヴェッリは『世界は「関係」ででできている(HELGOLAND)』において、量子力学の核心を「関係性(relationality)」に見出している。物理的実在とは、単独で存在するのではなく、他者との関係の中においてのみ成立する、という視点である。
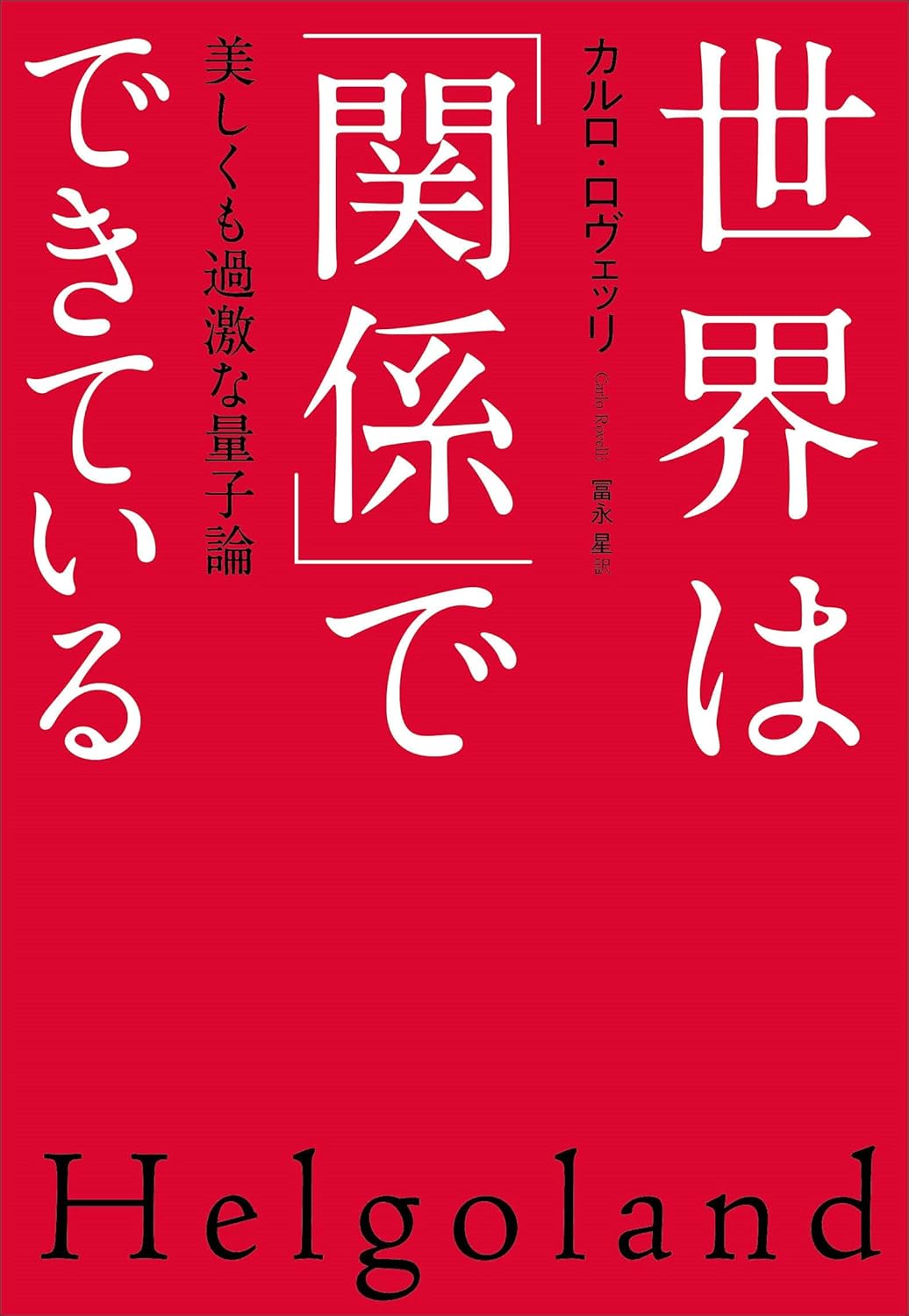
スモーリンもまた、時空を固定された背景としてではなく、関係的・動的なものと捉えるという意味でロヴェッリの立場と重なっている。
エリック・ワインスタインの批判
数学者であり理論家のエリック・ワインスタイン(Eric Weinstein)もまた、超ひも理論に対する批判を繰り返してきた。彼は「科学界は形式的に正しい理論にしか資源を配分しない閉鎖的な官僚主義に陥っている」と主張する。
ワインスタイン自身も「Geometric Unity」と呼ばれる独自理論を提唱しているが、その扱いが学術界で不当に冷遇されていることに警鐘を鳴らしている。
ワインスタインによれば、超ひも理論が科学的進歩の主導権を握ることによって、代替的なアイデアが育たず、革新が止まってしまったという点で、スモーリンと同様の問題意識を共有している。
科学に必要なのは「確信」ではなく「問い」
スモーリンはこう述べている。
“Science is not a democracy. It is not about consensus. It is about the confrontation between theory and nature.”
科学は民主主義ではない。合意形成の問題でもない。理論と自然の対話こそが科学である。
さらにこうも語る。
“The health of a science is measured not by its orthodoxy but by its openness to radical ideas.”
科学の健全さは、正統性によってではなく、急進的なアイデアにどれだけ開かれているかで測られる。
まとめ:物理学は再び歩き出せるのか
『The Trouble with Physics』は、一つの理論に対する批判を超えて、科学という営みそのものに立ち返ることの必要性を問う書である。物理学が本来持っていた創造性、探究心、多様性を再び取り戻すためには、制度や流行にとらわれず、「問い」を重視する文化を再構築する必要がある。
迷子になったのは理論そのものではない。問いかけることを忘れてしまった、科学そのものである。