【B#181】世界は関係でできている〜カルロ・ロヴェッリが語る“つながり”の世界
Table of Contents
はじめに
東京・渋谷でロルフィング・セッションと脳科学から栄養・睡眠・マインドの脳活(脳科学活用)講座を提供している大塚英文です。
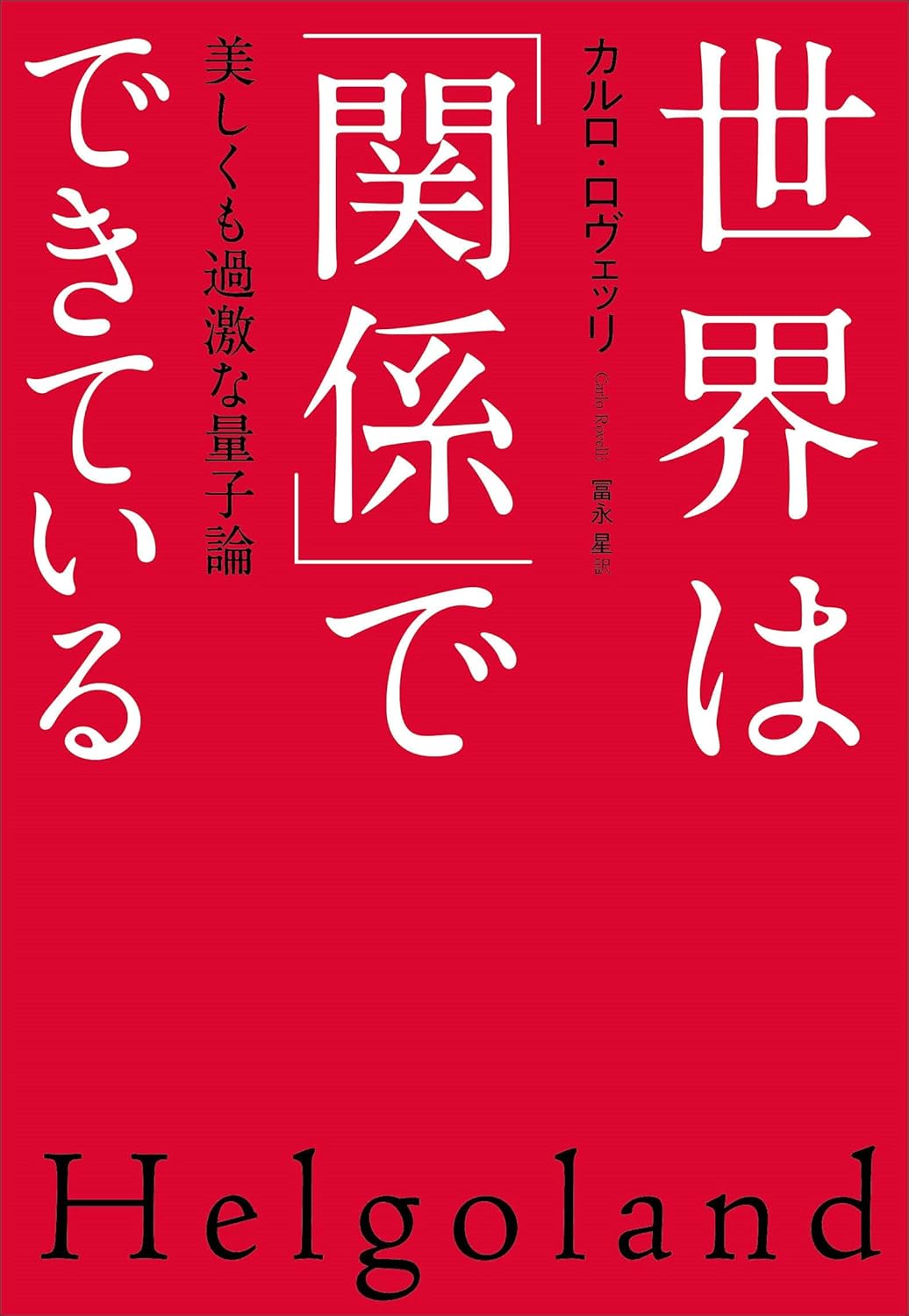
2025年の読書の年間テーマは「量子力学」だ。何冊か読んでいく中で、カルロ・ロヴェッリの『世界は関係でできている(原題:Helgoland)』は、本当に素晴らしく、気づきも多かった。今回の記事では、この本を中心に「関係性」について考えたい。
世界は「モノ」でできているのか?それとも「関係」なのか?
「この世界は何でできているのか?」という問いに対し、我々は、無意識のうちに答えながら生きている。
粒子?物質?エネルギー?それとも空間や時間?
物理学者カルロ・ロヴェッリは、この問いに対して一言
「世界は“関係”でできている」
と答えている。
すごく抽象度の高い答えのように見えるが、『世界は関係でできている』を読み進めると、それが物理学のみならず、哲学・文化・心理など、他分野にもつながる答えになっている。
🔬 関係的量子力学:状態は「誰かとの関係」によって決まる
ロヴェッリの専門は量子物理学(ループ量子重力論)。彼が唱える「関係的量子力学(Relational Quantum Mechanics, RQM)」では、次のように考えられている。
たとえば、目の前に猫がいると仮定する。だが、その猫の「毛のふわふわ感」や「目の動き」や「鳴き声」は、観察者である「私」との関係があるからこそ“そう感じる”のであり、猫単体に“絶対的なふわふわ”があるわけではない。
量子の世界も同じである。電子の位置やスピンの向きといった状態は、それを観察した他者(他の粒子や装置)との関係の中でしか意味を持たない。
エルンスト・マッハ:関係的世界観の先駆者
ロヴェッリの「関係性」の考え方は、19世紀の物理学者エルンスト・マッハの思想にその源流を見ることができる。
マッハは
「世界は感覚的要素の関係で構成されており、“モノ”という概念は、関係の繰り返しの中で生まれた抽象にすぎない」
と述べた。
つまり、「机」や「猫」といった存在も、それ自体に固定的な本質があるわけではなく、「色」「形」「触覚」「音」といった感覚の束=関係のまとまりにすぎないというのである。ロヴェッリはこの思想を受け継ぎ、量子力学の世界においても「モノではなく関係こそがリアリティである」と捉えている。
哲学・文化・心理学との交差:関係から見える世界の姿
ロヴェッリの語る「関係でできた宇宙」は、物理学だけでなく、人間の意識・文化・知覚・存在の理解ともつながっている。
1. ハイデッガーの現象学:「人は関係の網のなかで存在する」
ドイツの哲学者マルティン・ハイデッガーは、「人間とは“世界‐内‐存在”である」と述べた。つまり、人は何かと関係しながら、常に“なにかのなかで”存在している。
たとえば、コーヒーカップ。それは単に机の上にある陶器の塊ではなく、「温かい飲み物を飲む」という目的との関係の中で初めて「カップ」になる。
ロヴェッリの物理学もまた、粒子の性質は他のものとの関係の中でしか決まらないという意味で、ハイデッガー的な存在論と響き合っている。
2. カントの“見え方の哲学”:世界は「構成された関係」である
イマヌエル・カントは、「物自体(Ding an sich)」は私たちには知覚できず、世界とはあくまで私たちの“見方”に基づいて構成されたものだとした。
たとえば、赤いリンゴが赤く見えるのは、私たちの知覚装置が“赤”という波長を受け取るからであって、リンゴ自体に「赤い本質」があるわけではない。
ロヴェッリはこの思想を引き継ぎ、
「電子の位置やスピンも、“誰がどう見るか”によって変わる」
という、量子的な“関係のリアリティ”を提示する。
3. 文化人類学と“意味”の構築:すべては文脈の中で意味を持つ
文化人類学では、モノの意味や価値は絶対的なものではなく、文化的・社会的関係の中で構築されるとされる。
たとえば、水はある文化では神聖視され、別の文化では単なるインフラである。つまり、「水」の意味は、それを見る人や文化との関係性によって異なる。
ロヴェッリの関係的宇宙も、まさにこうした視点と重なっている。
粒子や出来事の「状態」や「意味」は、背景や観測との関係の中でのみ立ち現れる。
4. 心理学(ゲシュタルト):知覚は「関係のまとまり」として成立する
ゲシュタルト心理学では、人間の知覚は個々の要素ではなく、それらの関係的構造によって生まれるとされる。
三つの点が一直線に並ぶと、私たちはそこに「ライン(線)」を知覚する。このように、「形」や「意味」は、関係パターンのなかに現れる。
ロヴェッリの考えでは、粒子や現象の「あり方」もまた、世界のなかの他の存在との関係のなかにこそ立ち現れる。
プラトン的「絶対的本質」からの脱却
プラトンは、「この世界の背後には“イデア”と呼ばれる絶対的で普遍的な実在がある」と考えた。
しかし、ロヴェッリはこのような本質主義に異議を唱える。
「この世界には、固定された“本質”などない。あるのは関係の網のなかで動き続ける“状態”だけである」
ロヴェッリの量子宇宙観は、モノ中心の世界観から、関係中心の世界観への転換を示している。
まとめ:関係こそがリアリティである
カルロ・ロヴェッリの『世界は関係でできている』は、量子力学から始まり、哲学・文化・心理学へと広がっていく。そこには、「私たちは何者で、どのように世界と関わっているのか?」という深い問いが込められている。
| 観点 | 内容 |
|---|---|
| 物理学 | 粒子の状態は観察者との関係によってのみ確定する(RQM) |
| マッハ | 世界は感覚的要素の関係で構成されている |
| ハイデッガー | 存在とは「世界内の関係性」そのものである |
| カント | 我々が知る世界は、構成された関係にすぎない |
| 文化人類学 | 意味は関係的・文脈的に構築される |
| 心理学 | 知覚は関係のパターンとして知覚される |
関係から自分自身を捉え直すということ
この本が私たちに伝えるのは、「私は孤立して存在しているのではない」という事実である。我々は常に、他者と、環境と、世界との関係”の中で存在している。
世界とは、断片の集まりではなく、つながりの網の中で絶えず変化し続ける構造体である。この見方を一度取り入れてしまえば、現実の感じ方そのものが変わっていくはずだ。
この本をお勧めしたい人
この本は、下記の人に手に取ってほしい。
- 「この世界は何でできているのか?」という問いを、物理学だけでなく、哲学的・感覚的にも深めたい人
- 関係性、つながり、文脈というキーワードに興味を持っている人
- ハイデッガー、カント、マッハ、文化人類学、ゲシュタルト心理学などに興味がある人
- 難解な「量子力学」について「世界と向き合う哲学的態度」として読み解きたい人
少しでも、この投稿が役立つことを願っています。






