【B#180】なぜGoogleは世界を変える企業になれたのか?〜創業者の個性、社風、人事制度から読み解く
Table of Contents
はじめに
東京・渋谷でロルフィング・セッションと脳科学から栄養・睡眠・マインドの脳活(脳科学活用)講座を提供している大塚英文です。
今回は、Googleという企業の成功の背後にある、独自の文化・哲学・構造的仕組みについて、以下2冊を中心に、組織文化と創造性の関係性を探っていく。
Steven Levy『In the Plex: How Google Thinks, Works, and Shapes Our Lives』
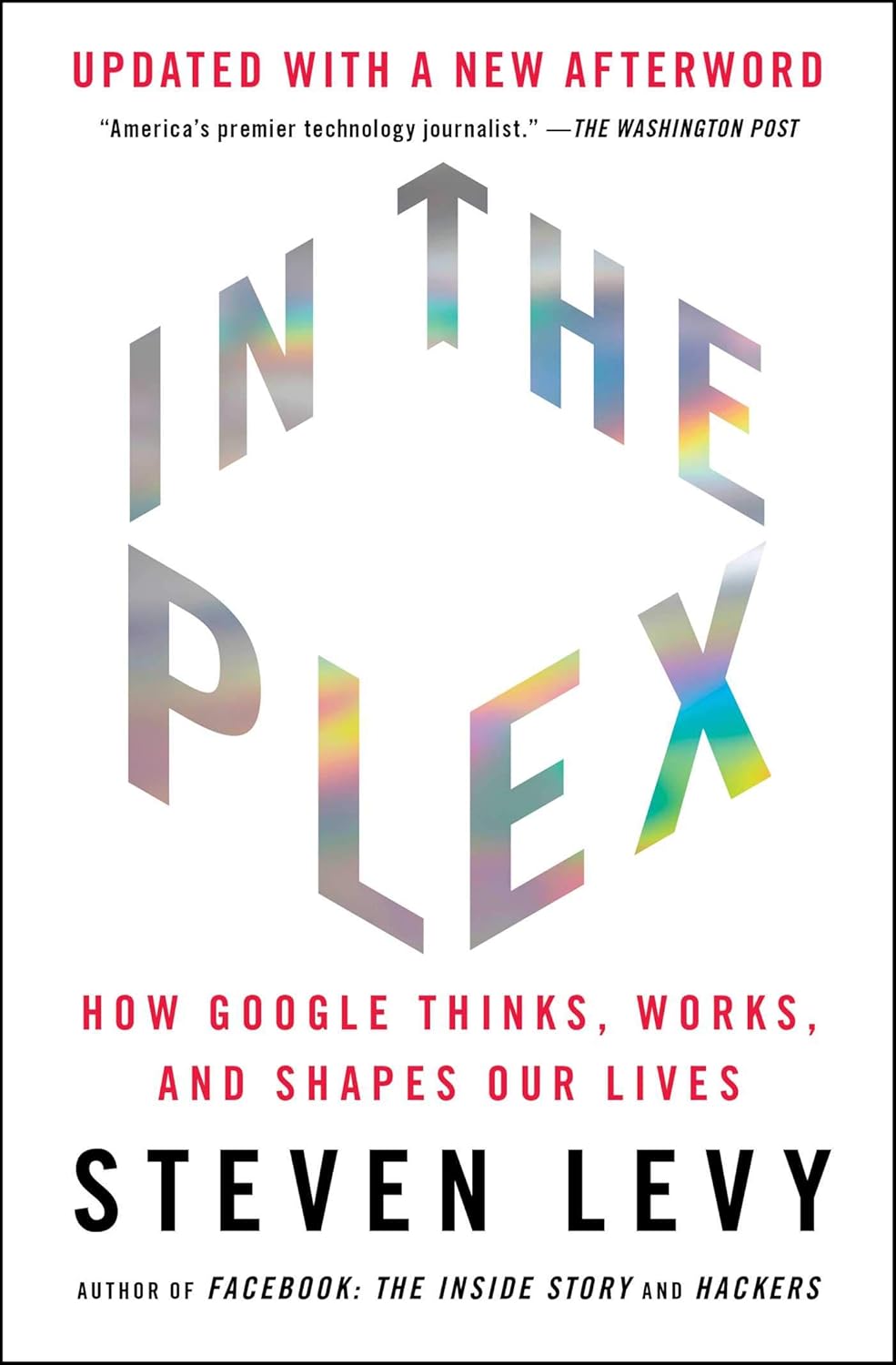
Eric Schmidt, Jonathan Rosenberg『How Google Works』
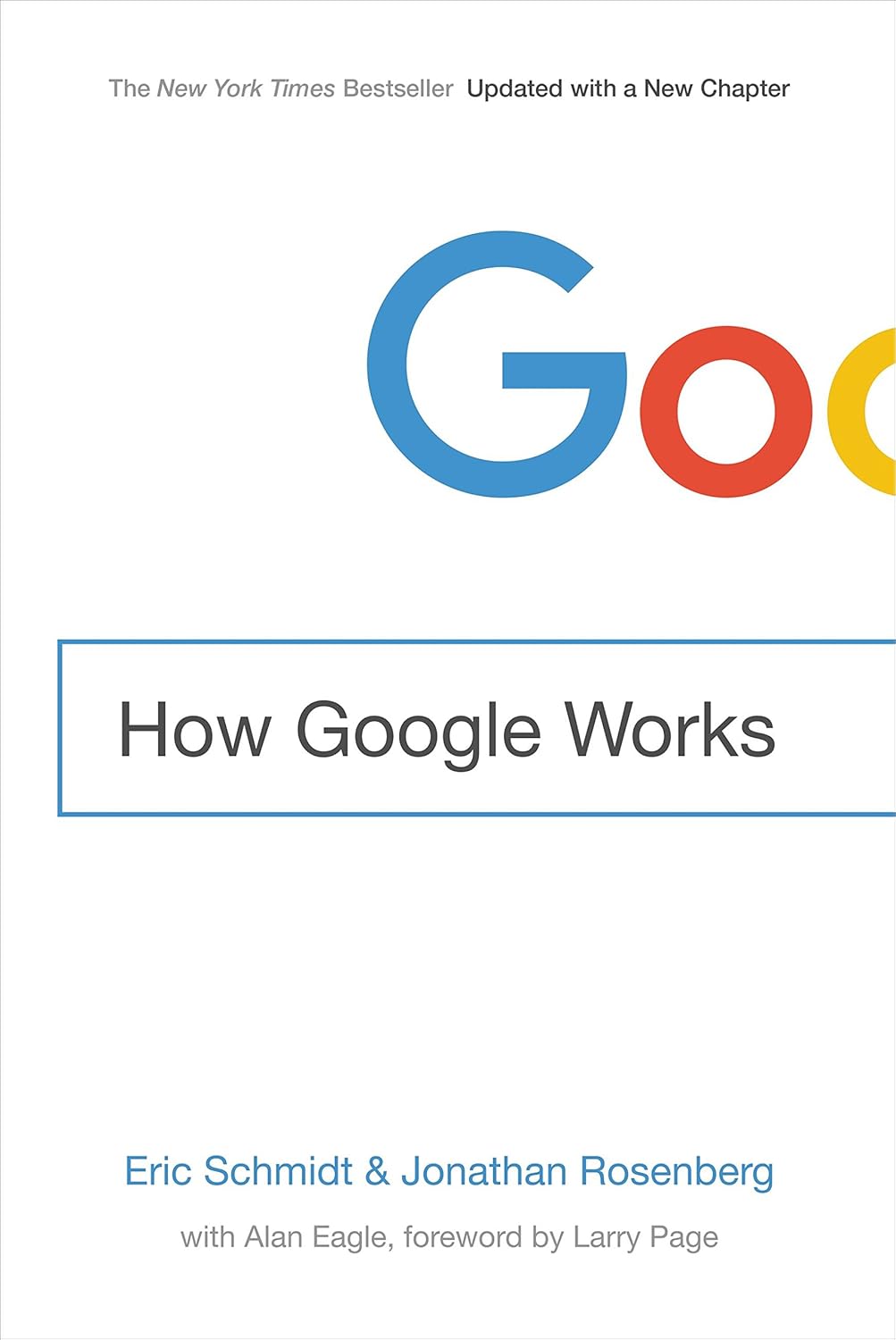
この2冊の本を通じて、単なるIT企業を超え、人間の思考、学習、創造性の本質に挑戦してきた組織としてのGoogleの姿を見ていきたい。
創業者:Larry PageとSergey Brinの「変人性」が出発点
Googleの創業者であるラリー・ペイジとセルゲイ・ブリンは、単なる天才エンジニアではなかった。彼らに共通するのは、常識を疑い、世界に未解決の問題を見出し、それを独自に再定義しようとする姿勢である。
“They were not businesspeople trying to cash in; they were visionaries trying to solve an unsolved problem.”
「彼らは、金儲けを狙うビジネスマンではなかった。彼らは、未解決の問題を解こうとするヴィジョナリーだった。」
― In the Plex
2人はスタンフォード大学で出会い、自由な知的対話と研究の文化のなかで、検索エンジンの根本的再設計に取り組み始めた。そこには、「問いを立てる力」が養われる学問的環境があった。
モンテッソーリ教育と「好奇心を駆動力とする学び」
興味深いのは、ラリー・ペイジとセルゲイ・ブリンの両名がモンテッソーリ教育を受けていたことだ。
モンテッソーリ教育は、子どもの「自主性」や「探究心」を重視し、「教え込む」のではなく「集中して取り組む力」や「問いを見つける力」を育む教育法である。
この教育の影響について、2004年の米ABCニュース番組『20/20』で、2人は次のように語っている。
“We both went to Montessori school, and I think it was part of that training — of being self-motivated, questioning what’s going on in the world, doing things a little bit differently.”
― Sergey Brin, ABC News 20/20 interview, 2004
(僕たちは2人ともモンテッソーリ教育を受けたんです。自分で動機づけされて、世界で何が起きているのかを疑い、ちょっと違ったやり方をする。そんなトレーニングの一部だったと思う。)
“I think it was part of that training of not following rules and orders, and being self-motivated, questioning what’s going on in the world, doing things a little bit differently.”
― Larry Page, ABC News 20/20 interview, 2004
(僕にとってモンテッソーリ教育は、「ルールや命令に従うな」「自分で動機づけろ」「世界を疑え」「違うやり方でやってみろ」と教えてくれる訓練だったと思う。)
こうした姿勢は、Googleの組織文化に深く刻み込まれている。社員一人ひとりが自分の興味に基づいて動く自由を持つ仕組みも、このモンテッソーリ的価値観の延長線上にある。
まるで大学のような社風:自由・知性・フラットさ
Googleの本社キャンパスは、しばしば「企業というより大学のようだ」と評される。その理由は、以下のような文化的特徴にある。
- 上下関係が希薄で、誰もが自由に意見を言える構造
- 社内食堂・ジム・洗濯機など生活機能の完備による、創造的時間の最大化
- 会議ではデータと論理が優先され、肩書きは関係ない
“Smart creatives want to spend their time figuring things out, not just doing what they’re told.”
「スマート・クリエイティブたちは、ただ言われたことをやるのではなく、自ら考え、問題を解決することに時間を使いたいのだ。」
― How Google Works
このような環境が、「知的対話」「試行錯誤」「実験精神」を自然に生み出す装置として機能している。
人事制度:採用こそが最も重要な戦略
『How Google Works』で繰り返し強調されているのは、Googleにおける採用の重みである。
- **学歴や経験よりも「学ぶ力」**を評価
- 採用には多層的かつ横断的なプロセスを導入
- **自律的で創造的な人材(Smart Creative)**を最重要視
“Hire only people who are smarter than you.”
「自分より賢い人しか雇うな。」
― How Google Works
採用された人材には大きな裁量と自由が与えられ、「やりたいことに取り組み、結果を出す」ことが期待される。
この徹底した信頼と選抜の文化こそが、Googleの核にある。
イノベーションはどう生まれたか?
Googleは、「余白」や「実験空間」をあらかじめ制度として設計することで、偶然に依存しないイノベーションの土壌を構築してきた。
代表的な施策:
- 20%ルール:業務時間の20%を自分のプロジェクトに充てることが許される
→ Gmail や Google News はこの制度から生まれた - “Launch and iterate”文化:完璧を目指すより、まず出してから磨く
- OKR(Objectives and Key Results):全社的に目標と成果を可視化する仕組み
“Create the environment where innovation happens, don’t try to manage it directly.”
「イノベーションが自然に起きる環境をつくれ。それを管理しようとするな。」
― How Google Works
さらに、Googleの初期からプロダクトの品質とユーザー体験を支えてきた**Marissa Mayer(メリッサ・メイヤー)**は、次のように語っている。
“Creativity loves constraint.
That’s where the real art comes in — to figure out how to work within the constraints and make something really beautiful.”
「創造性は制約を好む。真の芸術とは、その制約の中でどうやって美しいものを生み出すかを見つけ出すことにある。」
― Marissa Mayer, quoted in In the Plex
Googleでは、自由な発想だけでなく、スピード・シンプルさ・ユーザー中心という制約も明確に設計されていた。この制約と自由のダイナミズムこそが、革新的なプロダクト群を生んだ背景である。
Googleから学べること
Googleの成長は、単にテクノロジーや資金力では説明できない。その本質には、人間の好奇心・自律性・知性を信じ抜いた組織設計と文化的意志が存在しているといっていい。
- 子どもの教育(モンテッソーリ)
- 創業者の思想
- フラットな組織文化
- 人材の見極めと信頼
- イノベーションを生む設計思想
これらは、Google固有のものではないが、イノベーションを引き起こす組織にとって重要なのではないかと思う。
少しでもこの投稿が役立つことを願っています。






