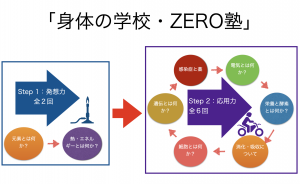【B#177】ピクサーから学ぶ〜創造的な組織とBRAIN TRUST、CANDIDの考え方
Table of Contents
はじめに
東京・渋谷でロルフィング・セッションと脳科学から栄養・睡眠・マインドの脳活(脳科学活用)講座を提供している大塚英文です。
トイストーリー(Toy Story)、モンスターズ・インク(Monster’s Inc.)ファインディング・ニモ(Finding Nemo)等、合計33作品を世に発表してきた、ピクサー・アニメーション・スタジオ(Pixar Animation Studio、以下ピクサー)。
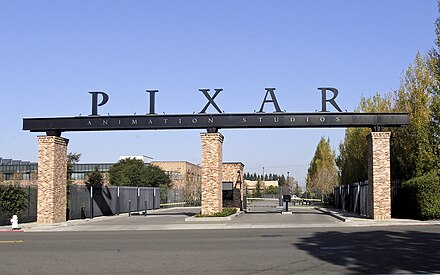
できるだけ、続編は出さすに新作にこだわって作ってきただけではなく、一人の天才に頼らずに、創造的な組織を作り上げたところに成功の秘訣がある。
創業者の一人、エド・キャットムル(Ed Catmull)(エイミ・ワラスとの共著)は、『ピクサー流・創造するちから・小さな可能性から大きな価値を生み出す方法(Creativity Inc.)』の中で、ピクサーが単発の成功ではなく、継続的に革新的な作品を生み出せる組織を作り上げることができた理由について詳しくまとめている。
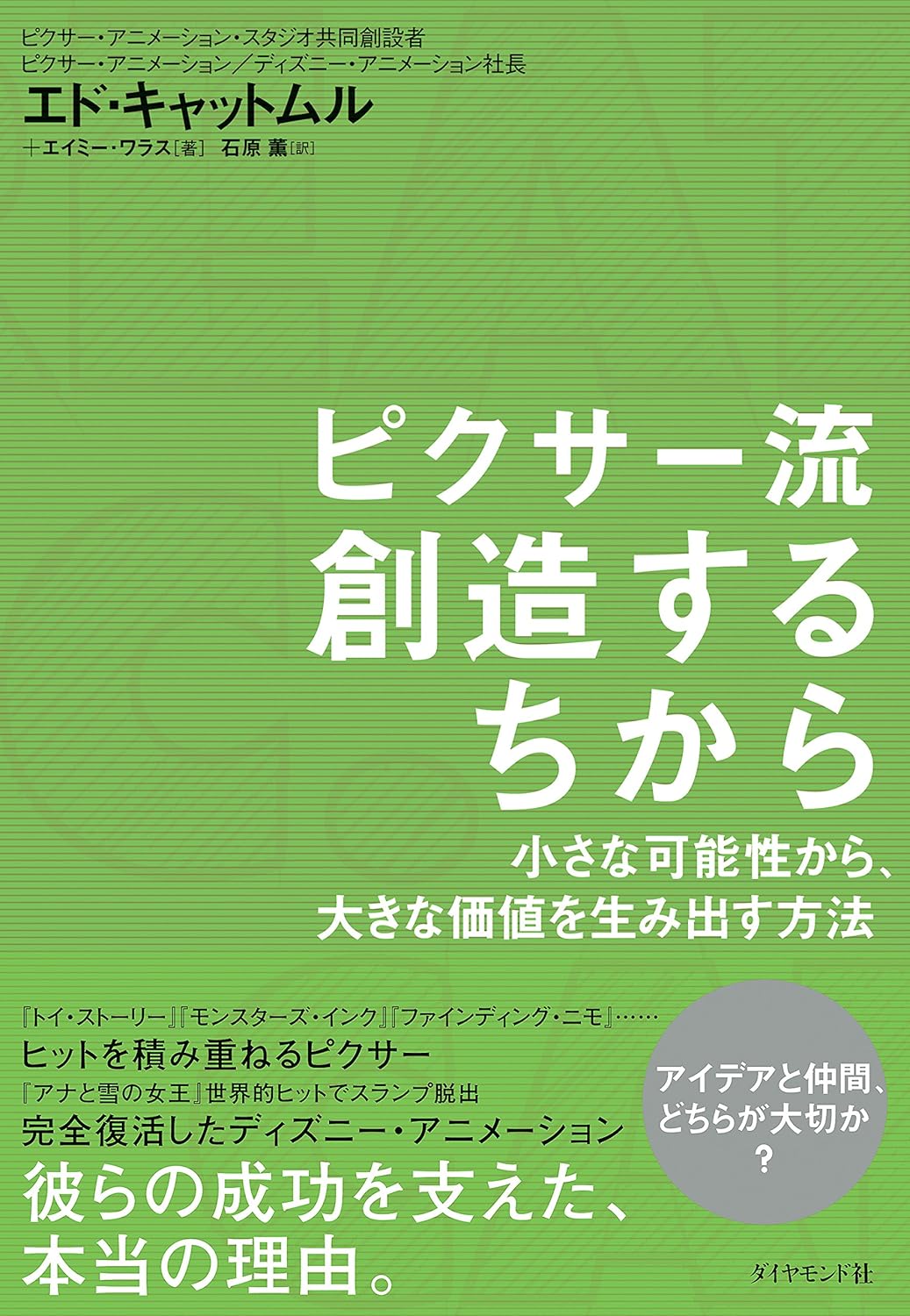
ピクサーは、キャットムル、ジョン・ラセター、スティーブ・ジョブスらによって設立。コンピュータ・グラフィックス(CG)にこだわった革新的なアニメーションスタジオとして発展していく。興味深いのは、CGよりもストーリーにこだわった上で、創造性を持続的に生み出す組織 を作り上げていったことだ。
今回のブログでは「創造するちから」を参考に、創造的組織を作り上げていく上で、ピクサーはどのような工夫をしたのか?キャットムルが語っている3つの要素である「人」「文化」「システム」を中心にまとめたい。
創造的な人材を引きつけ、育てる仕組み
「正しい人」を採用し、自由を与える
ピクサーでは、スキルよりも創造的なマインドを持つ人材を採用 し、 管理しすぎずに自由に考えさせる 文化を築いた。
キャットムルの考え方:
- 「アイデアよりも、人のほうが重要である」
- 最高の人材がいれば、アイデアが不完全でも良いものに進化できる。
- 逆に、完璧なアイデアでも、適切な人材がいなければ失敗する。
例えば、『ファインディング・ニモ』の制作時、ストーリーが行き詰まった際に、監督のアンドリュー・スタントンは自由に試行錯誤する時間を与えられた。結果として感動的な物語が生まれることになる。
創造性を支える文化の構築
率直なフィードバックを奨励する(CANDID)
ピクサーの文化の核心には、「率直な意見を交わし合うこと」。そこで、 BRAIN TRUST という名前の会議(仕組み)を作った。
BRAIN TRUSTの特徴は、
- 失敗を責めず、学びの機会とする
- 忖度なしの意見交換ができる環境を作る
- 「相手のために厳しいことを言う」という文化を根付かせる
エド・キャットムルの本には、「フィードバックが機能しない組織では、問題が隠され、創造性が枯渇する」と表現している。
失敗を奨励し、リスクを恐れない
ピクサーの社風は「失敗を恐れない文化」 。キャットムルによると、創造的な組織を持続させるうえで不可欠な要素だという。
- すべての映画は最初はダメな状態(“All movies suck at first”)からスタート(Ugly baby(醜い子供)と表現)
- 完璧を求めるのではなく「試して改善する」プロセスを重視
- 失敗をした人を責めるのではなく、「なぜ失敗したか?」を学ぶ機会
例えば、『トイ・ストーリー2』では、途中で物語が破綻し、ほぼ作り直しになったが、失敗を受け入れたことで、最終的に傑作に生まれ変わった。
継続的に改善するシステムを設計
ピラミッド型ではなく、「フラットな組織」
ディズニーのような伝統的な映画制作では、意思決定がトップダウンで行われることが多かった。一方、ピクサーは 創造的な現場の意見を尊重するフラットな組織を目指した。
- 監督やアニメーターなど、現場の人間が主導権を持つ
- 経営陣がクリエイティブに口を出しすぎない
- 「誰でもアイデアを提案できる」文化を作る
問題は隠さず、可視化する
ピクサーでは、「問題を隠すのではなく、見えるようにする」ことを重視している。エド・キャットムルは、組織における最大のリスクは、問題が隠蔽されることだという。
- フィードバックの場を定期的に設ける(BRAIN TRUST)
- 「言いにくいことを言う文化」を奨励する(CANDID)
- 「フィードバックを受ける側の姿勢」も重要視する
例えば、映画の中盤でストーリーが弱い場合、制作チームが率直にそれを指摘し、議論を重ねることで最適な形にブラッシュアップされる。
さて、キャットムルが語っている3つの要素である「人」「文化」「システム」のうち、三つの要素を体現している、BRAIN TRUSTについて、もう少し詳しくまとめたい。
BRAIN TRUSTと創造性
BRAIN TRUSTの特徴
BRAIN TRUSTは、ピクサーの映画制作プロセスの中核をなす フィードバックと改善の仕組みの一つ。作品の単なるレビュー会議ではなく、創造的な問題を解決し、作品の質を向上させるために行われている。
主な特徴:
- 少人数の経験豊富なメンバーが集まり、率直に意見を交わす
- ヒエラルキーを排除し、すべての意見が平等に扱われる
- 批判ではなく、作品をより良くするための建設的なフィードバックが目的
- 監督は意見を強制されるわけではなく、最終的な判断は自ら行う
この仕組みにより、監督や制作チームは 新たな視点を得て、作品を客観的に見直すことが可能になる。
BRAIN TRUSTの運用
BRAIN TRUSTは、映画の制作プロセス全体を通して定期的に開かれているという。通常、映画がある程度の形になった段階で ストーリーボードや初期アニメーションを基にレビューを実施。物語の構成やキャラクターの成長、感情的なインパクトなどを徹底的に議論します。
メンバーには、ジョン・ラセター、アンドリュー・スタントン(『ファインディング・ニモ』監督)、ピート・ドクター(『モンスターズ・インク』監督)など、成功経験のある監督や脚本家が参加。彼らが、忖度なしに率直な意見(CANDIDと表現)を述べることで、映画の完成度を高めていく。
ピクサーの制作現場では以下のような場面があったという。
- 『トイ・ストーリー1』のウッディのキャラクター修正
初期のウッディは 「自己中心的で嫌なやつ」 という性格だった。BRAIN TRUSTのメンバーは「観客が感情移入できるキャラクターではない」と指摘。
→ 結果、ウッディの性格を「リーダーだが、不安を抱えた存在」に修正し、バズとの関係性がより深みのあるものになった。 - 『カールじいさんの空飛ぶ家』の冒頭10分の改良
初期の案では、カールとエリーの過去の回想シーンは短かった。しかし、BRAIN TRUSTの意見により、 彼らの人生をより詳細に描くことで、観客が深く共感できるようになった。
→ 結果、あの感動的なオープニングが生まれ、観客の涙を誘う名シーンに。
BRAIN TRUSTの意義について、キャットムルは以下の動画で詳しく語っているので、ご興味のある方はチェックくださいね。
まとめ
今回のブログでは、キャットムルの著書の「創造するちから」を参考に、創造的組織を作り上げていく上で、ピクサーはどのような工夫をしたのか?
キャットムルが語っている3つの要素である「人」「文化」「システム」を中心にまとめさせていただいた。特に、BRAIN TRUSTの仕組みは興味深いので、詳しく説明した。
少しでもこの投稿が役立つことを願っています。