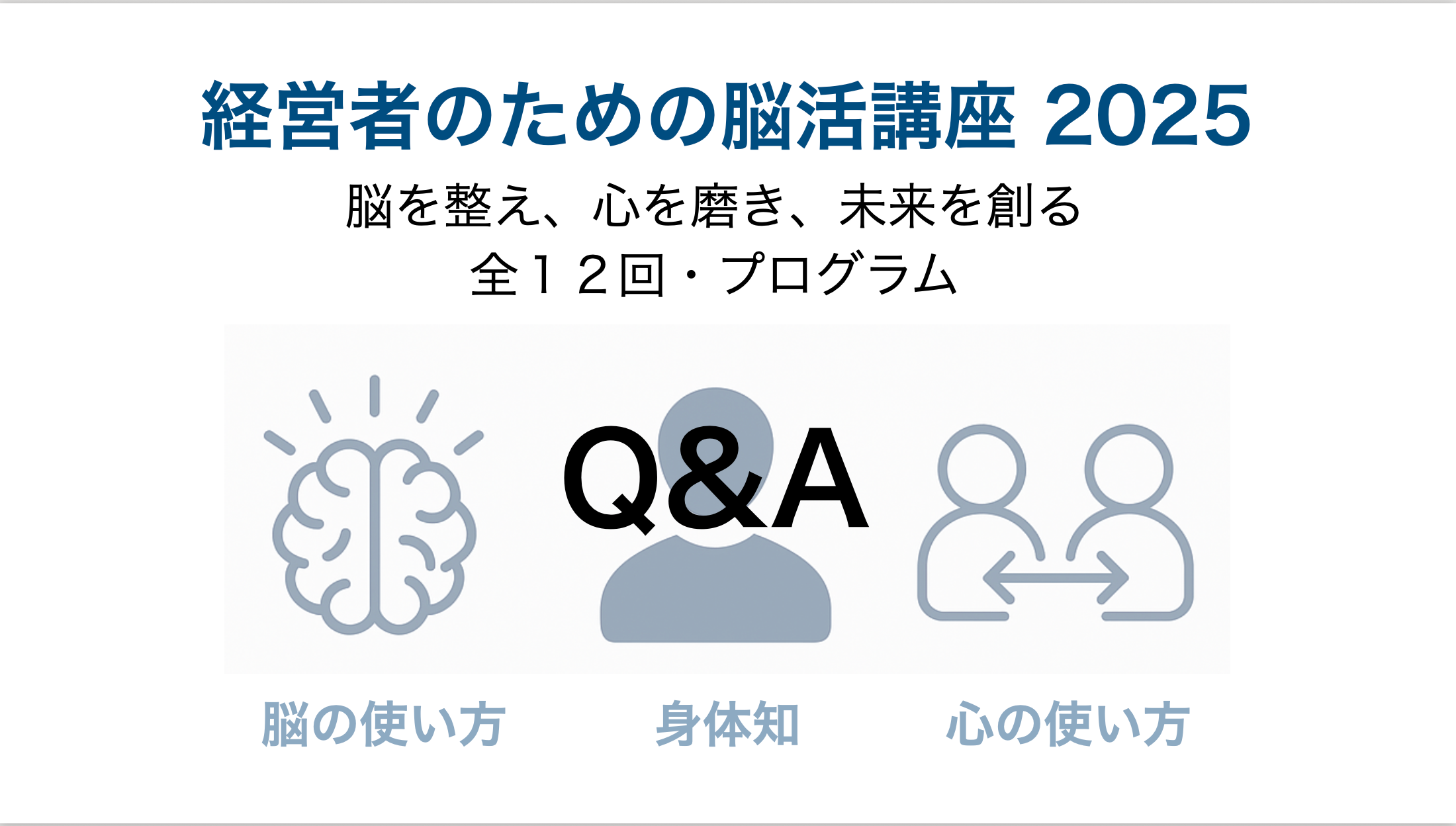【N#123】エビデンスに基づく医療①〜「科学論文」はどう審査されるのか〜「査読」の歴史と課題
Table of Contents
はじめに
こんにちは!東京・渋谷でロルフィング・セッションと栄養・タロットカウンセリングを提供している大塚英文です。
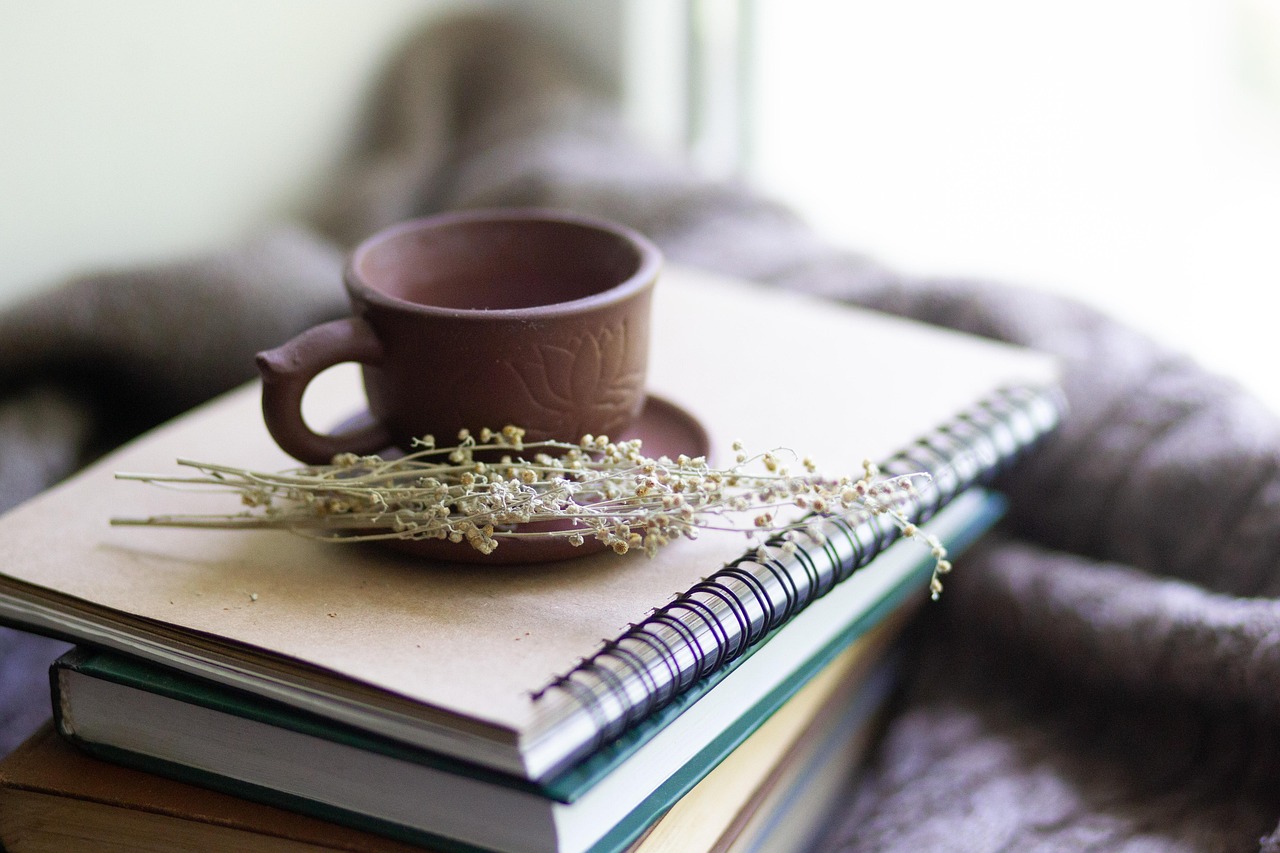
エビデンスに基づく医療と叫ばれているが・・・
医療では、事実(エビデンス)に基づく治療(EBM、Evidence Based Medicine)が叫ばれている。EBMによって、製薬会社と医師との共同作業で治療ガイドライン(一種のアルゴリズム)を決定。医師によって病気が診断されると、治療ガイドラインに沿って、治療が決まる。
エビデンスは、何も疑問にも持たれることなく、進む。
そもそも
「科学の考えるエビデンスとは何か?」
「知識とはなにか?」「どのようにして知識が生まれるのか?」
知識が生まれる現場にいないと、考える機会がないと思う。
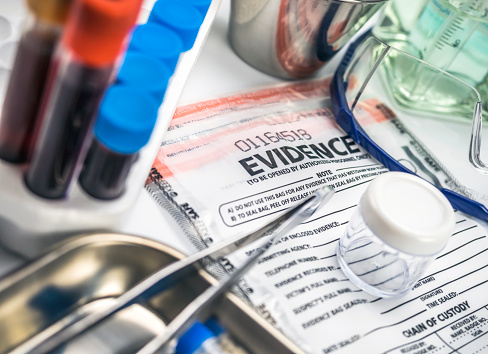
そこで、今回は「知識」について考えたい。
「知識」とは何か?〜科学論文と「査読」制度
そもそも知識とは何か?
「印刷されたもの(例、科学では論文や本)が知識」
であり、
「印刷された知識って正しいのか?」
誰が、真贋を見極めるか?が重要となる。
一方で、人間は、知識と対峙している時、以下のような弊害もあるのだ。
「知識を身につけてしまうと、その目線で物事を見てしまい、ありのまま現象を見れなくなる」
「観察力を磨く必要があるのに知識が仇になってしまう」

大学院で研究をしていたときに、データを集め、新しい知識が生まれる(論文を書く)現場を見る幸運に恵まれ、科学雑誌に論文が掲載されるときに、査読(Peer Review、ピアレビュー)を経ることがわかった。
手順は以下の通りだ。
- 研究者がデータを集め、論文という形でまとめたら、科学雑誌が発行する出版社に原稿を郵送する。
- 出版社は、科学誌に掲載する価値があるかどうかを編集者(主に科学者)が判断(これは報酬あり)。
- 編集者がOKならば、レビューに回され、複数の同じ研究分野の研究者によって、論文が掲載価値があるかどうか、判断される。
- 掲載価値があるかどうかは、基本的に無償で、ボランティアで行われており、このプロセスのことを「査読」と呼ぶ。
この構造は「いびつな構造」と指摘する識者(英国の新聞「Guardian」は問題ありと指摘した記事もある、以下の情報はこの記事からまとめている)もいるが、専門家の間で、この制度を批判する声は全く聞かれない。
しかしながら、考えてみれば「いびつな構造」と言ってもいい。
要は、
「お客さんから受け取った「原材料(論文)」」
を
「他のお客さんに品質管理(査読)を依頼」
し
「チェックが済んだ商品(論文が掲載された科学誌)を他のお客さん(世界中の科学者)に売る」
という構造になっているからだ。
私は民間会社(製薬会社)に勤めた経験があるが、企業で、このようなことが起きたら、クレームになること必須だ。如何に、査読制度は、科学者の良心によってなりなっているかが理解いただけるかと思う。
意外と知られていないのは、誰が査読制度を作ったか?だ。
「査読」制度はどのように生まれたのか?〜出版社のビジネスモデルの成功
査読制度を作ったのは、ユダヤ系チェコ出身で、英国移民のロバート・マクスウェル(Robert Maxwell)。余談になるが、未成年者に対する売春の勧誘の疑惑で米国で有名になったジェフリー・エプスタイン(Jeffery Epstein)の長年のビジネスパートナーを務めたギレーヌ・マクスウェル(Ghislaine Maxwell)は、ロバートの娘だ。
ロバートは、第二次世界大戦の時に、ナチス・ドイツの迫害を逃れ、英国へ亡命。英国軍で功績を上げて、連合軍が占領するドイツ・ベルリンで諜報部員として活躍。9種類の言語を操ることができ、囚人を尋問していたという。

英国で問題だったのは、最高レベルの科学者がいたのに(抗生物質を発見したアレクサンダー・フレミング、進化学者のチャールズ・ダーウィン等)、英国の科学雑誌のレベルが低かったことだった(現在、英国には、NatureやLancet、BMJ等といったインパクトファクターが高い雑誌がある)。
戦後、英国政府主導で、ドイツで有名だった出版社・Springerのノウハウを、英国の出版社であるButterworths(現Elsevier)が学ぶ。ここにロバートが関わることになる。
ロバートは、英国国内に配送する業務を請負、出版物の販売権を獲得し、Springerの経営に参画していく。経営権を手にしたマクスウェルは若い科学者のポール・ロスバウドを雇い、科学編集者にした。その際、科学雑誌の名前をPergamon(ギリシャ語で「知恵」という意味)に改称する。
ロスバウドは、研究分野を広げるためには、新しい科学雑誌が必要だと著名な学者に働きかけ、説得工作を行う。このビジネスモデルをロバートが引き継ぐことになる(後に、ロバートのビジネスの方法に嫌気をさしたロスバウドは、Pergamonから離れる)。
1959年には、Pergamonは40雑誌、6年後に150雑誌にまで増えていった(競合のElsevierは、10雑誌で、その後10年かけてようやく50まで到達することになる)。
雑誌が多くなると、編集者を含め、人材不足に陥る。苦肉の策として、ボランティアで成り立つ専門家による査読制度を取り入れ流。人件費を大幅に削減に成功し、国家から研究費が潤沢に入っていた、大学・研究機関に雑誌をパッケージとして販売(Pergamonの雑誌の一括購入を条件にする等)で、ビジネス的に大成功する。
1985年には、5割近くの利益率を確保し、1991年に出版大手のElsevierが買収(4億4000万ポンド(現在の価値にして約1400億円))する。そして、世界最大の科学分野の出版社Elsevierは、売上の約40%が利益という、GoogleやApple、Amazonなどのハイテク企業をも、完全に超える、すごい企業が誕生した。
「査読」制度は問題ないのか?〜新しい知識や発想に対しては・・・
「なぜ「査読」を行うのか?」
その根拠として、個々の研究者(研究グループ)が自分たちだけで仕事の価値を評価するのは難しいという前提がある。
一方で、こういった意見もある。
生態学者のAllan Savoryさんの見方について紹介したい(英語を意訳しています、下記が動画)。
人は、科学について話すことが多いが、そもそも科学とは何か?考えたことがあるだろうか。
大学を卒業して、修士、博士を得るが、研究現場に出すと、彼らは文字通り、査読された論文以外は信じなく、
それしか受け入れない。彼らに、観察してみよう、考えよう、議論しようとたとえ言ったともしても・・・
それをしない。
科学の見方が査読の論文に基づいたものになってしまっている。
論文が査読されるという意味は、単に、すべての人が同じように考えたということで、
その承認を受けたことにすぎないと言える。
もし、予想外の形で新しい知識や新しい発想が出てきたら、それを査読できるのだろうか?
実は、査読の仕組みって、科学の発展を止めてしまうリスクもあるのだ。
世界で最も多くの人が聴いているポッドキャストを主宰するJoe Roganは、数学者・物理学者のEric Weinstein博士との対談で、査読制度が取り入れられるようになったことで、超ひも理論を例に、物理学にイノベーションが生まれにくくなり、発展の阻害の大きな原因になっている可能性があると指摘している(以下英語版、ご興味のある方はチェックください)。
現代医療とどう結びつくのか?〜査読制度、専門家の意見
先ほど、医療では、事実(エビデンス)に基づく治療によって行われていると書いた。それが、正しい間はいいと思うが・・・。査読制度を見ると、専門家があくまでも正しいという前提で動いていることがよくわかる。
もし、
既存の治療に効果がない場合はどうか?
治療の前提が間違っている場合はどうか?
代替医療の検証はどうか?
等、
医療のイノベーションを起こそうと思った時に、論文の前提となる査読制度が障害になる。
まとめ
今回は、医療や科学知識の中で見逃されている、論文のベースとなる「査読」の仕組みを歴史から書いた。この投稿が少しでも、お役に立てれば幸いです。