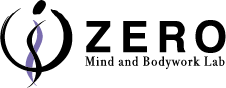【B#255】2025年・認知科学をめぐる読書──「心の理論」ではなく、「世界と関係する仕組み」として
Table of Contents
はじめに
こんにちは。
渋谷を拠点に、ロルフィング®やコーチング、タロット、脳活講座を行き来しながら、考えること・感じること・身体感覚(肚・丹田)が、自然にひとつの判断としてまとまっていく状態を取り戻すための場をつくっている大塚英文です。
2025年は、3年間のテーマの最終年として「脳(記憶+脳科学)」を、そして1年間のテーマとして「量子力学」を集中的に読み続けた。結果として年間310冊を読むことになった。そうはいうものの、予定通りいかず、途中から「量子力学・認知科学・組織の経営」という三つのテーマへと変更していく。
強く意識するようになったのは、
理論そのものよりも、その理論がどのような「世界観」を生み、どのような「人間観・組織観」を支えているのか
という点だった。
量子力学を読んでいるときにも感じたことだが、本当に面白いのは数式や理論そのものではない。それらが前提としている「世界観」や「人間観」が、静かに書き換えられていく瞬間だった。
同じことが、認知科学を読む中でも起こっていた。
前回は量子力学を扱ったので、今回は、認知科学関連書籍の中から、特に「一本のストーリー」を形づくった5冊を取り上げたい。
因果で世界を理解しようとする脳
最初に紹介する1冊目は、ジューディア・パール(Judea Pearl)の「因果推論の科学(The Book of Why – The New Science of Cause and Effect)」。
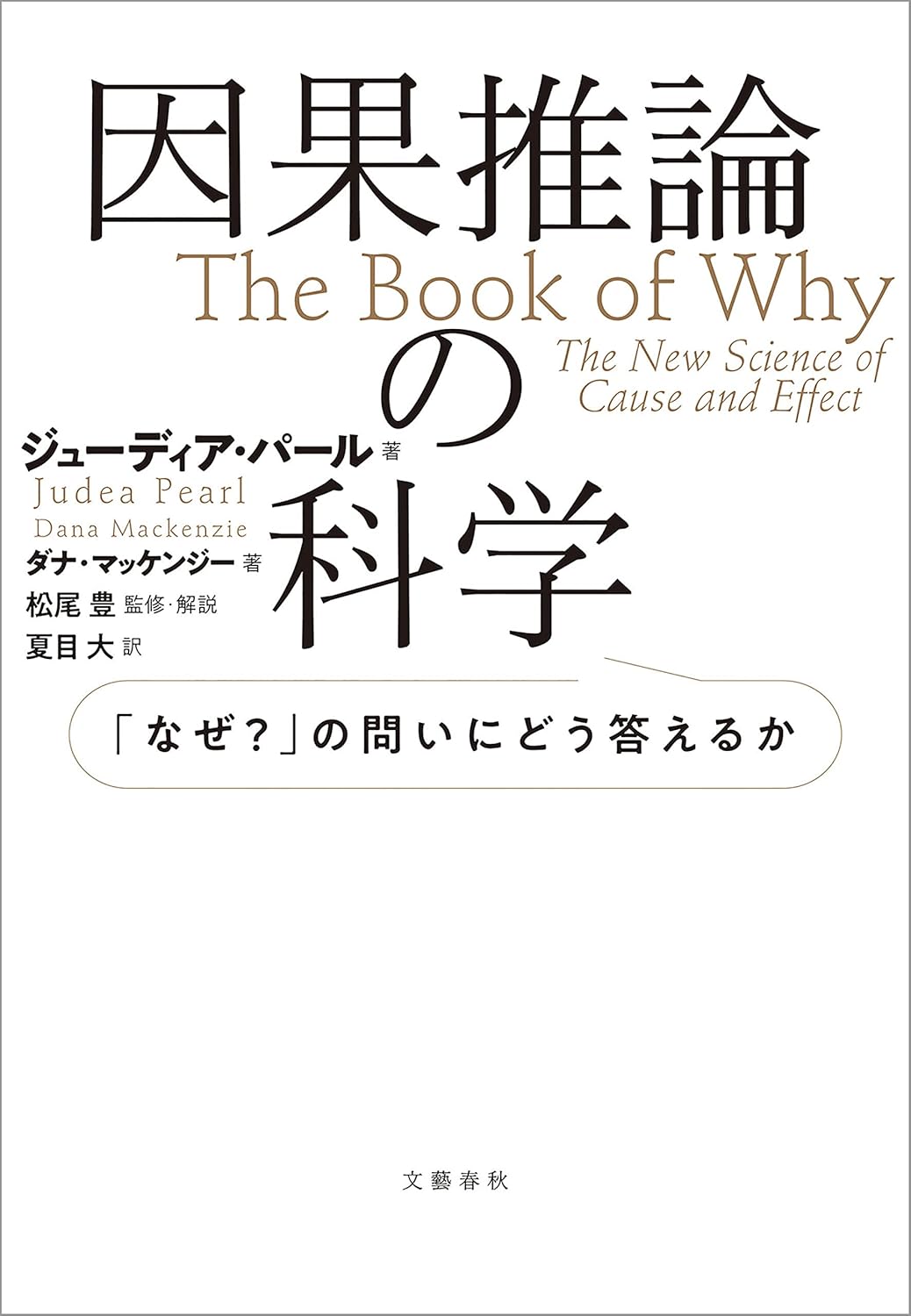
この本が面白いと思ったのは、自分が長年「当たり前」だと思ってきた人間の理解の仕方が、はっきりと言葉にされたからだ。パールは、人間の認知を三つの段階で説明する。彼はこれを「因果のはしご(Ladder of Causation)」と呼んでいる。
因果のはしご──観察(Seeing)
最初の段階は、観察(Seeing)である。
「Aが起きたとき、Bが起きている」
統計やデータが扱うのは、基本的にこのレベルだ。相関を見つけ、パターンを抽出する。AIが最も得意とする領域でもある。
因果のはしご──介入(Doing)
次の段階は、介入(Doing)だ。
「もしAを変えたら、Bはどうなるか?」
ここでは、人間は単なる観察者ではなくなる。世界に手を入れ、操作し、その結果を考える。このレベルに到達した瞬間、世界は“眺めるもの”から“関わるもの”へと変わる。
因果のはしご──反事実(Imagining / Counterfactuals)
そして、パールが最も重要だと強調する第三の段階が、反事実(Imagining / Counterfactuals)である。
「もしあのとき、別の選択をしていたら、世界はどうなっていただろうか?」
この問いは、データからは直接得られない。それでも私たちは、どうしても考えてしまう。
あのとき別の言葉を選んでいたら。あの決断をしなければ。あの出来事がなかったとしたら。
後悔、学習、責任、成長。
それらはすべて、人間独特の思考なのだが、この反事実のレベルから生まれる。
この三段階を読んだとき、私ははっきりと感じた。人間の知性とは、情報処理能力の高さではない。
「なぜ?」と問い、
「もしも」を想像し、
過去を書き換えられないと知りながら、なお意味を見出そうとする力なのだと。
量子力学との関係性
量子力学を読んでいるときに何度も出会った感覚を思い出される。観測とは、世界をそのまま写す行為ではない。世界を、ある枠組みで記述し直す行為である。
私たちは、世界を直接知っているわけではない。因果という仮説装置を通して、世界と関係している。
パールの本は、認知科学を「脳の中の計算モデル」から「人間が世界とどう関係せざるを得ないかの学問」へと引き上げてくれた。
そしてこの視点は、後に続く
判断の歪み、
認知の外部化、
習慣の固定化、
文化と関係性の話へと、自然につながっていく。
判断とは、世界に「どう関わるか」を決める行為である── 観察と介入のあいだで揺れ動く心
2冊目は、ダニエル・カーネマンの「ファスト&スロー・あなたの意思はどのように決まるか?(Thinking, Fast and Slow)」 だ。
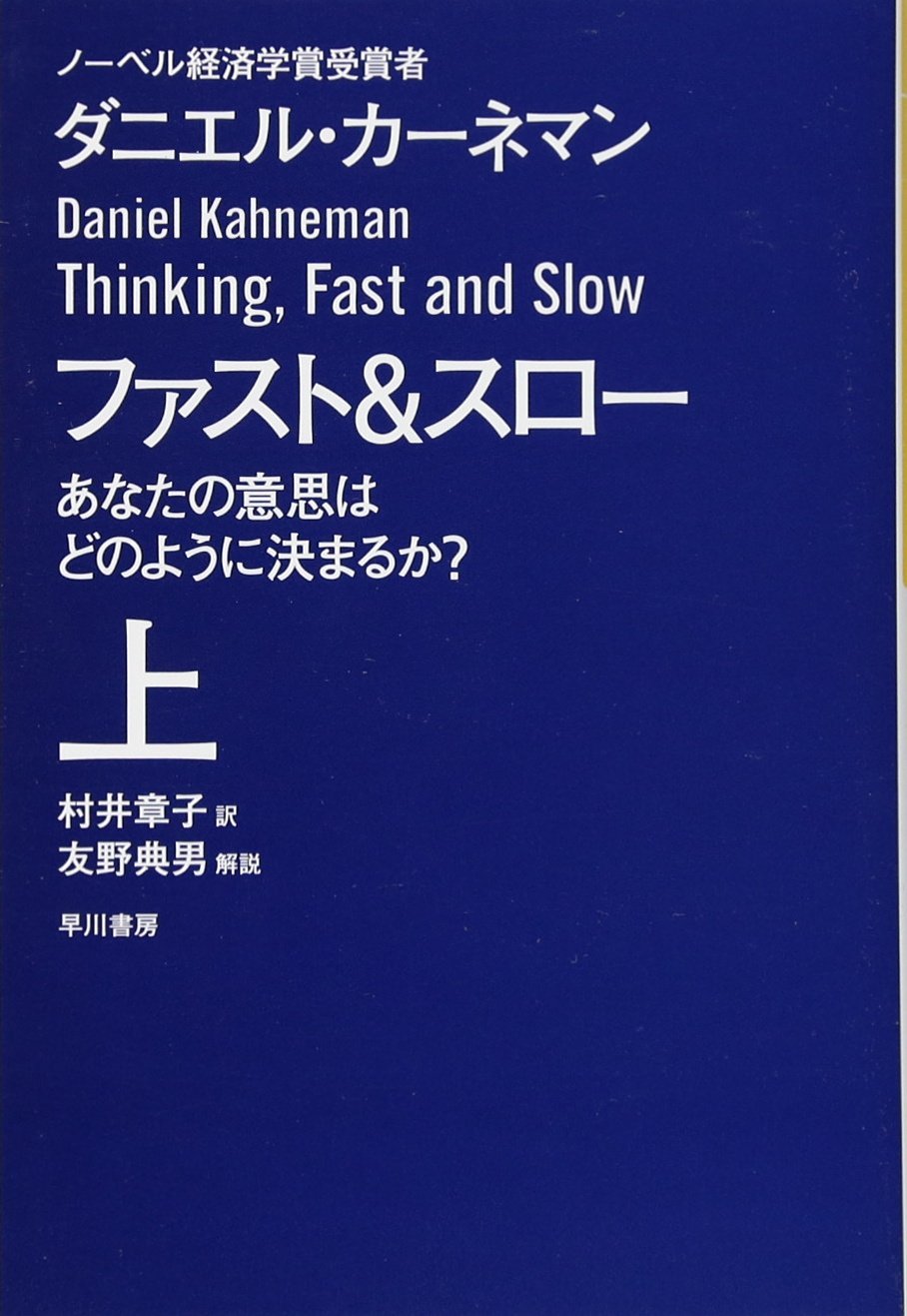
カーネマンの本を語るうえで、避けて通れない前提がある。それは、カーネマンが紹介する、人間の脳が二つのまったく異なるモードを持っている、という事実だ。
一つは、速く、自動的で、ほとんど努力を必要としない脳。もう一つは、遅く、意識的で、エネルギーを要する脳。カーネマンはこれを、それぞれシステム1(早い脳)、システム2(遅い脳)と呼んだ。
「早い脳」──推測を事実と勘違い
この区別に初めて触れたとき、多くの人は「なるほど」と思うだろう。だが、本当に重要なのはその先にある。私たちは、人生のほとんどを“早い脳”で生きている。
早い脳は、世界を即座に観察する。顔色、声のトーン、空気感、違和感。それらを一瞬で読み取り、「だいたいこういう状況だ」と判断を下す。この脳は、驚くほど有能だ。もし毎回、遅い脳を立ち上げなければならなかったら、私たちは朝ベッドから起き上がることすらできないだろう。
だが同時に、早い脳には致命的な弱点がある。それは、自分が推測していることを、事実だと思い込んでしまう点だ。観察と解釈が、ほとんど区別されないまま進んでしまう。
ここで、パールの言う因果の第一段階──観察──が、すでに揺らぎ始めている。
「遅い脳」──本当にそうか?
一方、遅い脳はどうか。
遅い脳は、疑い、立ち止まり、計算する。「本当にそうだろうか?」「別の可能性はないだろうか?」
つまり、遅い脳は、介入を決めるための脳である。しかし、この脳には大きな制約がある。疲れやすく、時間がかかり、そして何より、怠け者なのだ。
だから私たちは、「考えたつもり」になっていても、実際には早い脳の判断を、遅い脳が後追いで正当化しているだけ、ということが頻繁に起こる。
この構造を知ったとき、私は少し苦い感情を覚える。自分が慎重に下したと思っていた判断の多くが、すでに無意識のうちに決まっていた可能性に気づいてしまったから。
パールの3段階との関係性
ここで視点を、観察/介入/反事実という軸に戻してみる。
早い脳は、観察を一瞬で済ませ、そのまま介入へと滑り込む。遅い脳は、本来ならその間に入り込み、介入を調整する役割を担う。だが現実には、遅い脳が立ち上がる前に、行動は始まってしまっていることが多い。
そして、行動の結果を見てから、私たちはようやく第三段階──反事実へと進む。
「あのとき、別の選択をしていたら」
「もっと考えていれば、違う結果になったのではないか」
後悔、納得、学習、意味づけ。それらはすべて、介入の後に生まれる物語だ。
量子力学との関係性
量子力学を読んでいたとき、私は似た構造に何度も出会った。
量子の世界では、
- 観測が状態を定め
- 操作が結果を変え
- その意味は、あとから解釈される
順序は一見明確だが、実際には観測と解釈は密接に絡み合い、切り離せない。人間の判断も同じだ。
早い脳は、観測と解釈をほぼ同時に行い、遅い脳は、操作(介入)を合理的だったかのように説明し、私たちは反事実を通して、「あの判断には意味があった」と語り直す。カーネマンの本は、この不安定で、ぎこちないプロセスを、言語化。理解を深めてくれる。
この本を読み終えたあと、私は「良い判断」「悪い判断」という言葉を、以前ほど簡単には使えなくなった。判断とは、正しさの問題ではない。限られた観察、疲れやすい遅い脳、そして止められない早い脳の協働作業なのだ。
重要なのは、「もっと考えろ」と自分を責めることではない。むしろ、
この二重構造を前提にして、
どんな環境を整え、
どんな関係性をつくり、
どこで介入を遅らせるか
を設計すること。
この視点は、次に続く「認知を環境へ外部化する」というレヴィティンの議論へと、自然に接続していく。
人間は、賢くなることで判断を誤るのではない。人間であるがゆえに、こう判断せざるを得ない。カーネマンの本は、その事実を突きつけると同時に、そこから先へ進むための、静かな出発点を与えてくれる。
関連ブログ
「思考の仕組みを知れば、意思決定が変わる──ダニエル・カーネマン「ファスト&スロー」」
「「人間の非合理性」を見つめた天才コンビ──『The Undoing Project』が描く心の探究の旅」
認知は、脳の中だけで完結しない── 人間は「環境と一緒に考える」存在である
3冊目は、ダニエル・レヴィティン(Daniel J. Levitin)の「The Organized Mind: Thinking Straight in the Age of Information Overload」(邦訳なし)だ。
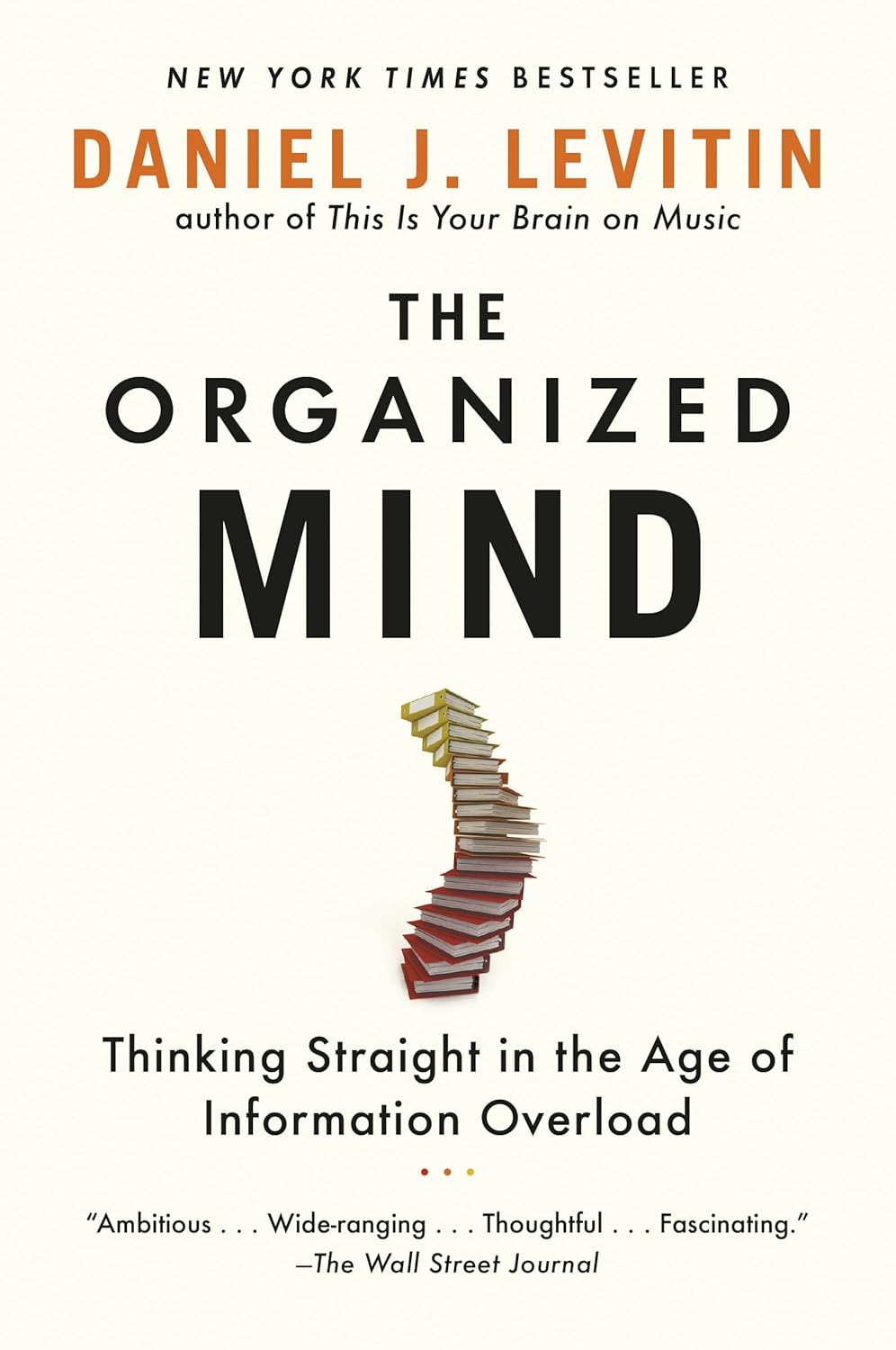
カーネマンの本では、早い脳が判断の大半を引き受け、遅い脳は疲れやすく、パールの本で言う、介入のタイミングには間に合わないことが多い。そうなると、一瞬、ではどうしたら、私たちはどうやって日々の生活や仕事を成り立たせているのか、という疑問が自然に湧いてきた。
そのような時に、ダニエル・レヴィティンの本は、明快な答えを与えてくれる。
この本を一言で言うなら、人間は、脳だけで考えているのではないということだ。
人間の記憶・注意の脆弱性
レヴィティンは、脳科学者として、人間の記憶や注意がいかに脆弱であるかを、丁寧に説明する。私たちは同時に多くのことを覚えられないし、集中力はすぐに途切れ、判断の質は簡単に落ちる。だが、この本のトーンは決して悲観的ではない。なぜなら、人間はその弱さを前提にして生きる方法を、すでに発明してきたからだ。
それが、認知の外部化である。
メモを取る。
予定をカレンダーに書く。
役割を分ける。
チェックリストを使う。
会議体やルールをつくる。
これらは単なる便利ツールではない。脳の限界を、環境によって補うための知的戦略なのだ。
考える場所を、脳の外へ移す意味
ここで、パールの因果の三段階に立ち戻ってみる。
観察の段階で、私たちはすでに多くを見落とす。介入の段階では、早い脳が先走り、遅い脳は追いつけない。反事実の段階では、あとから物語を作り、意味づけをする。この不完全さを、意志や努力で埋めようとすると、必ず無理が生じる。
レヴィティンが示すのは、まったく別の方向性だ。「考える場所」を、脳の外へ移すのである。
認知の一部を、環境に預ける。そうすることで、脳は本来得意な仕事──気づき、判断、関係づけ──にエネルギーを使えるようになる。
量子力学との関係性
量子力学を読んでいたとき、私は似た構造を思い出した。
量子の世界では、観測装置や実験設定そのものが、結果を規定する。観測者は、世界から切り離された存在ではない。
人間の認知も同じだ。環境は、単なる背景ではなく、認知の一部なのである。
ノート、ホワイトボード、ToDoアプリ、組織構造、文化。
それらはすべて、「思考を助ける装置」であり、
同時に「判断を歪めもする装置」でもある。
だからこそ、認知科学は、個人の頭の中だけを見ていては不十分になる。
脳の理論から生き方と設計へ
レヴィティンの本を読んで、私は強い安心感を覚えた。人がうまくいかないのは、集中力が足りないからでも、意志が弱いからでもない。環境が、その人の認知に合っていないだけかもしれない。この視点は、個人のセルフマネジメントを超えて、組織や社会の設計へと自然に広がっていく。
判断を人に委ねすぎない。
記憶に頼らせすぎない。
早い脳が暴走しないように、介入のスピードを環境で調整する。
それは、人間を「正す」ためではなく、人間を人間のまま機能させるための工夫なのだ。
こうして見ると、流れははっきりしてくる。
パールは、人間が因果で世界を理解せざるを得ない存在であることを示し、
カーネマンは、その判断がいかに自動化され、歪みやすいかを可視化し、
レヴィティンは、その不完全さを前提に、人間が環境とともに考える存在であることを明らかにする。
認知科学は、ここでようやく「脳の理論」から「生き方と設計の学問」へと姿を変える。そして次に問われるのは、自然とこの一点になる。それでも、なぜ人は変われないのか。学習された行動は、どうすれば書き換えられるのか。この問いを正面から引き受けるのが、次に紹介する、ラッセル・ポルドラックの本だ。
変われないのは、意志が弱いからではない── 学習された脳回路という「現実」
4冊目に紹介するのは、ラッセル・ポルドラック(Russell A. Poldrack)の『習慣と脳の科学:どうしても変えられないのはどうしてか?Hard Habit to Break』だ。
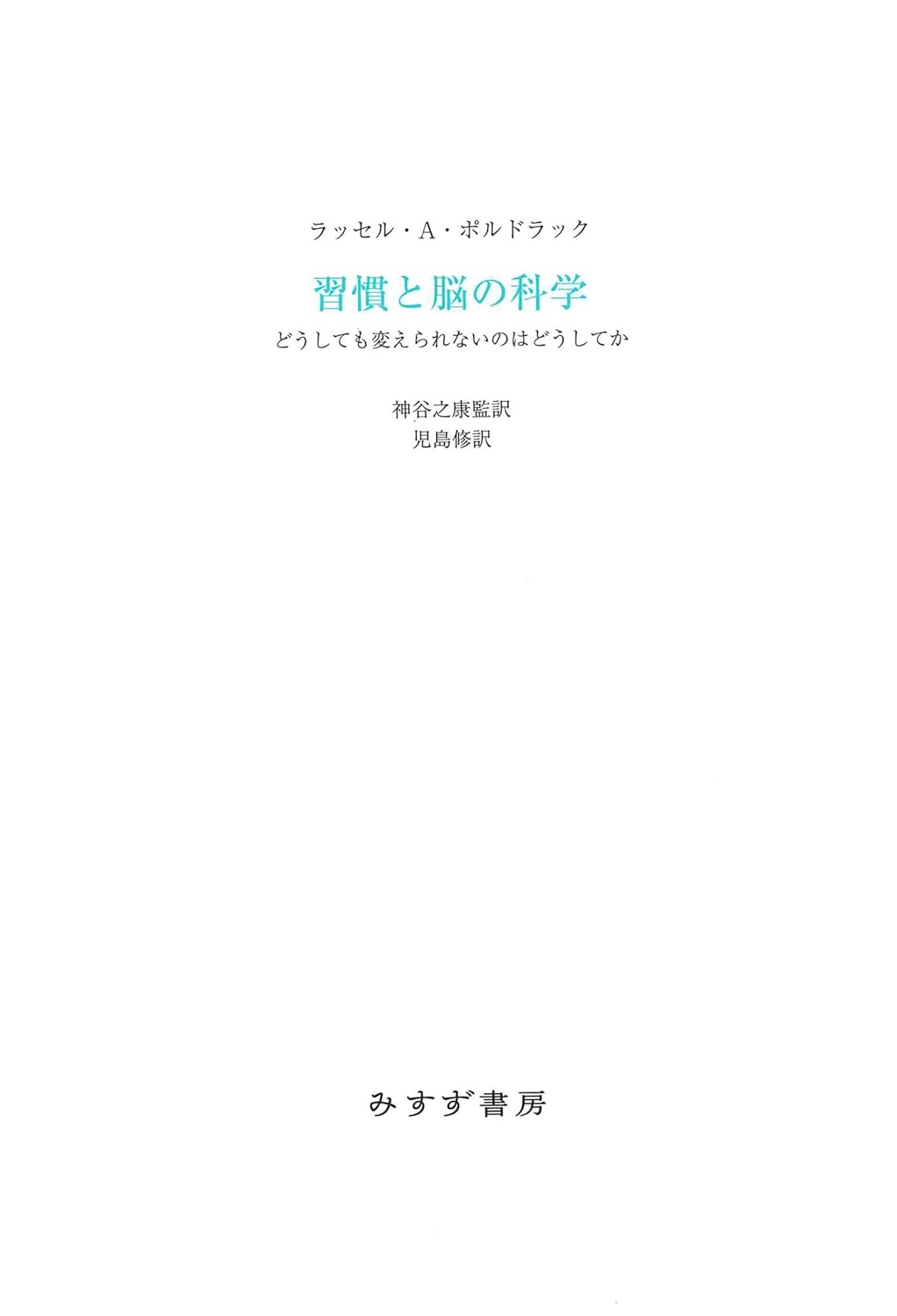
学習された脳回路は、行動の良し悪しとは関係ない
レヴィティンの本では、外部環境を整える重要性を語っているが、一方で、それでも、なぜ人は変われないのか。環境を整え、理解もしている。それなのに、同じ行動を繰り返してしまうのはなぜなのか。
この問いを、最も冷静に、そして最も容赦なく引き受けているのが、ラッセル・ポルドラックの本である。
この本を読んでいると、次第に「気合」や「決意」という言葉が、現実味を失っていく。なぜなら、ポルドラックが扱っているのは、動機や性格ではなく、学習された脳回路だからだ。
人は行動を繰り返すうちに、ある特定の回路を強化していく。それは報酬によって強化され、文脈によって呼び起こされ、やがて意識的な判断を必要としなくなる。
ここで重要なのは、その行動が「良いか悪いか」は、脳回路にとっては関係がないという点だ。
脳は、意味ではなく、結果で学習する。一時的に楽になる。不安が下がる。面倒なことを避けられる。それだけで、回路は十分に強化される。
ここで、これまでの流れを思い返してみる。
カーネマンが描いた「早い脳」は、自動的に反応する。レヴィティンが示した「環境」は、その反応をさらに滑らかにする。ポルドラックは、その背後で起きていることを、もう一段深いレベルで説明する。変化を妨げているのは、判断ではない。すでに学習された反応そのものなのだ。
観察の段階で、早い脳が状況を捉え、介入の段階では、意識が立ち上がる前に行動が始まり、反事実の段階で、私たちはようやく「なぜ変われなかったのか」と考え始める。
だが、その時点では、行動はすでに起きている。
変われない自分は、学習した結果起こる
この脳の構造を知ったとき、私は奇妙な安心感を覚えた。それは、「変われない自分」を責める理由が、静かに消えていく感覚だった。努力が足りないわけでも、理解が浅いわけでもない。ただ、学習が起きていただけなのだ。
しかもその学習は、多くの場合、生き延びるために必要だった。不安を避ける。衝突を回避する。エネルギーを節約する。それらは、かつては合理的な戦略だった。
ポルドラックの議論が重要なのは、「では、どうすれば変われるのか」という問いを、安易に希望で終わらせない点にある。彼は繰り返し示す。回路は、上書きされるのではなく、競合する。
古い習慣は消えない。ただ、新しい回路が育ち、状況によって使われる頻度が変わるだけだ。
ここで、変化のイメージが大きく変わる。
変わるとは、決断することではない。変わるとは、新しい学習を、十分な時間と文脈の中で繰り返すことなのだ。
量子力学との関係性
量子力学を読んでいたとき、私は「不可逆性」という言葉に何度も出会った。一度起きた出来事は、完全には元に戻らない。人間の脳も、同じだ。一度形成された回路は、なかったことにはならない。
だが、それは絶望ではない。
不可逆であるからこそ、変化は“上書き”ではなく、“重ね書き”として起こる。この視点に立つと、変化は突然の飛躍ではなく、静かで、地味で、しかし確実なプロセスとして見えてくる。
人は学習した通りに反応する生き物
ポルドラックの本を読み終えたとき、認知科学は、ついに「行動の現実」にまで降りてきたように感じられた。人は理解してから変わるのではない。判断してから動くのでもない。人は、学習してきた通りに反応し、あとから意味を与え、それでも再び学習し直す可能性を、かろうじて残している。
この理解は、厳しい。だが同時に、驚くほど人間に優しい。なぜなら、変化を「意志」ではなく、時間・環境・関係性の問題として捉え直すことができるからだ。
こうして、一本の線がはっきりと見えてくる。
人は因果で世界を理解し(パール)、
早い脳で判断し(カーネマン)、
認知を環境に委ね(レヴィティン)、
学習された回路に従って行動する(ポルドラック)。
では最後に残る問いは、ただ一つになる。その学習は、どこで、誰と、どの文化の中で起きているのか。この問いを引き受けるのが、次に続く メスキータの本である。
心は「私の中」にあるのではない── 認知は、関係と文化のあいだで生まれる
最後の5冊目は、バチャ・メスキータ(Batja Mesquita)の『文化はいかに情動をつくるのか――人と人のあいだの心理学、Between Us – How Cultures Create Emotions』だ。

ここまで様々な認知科学の本を読み進めてきて、私は一つの違和感を抱き始めていた。因果で世界を理解し、早い脳と遅い脳で判断し、認知を環境に外部化し、学習された回路によって行動する。その説明は、驚くほど整合的で、説得力がある。それでも、どこか決定的に欠けているものがあるように感じられた。
その判断は、どこで起きているのか。
その学習は、誰とのあいだで起きているのか。
バチャ・メスキータの『Between Us』は、その問いに、正面から答える本だった。
この本が突きつけてくるメッセージは、非常にシンプルで、そして深い。感情や自己は、個人の内側にあらかじめ存在しているものではない。それらは、人と人との関係、文化、社会的文脈の中で形成される。
怒り、悲しみ、誇り、恥。それらは普遍的な感情ではある。しかし、それが「いつ」「どこで」「どのように」立ち上がるかは、文化によってまったく異なる。つまり、私たちが「自分の感情」だと思っているものの多くは、実は関係性の中で作られされ、学習されてきた反応なのだ。
関係性の中で意味づけが行われる
ここで、これまでの流れを、もう一度静かに振り返ってみる。
パールが示した「因果の三段階」。観察、介入、反事実。
私たちは、何が起きているかを観察し、どう振る舞うかを選び、あとから「あのとき、別の選択をしていたら」と意味づけをする。
だがメスキータは問う。
その観察は、どの文化の目でなされているのか。
その介入は、どんな関係性の期待のもとで行われているのか。
その反事実は、どんな物語を許す文化の中で語られているのか。
ここにきて、認知科学はついに「脳」や「個人」を超え、関係と文化という場へと視野を広げる。
量子力学との関係性
量子力学を読んでいたとき、私は何度も「性質は、それ単独では存在しない」という考え方に出会った。粒子の状態は、観測との関係の中で立ち現れる。
メスキータの議論は、この感覚と驚くほど重なっている。
感情も、自己も、価値観も、
関係の中で立ち現れる。
「私はこういう人間だ」という自己像ですら、固定された本質ではなく、関係の履歴が編み上げた一つのパターンにすぎない。
人は、因果で世界を理解し、早い脳で反応し、遅い脳で正当化し、環境に認知を預け、学習された回路で行動する。だがそのすべては、常に「誰かとのあいだ」で起きている。
判断は、孤立した頭の中で完結していない。習慣は、文化の中で育つ。変化は、関係性の中でしか起こらない。
認知科学とは、人間が世界とどのように関係しながら生きる学問
こうして、認知科学は、単なる「心の仕組みの説明」ではなく、人間が世界と、他者と、どのように関係しながら生きているのかを描く学問として姿を現す。
量子力学が、「世界はモノではなく関係でできている」という世界観を私に与えてくれたように、認知科学もまた、「心は個人ではなく、関係の中にある」という人間観を、与えてくれる。
関連ブログ
「感情は「内側」ではなく「間」にある──感情と文化の新しい関係性」
まとめ──認知科学を読むことは、生き方を問い直すこと
これら5冊を通して、私は「より正しく考える方法」よりも、「人間とは、そもそもどういう前提で世界と関わっている存在なのか」を学んだように思う。人は合理的ではない。だが、それは欠陥ではない。人は自由ではない。だが、それは絶望ではない。
人は関係に縛られている。だが、その関係こそが、変化の可能性でもある。
認知科学を読むということは、自分を責めるための知識を増やすことではない。人間を、人間のまま理解し直すことなのだと思う。
そしてその理解は、生き方、関係性、組織、そして実践へと、確実につながっていく。