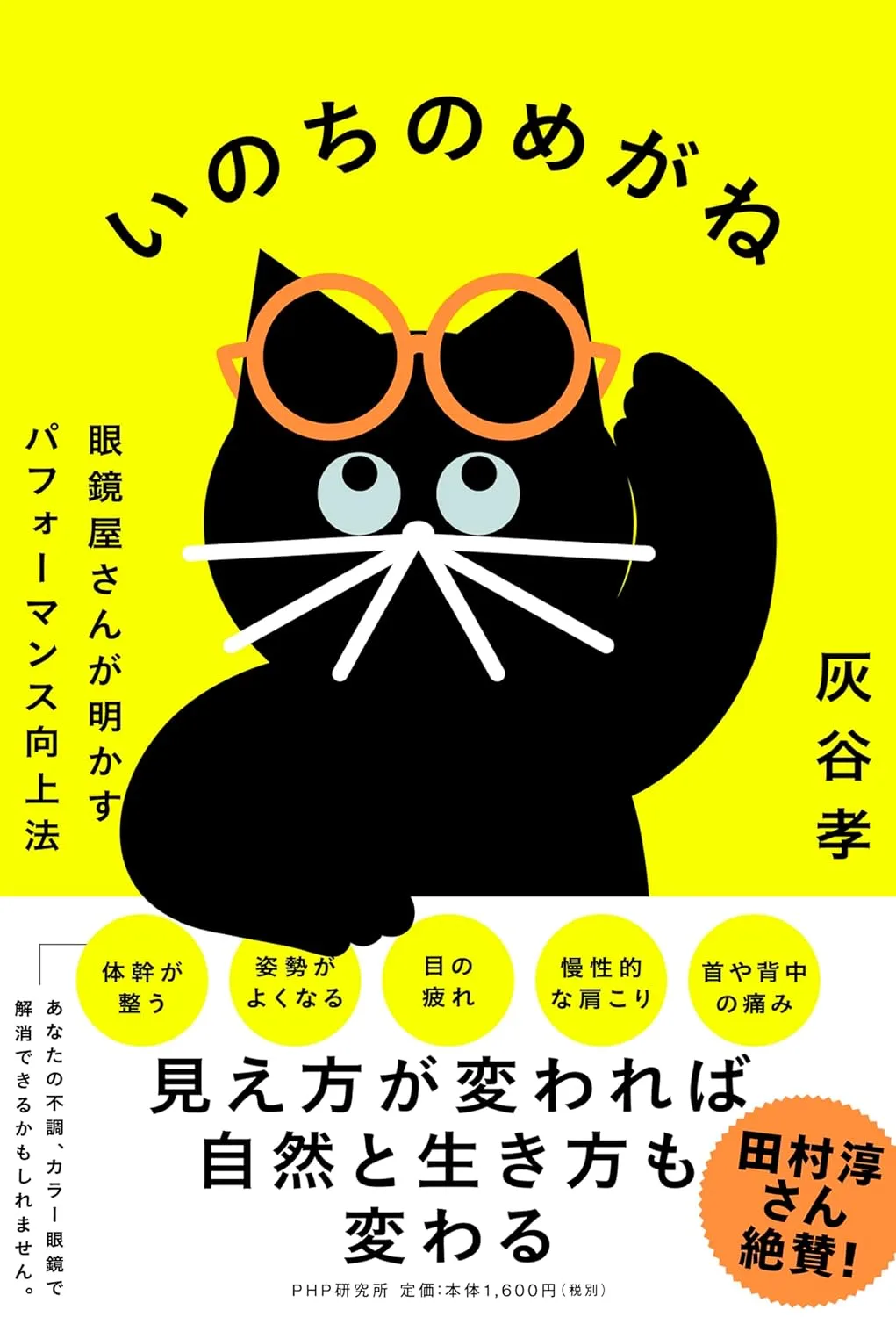【B#240】「人工的に生命を創造する研究からみる、生命と知性の本質とは」のセミナーを拝聴して
Table of Contents
はじめに
こんにちは。渋谷でロルフィング・セッションと脳科学をベースにした講座を提供している大塚英文です。
2025年11月12日(水)の午後6時半から都内で安川新一郎さん主催で行われたセミナー(BRAIN WORKOUT EXTENSION)に参加した。第2回のテーマは、人工生命(第1回の人類学についてはこちらをご参照ください)。
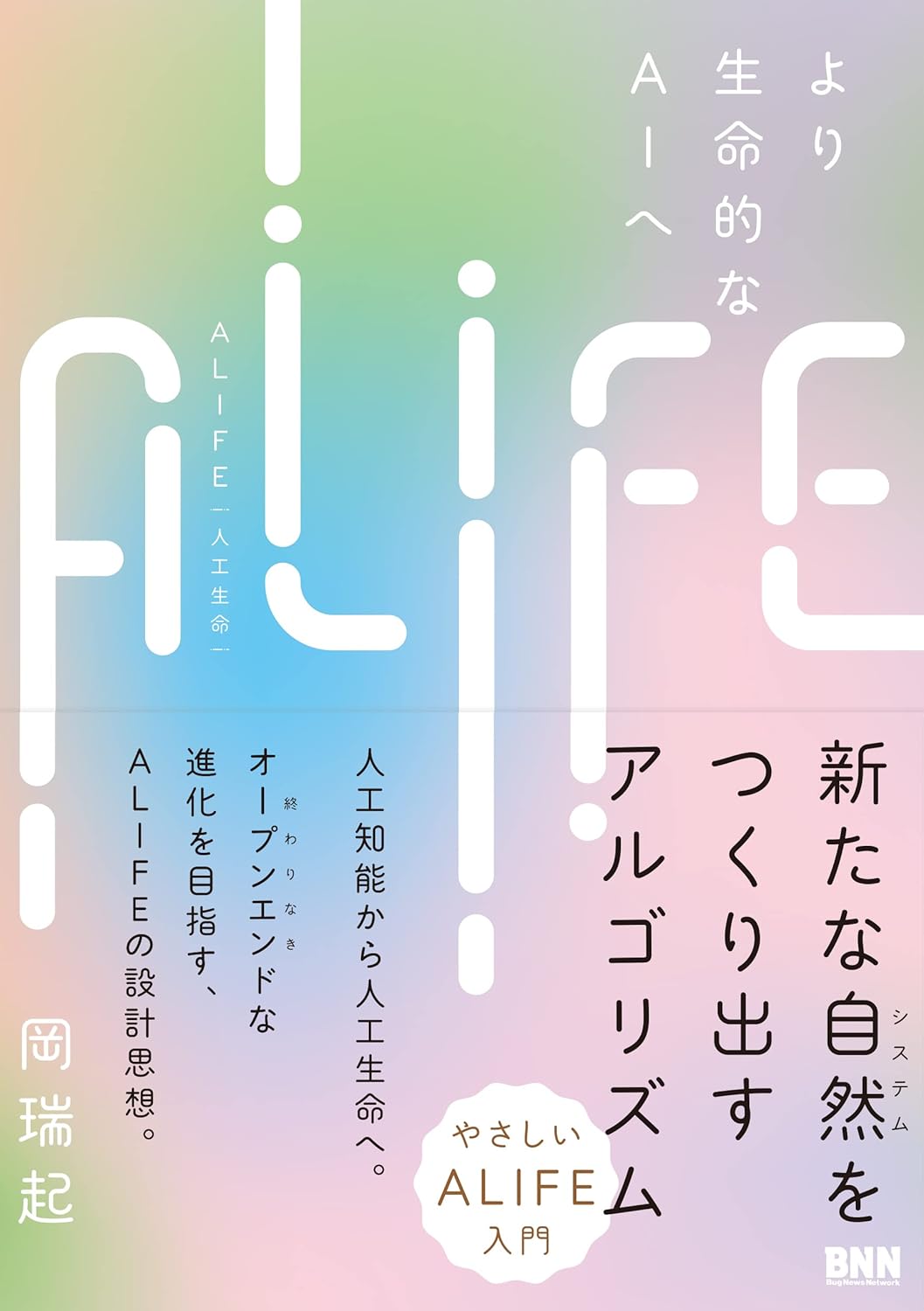
私は大学院時代に分子生物学や免疫学を専攻していたものの、人工生命という研究領域には、これまでほとんど馴染みがなかった。人工知能(AI)という言葉と混同してしまうことも多く、両者は同じ分野の延長線上にあると思い込んでいた。しかし調べていく中で、AIとALIFEは根本的に異なる問いを立てていることが分かった。
主催者の安川さんから
「人工生命は“生命とは何か”を根底から考えさせる、とてもメタな世界です」
と聞き、興味を抱いて参加を決めた。
今回の登壇者は岡瑞起先生。専門は「人工生命」。今回も初対面であったため、事前に著書「ALIFE | 人工生命 ―より生命的なAIへ」を手に取り、基礎的理解を得たうえで臨むことにした。以下では、まず本書のエッセンスを紹介し、その後、当日の講義内容と照らし合わせながら整理していく。
ALIFE | 人工生命 ―より生命的なAIへ(岡瑞起先生の本)
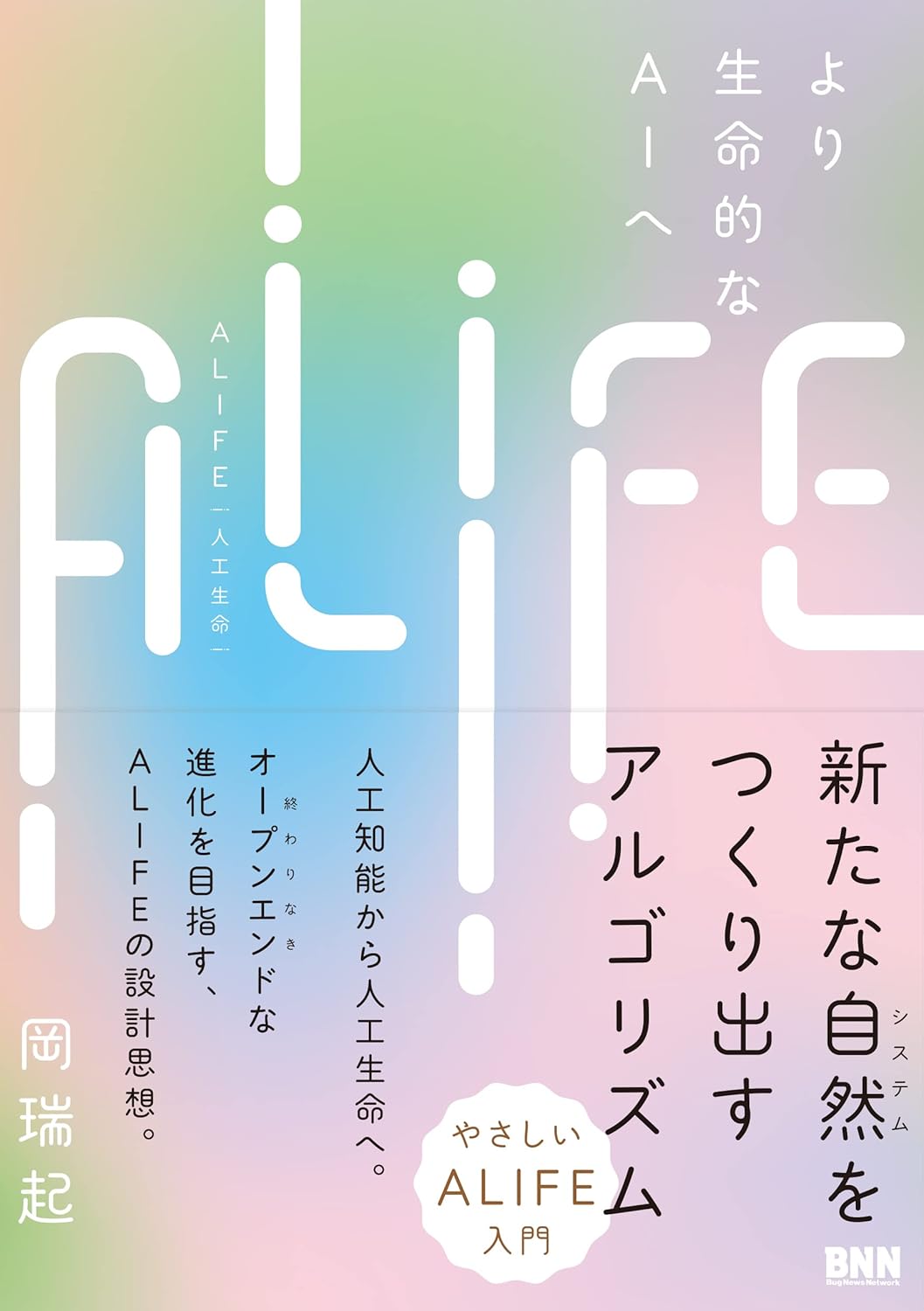
この本で特に印象に残ったのは、人工生命(ALIFE、Artitifical LIFE)と人工知能(AI、Artificial Intelligence)の違いが、技術レベルにとどまらず、思想そのものの違いにまで及んでいるという点である。
AIは「知能とは何か」を理解し、それを人工的に再現しようとする技術・研究であるのに対し、ALIFEは「生命とは何か」を、人工的に構成することで探究しようとする研究とみなして良さそうだ。
両者の定義から、目指している方向性の違いがはっきりと見えてくる。
人工知能と人工生命 ― 定義から見える方向性の違い
人工知能(AI)―最適化を目指す技術
人工知能は、人工的に「人間のような知能」を実現することを目指す分野である。人間の判断・推論・学習能力を計算機で再現し、より効率的に問題を解くことが中心となる。あらかじめ目的が明確に与えられ、その目的に向けて最適な解を探索することが本質である。
人工生命(ALIFE)―生命の本質を構成的に探究する研究
人工生命は、人工的に「生命のような存在」をつくり、生命そのものの本質を理解しようとする研究分野である。ここで扱う生命は、細胞やDNAといった物質的生命に限定されない。
生命が本来持つ性質――境界、代謝、適応、成長、繁殖、進化、生態系――を抽象化し、計算機・ロボット・化学物質など異なる素材から構成的に立ち上げようとする。「構成することで理解する」というアプローチが、人工生命の独自性である。
AIは“最適化(optimization)”を目指し、ALIFEは“終わりなき進化(open-endedness)”を目指す
AIが向かうのは、明確なゴールへ最短距離で到達しようとする「最適化(optimization)」である。チェスや囲碁の勝率を最大化し、画像認識の精度を高める。そこでは学習は解に収束し、タスクが終わればプロセスも完結する。
一方、人工生命が重視するのは、その対極にある「終わりなく続く進化」、すなわち open-endedness である。自然界の生命は常に変化し、絶えず分岐し、新しい形態を生み出してきた。人工生命研究者は、この「終わりのない進化」を人工的なシステム上で再現できるのではないかと考えている。
そこでは、
- 目的があらかじめ決まっていない
- 予測不可能な変化が続く
- 多様性が自発的に生まれる
- 終わりがない
といった性質が重視される。
AIが「賢さ」を極めていく方向に進むと、人間味が薄れ、均質化してしまう可能性がある。それに対しALIFEは、生命らしい「変化し続ける性質そのもの」を価値とするのである。
生物学者と人工生命研究者の違い
生命科学(分子生物学・生化学)は、既存の生命を観察し、物理・化学の法則に基づいて現象を説明する学問である。
細胞を分解(破壊)し、パーツ(分子・原子・量子)に分け、その知見を積み重ねていくことで生命を「理解」しようとする(詳細は「ジェームズ・ワトソン ― 「生命の設計図」を解き明かしたアウトサイダー、その光と影」参照)。
ダーウィンの進化論(詳しくは「チャールズ・ダーウィンの「進化論」——ジェントルマン社会が生み出した成果」参照)やメンデルの遺伝学が確立されるにつれ、生物種に共通する原理を探究する流れが強まる。
生命科学のメインストリームの研究では、大腸菌、ウイルス、ショウジョウバエ、マウス、線虫といったモデル生物を用いて複雑な生命現象を解析する研究手法も発展していく。これらはいずれも、生命現象を機械的かつ再現可能なプロセスとして扱う、還元主義的な科学の流れに位置づけられる。
しかし、その過程では「生命とは何か」という根源的な問いが後回しされるという側面もある。生命のパーツを詳細に理解できても、生命の持つ創発性や多様性、その“らしさ”を完全に説明しきれない場面が依然として残る。
一方で、人工生命(ALIFE)は生命の性質を抽象化し、実際に「構成し直す」ことで生命を理解しようとする学問である。既存の生命体だけでなく、自然界に存在しない生命も対象となり得る点で、生命科学とは研究姿勢が根底から異なることを感じる。
生命科学が「理解するために分解する」学問であるとすれば、人工生命は「理解するために創る」学問である。
人工生命研究者は、生命が備える境界、代謝、適応、成長、繁殖、進化といった性質の根源を、計算機モデル、ロボット、化学システムなど多様な素材を用いて再構成しようと試みる。この構成的アプローチは、生命科学では見落とされがちな「生命の創発性」に新たな光を当てる可能性を持つ。
今回の本や講演を通じて痛感したのは、人工生命は単なる模倣ではなく、「生命そのものを創造する」ことを通して生命の本質に迫ろうとする点にこそ意義があるということである。人工生命の視点は、生命科学に新たな補助線を引き、生命現象をより広い視野で見るきっかけになるのではないかと思う。
人工生命の三つの分野
人工生命は、大きく三つの研究分野に分けられる。
- ソフトな人工生命
コンピュータ上のシミュレーションによって、生命や進化を再現しようとする分野である。進化アルゴリズムやセル・オートマトン、人工生態系などが含まれる。 - ハードな人工生命
生命の性質を持つロボットや物理システムを構築し、現実世界での振る舞いを観察する分野である。 - ウェットな人工生命
化学物質や生体分子から人工細胞をつくり、生命現象を最も物質的なレベルから再構成するアプローチである。
これら三つの領域を横断しながら、生命の持つ「生成し続ける力」を明らかにしようとするのが人工生命と言える。究極の目標は、自然界と同じように「新しい存在が絶えず生まれる」進化そのものを人工的に立ち上げることである。
単なる生物の模倣ではなく、生命の根源的メカニズムを異なる素材で再創造しようとする挑戦であり、AIの「賢さの最適化」とは対照的に、「生命の創発性」を重視する姿勢が印象的であった。
前置きが長くなったが、これらの事前知識をもとに、今回のセミナーの内容について整理していきたい。
「人工的に生命を創造する研究からみる、生命と知性の本質とは」(今回のセミナーの内容)
AIと人工生命──両者を分ける“目的”の違い
まず、AIとALIFEを分ける大きなポイントとして、「目的」の違いが挙げられた。
AIが得意とするのは、与えられた目的や指標に対して、最適な答えを導き出すことである。大規模言語モデルに代表される現在のAIは、膨大なデータをもとに「もっとも適切だと推定される答え」を選び取る。そのため、性能が向上すればするほど「無駄のない、洗練された出力」が生まれていく。
しかし岡先生は、「AIが賢くなり過ぎると人間味を失う」という点を強調していた。最適化とは、本質的に「余白を削っていく営み」であり、揺らぎ、失敗、偶然といった、人間が「生命らしい」と感じる要素が入りにくい。どれほど性能が上がっても、私たちが自然に抱く「あたたかさ」や「生命の気配」は宿りにくいのである。
人工生命(ALIFE)の目指すもの──“終わりなき進化”
これに対し、人工生命が目指しているのは、「完成された状態」に収束するのではなく、変化・進化を続けるシステムをつくることである。
自然界の生命は、40億年もの間、環境と相互作用しながら、驚異的な多様性を生み続けてきた。発見されているだけでも870万種、未分類を含めると3000万種に及ぶとも言われる。そのプロセスは決して最適化ではなく、むしろ偶然、揺らぎ、逸脱、試行錯誤といった「非最適」の積み重ねの先に、多様性が生まれてきたと捉えることができる。
要は、生命は「正しい答え」を求めて進化したのではなく、「新しい可能性」を開き続けた結果として、現在の豊かな多様性が生まれているのである。AIが答えに収束する技術だとすれば、人工生命は「問いを増やし続ける」技術である、と岡先生は述べていた。
なぜ“新しいことをし続けること”が創造性につながるのか――目標からの解放としての open-endedness
ここで印象的であったのは、「なぜ新しいことをし続けることが創造性につながるのか」という問いに対する説明である。岡先生の話を自分なりに整理すると、少なくとも次の三つのポイントがあるように思う。
- 単純な行動から複雑な行動へと進化する
最初は単純な動きや反応しかできないシステムであっても、新しい行動を試み続けることで、徐々にレパートリーが増え、それらが組み合わさることで、より複雑で洗練された振る舞いが生まれる。複雑さは、一足飛びに出現するのではなく、「新しい行動の積み重ね」の結果として現れる。 - 思わぬ行動が目標達成の足掛かりになる
当初の目的から見ると「寄り道」や「無駄」に見える行動が、後になって別の課題を解決する鍵となることがある。生命の歴史を振り返れば、本来別の用途だった構造が新しい機能を獲得している例はたくさんある。新しいことをし続けることで、未来の問題解決のための“足場”が蓄積されていくのである。 - 過去の行動が蓄積され、探索空間が豊かになる
何度も試行錯誤を繰り返すうちに、「試してみた軌跡」そのものがシステムの内部に蓄積される。その履歴があるからこそ、「これまでにない組み合わせ」や「これまでとは違う抜け道」が見えてくる。新しいことをし続けるとは、単に現在を変えるだけでなく、「未来の創造性の土台」を増やし続ける営みでもある。
人工生命の世界には、「Novelty Search(ノヴェルティ・サーチ)」と呼ばれる考え方がある。これは、あらかじめ決められた目標にどれだけ近づいたかではなく、「これまでとどれくらい違うか(どれだけ新しいか)」に報酬を与える探索手法である。
一見すると遠回りに見えるが、「目標」そのものからいったん解放されることで、従来の最適化では決して到達できなかった解や構造にたどり着くことがある。ここには、「目標から自由になることが、むしろ創造性を高める」という逆説がある。
生命の進化もまた、ある種の“自然版 Novelty Search”と捉えることができる。目的に縛られず、新しいことをし続けること。それ自体が、創造性を駆動する最も根源的なメカニズムなのだと感じさせられた。
自然の進化が示す「創造性」と多様性
自然界の生命は、どうしてここまで多様になったのか。単純な最適化だけでは説明できない事実が、そこには存在する。
生命は、
- 自己を維持する仕組み(autopoiesis)
- 身体を通して環境と相互作用する特性(embodiment)
- 終わりのない探索(open-endedness)
の三つを絶え間なく繰り返してきた。その結果として、鳥類の翼、昆虫の複眼、哺乳類の神経系、光合成など、地球上には想像を超える多様な機能と形態が誕生した。進化の本質は、効率性ではなく創造性である。この視点に立つことで、AIとは違う世界の見え方が浮かび上がってくる。
生命性を取り戻す3つのアプローチ──Embodiment/Organic Alignment/Open-mindedness
岡先生は、生命性を取り戻すアプローチとして、
- 身体性(Embodiment)
- 支配ではなく共存するアライメント(Organic Alignment)
- 目的からの解放(Open-endedness)
の三つを紹介し、具体的な事例とともに説明してくれた。
Embodiment(身体性)──知性は身体から生まれる
現在のAIには身体がなく、環境との相互作用から創造性を得る機会が乏しいという指摘がなされた。ここで紹介されたのが、ALTER というアンドロイドの事例である。
ALTERは、人型ロボットの身体と大規模言語モデル(LLM)をカップリングしたシステムである。関節角度や姿勢、カメラ映像といった身体側のセンサ情報がLLMに入力され、LLMからの出力が再び身体の動きとして具現化される。これにより、単なる「文字だけを扱うAI」では見られない振る舞いが現れる。
たとえば、
- 自分の姿をカメラ越しに「見る」ことを前提にしたセルフィー的な動き
- 音楽に合わせて指揮者のように腕を動かす振る舞い
など、環境との相互作用と身体感覚を前提とした表現が生まれるのである。この事例は、「知性は身体と切り離された抽象的計算ではなく、身体と世界との循環の中で立ち上がる」ということを非常に分かりやすく示していた。
Organic Alignment(支配ではなく共存)
AIのアライメントは、これまで「管理・制御(control)」を中心に論じられてきた。しかし生命的知性を扱う際には、その発想では限界があると岡先生は述べていた。
近年の大規模言語モデルでは、“倫理的に見えるように回答を修正する”いわばアライメント偽装(alignment faking)が起きている。これは、人間がトップダウンで押しつける規範を、AIが表面的に模倣しているだけで、内的な動機づけが伴わない状態である。
一方で、人工生命がモデルとする生命の本質は、
- 中心の支配者がいない
- 多数の要素が局所的に反応し合う
- その結果として秩序が生まれる
という点にある。この点を説明するために、岡先生はマーヴィン・ミンスキーの “Society of Mind(心の社会)”の比喩を引用していた。ミンスキーによれば、心は単一のエージェントではなく、「多様な小さなエージェントの協力・競合から立ち上がる」社会である。
人工生命におけるアライメントも同様であり、一方向的な制御ではなく、多様な要素が緩やかに調和し続ける構造が求められる。岡先生は、この関係性のあり方を Organic Alignment(有機的アライメント)と呼んでいた。
それは「管理する/従わせる」モデルではなく、環境・AI・人間の三者が共進化する構造そのものをデザインする発想と言ってよい。ALTERもまた、「ロボットの身体」「環境」「LLM」の三者が相互に影響することで動きを生成する点で、Organic Alignment の具体例である。
Open-endedness(目的からの解放)
AIは「目的がなければ動かない」。一方で生命は、特定の目的に縛られず、逸脱・変異・探索を繰り返しながら進化していく。岡先生は、生命的な知性を人工的に創り出すには、目的そのものから自由になる必要があると述べていた。私たちが生命に「神秘」や「豊かさ」を感じる理由は、まさにこの終わりなき創発性にある。
さらに人工生命の視点を学ぶことで、ダーウィンの進化論そのものへの理解も一段と深まったと感じている。進化はしばしば「最適化」と誤解されるが、生命の多様化は最適化の結果ではなく、偶然・ゆらぎ・逸脱が幾重にも積み重なった「開かれたプロセス」である。自然選択はあらかじめ設定された目的に向かうのではなく、環境との相互作用の中で「たまたま残り得たもの」が次世代へ受け継がれる仕組みである。
ALTERや進化計算の一部では、AIが新たな動きを獲得し続ける仕組みを導入することで、目的ではなく「進化のプロセス」そのものを実現しようとする試みが行われている。Open-endednessは、AIを生命的知性へと変換するための、重要な思想的コアであると感じた。
おわりに──生命と知性の未来に向けて
AIが急速に発展する現代は、私たちに「生命とは何か」「知性とは何か」をあらためて問い直させる時代でもある。
今回の講義を通じ、私は次のように感じた。
生命は、最適化ではなく、創造と関係性のプロセスである。知性は、身体・環境・探究から生まれる。
そしてAIは、生命性を欠いたまま“賢さ”だけを高めても、私たちが本当に求める存在にはならない。
人工生命の研究は、その根本に触れている。AIと人間がどのように共に進化していくのか。その未来を考えるための、重要な視点を与えてくれるものになった。
このような貴重なセミナーを企画いただいた安川さん、運営スタッフの皆様、ありがとうございました!そして、岡先生。素晴らしいプレゼンに感謝しています。