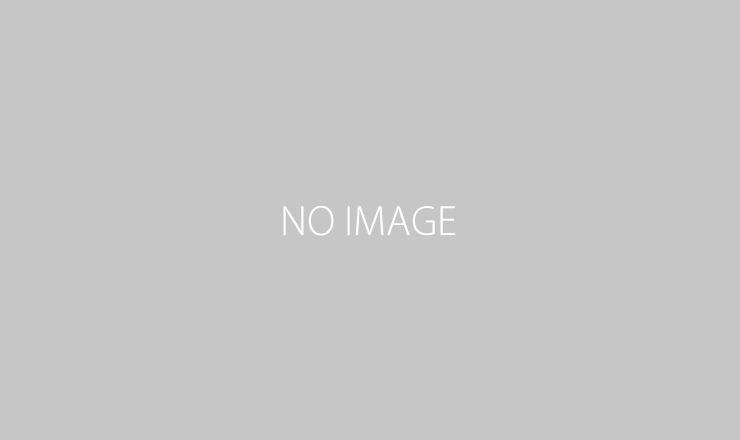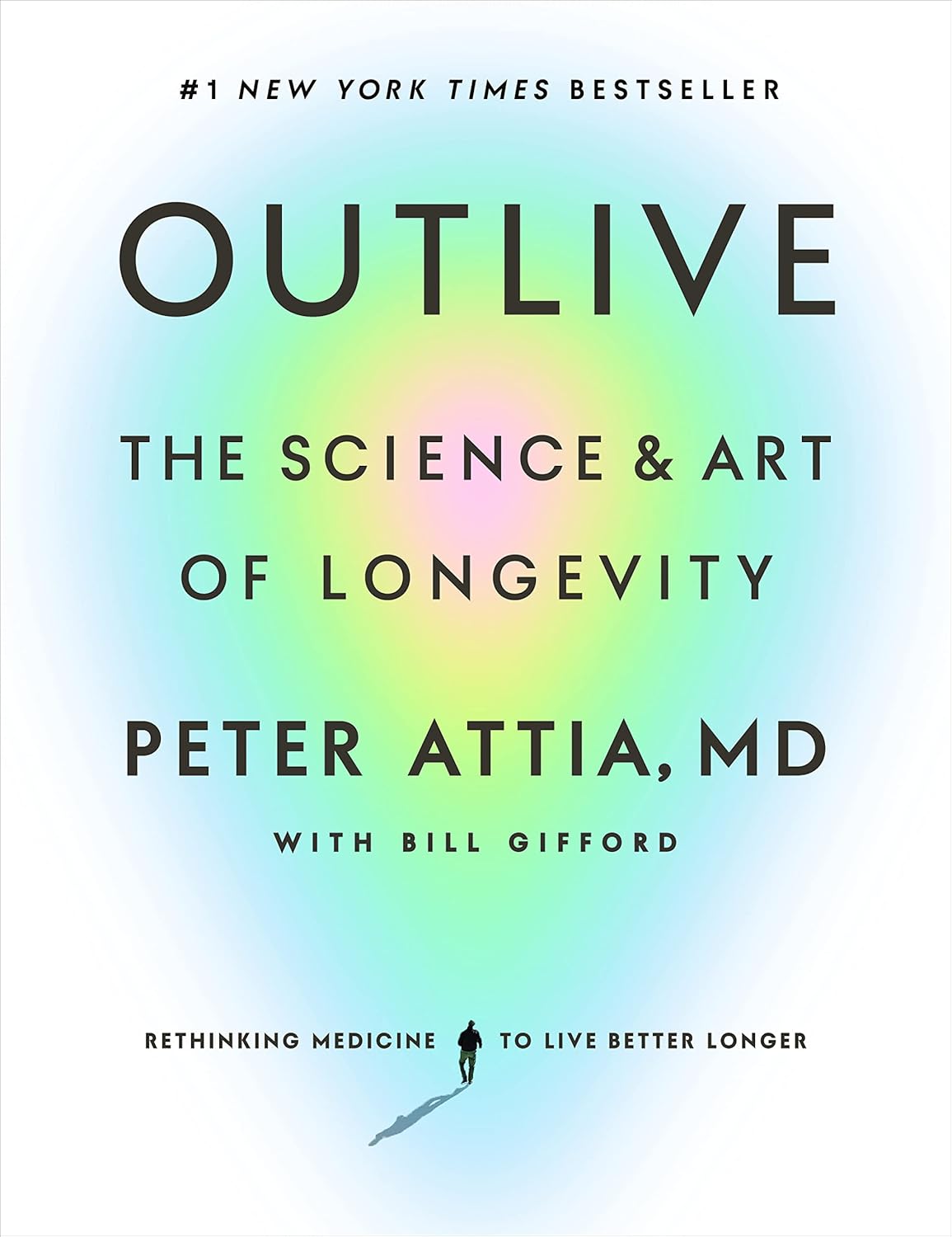【B#229】米国の大学院に見る「研究者を育てる教育」──なぜ日本と米国で大学院の質が違うのか
Table of Contents
はじめに
こんにちは。渋谷でロルフィング・セッションと脳科学をベースにした講座を提供している大塚英文です。
私は、2001年3月に東京大学大学院医学系研究科・免疫学教室で「博士号(PhD)」を取得。日本医科大学で博士研究員を経て、製薬業界へ転身した。「博士号を取得した」と書いても、どういう意味なの?恐らく、ピンとこない方のが多いと思う。
大学院でどのような教育を受けるのか?わかりやすく書かれた本がある。それは、免疫学者で、長年米国でご活躍された石坂公成先生の著書『我々の歩いてきた道ーある免疫学者の回想』だ。
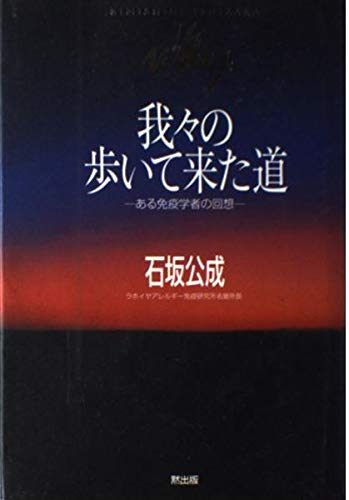
参考に、以前のブログで、2025年のノーベル賞受賞者の坂口志文先生について書いた。その時に、坂口先生の対象となった制御性T細胞は、多田富雄先生の成果であった、サプレッサーT細胞と関係が深かったこと。多田先生の師匠の石坂先生のことに触れた。ぜひ、ご興味のある方は、チェックいただきたい。
今は亡き、石坂公成教授といえば、アレルギー研究の世界的第一人者であり、免疫グロブリンE(IgE)の発見で知られる人物である。彼が1950年代後半から1960年代にかけてジョンス・ホプキンス大学(Johns Hopkins University)で研究・人材育成に努めていた。
今回は、日米の大学院の教育から、研究者というのはどのように育てていくのか?石坂先生の本を通じて、このことについて考えてみたい。
研究者を「作る」教育──米国のPhDコースと補助金
石坂先生は、大学院の教育の目的は、プロの研究者になる学生を教育することであると明確にする。そのための仕組みを本で紹介している。
プロの研究者を育成するプログラムを「PhD(博士号)コース(日本語で言えば博士課程)」と呼び、米国では厚労省にに該当するNIH(米国国立衛生研究所)からの補助金(グラント)によって賄われている。
この補助金には、入学を許された大学院生が大学へ納める月謝、生活費、学会へ参加する旅費まで入っている。それだけではなく、大学院生が受ける授業のための費用、外部の大学から派遣される講師に対する謝礼、雑費も含むという。要は、大学が負担することがない補助金なのだ。
しかしながら、この補助金を取得するためには、このコースを主催する教授、准教授がそれまでどのような教育をしてきたのか?教育した大学院生や博士研究員がどれだけ他の大学の教授や准教授になったか、限られたパイを目指して熾烈な競争の元で、この補助金が与えられるのだ。
ジョンス・ホプキンスの例──大学院生の採用から育成へ
石坂先生がいた頃のジョンスポプキンズ大学の免疫学の大学院生の場合は、毎年20ー30名の応募者の中からPhDコースのための大学院を受ける大学卒業生は、全国一斉の試験を受験。内申書と照らし合わせて10人に絞った上、学生を大学に呼び、3−4名の教授、准教授と1対1のインタビューを受け、討論し、採用を決める。
しかも、PhDコースに入り、授業料が免除になったからって安泰というわけではない。学生は、最初の1年間で、免疫学だけではなく、生化学、分子生物学、細菌学、細胞生物学などの授業を受講する。外部の大学からの支援によって教育を受けることになる。
興味深いのは、
「どういうことがわかっていないのか?」
「自分はどう考えているのか?」
などを議論。知識を教えるよりも考え方を教えることになる。
このコースを終えると、一人の指導教官を選んで、配属先が決まる。そこで学位論文のための実験が始まる。学生の実験は指導教官の研究費から行われるが、学生の給料は政府からの補助金で賄われているので、教育は大変だが、うまくいけば、指導教官の成果になる。
学位取得までの道──どのような審査が待っているのか?
入学してから2年後(日本でいえば修士)には、5ー6人の前で口頭試問を受ける。ここで、この大学院生が博士に進む人材として適切かが試される。試験には免疫以外に生化学や分子生物学の教授も入っていて、様々な分野から、
「自分は何をしているかを知って実験しているのか?」
「このイオン交換樹脂を使うと血漿タンパクを分画できるのか?」
「なぜ蛋白質に等電点があるのか?」
といった根本的な質問が飛び交う。
石坂先生の本には、
「どれをとっても免疫学の教科書には答えは書いていないのだが、プロの研究者は自分が何をやっているかを知って実験をしなければならないというのが、我々のプリンシプルだった」
と書いている。
なぜかというと、サイエンスでは、技術もどんどん進歩し、20年後は誰も使っていないかもしれない。このため、プロの研究者は、誰にも教えられなくても新しい方法の基礎となる理論を理解し、その方法のキーポイントを自分でマスターするスキルが必須。自分が何をやっているのかわからなければ対処できないのだ。
石坂先生が強調していたのは、論文の本数や雑誌の格は博士号を取得する基準ではなく、むしろ「一人前のプロの研究者をつくりのが目的であって、研究を完成させるのは二の次」と考えていたことだ。
日本では学位を取るためには、引用度の高い「ネーチャー」や「サイエンス」のような雑誌に論文を出すことが必要だと言われることが多い。私も東京大学の大学院生だった頃、このような風潮を強く感じた。石坂先生によると、一人前のプロの研究者になってからできることという。
博士の終盤には、数百ページに及ぶ学位論文を自分で書き、指導教官のみならず、3人の教授たちに徹底的に直される。そして、最後に5−6名の教授たちの前で、自分の学位論文の内容を説明し、2−3時間、あらゆる質問が浴びせられ、自分の主張を防衛(学位審査、英語でDegree defence)できれば、学位が与えられるのだ。
石坂先生は本でこう語っている。
「我々が自信を持って世に送り出せる学生にしか、学位は与えなかった。」
この言葉には、教育者としての覚悟がにじんでいる感じがした。形式的な学位ではなく、「研究者を育てること」こそが教育の目的であるという明確な信念があると言っていいと思う。
「寺子屋式教育」──師弟が共に考える場
石坂先生は自身の研究室を「寺子屋式教育」と呼んでいた。石坂先生は、独立した研究者は、4年間の大学院教育と2−3年間のポストドク(博士研究員)としての訓練を経て出来上がる考えていた。
この期間に自分がこれから全力を注いでいく研究課題を見つけ、自分の考えに基づいて研究計画を作り、研究費を申請して一本立ちすることだ。特に、石坂先生は博士研究員の養成に力を注いだ。
学生一人ひとりの実験をすべて把握。日々の進捗を共有しながら同じ問題意識を持って取り組む。独立研究者に必要な自覚を育成するために「研究者としての長所と短所」を知ること。その上で、長所を伸ばす教育を大事にしたという。
大学院から博士研究員までの間の6−7年間。2、3人の異なった指導者と何年か議論をし、指導教官からのアプローチの仕方を知る。日本の場合は、同じ大学院、博士、助手にとどまる事が多いが、米国ではまずそれがない。
石坂先生が指摘するのは、異なる大学や研究所で複数の指導者から学ぶことは、「独立した研究者」を育てる上で不可欠。日本ではそれが制度的にも文化的にも困難であるため、結果として視野の狭い研究者を生みやすいと指摘する。
日本では「若いうちから早く独立させて自分の考えで研究をさせる」事が多いことも指摘。しかし、我々が知っていることは(そして若い人たちが知らないことは)、自分の知識から考えついたことは、必ず他の研究者も気がついている点を知る事が大事だということ。
逆に、研究者として大切になるのは、偶然の発見をものにできることを強調している。そのような発見は期待から外れるもの。自分にとって意外だったことは、他の研究者は気づかない可能性が高いのだ。実験が失敗したとしても、新しい発見につながるかどうか。それにどう対処するか?研究者として最も大事な能力になる。
米国の制度──教育と研究を結ぶ仕組み
米国の大学院教育を支えるのは、理念だけではない。
その背後には、前述のように、NIHが提供する補助金(トレーニング・グラント制度)がある。この制度は、研究成果の即効性よりも、将来の研究者育成を優先する投資である。政治的には人気のない政策でありながら、米国の学界は一貫してこれを守ってきた。石坂先生はこう述べる。
「研究費を受けられるプロジェクトの数を犠牲にしてでも、トレーニング・グラントを維持しようとした。」
つまり、米国では教育と研究が一体化した仕組みが制度的に整っている。研究者を育てること自体が国家的な投資として位置づけられているのだ。
日本の大学院──「研究者を育てる」より「研究を回す」
一方、日本の大学院では、学生が「マンパワー」として扱われがちだと石坂先生は指摘する。
学生はしばしば教授のプロジェクトの一部として動き、研究者としての独立心や探究心を育てる教育的支援が不足している。
さらに深刻なのは、大学間の交流が乏しいことである。他大学に数年研究に出ることはほとんどなく、むしろ「うまくいかなかったのでは」と勘ぐられる風潮すらある。これにより、研究者が多様な指導者に出会う機会が奪われている。
独立とは何か──「早く」ではなく「深く」
石坂先生は、「若いうちに独立せよ」という日本的な風潮にも警鐘を鳴らしている。
米国の博士課程やポスドク制度では、学生は複数の師のもとで長期間訓練を受け、異なる手法や視点を学びながら、自分自身の研究スタイルを確立していく
それに対して日本の若手研究者の中には、「自分のアイデアがあるから」として早々に独立し、結果的に自己流のまま視野を狭めてしまう例があるという。
「どんな学者でも、自分が考えたこともないような問題について適切な助言を受けることがある。勝手なことをしていれば、その機会を失う。」
石坂のこの言葉は、真の独立とは、十分な訓練と対話を経た後に初めて成立するという深い教育哲学を示している。
終わりに──自由のための訓練
ジョンス・ホプキンスでの経験から、石坂公成先生が学んだのは「自由とは、訓練によって初めて獲得される」という真理である。
研究者が自由に発想し、探求するためには、「問いを立てる力」「批判的に考える力」「他者と対話する力」が必要である。それらを支えるのが、厳しくも温かい教育環境である。
日本と米国lの大学院教育の違いは、単なる制度の差ではなく、教育を「人を育てる過程」と見るか、「成果を出す手段」と見るかの哲学の違いと言っても良さそうだ。