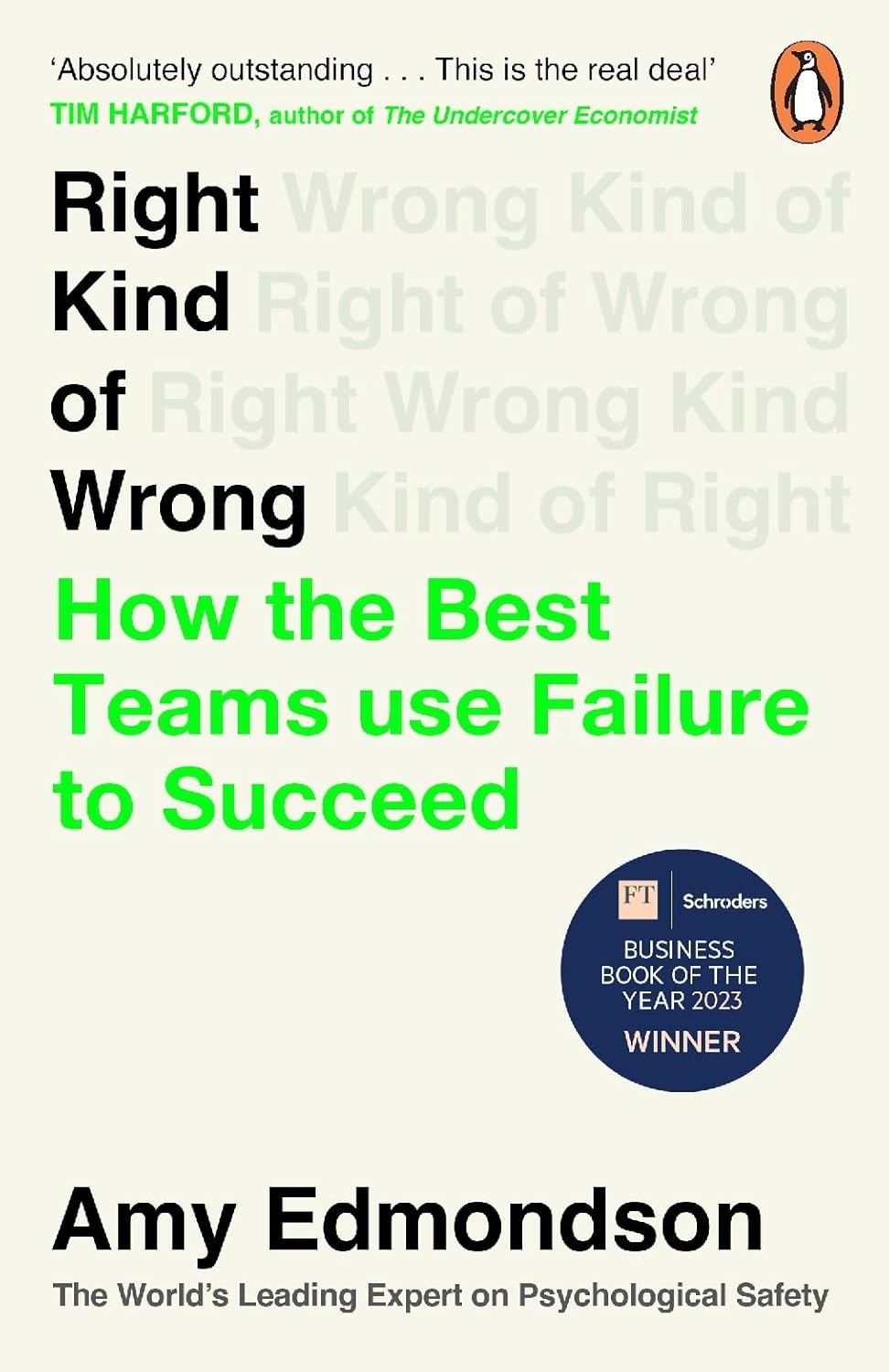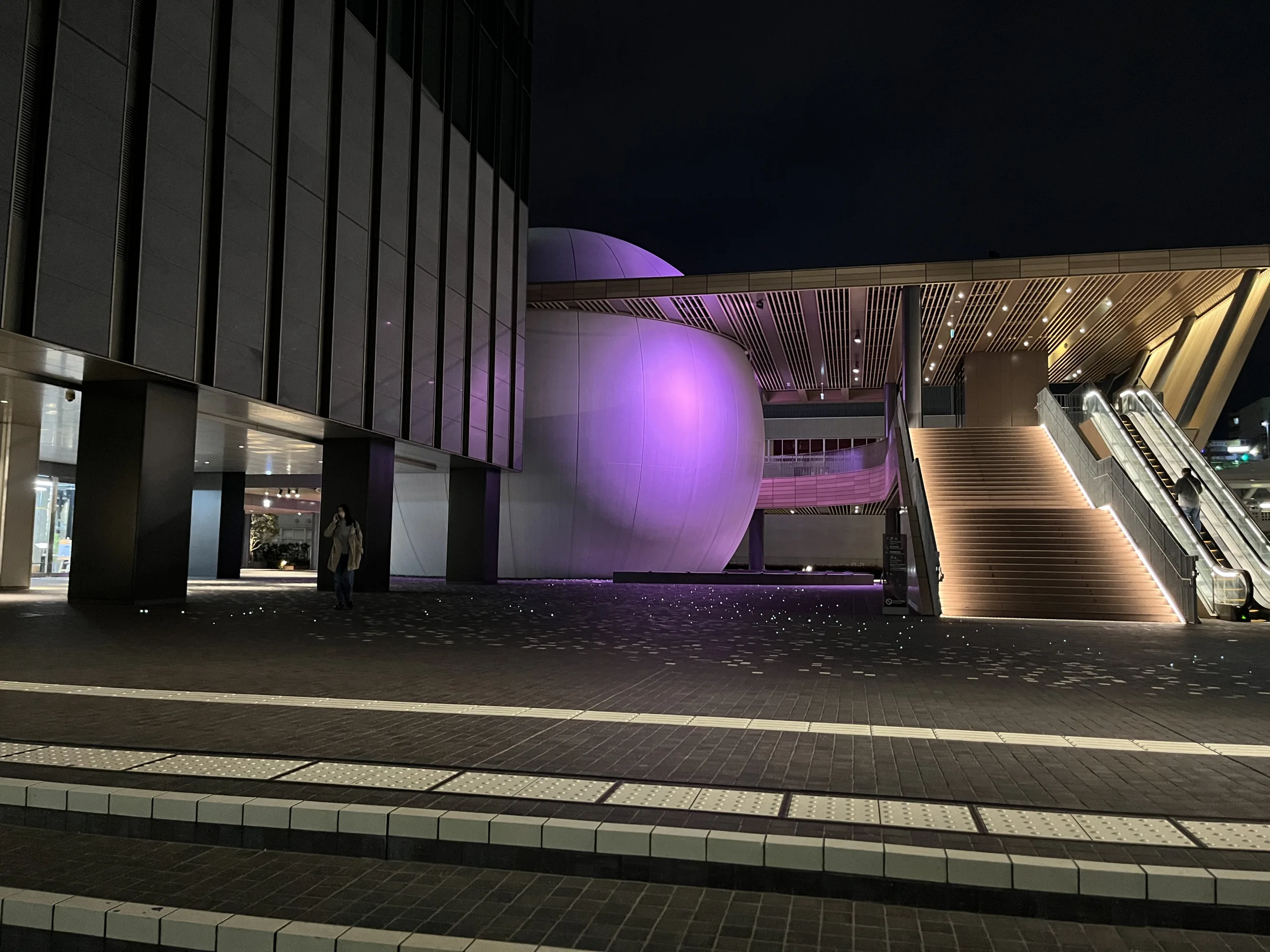【B#213】成人になっても発達できる──「意識の次元」を生きる──キーガンの成人発達理論から学んだこと
Table of Contents
はじめに
こんにちは、渋谷でロルフィングと脳科学ベースの講座・セッションを提供している大塚英文です。
ロバート・キーガンの「成人発達理論」を読んで
今回は、ロバート・キーガン(Robert Kegan)の『ロバート・キーガンの成人発達理論――なぜ私たちは現代社会で「生きづらさ」を抱えているのか(In Over Our Heads)』を読んで、2025年に出会った中で最も面白い本だった。

この本を読んで、最も衝撃的だったのは、大人になってからも脳は発達するという事実があることだ。
発達という言葉は、一般には乳幼児期から思春期にかけて語られることが多い。この本では、大人になってからも認識構造=そのものが変化しうるという視点を提示する。これは、近年注目されている脳の可塑性(neuroplasticity)──脳は一生を通じて変化し続けるという科学的知見とも深くつながっている。
キーガンの本は、以前にも取り上げたが、今回のブログでは、この理論から得た気づきを振り返り、なぜ今、成人の「意識の発達」を真剣に考える必要があるのかを探っていきたい。
なぜ発達理論を学ぶ必要があるのか──性格理論との違いから
現代社会では、性格理論に基づく分類(MBTI、ビッグファイブなど)に触れる機会が多い。これらは「人はどういうタイプか?」を把握する上で有用であるが、そこに「成長」という観点は存在しない。
キーガンはこうした固定的分類(trait-based typology)に対して、人が世界をどう意味づけているか(meaning-making)という枠組みそのものが時間と経験を通して変容するという視座を提供している。
つまり、性格理論が「あなたはどういう人か?」を問うのに対し、発達理論は「あなたは世界をどう構成しているのか? そしてそれは成長可能なのか?」を問うのである。
この違いは、教育、リーダーシップ、コーチング、心理療法など、他者の成長に関わるすべての領域において、根本的な意味を持つ。
構成主義と発達理論の違い──混同されがちな用語の整理
しばしば、「構成主義的発達理論(constructive-developmental theory)」という表現が使われる。これは、キーガンがジャン・ピアジェの流れを汲みつつ、人は世界を構成する存在であり、その構成の仕方が発達していくという考え方を示すものである。
ここで注意すべきは、構成主義(constructivism)自体が静的な世界観を拒否し、すべての認識が主体的に構成されているという前提を持つ点である。発達理論はそこに加えて、その構成の仕方自体が成長段階として変化すると見る。
すなわち、構成主義が「世界は人によって構成される」と述べるのに対し、発達理論は「構成の仕方が発達する」と述べている。この「動的な構成主義」こそが、キーガンの主張する成人発達理論の本質である。
「意識の次元」という発想はどこから来たのか
キーガンは、ピアジェが提示した子どもの認知発達段階を大人にも拡張できるのではないかと考えた。人間はただ経験を積むだけではなく、その経験の意味づけ構造(meaning-making system)自体が変わっていくのではないか。そうした問いから、「意識の次元(Orders of Consciousness)」というモデルが生まれた。
この理論は、自己や世界の捉え方が段階的に発達し、主観(subject)だったものを客体(object)化できるようになることが成長であるという構造で成り立っている。
四次元に到達する人は少ない
重要なのは、この発達が自動的に起こるものではないという点である。キーガンによれば、成人の約60〜70%が三次元(Socialized Mind)に留まり、自己の価値や行動基準を社会や他者の期待に委ねている。
四次元(Self-Authoring Mind)に到達するのは20〜30%程度であり、五次元(Self-Transforming Mind)に至る人はさらに少数である。
私たちは多くの場合、社会の目にどう映るかに影響された自己像の中で生きており、自らの原理で世界を再構成する能力を育むことは容易ではないという現実を突きつけられる。
参考に、キーガンが唱えた意識構造については、下記の表にまとめた。
一次元から五次元までの違い(意識構造の一覧)
| 次元 | 英語表記(Keganの原語) | 概要 | 特徴的な行動・認識 |
|---|---|---|---|
| 一次元 | Impulsive Mind | 衝動的段階 | 快・不快に支配される。衝動のまま反応する |
| 二次元 | Instrumental Mind | 道具的段階 | ルールや交換関係を理解するが、視点は自己中心的 |
| 三次元 | Socialized Mind | 社会的順応段階 | 他者の期待・規範・役割に基づいて自己を形成する |
| 四次元 | Self-Authoring Mind | 自己著者段階 | 自らの原則・信念に基づいて意思決定を行う |
| 五次元 | Self-Transforming Mind | 自己変容段階 | 多様な視点を統合し、自己や枠組みそのものを相対化・再構築する |
【事例】グローリアと3人のセラピスト──三次元から四次元への移行のリアル
1965年に制作された心理学教材「グローリアと3人のセラピスト」では、グローリアという一人の女性が、以下の三人のセラピストと連続してセッションを行う。
- カール・ロジャーズ(Carl Rogers)──来談者中心療法(Person-Centered Therapy)
- フリッツ・パールズ(Fritz Perls)──ゲシュタルト療法(Gestalt Therapy)
- アルバート・エリス(Albert Ellis)──論理情動行動療法(REBT)
この事例は、三次元から四次元への移行プロセスを理解する上で極めて示唆的な内容になっている。
ロジャーズのアプローチ:「共感」の中で生まれる自己基準
ロジャーズは、評価も誘導もせず、徹底して共感的にグローリアの語りを受け止める。「いま・ここ」の感情に焦点を当てながら、グローリアが自らの内的体験を掘り下げていくプロセスを支える。
その背景には、ロジャーズの以下のような言葉がある:
「他者の意見や願望ではなく、自分自身の経験に基づく基準を持てるようになること、自分の世界──価値観が、知覚の対象に内在・付随する世界に──存在する者としてみなすのではなく、経験を評価する者として捉えられるようになること」
これはまさに、三次元の「他者の価値観による自己」から、四次元の「自分自身の経験を基盤にした世界の構成」への移行を語っている。
パールズのアプローチ:「いま・ここ」での責任の獲得
パールズは対照的に、挑発的で厳しいスタンスをとる。グローリアが「娘にどう話せばいいかわからない」と言えば、「娘のせいにするな。お前の問題だ」と即座に返す。
彼の狙いは、「環境に適応して支援を得ようとする戦略」を手放させ、自分の感情・選択・行動の責任を今この場で引き受けさせることである。
その思想は、次のような言葉に凝縮されている:
「周囲の環境を巧みに使って支援を得ようとするのではなく、もっと自分で自分を支援することにエネルギーを使えるようになること」
エリスのアプローチ:「思考の枠組み」にメスを入れる
エリスは、グローリアの思い込みに対して「それは事実か?」「誰がそう決めたのか?」と問い、非合理的な信念を洗い出していく。
とくに、グローリアの「母親として恋愛感情を子どもに語るべきではない」という信念に対して、「それは若い頃に吸収した社会的メッセージを、今も無意識に再生しているだけだ」と指摘する。
彼が意図しているのは、以下のような行動変容である:
「敵対的・絶望的なメッセージ──若い時分に吸収し、自らに教えたのと同じ人生についての考え方、同じ価値観を、今も自らに教え込むがために生じるメッセージ──を自分に送るのをやめること」
主体と客体理論──「私」と「世界」は同時に生まれる
キーガンが示すように、私たちは「すでに存在している世界を、すでに存在している“私”が客観的に見ている」のではない。
むしろ、「私が世界をどう意味づけ、どう見るかという行為を通じて、“私”という主体と、“見られる対象”である世界が同時に立ち現れる」のである。「私が変われば、見える世界も変わる」のであり、見方そのものが変化することで、世界の意味や自分の位置づけが変容していく。
これは、外側の“事実”が変わるということではなく、「意味づけの構造=認識のフレーム」が変化することを意味している。
たとえば、子ども時代には「先生が正しい、親が正しい」という前提で世界を見ていたとしても、大人になるにつれ、「自分の経験に基づいて、何が正しいかを判断する」という視点が育っていく。このとき、「正しいかどうか」という価値だけでなく、「それを誰の視点で見ているのか?」という構造そのものが変わっている。
このように、自分のものの見方がどのように作られているかを意識できるようになること、そしてその構造を選び直す力を持つことこそが、キーガンの言う「成熟した大人」のあり方である。
おわりに──「変わることができる」という希望
キーガンの理論は、「人はどこまで成長できるか?」という問いに構造を与えるだけでなく、「自分の意味づけを変えることができる」という希望を与えてくれる理論である。
三次元にとどまることは悪ではない。だが、自分自身の価値観・原則を持ち、自らの世界を編み直す力を育むことは、混沌とした現代社会においてかけがえのない力となる。
そのプロセスを支えること──それが、教育者・コーチ・セラピスト・ボディワーカーとしての使命であると、改めて思う。