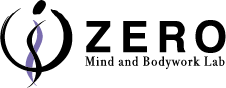【B#252】伊藤憲二『励起』を読んで③──コペンハーゲン研究所という「第三のモデル」
Table of Contents
はじめに
こんにちは!東京・渋谷でロルフィング・セッションと脳科学の基づく講座・タロットカードを使ったカウンセリングを提供している大塚英文です。
「励起──仁科芳雄と日本の現代物理学」との出会い
2025年、量子力学をテーマとした本を読んできたが、中でも、伊藤憲二さんの「励起──仁科芳雄と日本の現代物理学」という素晴らしい本と出会い、年末に1000ページ近くの文量をあっという間に読み終えることができた。

これまで見てきたように、19世紀から20世紀初頭にかけての物理学には、明確に異なる二つの研究文化が存在していた。
伊藤憲二『励起』が非常に面白いのは、この二つを単に比較するだけでなく、その両方を吸収し、まったく新しい研究文化を生み出した場として、各国と比較しながら、コペンハーゲン研究所を描いている点にある。
ボーアとコペンハーゲン研究所
その中心人物が、ニールス・ボーアである。彼が1921年に創設した理論物理学研究所(コペンハーゲン)
(現在のニールス・ボーア研究所)は、20世紀物理学において、他に類を見ない存在となった。ここは単なる研究施設ではない。新しい研究の〈あり方〉そのものを実験する場だった。
英国とドイツ、その「良さ」の統合
ボーア自身の経歴を見ると、コペンハーゲン研究所がなぜ特異な性格を持ったのかがよく分かる。
ボーアは、
- ケンブリッジ大学で
J.J.トムソンのもとに学び、 - その後、ドイツの研究文化とも深く接している
つまり彼は、
- 英国的な個人の思考力を極限まで問う文化
- ドイツ的な研究を共同体として進める制度文化
その両方を、身体感覚として理解していた数少ない物理学者だった。しかし、ボーアはどちらか一方を模倣することはしなかった。彼が選んだのは、言語化すると、両者を意図的に「ゆるめる」ことと言える。
コペンハーゲン精神──緊張ではなく、対話
コペンハーゲン研究所の最大の特徴は、研究所全体に漂っていた独特の雰囲気、いわゆる「コペンハーゲン精神」である。
ここでは、
- 厳密さ
- 権威
- 序列
よりも、
- 対話
- 試行錯誤
- 未完成なアイデア
が重視された。
ボーア自身、議論の途中で話を止め、「それはまだよく分かっていない」と率直に認める人物だった。未完成であることは、恥ではなく、思考が進行中である証拠だった。
研究活動と「遊び」の融合
この研究所を象徴するエピソードとして、著者が強調しているのが、研究と遊びが明確に分離されていなかったという点である。
コペンハーゲン研究所では、
- テニス
- 卓球
- チェス
といったスポーツやゲームが、日常的に楽しまれていた。重要なのは、これが「息抜き」や「余暇」として位置づけられていなかったことだ。
ボーアとその仲間たちは、スポーツやゲームを楽しむのとまったく同じ態度で科学研究を行っていた。勝敗に一喜一憂し、相手の一手を読み、予想外の展開を楽しむ。その姿勢が、そのまま理論物理の議論に持ち込まれていた。
遊びとしての研究、研究としての遊び
ここには、英国型の「過度な緊張」も、ドイツ型の「過度な制度性」もない。
あるのは、
- 自由に発言できる場
- 失敗を許容する空気
- 知的好奇心そのものを楽しむ文化
である。量子力学という、直感に反する理論を扱うためには、正しさよりも、まず試すことが必要だった。コペンハーゲン研究所は、そのための最適な環境だった。
人が集まる理由としての「雰囲気」
この研究所には、世界中から若い才能が集まった。
- ヴェルナー・ハイゼンベルク
- ヴォルフガング・パウリ
- ポール・ディラック
彼らを引き寄せたのは、設備や資金だけではない。「ここにいれば、考え続けられる」という感覚だった。議論は激しく、しばしば堂々巡りになり、結論が出ないことも多かった。それでも、その過程自体が楽しかったという。
量子力学にふさわしい研究文化
古典物理学は、
- 明確な因果
- 再現性
- 安定した概念
を前提としていた。
しかし量子力学は、
- 不確定性
- 相補性
- 観測と理論の不可分性
を扱う。
この新しい物理学には、硬直した制度や過度な競争は向いていなかった。コペンハーゲン研究所は、量子力学という学問にふさわしい柔らかく、遊び心に満ちた研究文化を、結果的に生み出した。
そして、ここに6年間留学した、仁科芳雄先生は、日本の理化学研究所に同じ精神を持ち込むことになる。
「励起」としてのコペンハーゲン
伊藤憲二『励起』というタイトルを、ここほど的確に体現している場所はないかもしれない。
コペンハーゲン研究所では、
- 人が集まり
- 話し
- 遊び
- ぶつかり
- また考える
この循環そのものが、研究所全体を高いエネルギー状態=励起状態に保っていた。
それは、
- 英国のような張り詰めた緊張
- ドイツのような制度的安定
とは異なる、第三の励起モデルと言える。
三つのモデルの対比(整理)
ここで、三つを並べてみると分かりやすい。
- 英国(ケンブリッジ)
→ 緊張によって個人を研ぎ澄ます - ドイツ(研究大学・研究所)
→ 制度によって研究を持続させる - デンマーク(コペンハーゲン)
→ 雰囲気と遊びによって思考を解放する
コペンハーゲンは、英国とドイツの成果を前提にしながら、研究を「楽しい営み」として再定義した場だった。
まとめ──なぜ、量子力学はコペンハーゲンで花開いたのか
量子力学がコペンハーゲンを中心に発展したのは、偶然ではない。
- 未完成な理論を許容する
- 直感に反する議論を楽しむ
- 正解よりも問いを愛する
そうしたボーアの態度が、研究所全体の文化として共有されていた。
伊藤憲二『励起』を通して見えてくるのは、科学の進歩が、人と人との関係性、空気、遊び心によって
いかに左右されるか、という事実である。
コペンハーゲン研究所は、その最も美しい実例の一つだと思う。