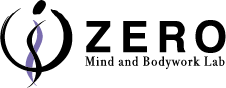【B#250】伊藤憲二『励起』を読んで①──ケンブリッジという「場」は、いかにして物理学者を生んだのか
Table of Contents
はじめに
こんにちは!東京・渋谷でロルフィング・セッションと脳科学の基づく講座・タロットカードを使ったカウンセリングを提供している大塚英文です。
「励起──仁科芳雄と日本の現代物理学」との出会い
2025年、量子力学をテーマとした本を読んできたが、中でも、伊藤憲二さんの「励起──仁科芳雄と日本の現代物理学」という素晴らしい本と出会い、年末に1000ページ近くの文量をあっという間に読み終えることができた。

この本は、日本の物理学のインフラを整えたと言われている仁科芳雄先生の伝記の形態をとっているが、同時に、20世紀物理学を生み出した各国の「知を生産する組織」の比較史が描かれている。
仁科先生が欧州に留学していた時代、物理学はもはや一人の天才が切り拓く学問ではなく、どのような制度・文化・組織のもとで研究が行われているかが決定的に重要になっていた。組織をどのように経営しているのか?について詳細に書かれているのがすごく興味深かった。
とりわけ印象深いのが、英国、特にケンブリッジ大学の物理学文化である。今回は、上記の本を参考に、英国の研究環境について焦点を当ててみたい。
中世大学であり続けたことの意味
ケンブリッジ大学は、中世に起源をもつヨーロッパ最古級の大学である。自然科学研究において、現代に至るまで世界の第一線にあり続けていること自体、すごい驚くべきことだと思う。
その象徴が、アイザック・ニュートンが就いたルーカス教授職である。ニュートン以来、ケンブリッジでは数理物理学の伝統が一つの「正統」として維持。チャールズ・ダーウィンも生み出したことについては、以前ブログで触れた。
19世紀に入ると、工業化と結びついた新しい研究機関や高等教育機関が各地に生まれる。その流れの中で、英国物理学を代表する存在だったケルヴィン卿が、ケンブリッジではなくグラスゴー大学を選択し、教えていたことは象徴となる。
つまり、理論を重視していたケンブリッジは、産業との結びつきという点では、新しい潮流に乗り遅れてしまったのだ。しかし、その代わりに極端なまでに純化された学問文化を守り続けた。
数学トライボスという「異様な装置」
19世紀ケンブリッジの物理学を理解する鍵は、数学トライボスにある。
これは単なる数学試験ではない。ニュートン力学に基づく天文学的問題など、数理物理学そのものが問われる過酷な試験であった。
この制度を精神的に支えたのが、「サイエンティスト」という言葉を作ったウィリアム・ヒューウェルである。
彼は「帰納的科学」を標榜しながらも、若い学生にとって最重要なのは演繹的思考力だと考え、数学教育を徹底した。
数学トライボスで上位に入ること、特に第一位に与えられる称号である「シニア・ラングラー」になることは社会的名誉だった。成績は新聞に掲載され、その後の人生を大きく左右したという。結果として、専攻を問わず、ケンブリッジの学生は数学に没頭していく。
チューター文化と「鍛えられた知性」
数学トライボス対策のため、専門の家庭教師(チューター)が現れた。中でも有名なのが、エドワード・ラウスである。
ラウスは問題を与え、答案を添削するという訓練を通じて、多くのラングラーを育てた。実は、同じ年に卒業したジェームズ・クラーク・マックスウェルを抑えて、彼自身がシニア・ラングラーになったことはよく知られている。
この制度は、「試験成績は訓練で作れてしまう」という意味で、教育評価としては破綻していた。実際、シニア・ラングラーが必ずしも優れた研究者になるわけではなかった。しかし結果として生まれた人材は、高度に洗練された数学と、長大で複雑な計算を厭わない知性を備えていた。
マックスウェルの『電気磁気論』が難解であるのは、このような環境で読まれることを前提に書かれていたからである。
理論偏重の限界と、キャベンディッシュ研究所
一方で、数学偏重は明確な弊害も生んだ。実験や工学との結びつきが弱まり、電磁気現象の研究では、工学と密接に結びついたドイツや他地域に遅れを取る。
この問題に対するケンブリッジの回答が、キャベンディッシュ研究所である。
キャベンディッシュ研究所は、19世紀後半、教育用実験室として構想され、学長(名誉職)であったウィリアム・キャヴェンディッシュの寄付によって設立された。初代所長にはマックスウェルが就任し、実験と理論を再び結びつける拠点が誕生する。
余談になるが、分子生物学の誕生のきっかけとなったDNA二重らせん構造の解明も、キャベンディッシュ研究所で生み出された。
トムソン、そしてラザフォードへ
キャベンディッシュ研究所を決定的に飛躍させたのが、第三代所長のJ・J・トムソンである。
彼は数学トライボスで鍛えられながら、オーウェンズ・カレッジでの教育を通じて、実験にも理解を持っていた。
さらに重要なのは、卒業生以外にも研究の門戸を開き、若い才能を集めたことである。
その最大の成果が、ニュージーランド出身のアーネスト・ラザフォードであった。電波検出器を発明していた彼は、キャベンディッシュで研究生となり、のちに原子核物理学を切り拓く。
「励起」とは、場が人を生む状態である
伊藤憲二が『励起』で描いているのは、マックスウェル、トムソン、ラザフォードといった個人の成功譚ではない。
・数学トライボスという極端な評価制度
・チューター文化による徹底した訓練
・理論偏重の反省としての実験拠点の再構築
・外部人材を受け入れる組織運営
こうした要素が重なり合い、ケンブリッジという場そのものが“励起状態”にあった。
その張り詰めた状態から、次の物理学が生まれていった。『励起』という題名は、物理用語であると同時に、
知を生む組織の状態を正確に言い当てた比喩なのだと、強く感じた。
まとめ
今回は、英国、特にケンブリッジ大学の物理学文化を中心に、「知を生産する組織」についてまとめさせていただいた。次回は、同じ視点からドイツの研究大学・研究所モデルについて取り上げたい。