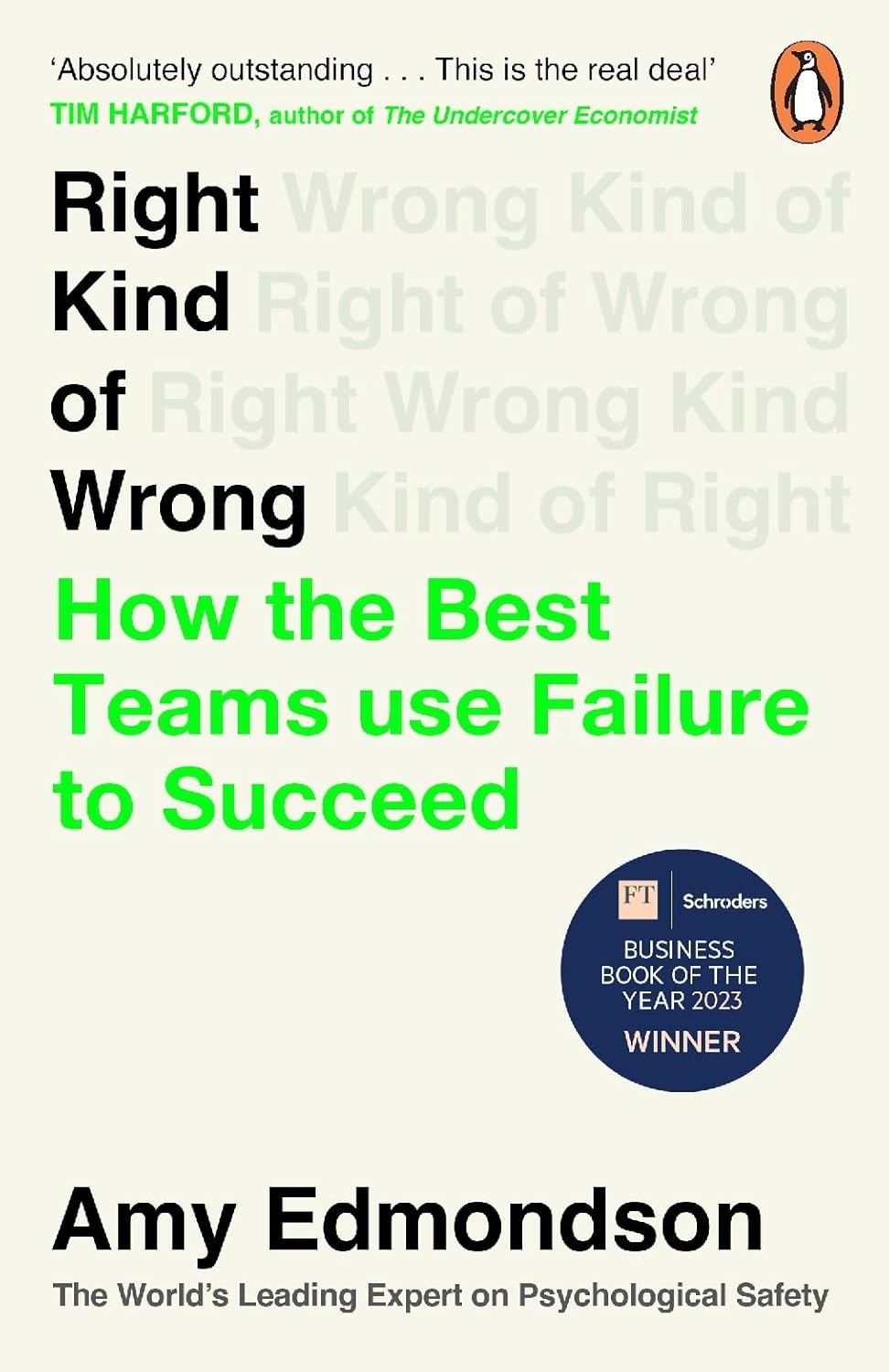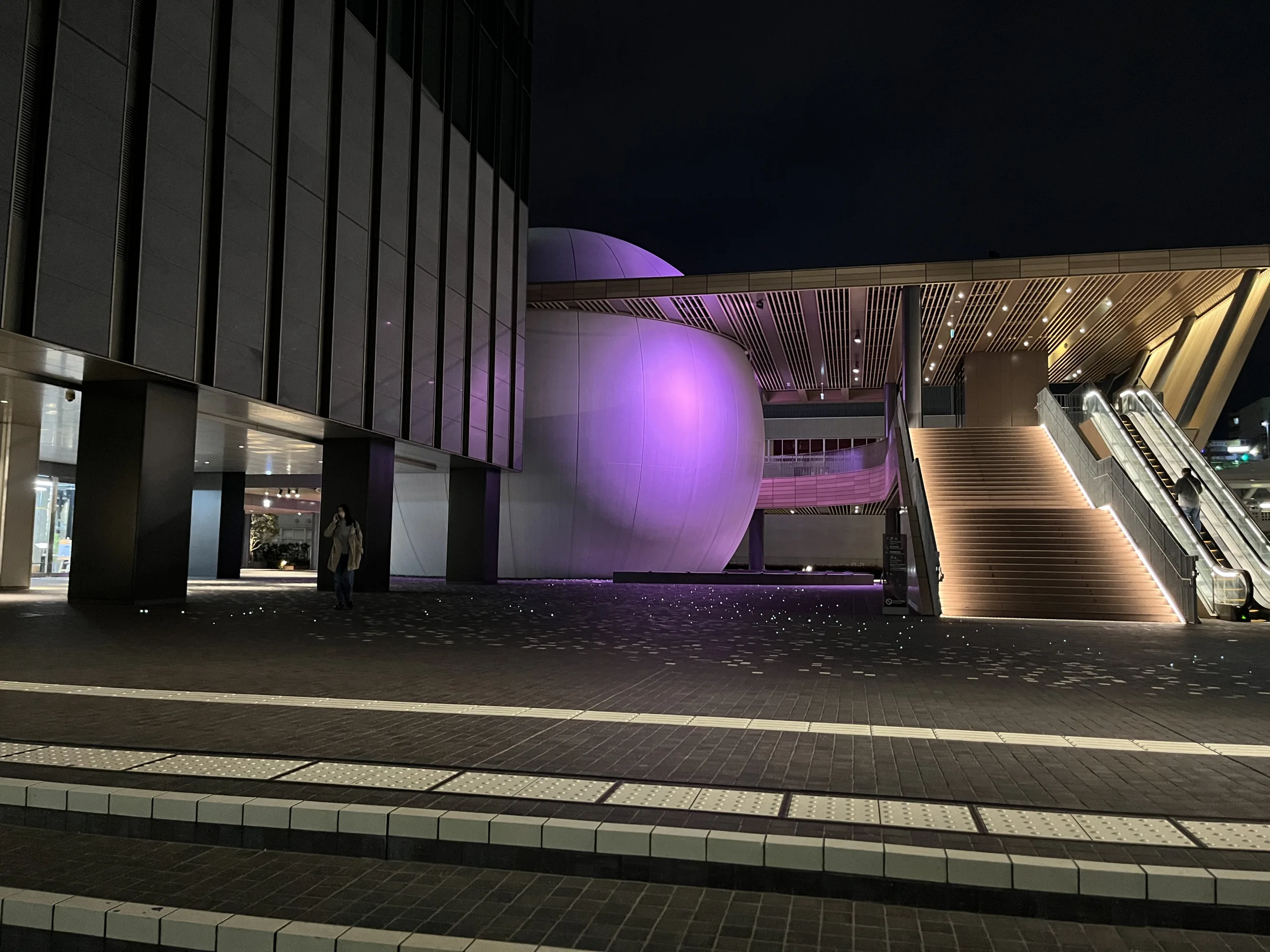【B#234】「隠れた潜在力」をどう引き出すか —— アダム・グラント『Hidden Potential』を読んで
Table of Contents
はじめに
こんにちは。渋谷でロルフィング・セッションと脳科学をベースにした講座を行っている大塚英文です。
今回は、組織心理学者アダム・グラント(Adam Grant)のHidden Potential: The Science of Achieving Greater Things(2023年)を紹介したいと思う。
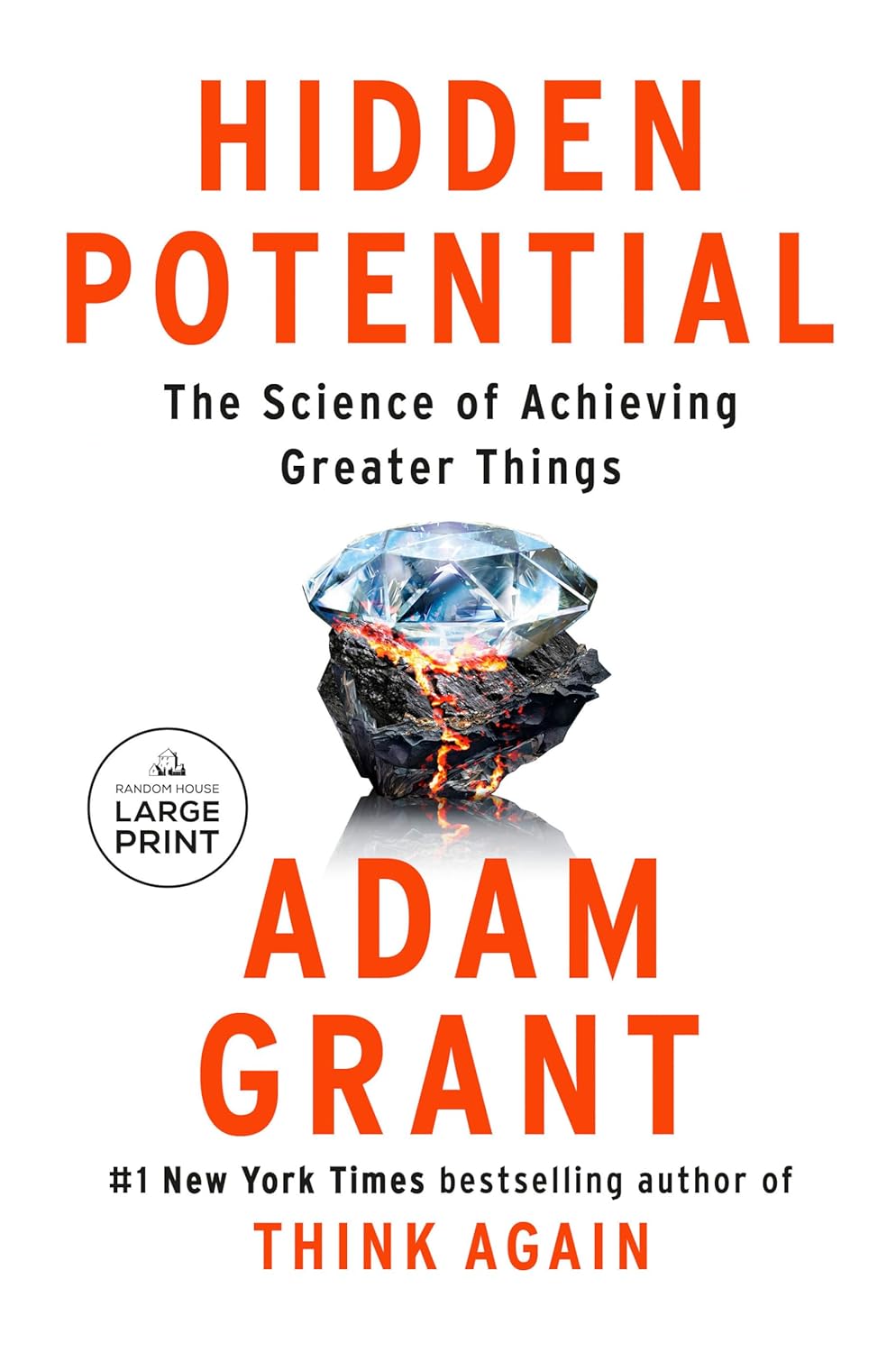
この本は、才能よりも「学び方」「成長のデザイン」「機会の構造」が人を変えるというテーマを掘り下げている。コーチングや脳科学の講座(脳活講座)を通して「人はどのように変わるのか」を見つめてきた私にとって、本書の内容は非常に共鳴するものであった。
潜在力とは「どこまで登ったか」で測られる
グラントは本書の冒頭でこう語る。
“The true measure of your potential is not the height of the peak you’ve reached, but how far you’ve climbed to get there.”
「真の潜在力とは、到達した山の高さではなく、そこまで登ってきた距離で測られる。」
多くの人が「才能」や「生まれつきの能力」で自分を評価しようとする。グラントは、それを真っ向から否定する。重要なのは、どこから始めたかではなく、どこまで登ったかである。
コーチングの現場でも同様である。
セッションの初期段階でクライアントが「私は自信がない」「もう遅いかもしれない」と語ることがある。そのとき、コーチが焦点を当てるのは“ゴール”ではなく、“変化のプロセス”である。つまり、成長の距離を意識化することが潜在力を引き出す鍵である。
成長は「快適ゾーンの外」で起こる
グラントは、人間の成長が生じる場所を“Learning Zone”と呼んでいる。
“Growth depends less on your innate talent and more on your willingness to venture into discomfort.”
「成長は、生まれつきの才能よりも、不快な領域に踏み出す意志にかかっている。」
学びとは、安心できる「快適ゾーン(Comfort Zone)」では起こらない。
少しだけ不安や不確実性を感じる領域——“やや不快なゾーン”——に身を置くとき、脳は最も活性化する。
これは神経科学でいう可塑性(neuroplasticity)にも通じる概念である。
脳活講座では、あえて「答えが一つではない問い」を提示することがある。
たとえば、「あなたにとって“よく生きる”とは何か?」という問い。
即答できないこの種の問いは、前頭前皮質と島皮質を活性化し、自己認識を深める働きを持つ。
つまり、不確かさを受け入れることが、脳の成長の条件なのである。
「キャラクター」が能力を支える
本書の中核をなす概念のひとつが、“Character Skills”である。
“Character skills are not about being the best student—they’re about being the best learner.”
「キャラクター・スキルとは、最も優れた生徒になることではなく、最も優れた学習者になることである。」
キャラクターとは、誠実さ、共感力、継続力、柔軟性、そして失敗から学ぶ姿勢などの総体である。
これらは認知能力(IQ)や専門スキル(Hard Skills)とは異なり、「変化を支える人間的な筋力」といえる。
コーチングでは、このキャラクター・スキルを育むことが本質である。
たとえば、クライアントが課題をうまく進められないとき、コーチは「何が足りないか」ではなく、「どんな在り方で向き合っているか」に焦点を当てる。
それがBeing(あり方)であり、Doing(やり方)を方向づける基盤となる。
脳活講座でも、自己理解を深めるために「自分がうまくいかなかった経験」をリフレクションする時間を設けている。
その際に重要なのは、「なぜ失敗したのか」ではなく、「どのように回復したか」を言語化することである。
これはまさに、キャラクター・スキルを可視化するトレーニングである。
潜在力を開く「環境のデザイン」
グラントはこう述べている。
“Potential is not a fixed property of individuals—it’s a reflection of the systems that support them.”
「潜在力は個人の中に固定された性質ではなく、それを支えるシステムの反映である。」
人の可能性は、本人の努力だけでなく、「どんな環境で」「どんな文化に支えられているか」によって決まる。
たとえば、コーチングでは「心理的安全性」が重要である。
クライアントが安心して弱さを出せる場があることで、初めて新しい行動実験が可能になる。
これは企業チームにも同じことが言える。
リーダーがミスを許容し、フィードバックを歓迎する文化をつくることで、組織全体が“学習するシステム”へと変化する。
脳活講座でも、環境設計を重視している。
講義後には「話す時間」「振り返る時間」「他者の意見を聴く時間」を設けることで、脳が情報を再統合する仕組みを意識的に作っている。
それは単なる知識伝達ではなく、**学びを支える“場の神経系”**のようなものである。
成長を促す5つの実践アプローチ
本書には実践的な原則がいくつも示されている。その中で、コーチングや脳活講座に直結する5つを挙げたい。
(1)Failure Budget:失敗の「予算」を設ける
“When we treat mistakes as experiments, we give ourselves permission to grow.”
「ミスを実験として扱うとき、私たちは自分に成長する許可を与える。」
クライアントが新しい行動を取るとき、「失敗してはいけない」という無意識のブレーキがかかる。
それを外すために、コーチは「今月は3回まで失敗OK」という“失敗予算”を一緒に設定することがある。
この単純な仕組みが、行動変化を生む。
(2)Learning Zone:快適さの外で学ぶ
成長は“安全かつ挑戦的な領域”において起こる。
脳活講座でも、毎回のセッションに「少し難しいテーマ」を一つ設けている。
参加者の島皮質が「やや不快」を感じるその瞬間こそ、神経系が新しい回路を作り始めている。
(3)Learning by Teaching:教えることで学ぶ
“Teaching others is the best way to learn yourself.”
「他者を教えることは、自ら学ぶ最良の方法である。」
講座後半では、参加者が互いに内容を教え合う時間を設けている。「学びを言葉にする」ことで、前頭前皮質が情報を再構築し、理解が深まる。
(4)Progress Visibility:成長を可視化する
人間の脳は、進歩を実感すると報酬系が活性化する。脳活講座では、各セッションの最後に気づきをシェアいただく。自己効力感を高めるこの仕組みが、学びの持続性を支えている。
(5)Growth Network:成長を支える仲間を持つ
“No one develops in isolation.”
「誰も孤立したままでは成長できない。」
グラントが強調するのは、個人の努力よりも「学びのネットワーク」である。コーチングでは、クライアントが“支援的ネットワーク”を築くことを重視する。講座でも、参加者同士が互いの成長を支援し合うコミュニティを育てる。
社会的視点と今後の課題
“We can’t all have equal talent, but we can ensure equal opportunity for growth.”
「すべての人が同じ才能を持つことはできないが、成長の機会を平等にすることはできる。」
本書は、才能主義から学習主義への転換を提案している。それは、教育・企業・家庭すべてに関わるテーマである。
脳活講座でも「誰でも脳を育て直せる」「可塑性は生涯続く」というメッセージを伝えている。この視点を社会に広げることが、次の時代の教育とコーチングの使命である。
まとめ —— 潜在力とは「築くもの」である
“Potential is not something you find—it’s something you build.”
「潜在力とは見つけるものではなく、築くものである。」
才能は天から与えられるものではない。それは、学び、挑戦し、失敗し、そして立ち上がるプロセスの中で築かれる。コーチングも脳活講座も、その“築く力”を支援するために存在している。
学びとは、外から情報を得ることではなく、内側にある潜在力が自らの形を見出す過程である。そしてその過程に必要なのは、「安全に挑戦できる環境」と「成長を信じる関係性」である。
私はこれからも、ロルフィング、コーチング、脳科学の三つの視点を融合し、人が“どれだけ登ったか”を共に見届ける場をつくり続けたいと考えている。