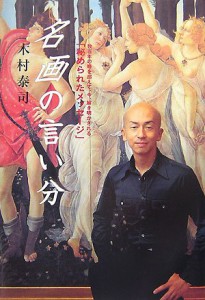【B#219】「脳は変わりうる」──神経可塑性について科学的にわかっていることの紹介
Table of Contents
はじめに
こんにちは、渋谷でロルフィング・セッションや脳科学をベースにした講座・コーチングを提供している大塚英文です。
Norman Doidgeの The Brain That Changes Itself (邦訳:脳は奇跡を起こす)は、神経科学における「脳は固定的である」という長年のドグマを覆し、神経可塑性(neuroplasticity)というパラダイムを一般読者にも伝えた画期的な本である。
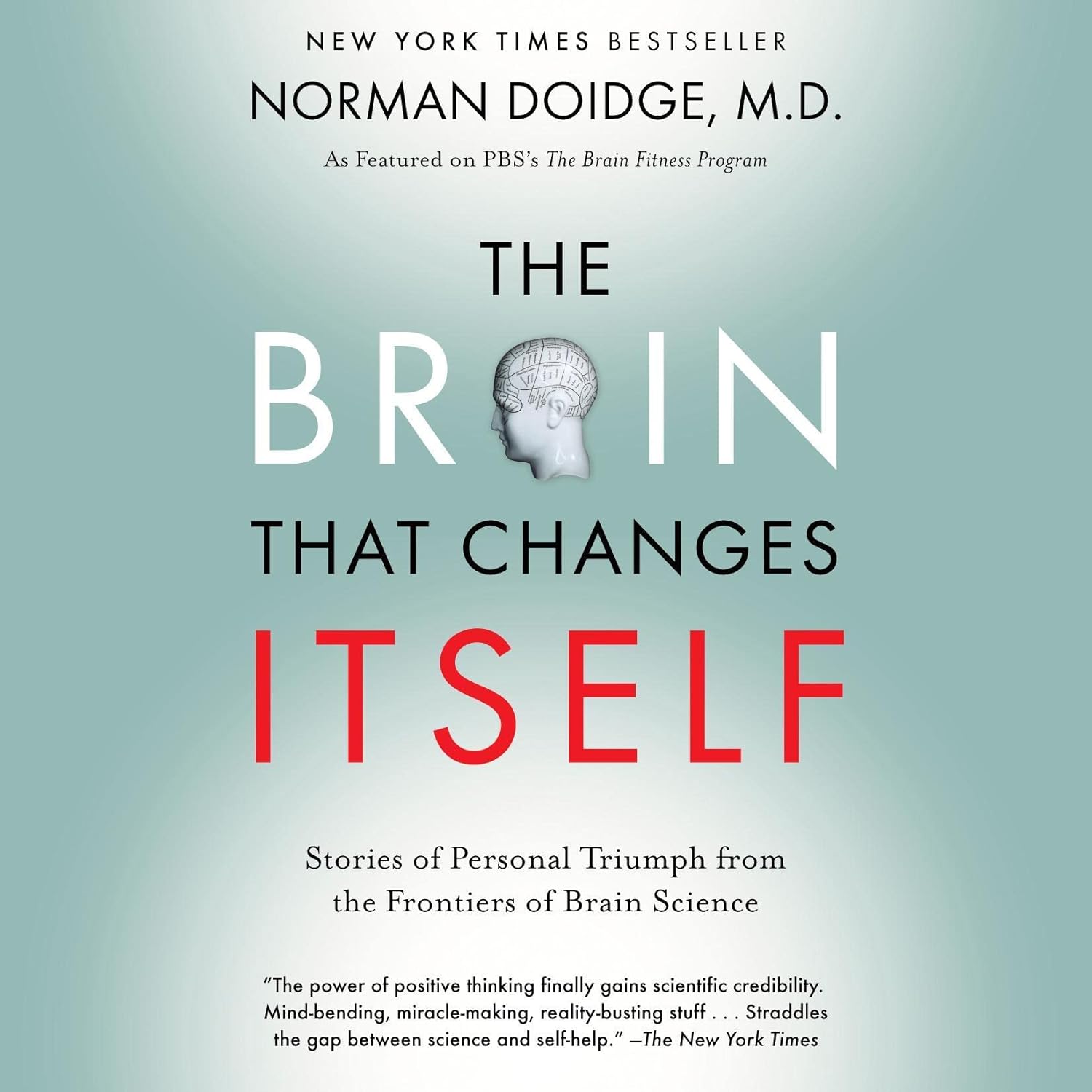
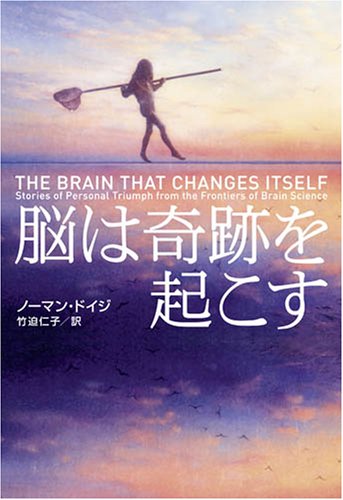
2014年、ロルフィングの基礎トレーニングを受けていたときに、推奨図書に指定されており、手に取った。この本では、臨床医や研究者の奮闘の物語が織り込まれ、脳が生涯を通じて学習・再編成する事実を浮き彫りにしている。
今回のブログでは、「脳の可塑性」という概念はどのように発見され、どのように臨床や教育の現場に結びついていったのだろうか。以下では、その歴史的系譜と主要な研究者たちの成果をたどりながら、Doidgeの描いた「変わりうる脳」の姿を整理してみたい。
脳の可塑性がどのような歴史を辿ったのか?──不変から可塑へ
19世紀末から20世紀半ばにかけて、脳は「完成したら変わらない器官」と考えられていた。だが、その見方を揺るがす思想や証拠は早くから現れていた。
William James(1890年)
哲学者で心理学者のWilliam Jamesは『心理学原理(Principles of Psychology)』の中でこう予見した:
“Organic matter, especially nervous tissue, seems endowed with a very extraordinary degree of plasticity.”
(有機的な物質、特に神経組織は、非常に並外れた可塑性を持っているように見える。)
これは、当時の脳科学においては異端の意見であったが、後に神経可塑性研究の先駆的な洞察と評価されることになる。
Donald Hebb(1949年)
カナダの心理学者Donald Hebbは『The Organization of Behavior』において有名な法則を示した:
“Cells that fire together, wire together.”
(一緒に発火する細胞は結びつく。)
これは今日「Hebbian learning」と呼ばれ、シナプス可塑性の理論的基盤となっている。ニューロンの繰り返し活動が結合を強め、学習や記憶の形成につながるという考えは、その後の神経可塑性研究に不可欠な理論枠組みを提供した。
Paul Bach-y-Rita(1960年代)
アメリカの神経科学者Paul Bach-y-Ritaは、父親の脳卒中後のリハビリ経験から「脳は機能を再配分できるはずだ」と直感した。彼は1960年代に視覚代行装置(sensory substitution device)を開発。盲人が舌や皮膚に与えられた触覚刺激を「視覚」として体験できることを示した。
Bach-y-Ritaはこう述べている:
“We don’t see with our eyes, we see with our brains.”
(私たちは目で見るのではなく、脳で見ているのだ。)
この装置は、感覚入力が失われても脳が他の経路を使って世界を知覚し直す能力を持つことを示し、神経可塑性研究における歴史的転換点となった。
その後、Merzenich、Schwartz、Ramachandranらの実証研究が積み重なることで、脳の可塑性についての科学的な知見が深まっていく。
Doidgeは、3名の成果をわかりやすく紹介しているので、以下まとめたい。
Michael Merzenich──脳地図研究とリハビリへの応用
研究の動機
Merzenichが脳の可塑性に関心を持ったのは、リハビリや教育に役立つ方法を科学的に探求したいという動機からであった。彼は臨床現場で「脳損傷を受けた患者がどのように回復していくのか」に疑問を抱き、「脳がどのように自己修復するのか」を明らかにすることこそ医学的に重要だと考えた。
その背景には、彼自身が取り組んでいた人工内耳の開発もある。人工内耳は機械的に音を入力する装置だが、それを「意味のある言葉」として解釈できるかは脳次第である。つまり「脳が新しい入力を学習できるか」が臨床応用の成否を決める──そこに彼の研究動機があった。
皮質マップの再編成
Merzenichは動物実験で、特定の指や感覚領域を繰り返し使うと、その部分に対応する脳の皮質地図が拡大することを示した。逆に、使用しない領域は縮小する。この「use it or lose it(使わなければ失われる)」原理は、リハビリや学習理論の基盤となった。
Doidgeはこう書いている:
“Merzenich proved that the brain’s maps are not fixed, but can be redrawn by practice, repetition, and experience.”
(Merzenichは、脳のマップが固定されたものではなく、練習・反復・経験によって描き直されることを証明した。)
この知見は、失語症の回復訓練や、学習障害に対するトレーニング法の開発へとつながっていく。
Jeffrey Schwartzと「Brain Lock」──意識が脳を再配線する
OCD治療と4ステップ法
Jeffrey Schwartzが対象とした、強迫性障害(OCD、Obsessive-Compulsive Disorder)は、不要な思考や衝動が繰り返し侵入し、患者を苦しめる病である。かつては「脳の異常だから薬物治療しかない」と考えられていたが、Schwartzは、意識的な注意の訓練が脳を再配線できることを示した。
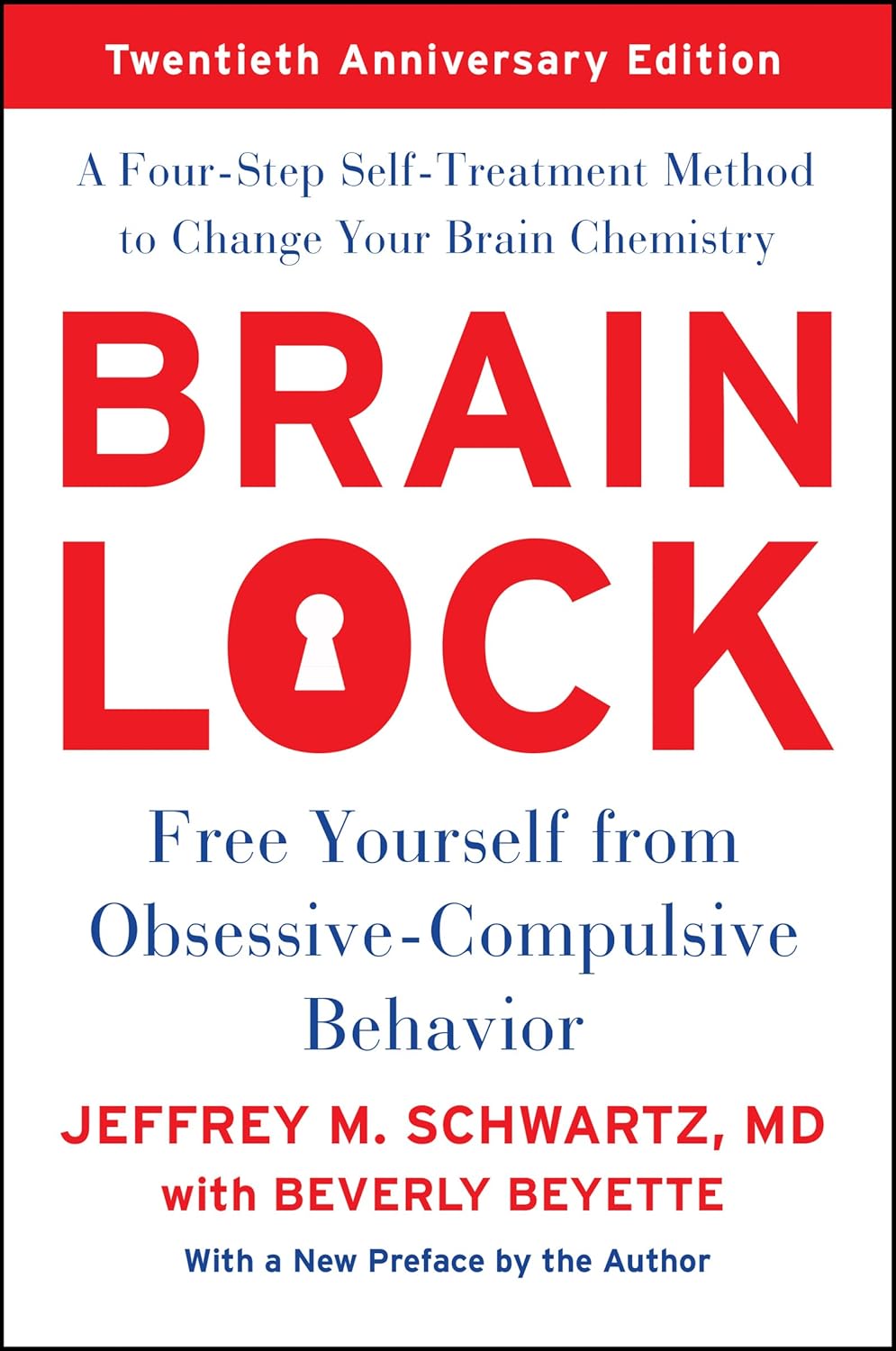
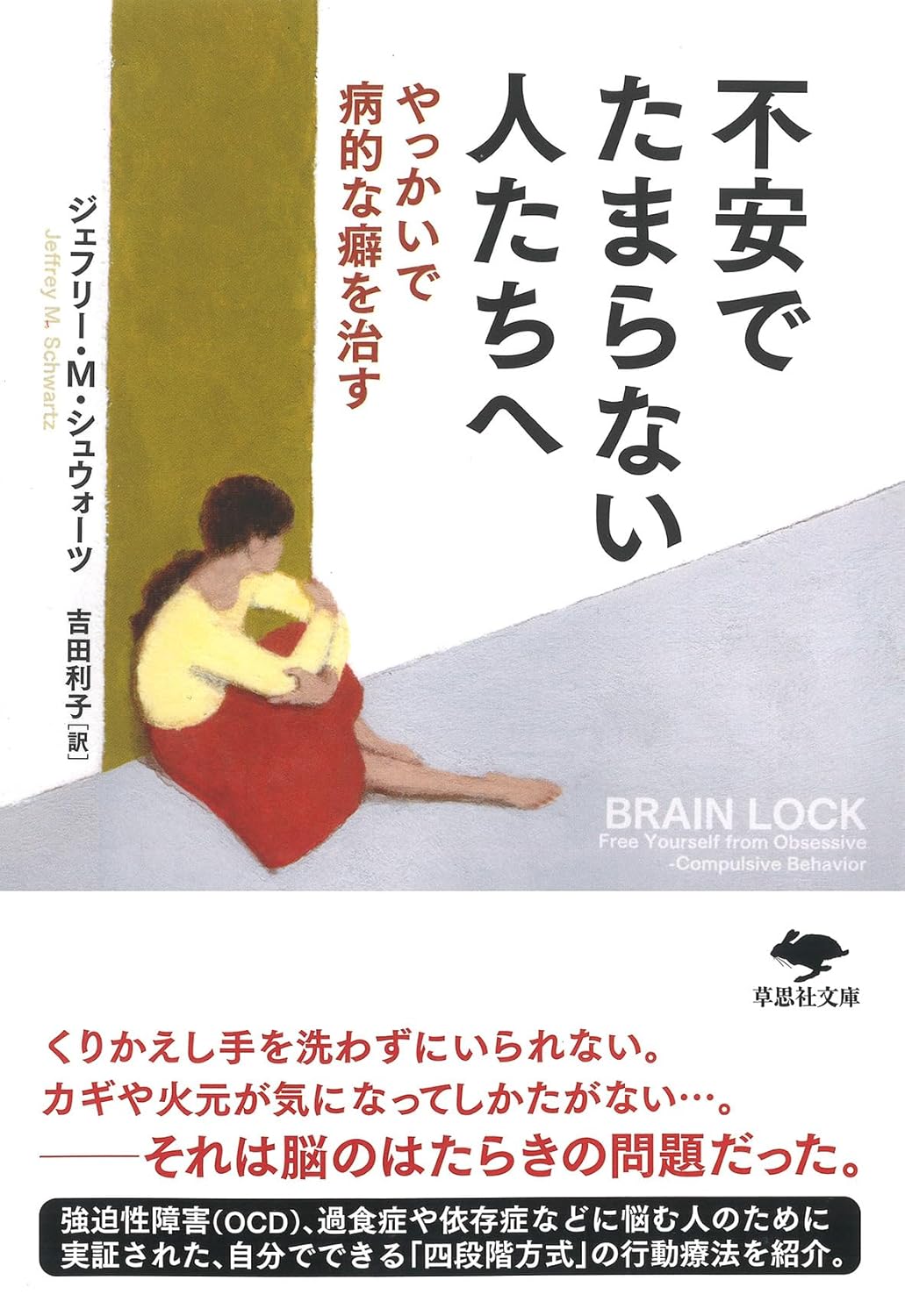
彼が開発した4ステップ法は「Brain Lock(邦訳:不安でたまらない人たちへーやっかいで病的な癖を治す)」に紹介されている:
- Relabel(ラベリング)
「これは強迫観念である」とラベルを貼る。 - Reattribute(再解釈)
「これは脳の誤作動によるもので、自分の本質ではない」と理解する。 - Refocus(リフォーカス)
注意を別の活動(趣味・仕事・運動など)に数分以上集中させる。 - Revalue(再評価)
強迫観念の価値を引き下げ、「無意味な信号」にすぎないと再評価する。
脳がどう変化するのか
Schwartzの重要な貢献は、この手法が「心理的に楽になる」以上のものを示した点である。患者が4ステップを繰り返すことで、脳画像(PETスキャン)上で尾状核や前頭皮質の代謝活動が正常化することを確認した。
Doidgeは次のように要約している:
“Patients who practiced the Four Steps showed measurable changes in brain activity, demonstrating that mindful effort could rewire neural circuits.”
(4ステップを実践した患者は、脳活動の変化が測定可能であり、意識的努力が神経回路を再配線できることを示した。)
この研究は、「心(mind)」の作用が「脳(brain)」を直接変えうるという、心身関係の科学的証拠となった。
V.S. Ramachandran:幻肢痛と「鏡の箱」
なぜ幻肢に興味を持ったのか
インド出身の神経学者V.S. Ramachandranは、神経心理学や神経学の臨床現場で、脳損傷患者の奇妙な症状に強い関心を抱いた。なぜかといえば、これらの症状は「脳がいかにして現実を構築しているか」を映し出す“窓”だと考えたからである。
彼はこう語っている:
“Neurological syndromes are nature’s experiments, revealing how the brain represents the body and the world.”
(神経学的症候群は自然の実験であり、脳が身体と世界をどのように表象しているかを明らかにするものだ。)
幻肢痛の克服
手足を失った患者の多くは「存在しない手や足が痛む」という幻肢痛に苦しむ。これは末梢の問題ではなく、脳の感覚マップに「手足が存在する」という回路が残っているために生じる。
Ramachandranは鏡の箱(mirror box)を開発し、失われた手の代わりに健常な手の鏡像を見せることで「失った手がまだ存在している」と脳に錯覚させた。これにより、患者は「麻痺して動かない幻の手を動かす」体験をし、痛みが軽減された。
Doidgeは次のように描写している:
“By tricking the brain with a mirror, Ramachandran allowed patients to move their phantom limbs and, in doing so, extinguish the pain.”
(鏡を用いて脳を欺くことで、Ramachandranは患者に幻の手足を動かさせ、痛みを消失させることを可能にした。)
この発見は、脳が「身体像(body image)」を動的に構築していること、そしてその像を再編成できることを示す画期的な証拠となった。
Turning Our Ghosts into Ancestors:トラウマの統合
Doidgeの本の中で象徴的なフレーズが「turning our ghosts into ancestors(私たちのゴーストを祖先に変える)」である。ここでいうゴーストとは、未解決のトラウマや古い神経回路の残滓を意味する。それを「祖先」に変えるとは、統合し、自分の物語の一部として未来への資源に変換することである。
これは単なる科学的発見ではなく、臨床・心理療法の文脈で重要な示唆を含む。すなわち、脳の可塑性は「機械としての脳の再配線」だけでなく、「人間存在の癒しと成長の可能性」にも直結しているのである。
まとめ:歴史的転換点としての神経可塑性
20世紀前半、神経学の教科書は「成人の脳は固定的である」と繰り返していた。だが、Merzenich、Schwartz、Ramachandranらの実証研究が積み重なることで、この常識は崩壊した。
Doidgeは結論としてこう述べている:
“The doctrine of the unchanging brain has collapsed. In its place stands a vision of a dynamic organ, capable of remapping itself throughout life.”
(不変の脳という教義は崩壊した。その代わりに、生涯を通じて自己を書き換えることができる動的な器官というビジョンが立ち現れた。)ぜひ、脳の可塑性についてご興味のある方、Norman Doidgeの The Brain That Changes Itself (邦訳:脳は奇跡を起こす)を手に取ることをお勧めしたい。