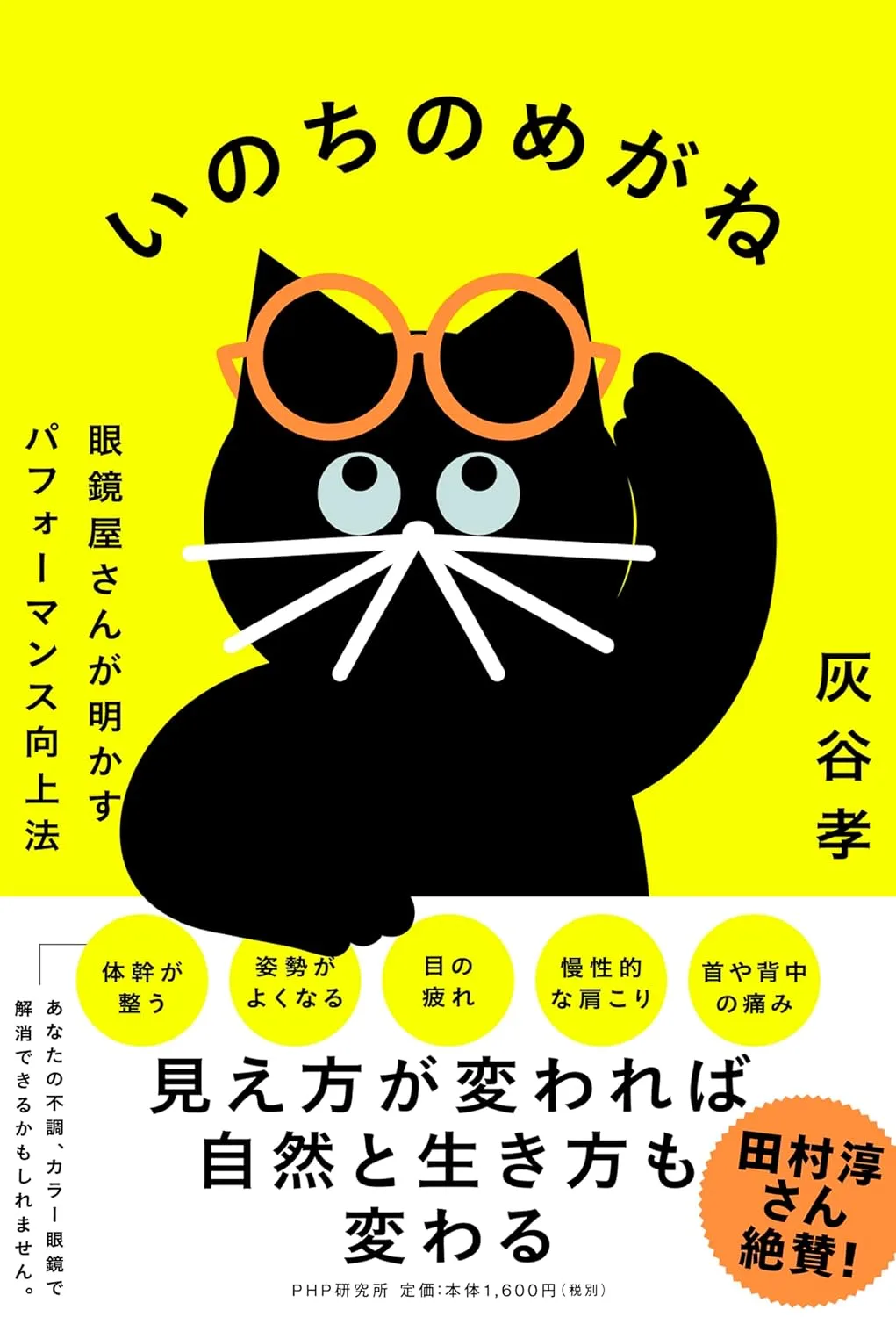【J#119】四万十川・巨石群・神社仏閣──川・石・龍に導かれる旅〜愛媛・高知の旅②
Table of Contents
はじめに
こんにちは、渋谷でロルフィング・セッションや脳科学に基づいた講座を提供している大塚英文です。
前回のブログでは、旅の初日として、高知県土佐清水市にある唐人駄馬巨石群や龍宮神社を訪れ、夜にはあしずりまつり花火大会を堪能した様子をご紹介した。

今回のブログでは、旅の二日目の足取りをたどりながら、「川」と「石」をめぐる一日をご紹介したいと思う。
川沿いをたどる移動──四万十川の下流から上流へ
二日目は、足摺岬から愛媛県松山市への長距離移動の日であった。朝、足摺サニーサイドホテルを出発。iphoneのmapアプリを使って、松山へのガイドを依頼。四万十川の下流域から上流にかけて、川の流れに沿って北上するルートを辿ることになった。
四万十川は「日本最後の清流」とも呼ばれ、手つかずの自然が残る貴重な河川である。川沿いには緑が生い茂り、透き通る水が岩を撫でながら穏やかに流れていた。

途中、四万十川を見ることのできる道を発見。細い道を通ることで、川のそばで、休憩をとることができた。水の音と風の音、そして蝉の声が混ざり合い、まるで自然が奏でる音楽の中に身を置くような感覚を覚えた。

更に、団体客で川下りを楽しんでいる方までも!川面を眺めながら、しばし呼吸に意識を持っていくことで、体内のリズムが自然と整っていくのを感じることができた。
そして、川の中に足を入れて、水の流れを感じたが、自然の中で、アーシングし「何もしない時間」が旅の中で持つ意味を、改めて思い知らされるひとときであった。
詩人の祈りの地──宇和島・大乗寺
四万十川を離れ、愛媛県宇和島市へと向かう。当初予定になかった、宇和島にある大乗寺を訪れることにした。四国唯一の臨済宗の僧堂。吉田藩伊達家の菩提寺であり、坂村真民先生が四十代の頃参禅に通われたお寺として知られている。
しかも、真民さんの講話に度々、大乗寺が登場したとのこと。これは行かねば!という気持ちで伺うことになった。

山の中腹にひっそりと佇むこの寺には、外界の喧騒とは無縁の静寂が広がっていた。境内に入ると、苔むした石段と古木に囲まれ、非常に広々としており、心が落ち着く感じがした。生前、真民さんが、大乗寺についてよく話されていたと、りゅう哉さんから伺っていたが、なんとなくその意味がわかった気がした。

海と空に開かれた巨石群──白石の鼻と白石龍神社
宇和島からさらに北上し、松山市南部の海沿いにある「白石の鼻巨石群」へと向かった。ここは、大小無数の花こう岩が広がる、瀬戸内海に突き出した岬状の地形である。

この地には、白石龍神を祀る社があり、古来より信仰の対象とされてきた。巨石群に興味があったのだが、昨日の龍宮神社に次ぐ、龍の名のついた神社。社に手を合わせたのち、巨石の間を歩く。すると、海風が吹き抜け、波の音が岩々に反響し、瀬戸内海の雰囲気がまるで一体になって、歓迎しているような印象を受けた。

空、海、石──それらが一つになるような、ふしぎな感じを受けた。

四国遍路の道──石手寺
この日の最後に訪れたのは、四国八十八箇所霊場の第五十一番札所である石手寺である。創建は奈良時代に遡り、鎌倉時代に再建された本堂は重厚な存在感を放っていた。

境内には巡礼者の姿もあったが、雰囲気は、モンゴルで見たチベット仏教の寺院、高野山で見た宿坊の近く、久々の密教世界を堪能する機会となった。

裏手には、洞窟巡り(マントラ洞窟)があるが、残念ながら、こちらは現地に遅く到着したため、体験することができず。機会があったら是非とも伺いたい場所だ。

川と石──変化と不変のはざまで
この日の旅路は、「川」と「石」と「龍」をめぐるものとなった。川という変化のあるものと、石という変化のないものの狭間が心地よく、それらの自然の流れに身を委ねることで、自分の内面を見つめる貴重な時間となった。
夜には、新居市の近くにある「ITOMACHI HOTEL0」に到着。翌日に備えての就寝。あっという間の2日目だった。

明日の予定──神社巡り+今治のものづくり
明日は、大三島にある「大山祇神社」や、四国最高峰・石鎚山の中腹に位置する石鎚神社・口之宮 本社を訪れる予定だ。その間、今治市を有名にしたタオルを展示している「タオル美術館」に立ち寄る計画を立てている。
次回の旅の記録も、どうぞ楽しみにしていただきたい。