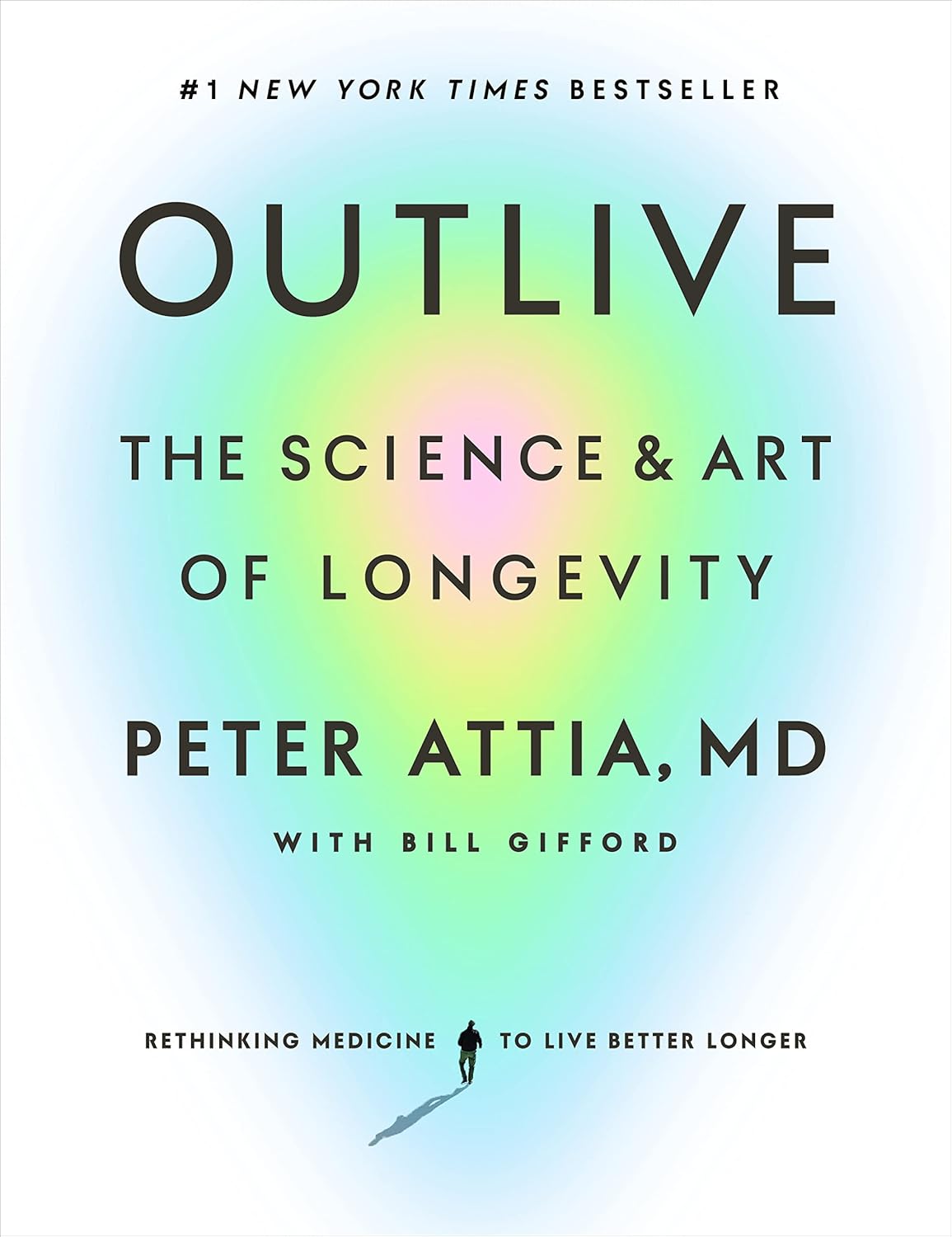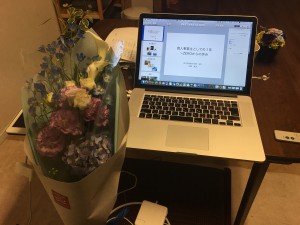【B#217】「知は創造される」──哲学の歴史から読み解く、知識経営論
Table of Contents
はじめに
こんにちは。渋谷でロルフィング・セッションや脳科学に基づいた講座を提供している大塚英文です。
経営と哲学──一見、まったく異なる領域に思えるこのふたつを深く結びつけて語った一冊が、野中郁次郎さんと竹内弘高さんによる『The Knowledge-Creating Company(知識創造企業)』である。
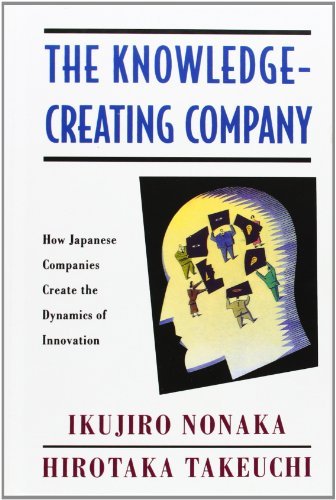
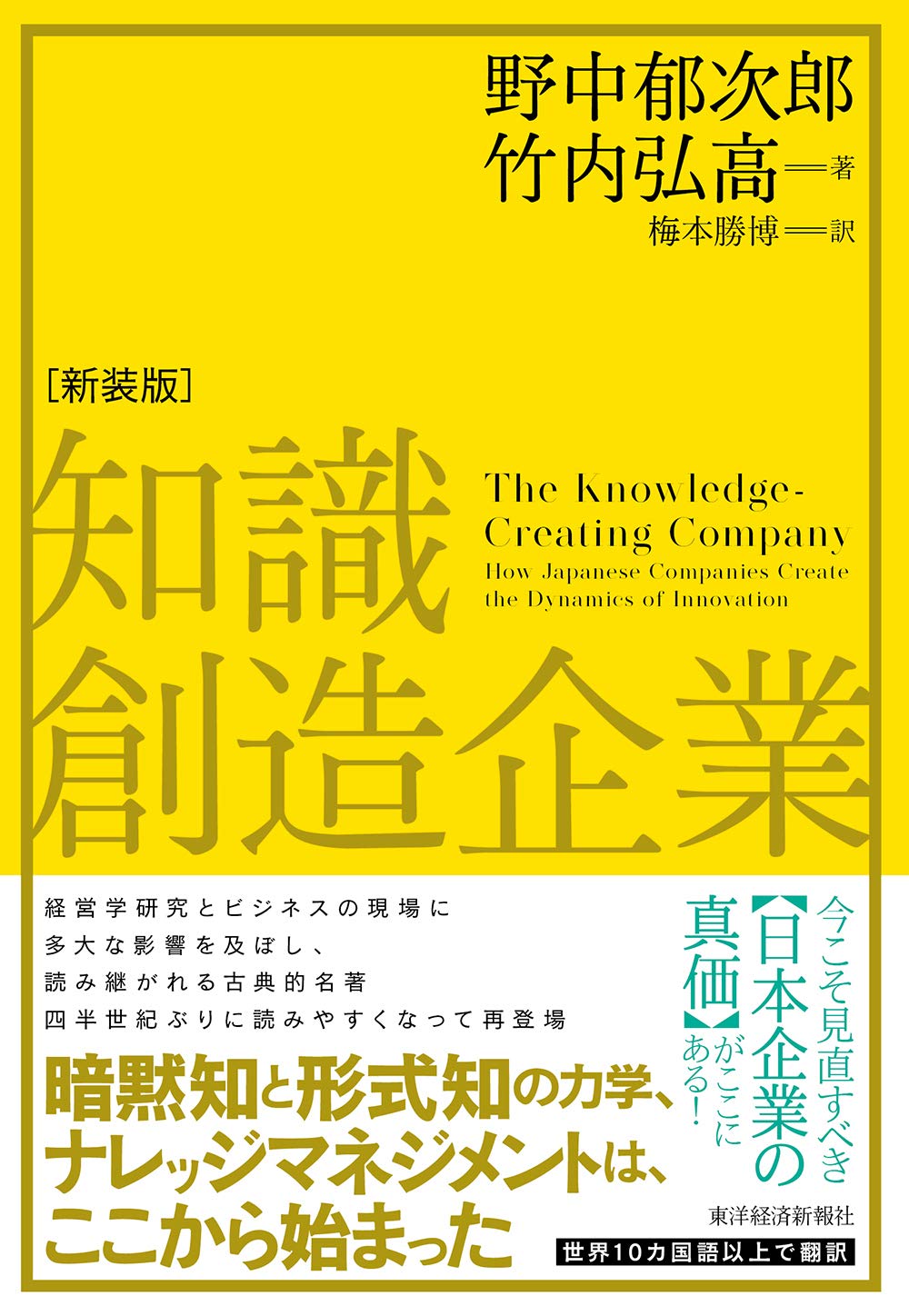
この本は、単なる日本企業の成功分析にとどまらず、「知とは何か」「人間とは何か」という根源的な問いに立脚し、知識の創造を企業経営の中核に据えた上で、哲学を語っているのが興味深い。
本稿では、組織経営を知る上で、どのように哲学から見ていくのか?主に、認識論(epistemology)の視点から、『知識創造企業』について見ていきたい。
ソクラテス的問いと暗黙知の発見
哲学の原点は、「知とは何か」という問いである。ソクラテス(Socrates)は、絶対的な知を持つことよりも、「無知を自覚すること」にこそ知の始まりがあると考えた。彼の方法は、相手に答えを教えるのではなく、問いを投げかけることで内在する知を引き出すというものであった。
野中さんが重視する「暗黙知(tacit knowledge)」は、まさにまだ言語化されていない知識である。経営者の役割とは、社員に答えを与えることではなく、問いを通じて内なる知を引き出すことであり、これはソクラテス的な“助産術”といえる。
プラトンの想起と「場(Ba)」という空間
プラトンは、知識とは「想起(anamnēsis)」であると考えた。人間は生まれる前にすでに真理を知っており、学ぶという行為はその記憶を思い出すことにほかならない。
この考え方は、野中さんが提唱する「場(Ba)」の概念と響き合う。場とは、人と人とが共鳴し合い、意味が創出される共有空間である。知識は個人の頭の中にあるのではなく、関係性と場の中で再構成されるものなのである。
実践知とSECIモデル──アリストテレスとの接点
アリストテレスは知識を三つに分類した。理論的知(エピステーメー)、技術的知(テクネー)、実践的知(フロネーシス)である。フロネーシスは、倫理的判断を伴う実践的な知であり、変化する状況下で最もふさわしい行動を選ぶための知恵である。
この三分類は、野中さんが示す知識創造プロセス──SECIモデル(共同化、表出化、連結化、内面化)──と強く結びついている。知は形式知として記述されるものだけでなく、身体に宿り、実践を通して深まっていくものなのである。
SECIモデルとは?
SECIモデルは、暗黙知(Tacit Knowledge)と形式知(Explicit Knowledge)との相互変換を通じて、組織内で知識が創造されるプロセスを示すフレームワークである。
SECIモデルの4つの知識変換プロセス
| プロセス | 知識変換の方向 | 説明 | 具体例 |
|---|---|---|---|
| 共同化 (Socialization) | 暗黙知 → 暗黙知 | 経験や身体的感覚を、言語を介さずに共有する | 職人が弟子に「背中で語る」、OJT、観察と模倣 |
| 表出化 (Externalization) | 暗黙知 → 形式知 | 感覚や経験を、言語や図式などの形式で表現する | 経験を言語化する、比喩・図解・ストーリーテリング |
| 連結化 (Combination) | 形式知 → 形式知 | 複数の形式知を組み合わせて、新しい体系を生む | 文書化・報告書作成・マニュアル化・ナレッジの統合 |
| 内面化 (Internalization) | 形式知 → 暗黙知 | 形式知を実践や体験を通じて自分の知として体得する | トレーニング、実習、経験学習、行動を通じた学び |
SECIモデルの特徴
- スパイラル構造:知識創造は一度きりで終わらず、4つのプロセスが循環しながら、個人・グループ・組織・社会レベルへと拡張される。
- 主観と客観の往還:暗黙知(身体的・文脈的・主観的)と形式知(記述可能・伝達可能・客観的)の往復が、創造性とイノベーションを生み出す源泉となる。
デカルトの合理主義と野中さんの批判的視点
近代に入り、合理主義の祖デカルトは「我思う、ゆえに我あり」と述べ、理性による明晰な知を真理の基準とした。このような近代合理主義は、経営の分野にも大きな影響を与えた。戦略、目標、分析、KPI──これらはすべて、対象を外から客観的に捉える「実在論(realism)」的な思考の延長線上にある。
一方、野中さんはこう述べている。
“Objective knowledge does not exist without the subjectivity of the individuals who create and use that knowledge.”
「客観的な知識は、それを創造し、活用する個人の主観性なしには存在しない。」
知識は、頭で考えるだけでは創造されない。身体、感情、関係性、文脈という“非合理的”な要素こそが、知の源泉なのである。
経験論の視点から──ロックとヒュームの知
ジョン・ロックは、人間の心は生まれたときには白紙であり、すべての知識は感覚経験から生じると主張した。
さらにデイヴィッド・ヒュームは、知識は印象(impression)の記憶と連想にすぎず、理性は感情の奴隷であると述べた。
“Reason is, and ought only to be the slave of the passions.”
「理性は感情の奴隷であり、そうあるべきである。」
身体感覚や感情、経験に根ざした知こそが、人間にとって真に意味のある知であるという立場は、野中さんの「暗黙知」や「場」の思想的背景と一致する。
カントと構成主義──「知は構築されるもの」
イマヌエル・カントは、「物自体(das Ding an sich)」は人間には把握できず、我々が知りうるのは、主観的な認識形式を通して構成された「現象」にすぎないと論じた。
この視点は、20世紀以降の構成主義(constructivism)に受け継がれている。
野中さんはこう述べる。
“Truth depends on the context and is created by human beings through their interactions.”
「真理は文脈に依存しており、人間が相互作用の中で創り出すものである。」
知識とは「発見するもの」ではなく、「創るもの」であり、環境や他者との関係性の中で生成されるダイナミックなプロセスなのである。
実在論と構成主義の違い
| 観点 | 実在論(Realism) | 構成主義(Constructivism) |
|---|---|---|
| 世界のとらえ方 | 世界は客観的に存在し、知識はその写し | 知識は主観・文脈・関係の中で構築される |
| 知識の定義 | 発見するもの、記録するもの | 意味を生成するもの、創造するもの |
| 組織での応用 | マニュアル、再現性、標準化 | 対話、経験、共鳴、暗黙知の共有 |
野中さんの理論は、構成主義に立脚している。
参考に、構成主義(Constructivism)とは、「知識とは外界に“すでに存在するもの”ではなく、主体が環境や経験との相互作用を通じて“構築するもの”である」とする認識論的立場である。
この考え方は、伝統的な「実在論(Realism)」──すなわち、「知識とは客観的に存在し、それを正確に写し取ることが学習や理解である」という立場──とは対照的である。
すなわち、構成主義とは、関係性・対話・経験の中で、絶えず生成されるものであり、組織とはその生成を支える「場」として考える立場なのだ。
現象学と身体性──知は“意味ある経験”として現れる
20世紀の現象学者メルロ=ポンティは、身体は単なる物理的存在ではなく、世界への“開かれ”であると説いた。
“The body is our general medium for having a world.”
「身体は、世界をもつための一般的な媒体である。」
野中さんが語る、直観・共感・身体性・沈黙・行間──そうした非言語的な知は、記号や命令ではなく、「場」によって育まれる。そして場を生み出すのは、感受性をもった人間である。
経営とは、知の創造という営みである
「知識創造企業」ではこう明言している。
“The essence of strategy lies in creating knowledge continuously and converting it into new products and services.”
「戦略の本質は、知識を継続的に創造し、それを新たな製品やサービスに転換していくことにある。」
経営とは、KPIや予算管理の技術ではない。問いを立て、意味をつくり、他者と交わり、現場の経験から未来の知を生み出す。経営とは、創造する人間の営みであり、哲学することなのである。
おわりに──いま、知を問い直すとき
変化の激しい時代、正解が見えない時代だからこそ、私たちは改めて「知とは何か」という問いに向き合う必要がある。
知は頭の中にあるのではなく、身体と関係性の中に宿る。現場にある沈黙や感覚の中にこそ、新しい知の芽が潜んでいる。
『The Knowledge-Creating Company』は、経営の実務に哲学の息吹を吹き込む書であり、奥が深い本だ。
ぜひ、組織経営の興味を持っている人のみならず、どのようにして知識を創造しているのか?その視点で見たい方に勧めたい一冊だ。