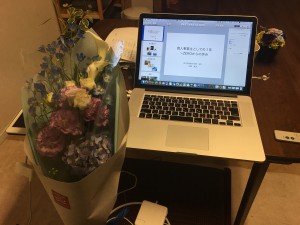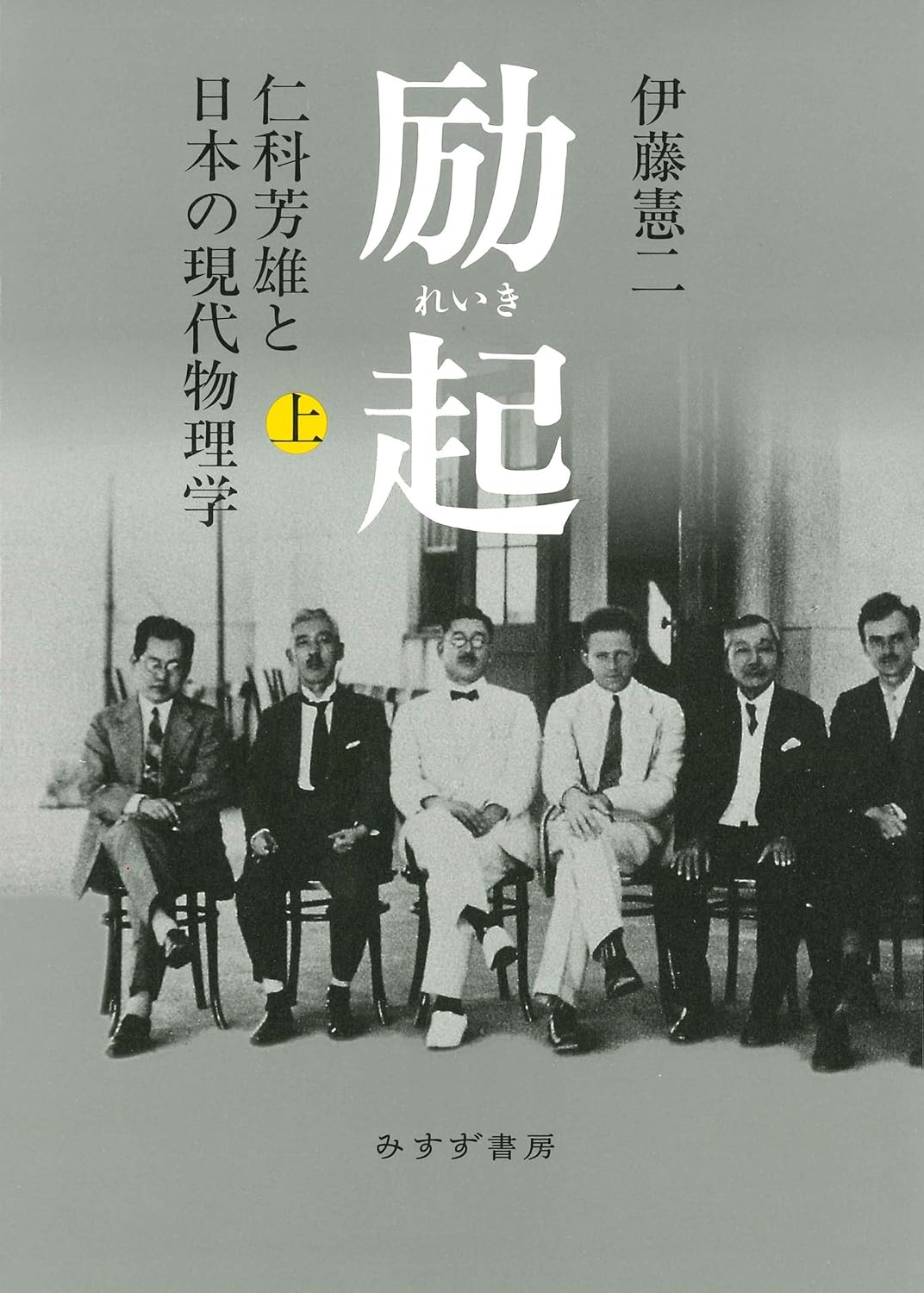【B#214】「人間の非合理性」を見つめた天才コンビ──『The Undoing Project』が描く心の探究の旅
Table of Contents
はじめに
こんにちは。渋谷でロルフィング・セッションと脳科学ベースの講座を提供している大塚英文です。
以前のブログでは、ノーベル経済学賞を受賞した心理学者ダニエル・カーネマンの代表作『ファスト&スロー(Thinking, Fast and Slow)』をご紹介した。
この本では、人間の思考には「速いシステム1」と「遅いシステム2」という二つのモードがあること、そして私たちがいかに自信を持って非合理な判断を下してしまうかについて、膨大な研究成果をもとに明快に語られていた。
そして今回は、その理論がいかにして生まれたのか?つまり、「新しい知識がどのように形づくられていったのか?」という創造のドラマに光を当てたいと思う。
ご紹介するのは、Michael Lewisの『The Undoing Project』(邦訳:後悔の経済学 世界を変えた苦い友情)だ。
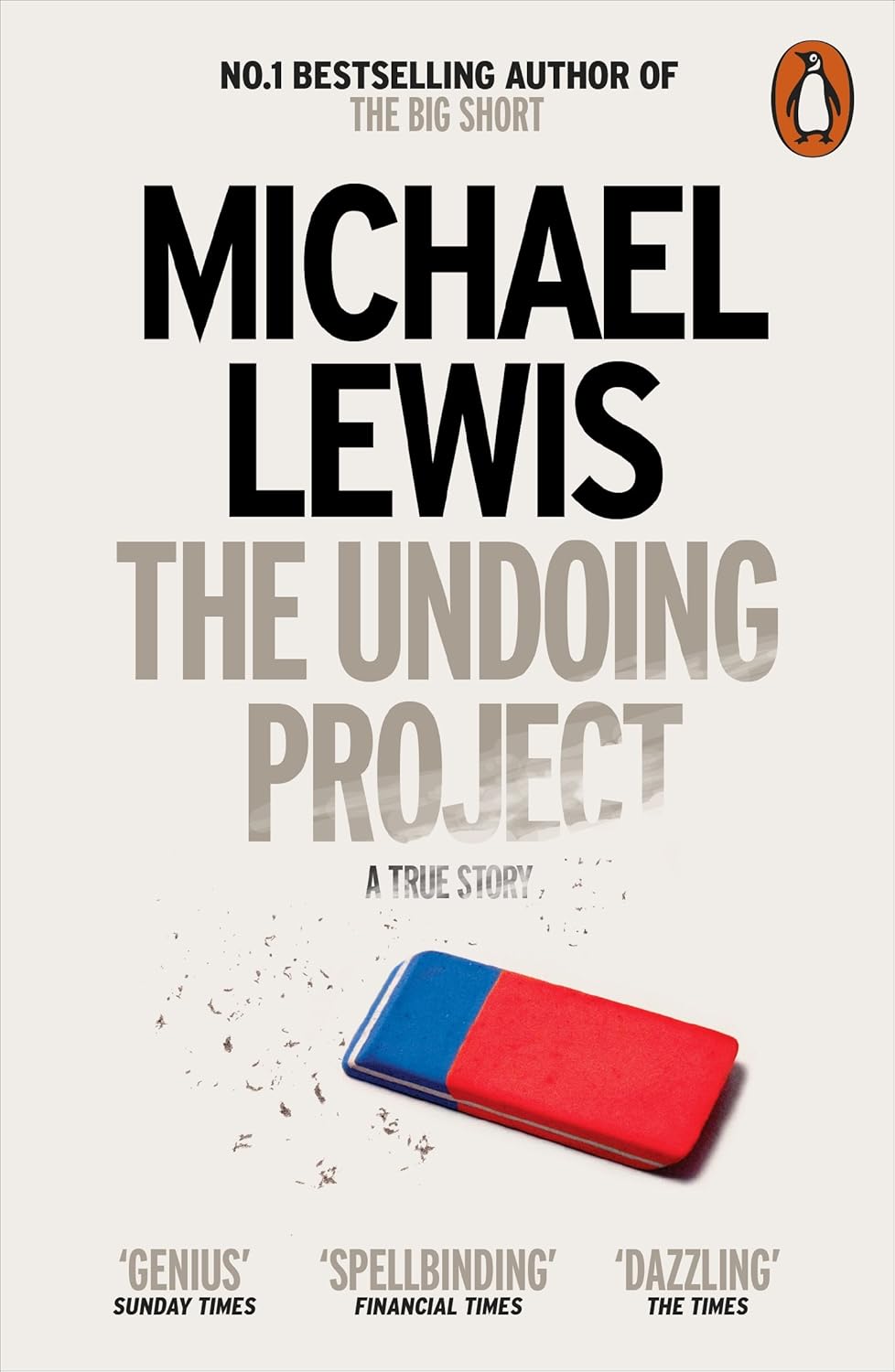
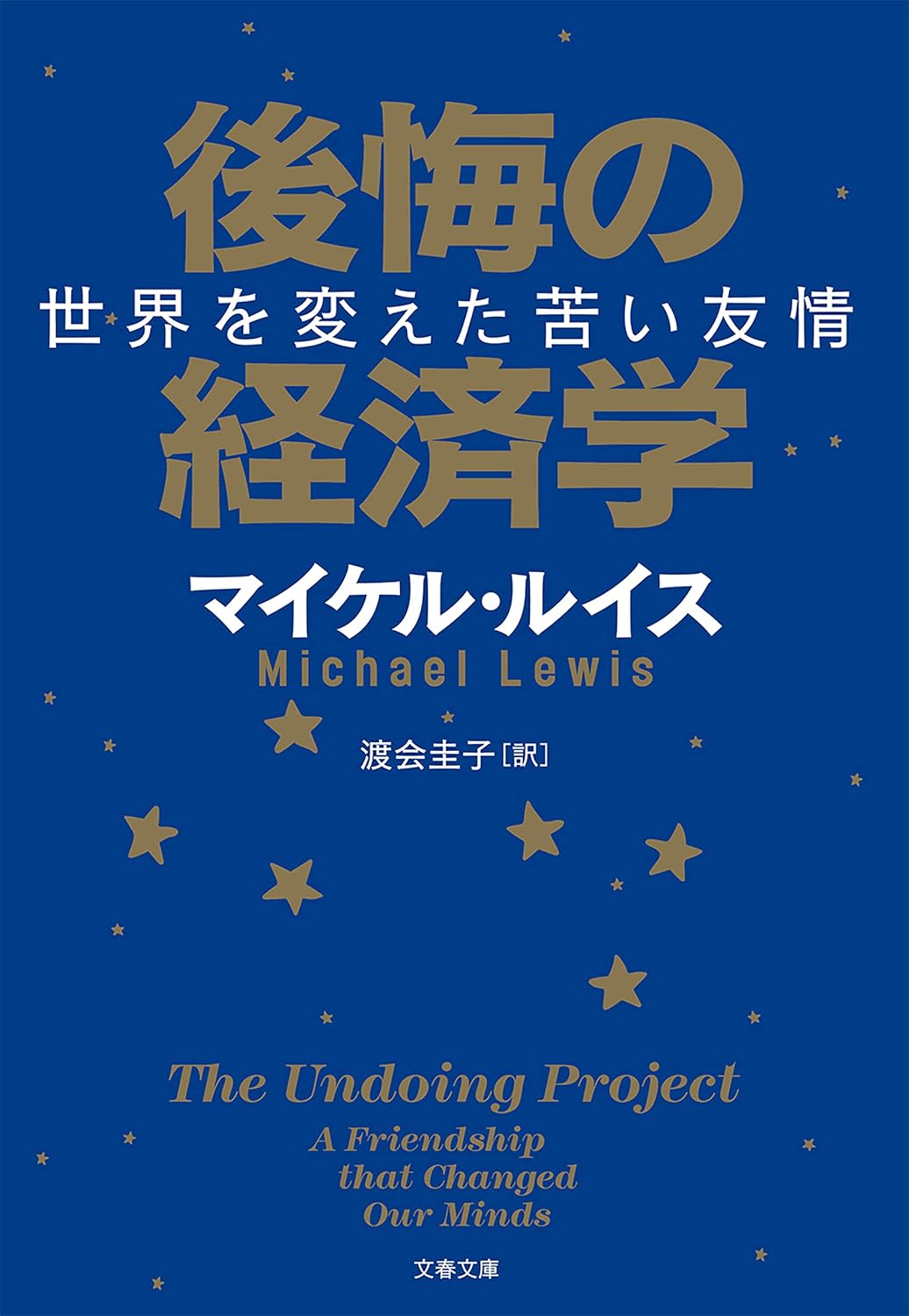
この本は、心理学者でありながら経済学に革命をもたらしたダニエル・カーネマンとエイモス・トヴェルスキー、二人の深い友情とコラボレーション、そしてその関係がどのように「人間の意思決定の仕組み」を明らかにしていったかを描いた物語だ。
非合理な人間の心理を科学的に解明するという試みにおいて、彼らがどのように出会い、どんな問いを共有し、どのようにして世界を変える理論を生み出していったのか──
今回はその「創造のプロセス」を丁寧に追いかけてみたいと思う。
正反対のようで惹かれ合った2人の性格
まず驚かされるのは、二人の性格がこれほどまでに対照的だったという事実。
ダニエル・カーネマン(Daniel Kahneman)
- ポーランド系ユダヤ人としてナチス占領下のフランスで幼少期を過ごす。
- 幼いころから「人間とは何か」「なぜ人は恐れ、判断を誤るのか」に強い関心を持つ。
- 内省的で繊細な性格。曖昧さや不確実さに耐える力を持ち、「問い」にこだわる。
エイモス・トヴェルスキー(Amos Tversky)
- イスラエル生まれ。若くして軍隊で英雄的な活躍をし、非常にロジカルで果敢な人物。
- 驚異的な記憶力と数学的な頭脳を持ち、どんな問題も形式化し、簡潔に整理する力を持つ。
- ユーモアがあり、快活で、議論では常に自信に満ちている。
Lewisは
「一人は言葉にならない問いを抱えた詩人、もう一人は数学の世界に生きる戦士」
と表現した。
まさに混じり合うことのなかった二つの思考スタイルが出会った奇跡だったといえる。
二人はどのように出会ったのか?
1970年代初頭、エルサレムにあるヘブライ大学で、カーネマンが心理学の教授として講義をしていたときのこと。
カーネマンは、教育心理学の授業で、受講生たちに“ある心理的錯覚に関する課題”を出しました。それに対して、トヴェルスキーは鋭い質問と独自の解釈を提示し、カーネマンを驚かせた。
その後、カーネマンはトヴェルスキーに「このテーマについて、一緒に考えませんか?」と声をかけた。
これが、20年以上にわたる共同研究の始まりとなる。
ふたりはコーヒーショップで延々と議論を交わし、ときには講義をすっぽかすほどに互いの会話に夢中になった。
なぜ意思決定に興味を持ったのか?
カーネマンの場合
カーネマンはイスラエル軍に心理学者として関わっていたとき、兵士の評価方法に違和感を覚えた。
上官たちは「この兵士はよくやっていたから、次も期待できる」と直感で評価していたのだが、実際のパフォーマンスと一致しないケースが多かったとのこと。
彼はここで、「人間の判断には、何かしらの“誤りのパターン”があるのではないか」と疑い始める。
つまり、「人はなぜ、確信を持って誤るのか?」──これがカーネマンの原点だったのです。
トヴェルスキーの場合
トヴェルスキーは、哲学と数学の両方に興味を持ち、意思決定理論(decision theory)をすでに数理モデルとして研究していた。しかしそこには「人間らしさ」が欠けていると感じていた。
カーネマンの直観的で人間くさい疑問に触れたとき、トヴェルスキーは「これは面白い」と感じ、一気に共同研究に引き込まれていく。
それぞれの強みと補完関係
カーネマンは「問いを立てる人」、トヴェルスキーは「答えを構築する人」だった。
二人のコラボレーションがこれほどまでに実り多いものとなった理由のひとつは、彼らの知的特性と性格が驚くほど補完的だったことにある。
カーネマンの強み:曖昧さと向き合う力
カーネマンは、徹底的に人間の「経験」に寄り添う思索家として知られていた。彼は人間の感情、記憶、そして判断の揺らぎに興味を持ち、それを観察し、言語化しようと努めた。
彼自身がこう語っている。
“I’m deeply suspicious of anything that looks like common sense.”
(私は「常識」に見えるものには、本能的に疑いの目を向ける)
たとえば、教師の評価や企業面接など、「人の判断」が大きな意味を持つ現場で、私たちはあまりにも安易に「印象」で人を評価し、確信をもって結論づけてしまう。カーネマンはその確信の背後にある「隠れた偏り」を見抜こうとした。
トヴェルスキーの強み:構造化と洗練された表現
一方、トヴェルスキーは、数学的で構造化された思考の持ち主だった。
どんなに曖昧で混沌としたアイデアでも、彼が手を加えると、それは瞬く間に「論文に載せられる理論」へと変貌する。
たとえば、カーネマンが「人は確率よりも物語を信じる」と感じたとき、トヴェルスキーはそれを「代表性ヒューリスティック」という明確な概念へと定式化した。
彼の名言のひとつがこちらだ。
“A part of good science is to see what everyone else can see but think what no one else has ever said.”
(優れた科学とは、誰もが見ているものを見ながら、誰も言ったことのないことを考えることだ)
まさに、カーネマンの観察眼とトヴェルスキーの論理的再構成力が、革新的な理論を生み出す源泉となった。
二人のやりとりの具体例:兵士評価の誤り
二人の典型的な協働スタイルがよく表れているのが、イスラエル軍における「兵士のパフォーマンス評価」に関する研究です。
あるとき、カーネマンは軍の訓練官たちに「叱責すると兵士は伸びる」と信じられていることに疑問を抱きました。データを取ると、実際には成績が良かった後には平均に戻る(回帰する)傾向があり、叱責の効果ではなく「統計的回帰」だった。
この仮説を、トヴェルスキーは瞬時に数式に落とし込み、論文として世に送り出します。このやりとりは、のちのプロスペクト理論にもつながる「誤った因果帰属」や「直感に基づく錯誤」の出発点となった。
二人が共にいるときの知的爆発
Michael Lewisは、本の中でこのように述べています。
“Together, they became a single mind that was more than the sum of its parts.”
(二人が一緒にいるとき、それは部分の総和以上の「一つの知性」になった)
つまり、カーネマンの「内省的な問い」が、トヴェルスキーの「大胆な定式化力」と出会うことで、どちらか一方では決して到達できなかった発見が生まれていった。
カーネマン自身による回想
のちにカーネマンはこう振り返ります。
“Every minute with Amos was a joy. Working with him was like dancing.”
(アモスと過ごす時間は、どの瞬間も喜びだった。彼との仕事はまるで踊るようだった)
このような「踊るような知的協働」は、単なる共同研究ではありません。
それは、知性と情熱と友情が重なり合った「創造的プロセス」そのものでした。
なぜコラボがうまくいかなくなったのか?
ふたりの関係には、やがてほころびが生まれる。原因は、「外からの評価の不均衡」だった。
- トヴェルスキーは話が明快で、人前でも堂々と話すため、メディアや学会で注目されやすかった。
- 一方のカーネマンは、人前に出ることを好まず、陰に回ることが多かった。
そのため、多くの人が「この業績はトヴェルスキーのもの」と誤解して称賛し、カーネマンは深く傷つく。
一時期は、「なぜ彼は私の名前を出してくれないのか?」という思いを抱えながら研究を続けていたとも言われる。
やがて二人は別々の道を歩み始めましたが、トヴェルスキーが癌で亡くなる直前、カーネマンは彼にこう伝える。
「僕の人生の中で、あれほど楽しかった時間は他にないよ。君との時間が、僕の最高の思い出なんだ。」
ヒューリスティックとバイアスの発見
カーネマンとトヴェルスキーの業績の中でも、特に有名なのが「ヒューリスティックとバイアス」の研究だ。
代表性ヒューリスティック(Representativeness Heuristic)
- ある人物が「教師らしい」か「エンジニアらしい」かといった「らしさ(representativeness)」だけで判断し、統計的な情報(ベースレート)を無視してしまう傾向。
- 例:几帳面で物静かな人に出会ったとき、その人を「図書館司書だ」と思い込むが、実際にはセールスマンの方が人口的に多い可能性がある。
このように、私たちは確率や統計よりも、「直感の物語性」に従って判断する傾向がある。
プロスペクト理論とノーベル賞
さらに彼らは、プロスペクト理論(Prospect Theory)を提唱した。
- 人間は「得をすること」よりも「損をすること」に強く反応する(損失回避)。
- また、期待値が同じでも、提示のされ方によって選択が変わる(フレーミング効果)。
この研究によって、経済学における「人は常に合理的に行動する」という前提が崩れた。
2002年、この功績によりカーネマンはノーベル経済学賞を受賞しました。もしトヴェルスキーが生きていれば、彼もまた同時受賞していたはず(ノーベル賞は故人に授与されないため)。
経済学と社会への影響
彼らの研究は、心理学だけでなく、次のような分野に大きな影響を与えました:
- 経済政策の設計(ナッジ理論など)
- 医療現場の意思決定(医師の判断の偏り)
- スポーツやビジネスにおけるスカウティング
- 投資判断・マーケティング手法
- 行動経済学の誕生と普及
Michael Lewisの前作『マネーボール』も、人間の直感的判断がいかに非合理であるかを実証的に描いており、その思想的バックボーンにトヴェルスキーとカーネマンの研究があることを、本作『The Undoing Project』で明かしています。
まとめ:「Undoing=解きほぐす」という営み
タイトルの「Undoing(取り消す、ほどく)」は、私たちが何気なく信じている「自分の判断力」への疑いを意味している。
カーネマンとトヴェルスキーは、決して人間の欠点を責めたわけではありません。
むしろ、人間らしい「不完全さ」と向き合い、そのメカニズムを明らかにすることで、よりよい意思決定を支える知識の礎を築いたのです。
本書は、心理学・経済学の知的探究としても、人がどのように他人とコラボするのか?深い友情とすれ違いの人間ドラマとしても、読める本で、非常に面白い一冊になっている。