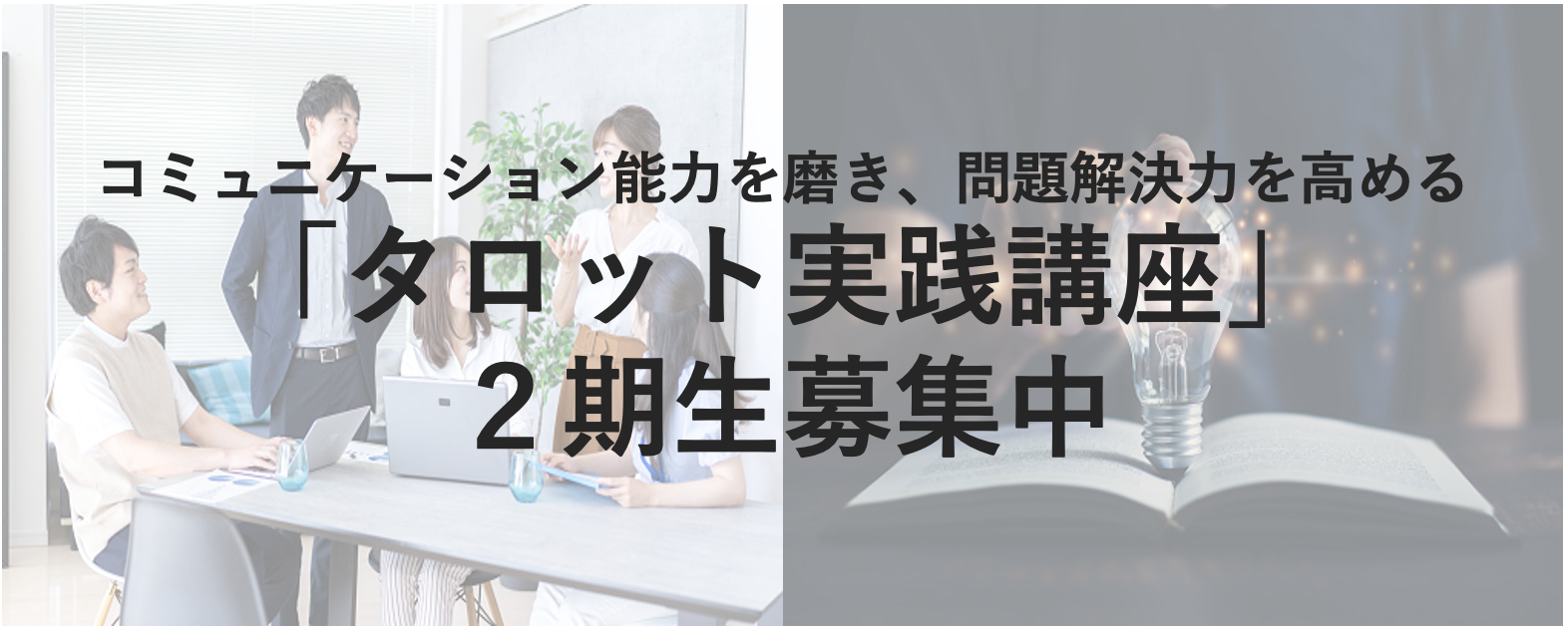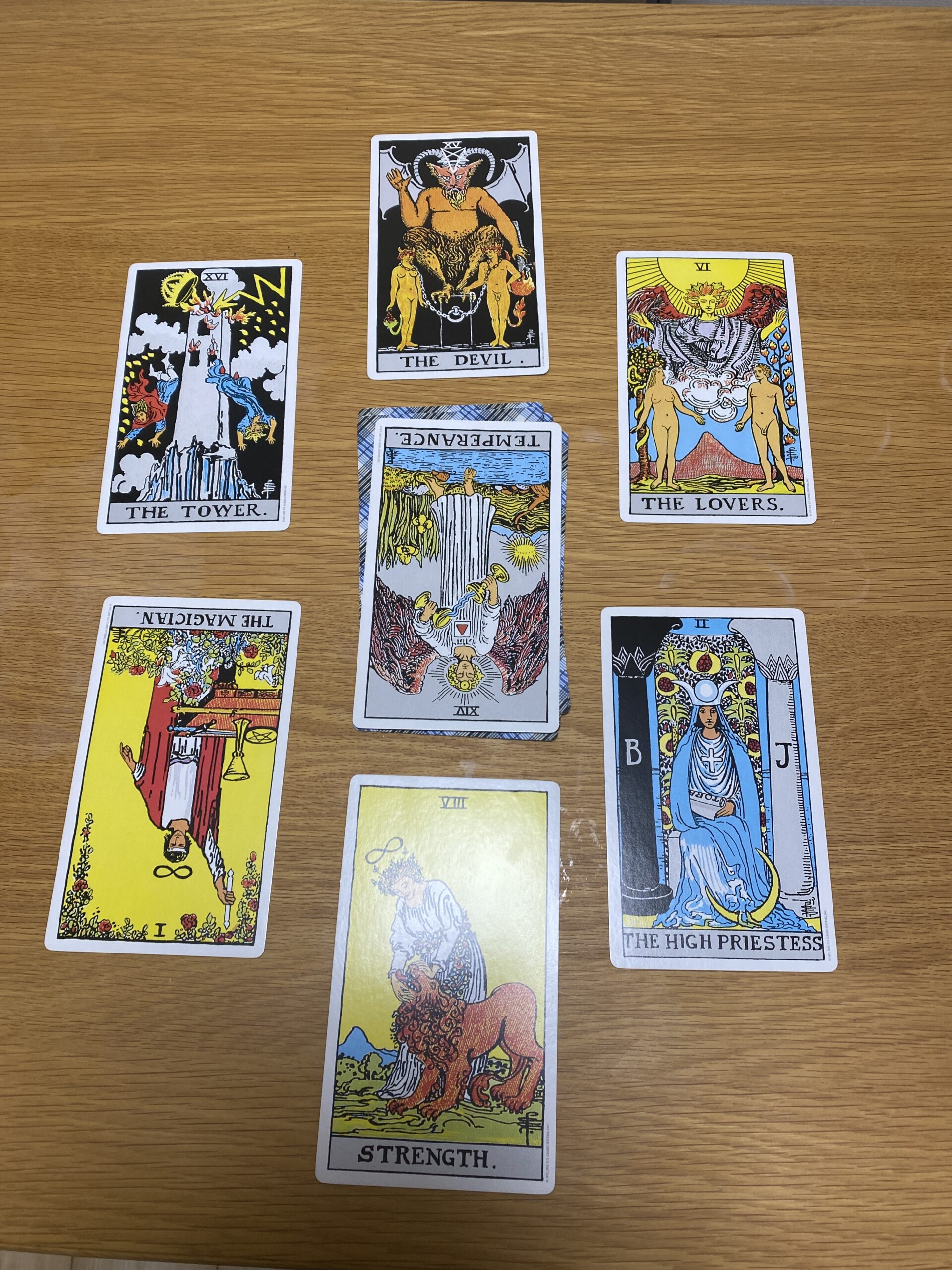【B#182】習慣の力を味方にする:脳と行動の科学から学ぶ、変化のつくり方
Table of Contents
はじめに
東京・渋谷でロルフィング・セッションと脳科学から栄養・睡眠・マインドの脳活(脳科学活用)講座を提供している大塚英文です。
今回は、チャールズ・デュヒッグによるベストセラー『The Power of Habit(習慣の力)』から、私たちの行動と脳の関係、そして習慣を変えるための具体的なヒントを紹介したい。
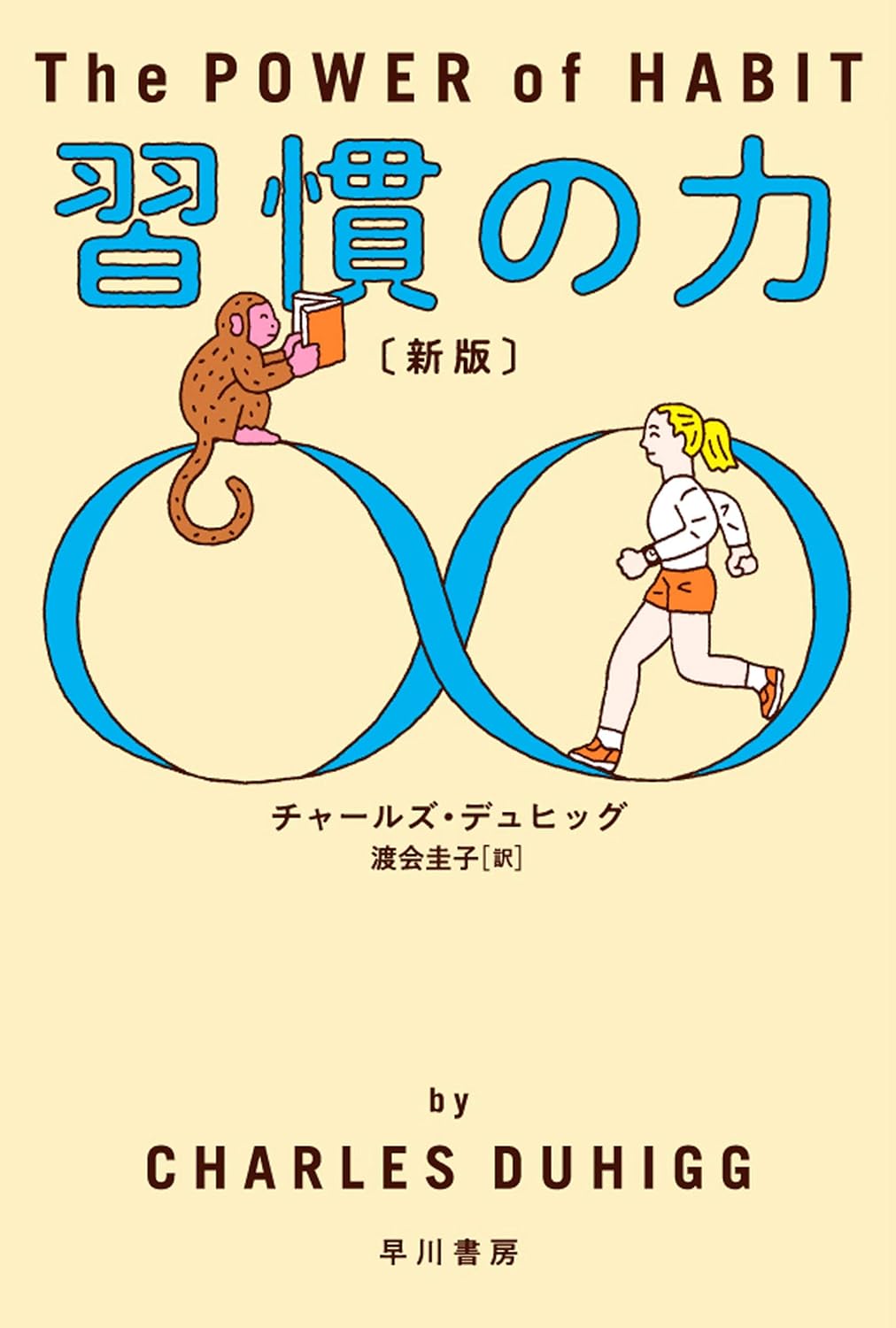
習慣は「脳の省エネ戦略」〜なぜ変えるのが難しいのか?
私たちの行動の多くは、実は「考えずに繰り返しているもの」。その背後にあるのが、脳の大脳基底核(Basal Ganglia)だ。繰り返しの行動を自動化し、エネルギーを節約する役割を担っている。
習慣とは何か?
“Habits, scientists say, emerge because the brain is constantly looking for ways to save effort.”
― Charles Duhigg, The Power of Habit
(習慣は、脳が常にエネルギーを節約する方法を探しているために現れる、と科学者たちは言う。)
習慣とは、「一度覚えた行動を自動的に実行することで、脳の負荷を減らす仕組み」と言える。
習慣の「ループ構造」
デュヒッグは、習慣の核となる仕組みをこう定義している。
“This process within our brains is a three-step loop. First, there is a cue, a trigger that tells your brain to go into automatic mode and which habit to use. Then there is the routine, which can be physical or mental or emotional. Finally, there is a reward, which helps your brain figure out if this particular loop is worth remembering for the future.”
― Charles Duhigg, The Power of Habit
(習慣は、脳内で「Cue(きっかけ)→ Routine(行動)→ Reward(報酬)」という3段階のループとして構成されており、報酬によってそのループが記憶されるかどうかが決まります。)
このループが一度形成されると、脳はそのパターンを強化し、自動的に行動が起きるようになる。だからこそ、習慣をやめるのは難しいといえる。
習慣は「変える」ことはできる——正しい方法で
一方で、デュヒッグは「習慣は消すことはできないが、書き換えることはできる」といっている。
習慣を書き換える「黄金律」
“The Golden Rule of Habit Change: You can’t extinguish a bad habit, you can only change it.”
― Charles Duhigg, The Power of Habit
(習慣を変える黄金律:悪い習慣は消すことはできない。ただ、置き換えることはできる。)
重要なのは以下の3点です:
- Cue(きっかけ)はそのまま使い
- Reward(報酬)も変えずに
- Routine(行動)だけを別の健全なものに置き換える
“If you keep the same cue and the same reward, a new routine can be inserted.”
― Charles Duhigg
(同じきっかけと報酬を保ちつつ、新しいルーチンを挿入することができれば、習慣は変えられる。)
習慣を変える3つの実践ポイント
習慣ループを観察し、記録する
自分がどんなCueで、どんなRoutineに入り、どんなRewardを得ているのかを記録することが最初のステップ。
新しいRoutineを実験する
Rewardが「気分転換」なら、それを他の行動でも得られるかを試してみる。小さな実験を繰り返す中で、新しいルーチンが定着していく。
信念と「小さな勝利(Small Wins)」を積み重ねる
習慣の変化には「これならできる」という感覚が重要です。日々の小さな成功体験が、次のステップを後押ししてくれる。
習慣は「個人」だけでなく、「組織」や「社会」も変える
デュヒッグの本の面白いところは、個人の習慣だけでなく、企業や社会の変化においても、習慣がどれほど大きな力を持つかが示されているところだ。印象的な3つの事例を紹介する。
【事例①】アルコア社:安全という「習慣」を変えて企業文化を一新
1990年代、アルコア社の新CEOポール・オニールは、業績ではなく「労働現場の安全性」に全力を注いだ。
“If you want to understand how a company operates, you look at how it handles a crisis. That’s when habits are revealed.”
― Charles Duhigg
(組織の本質を知りたければ、危機にどう対応するかを見ればいい。そのときにこそ、その組織の「習慣」が明らかになるのだ。)
「安全第一」の習慣が企業全体に浸透した結果、従業員の意識や風土が変わり、アルコアは生産性と利益を同時に向上させることができた。
【事例②】スターバックス:感情習慣のトレーニング
スターバックスでは、従業員が困難な状況でも冷静に対応できるよう、意志力と感情コントロールの訓練をしている。
“Willpower isn’t just a skill. It’s a muscle, like the muscles in your arms or legs, and it gets tired as it works harder, so there’s less power left over for other things.”
― Charles Duhigg
(意志力は単なるスキルではない。それは筋肉のようなもので、使えば疲れ、使える力も減ってしまう。)
だからこそ、意志に頼るのではなく、行動を習慣にするトレーニングが有効なのだという。
【事例③】公民権運動:社会を変えた「人々の習慣」
1955年、ローザ・パークスのバス拒否事件が起きたとき、それがただの抗議に終わらなかったのは、教会と地域コミュニティという習慣的な結びつきがあったからです。
“Movements don’t emerge because everyone suddenly decides to face the same direction at once. They rely on social habits, the invisible networks of friendships and the expectations of communities.”
― Charles Duhigg
(社会運動は、人々が突然同じ方向を向くことで始まるのではない。それは、友情のネットワークやコミュニティの期待という「社会的習慣」によって広がるのだ。)
このようにして、人々の習慣が社会全体を動かす原動力にもなりうる。
習慣を味方にするということ
習慣は、放っておけば私たちを支配しますが、意識してデザインすれば人生を変える味方になる。
- 習慣ループを観察し、記録する
- Routineを置き換える戦略を立てる
- 小さな成功体験を積む
そ個人だけでなく、組織や社会にも応用できる視点があることを、この本は私たちに教えてくれる。
この本をおすすめしたい人たち
『The Power of Habit』は、単なる「自己啓発書」ではない。脳科学・心理学・社会行動の深い洞察に基づいた実用的なガイドになっている。
この本については、
- 日々の生活の質を上げたいと感じている方
- 悪習慣を断ち切りたいが、何から始めればいいかわからない方
- 部下やチームの行動変容を促したいマネージャー・リーダー
- 子育てや教育の現場で「習慣づけ」の大切さを実感している方
- 組織文化やチームの風土を変えたい経営者・ファシリテーター
- 社会運動やコミュニティ形成に関心のある方
にお勧めしたい。
習慣は、私たちの「無意識」を司る力となる。この一冊は、自分の人生を再設計するための「見えない設計図」を与えてくれるといっていい。
少しでもこの投稿が役立つことを願っています。