【B#175】ソニー創業者・井深大さんから学ぶ〜創造性を育む、組織の作り方
Table of Contents
はじめに
東京・渋谷でロルフィング・セッションと脳科学から栄養・睡眠・マインドの脳活(脳科学活用)講座を提供している大塚英文です。
今年の3月に、ソニー創業者の井深大さんの「自由闊達にして愉快なる〜私の履歴書」を久々に読んだ。iPhoneやMacを製造しているアップル社に大きな影響を与えたソニー。創業期に何を考え、どのように会社を発展させてきたのか?組織づくりの観点から興味を持っていたからだ。
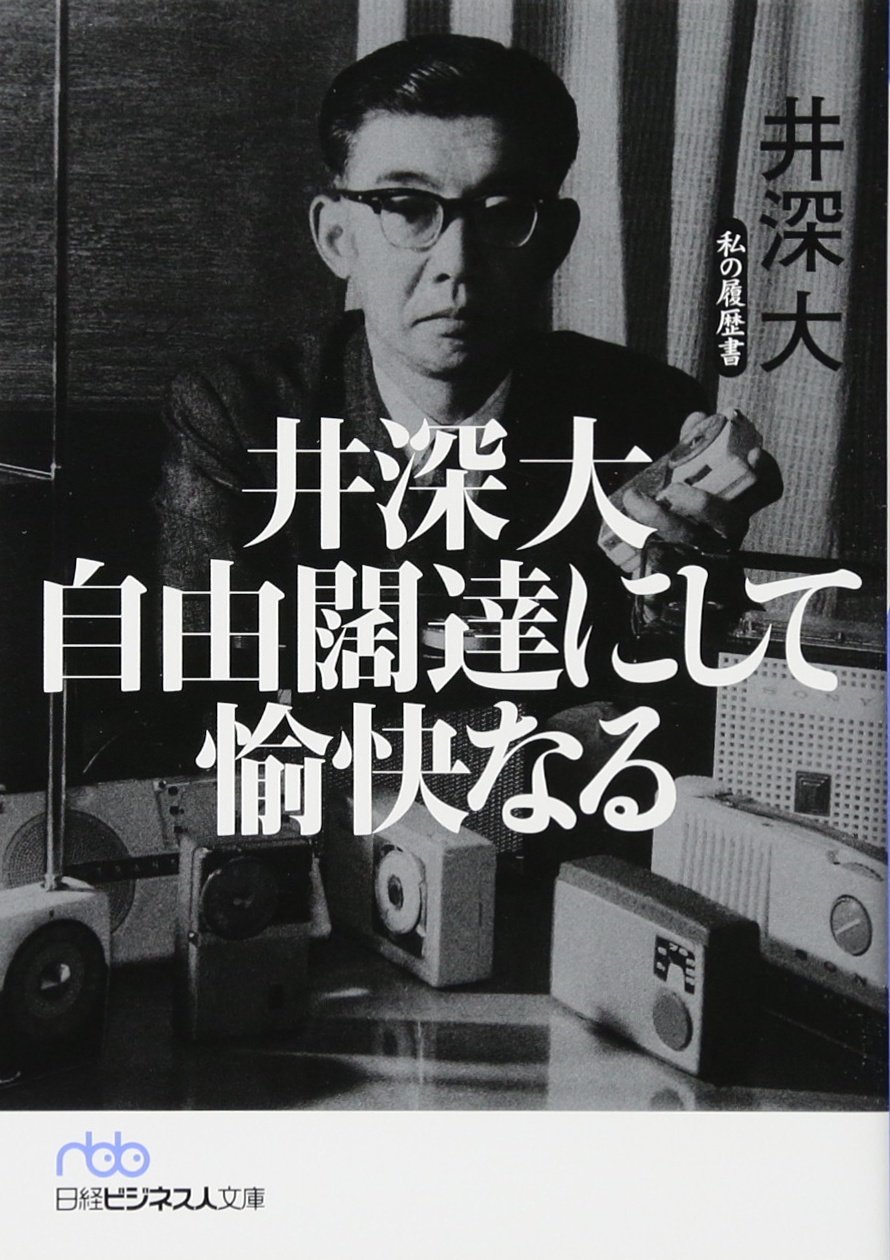
この本で初めて知ったのだが、井深さんは、マンハッタン計画、アポロ計画、新幹線開発などの大規模技術プロジェクトに関心を持っていたらしい。これらのプロジェクトでは、最先端の技術開発手法や管理手法が使用されていたが、ソニーの経営や製品開発に応用された。
今回は、井深さんがどのようにこれらのプロジェクトを学び、ソニーの製品開発に活かしたのか?を中心に5つの視点からまとめてみたい。
巨大なプロジェクト管理とチームワーク〜優秀な技術者の協力を重視
マンハッタン計画やアポロ計画では、多くの優秀な科学者・技術者が集まり、それぞれの専門分野を活かしながら巨大な目標に向かって協力体制を築いた。
井深さんは、優れた技術者が集まり、目標に向かって協力することの重要性を学び、ソニーの製品開発にも応用。トランジスタラジオやウォークマンの開発では、社内外の技術者を集めることに成功している。
長期的な視点での技術開発〜未来を見据えた投資
アポロ計画や新幹線の開発では、すぐに利益が出るわけではなく、長期的な視点で技術投資を行われた。井深さんも、ソニーの経営にその考えを取り入れ、短期的な利益よりも長期的な技術投資を重視。

トランジスタ技術の導入や、世界初の家庭用ビデオテープレコーダーの開発等は、今までにない製品を開発するため、将来を見据えた投資を行った。
小型化・軽量化・品質の重要性〜トランジスタラジオやウォークマンの開発
新幹線の開発では、速度を上げるために車両の軽量化が重要視されました。また、アポロ計画では、宇宙船の機器をできるだけ小型・軽量化することが求められました。

井深さんは「技術を極限まで小さく、軽くすることが新しい市場を生む」と、消費者の視点で物事を考え、トランジスタラジオ、ウォークマン等、小型・軽量の製品を開発へと結びつけていった。特に、ウォークマンは、井深さんの発想だったとのことだ。
更に、アポロ計画では、極限環境での精密機械の開発には、徹底した品質管理と信頼性の確保が不可欠だったという。ソニーは、1960年代から品質管理の徹底を進め、「Made in Japan」の信頼性向上に貢献していく。
革新技術への挑戦と失敗を恐れない姿勢〜新技術を積極的に採用
マンハッタン計画やアポロ計画では、未知の技術に挑戦し、多くの失敗が積み重ねられた。井深さんは、新しい技術に挑戦し続けることの重要性を学び、ソニーでも失敗を恐れずに新技術を積極的に採用していく。

トリニトロン方式のカラーテレビ、CDの開発では、従来の技術にとらわれず、新たな技術を生み出していく。
国家規模の技術開発からの学び〜日本の技術力向上への貢献
マンハッタン計画、アポロ計画、新幹線開発はいずれも国家レベルのプロジェクトとして取り組まれた。井深さんは、これらの事例から「優れた技術は国家の発展に寄与する」と考え、日本の技術力向上のために尽力し。技術開発を通じて日本の競争力を高めることを目指し、ソニーを世界的企業へと成長させることに成功した。
まとめ
井深さんは、マンハッタン計画、アポロ計画、新幹線開発などの大規模技術プロジェクトに関心を持っていたことから、今回のブログでは、「自由闊達にして愉快なる〜私の履歴書」を参考に、どのようにこれらのプロジェクトを学び、ソニーの製品開発に活かしたのか?を中心にまとめさせていただいた。
少しでもこの投稿が役立つことを願っています。






