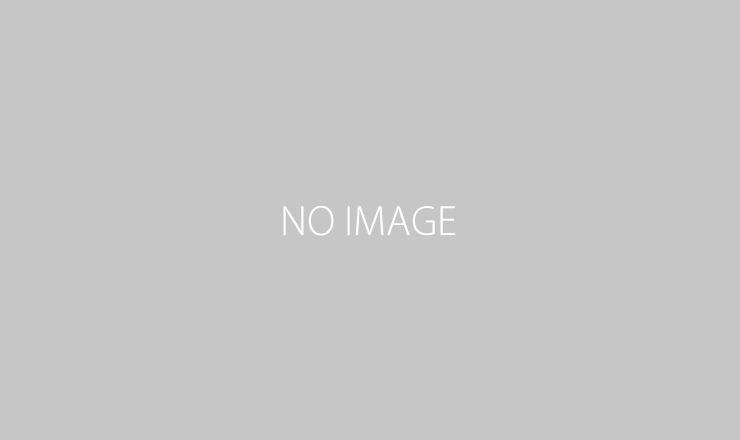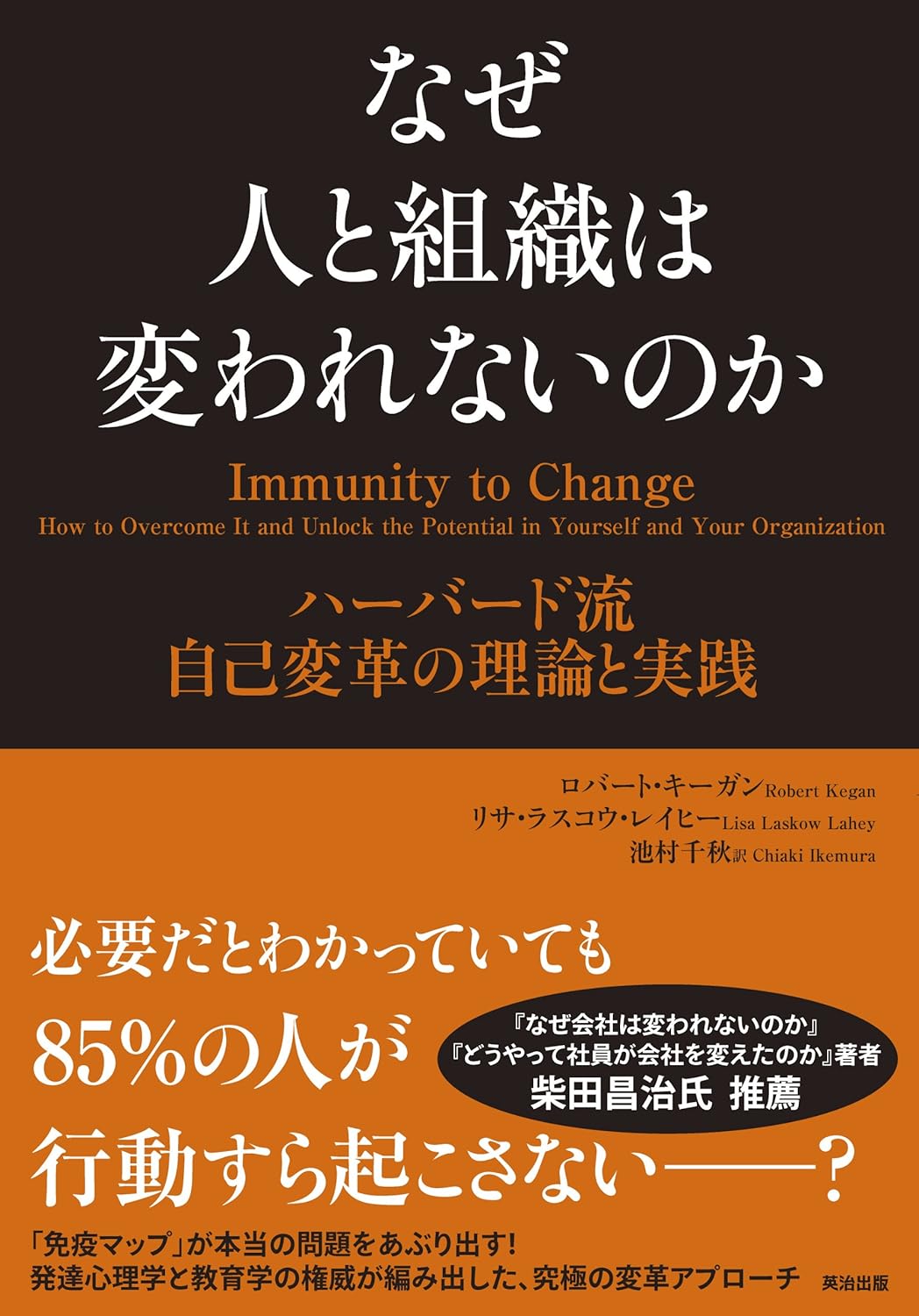【N#206】健康寿命を支える3つの運動視点──持久力・筋力・安定/姿勢をバランスよく鍛える
Table of Contents
はじめに
こんにちは、渋谷でロルフィング・セッションや脳科学をベースにした講座を提供している大塚英文です。

健康寿命を延ばすうえで欠かせないのが「運動」。しかし、「何をすればいいのか?」は意外と曖昧になりがち。Peter Attia の『Outlive』や私が行っている脳活講座では、運動を次の3つの柱に分けて考えることを提案している。
- 有酸素・持久系(Aerobic Endurance)
- 筋力・抵抗運動(Strength / Resistance)
- 安定・姿勢(Stability)
この3つをバランスよく取り入れることが、年齢を重ねても自分らしく動ける身体を保つ秘訣となる。
有酸素・持久系──心肺機能と代謝の柔軟性を鍛える
持久力のトレーニングでは「カロリー消費」よりも「ミトコンドリア」の健康がポイント。
ミトコンドリアが元気だと何が良いのか?
ミトコンドリアは「細胞の発電所」と呼ばれ、私たちが使うエネルギー(ATP)の大部分をつくり出している。
元気なミトコンドリアが多いほど、
- 脂肪と糖を効率的に使える代謝の柔軟性が高まる
- 内臓脂肪の蓄積を防ぐ
- 慢性炎症や酸化ストレスを抑える
- 疲れにくく、回復が早くなる
逆にミトコンドリアが弱ると、脂肪を燃やせず糖依存になり、血糖値の乱高下や慢性疲労、生活習慣病のリスクが高まる。

最大酸素摂取量(VO₂ MAX)とは?
最大酸素摂取量とは、「運動中に体が一度に取り込んで利用できる酸素の最大量」のこと。単位はmL/kg/minで表され、全身持久力の総合的な指標であり、寿命の予測とも強く相関する。
VO₂ MAXが高いほど、長時間・高負荷の運動を続けられる能力が高くなります。加齢とともに低下しますが、適切なトレーニングで維持・改善が可能だ。
実践のポイント
- ZONE2トレーニング(最大心拍数の60〜70%)を週合計3時間ほど行う
例:サイクリング、ジョギング、速歩き - 会話がギリギリできる強度が目安
- VO₂ MAXはApple WatchやGarmin、OURA RINGなどで計測可能
私の事例
私はOURA RINGで、どのZONEのトレーニングを行っているのか?チェックしている。持久力向上の一環として、ブラジリアン柔術のトレーニングも取り入れている。柔術は試合やスパーリングの中で有酸素・無酸素運動が組み合わさり、心肺機能と瞬発力の両方を鍛えられるのが特徴だ。
筋力・抵抗運動──加齢に負けない筋肉をつくる
筋肉は40歳以降、年1%ずつ減少します。特に速筋の低下は転倒リスクや生活の質低下に直結。筋肉量が少ない人は死亡リスクが高まり、握力の低下はサルコペニアの兆候になる。

転倒と死亡率の関係
『Outlive』では、65歳以上の人が転倒して骨折すると、その後1年間の死亡率が顕著に高まるというデータが紹介されている。
理由は、骨折による活動制限が筋力と心肺機能の急激な低下を招き、さらに免疫力低下や合併症(肺炎、血栓など)を引き起こすため。つまり、筋肉を維持し転倒を防ぐことは、寿命そのものを守ることにつながるのだ。
実践のポイント
- ウェイトトレーニング(80%1RM ×8回 ×3セットを週2〜3回)
- 自重トレーニング(スクワット、腕立て、プランクなど)
- 握力維持・向上:鉄棒にぶら下がる「デッドハング」
- 男性は2分、女性は90秒(40歳基準)を目標
- 握力・肩・体幹を同時に鍛えられる
私の事例
私は筋力・抵抗運動の一環として、ヨガの練習を日常的に行っている。ヨガは見た目の柔軟性だけでなく、自重を支えるポーズで筋力を鍛え、姿勢筋を強化。プランク、戦士のポーズ、橋のポーズなどは特に体幹と下半身の筋力に効果的だ。
安定・姿勢──全ての動きの土台を整える
いくら筋力や持久力があっても、姿勢やバランスが崩れると怪我や疲労につながる。安定性は「動きの質」を高める要であり、ヨガやボディワークはその力を引き出す。

実践のポイント
- ヨガ・ピラティスで軸を整える
- ボディワークで感覚を高め、負担の少ない姿勢を身につける
- ゆっくり・丁寧な動きで体幹を安定させる練習
まとめ──3つの視点で未来の身体を設計する
- 持久力:VO₂ MAXを意識し、心肺機能と代謝の柔軟性を高める
- 筋力:筋肉量と握力を維持し、日常動作と競技パフォーマンスを支える
- 安定・姿勢:怪我を防ぎ、効率的な動作を実現する
私自身、ブラジリアン柔術・ヨガ・ぶら下がりトレーニングなどを組み合わせて実践することで、3つの柱をバランスよく鍛えている。健康寿命を延ばす運動は、一つの方法に偏らず、この3要素を網羅することが鍵だ。
未来の自分のために、今日から3つの柱を意識した運動習慣を始めてみませんか?