【B#174】「科学の楽園」の理化学研究所〜どのように創造的な組織を作るか?〜科学と産業の融合の事例
Table of Contents
はじめに
東京・渋谷でロルフィング・セッションと脳科学から栄養・睡眠・マインドの脳活(脳科学活用)講座を提供している大塚英文です。
私は毎年、テーマを決めて集中的に本を読む習慣を持っている。2025年は、量子力学と脳の記憶のメカニズムを中心に手に取って本を読んでいる(詳細は「私の読書の方法〜2024年〜」参照)。
量子力学の発展を調べていくと「創造的な組織」作りが、学問に大きな影響を与えていたことがわかった。前回は、ヨーロッパで、どのような組織づくりが行われたのか?コペンハーゲン精神とゼミナールをキーワードに紹介した。
今回は、日本での量子力学の発展において、コペンハーゲン精神を参考に「創造的な組織」作りが行われた理化学研究所について取り上げたい。宮田親平著の「「科学者の楽園」をつくった男 大河内正敏と理化学研究所」を参考に紹介したい。
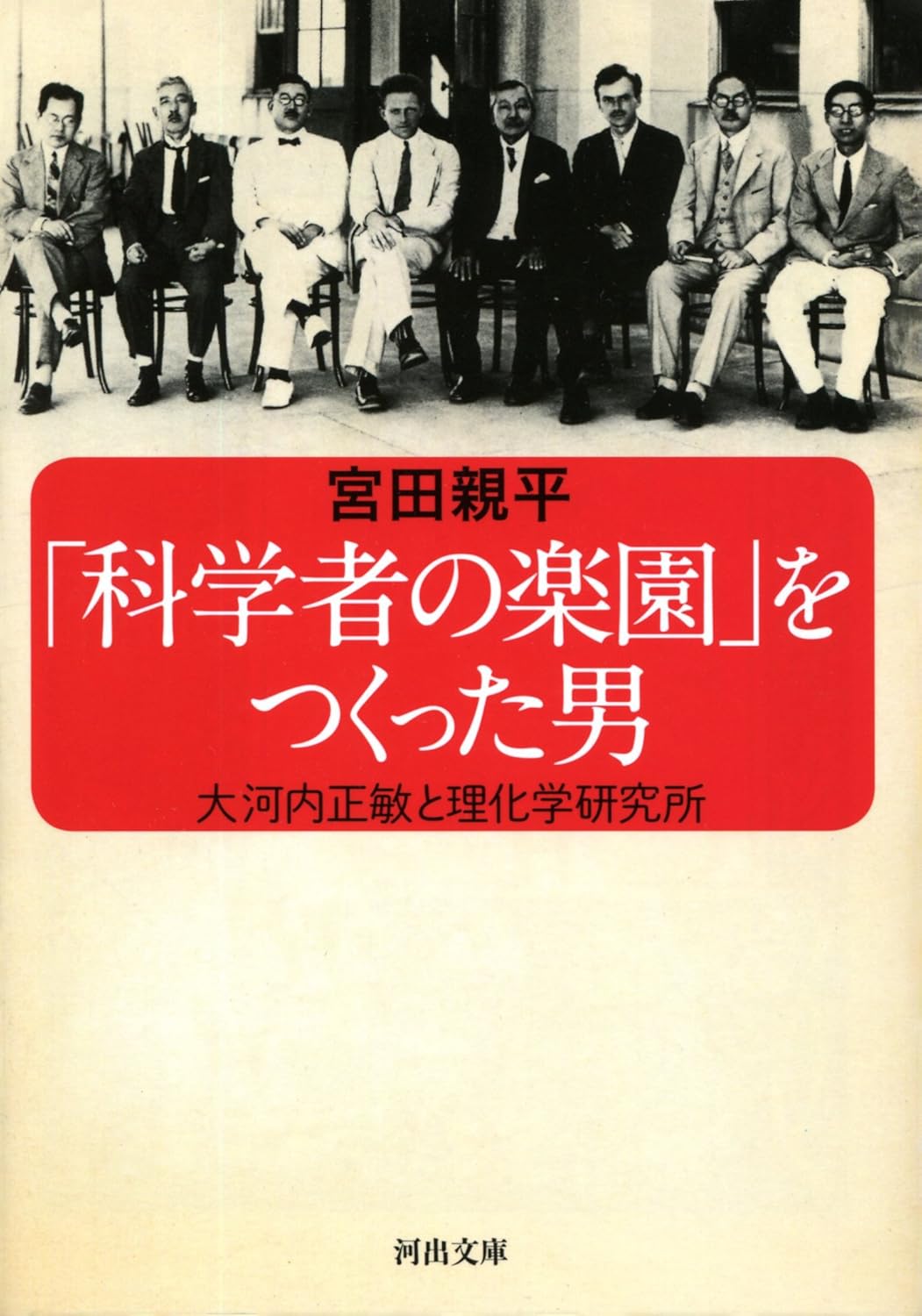
理化学研究所(理研、RIKEN)とは何か?
理化学研究所(理研)は、1917年3月20日に設立された。歴史は、1913年に高峰譲吉が国民科学研究所の必要性を提唱したことから始まる。高峰は、理化学工業の時代が到来すると予見し、日本も基礎科学の研究所を設立すべきだと訴えた。提案に賛同した渋沢栄一らが支援し、1917年に東京・文京区駒込に理研が設立された。
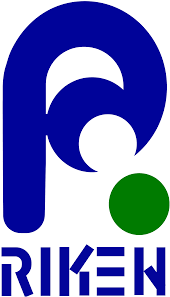
初代所長の菊池大麓が就任後5カ月で急逝。2代目所長の古市公威も健康上の理由で1921年9月に辞任。同年10月に大河内正敏が第3代所長に就任した。大河内によって理研が大きな変革を迎え、組織も大きくなった。例えば、研究所運営の方針として、学術研究と実際を結びつけ、産業の基礎を確立することを徹底させた。
その結果、
- 研究体制の改革:部制を廃止し、主任研究員制度を新設。主任研究員に研究テーマ、予算、人事の裁量権を与え、自由な研究環境を構築。
- 研究成果の実用化:研究成果を産業発展に役立てるため、理研産業団(理研コンツェルン)を形成。多数の特許や実用新案を企業化し、その収益を研究費に充てる仕組みを確立。
のような改革が行われた。理研は基礎科学の研究機関としてだけでなく、産業界とも密接に連携し、日本の科学技術と産業の発展に大きく貢献する。特徴的だったのは「科学の楽園」を作ることだった。
理研の特徴①〜「科学の楽園」の理念
大河内が目指したのは、科学者が自由に研究できる理想的な環境「科学の楽園」の創造だった。研究者が純粋な好奇心に基づいて研究できる環境を提供することが、画期的な発見につながると考えていた。そこで、研究者の自主性を尊重し、自由な発想が生まれる場を作ることに注力していく。
理研の特徴②〜創造性を引き出す仕組み
大河内は、理研を単なる研究機関ではなく、創造性を最大限に引き出す場とするため、以下のような仕組みを導入した。
- 研究の自由度の確保
研究テーマは、トップダウンではなく、研究者自身の興味や能力に応じて選ばれることを重視。独創的なアイデアが次々と生まれる土壌が作られた。 - 研究者への厚遇
優秀な研究者を集めるため、給与や研究費を十分に与え、海外の研究機関と比較しても遜色のない環境を提供した。 - 最新設備の導入
研究に必要な最新機器を積極的に導入し、研究者が最大限の能力を発揮できるようにした。 - 交流の促進
異分野の研究者同士が自然に交流できるような環境を整え、分野を超えたアイデアの融合を促した。
理研の特徴③〜研究成果の企業化と「理研コンツェルン」
大河内は、基礎研究の成果を社会に還元することの重要性を理解していた。理研で生まれた技術や知見を積極的に企業化し、実用化を進めていく。今でいう産学共同だ。
- 理研コンツェルンの形成
理化学研究所の研究成果を基に、多くの企業が設立され、「理研コンツェルン」と呼ばれる巨大な産業グループが形成された。理研コンツェルンは、化学、製薬、電子、機械など多岐にわたる分野で事業を展開し、日本の産業発展に大きく寄与していく。 - 成功した製品・技術
理研で開発された技術を基に、合成繊維、医薬品、電子機器など、さまざまな分野で画期的な製品が生み出されました。カメラメーカー「リコー(RICOH)」の起源が理研にあることは、その成功例の一つとして知られている
理研の特徴④〜理研の代表的研究者とその成果
大河内の方針のもと、理研では多くの優れた科学者が活躍し、世界的な成果を上げていく。
仁科芳雄(原子物理学とコペンハーゲン精神)
仁科は、日本における近代的な原子核物理学の基礎を築いた人物。彼は、理研でサイクロトロン(粒子加速器)を建設し、原子核の研究を推進。この研究は、日本における原子力科学の発展に大きく貢献した。
仁科は1920年代にデンマークのニールス・ボーア研究所に留学し「自由な議論とアイデアの共有」を重視し、上下関係に縛られず、科学者同士が対等な立場で意見を交換するという「コペンハーゲン精神」に触れる。
帰国後、コペンハーゲン精神を理研に持ち込み、若手研究者が自由に議論できる環境を作った。理研は新しい物理学の発展に貢献し、日本の理論物理学・素粒子物理学の礎を築くことになりました。
朝永振一郎(量子電磁力学)
理研に所属しながら量子力学の研究を進め、後に「くりこみ理論」を提唱。この理論は、ノーベル物理学賞(1965年)の対象となり、日本の物理学の発展に大きく貢献した。仁科の影響を受け、コペンハーゲン精神を実践しながら研究を進めたことも、彼の成功の要因の一つだったという。
鈴木梅太郎(ビタミンB1の発見)
鈴木は、脚気の予防に関係する成分としてビタミンB1(オリザニン)を発見。栄養学や食品科学の発展に大きな影響を与え、健康維持のための栄養学の確立に貢献する。
真島利行(合成染料の開発)
理研において合成化学の研究を推進し、日本における染料工業の発展に寄与。日本国内での染料製造技術が向上し、化学工業の発展に貢献する。
池田菊苗(うま味成分グルタミン酸の発見)
池田は、昆布のうま味成分がグルタミン酸であることを発見。「味の素」の基礎を築いた。この発見は、世界の食品産業に大きな影響を与えました。
長岡半太郎(原子模型の提唱)
長岡は、日本における近代物理学の先駆者であり、原子構造についての研究を進め、土星型原子模型」は、後の原子構造研究の発展に影響を与えたという。
まとめ
大河内が作り上げた理研は、「科学の楽園」としての理念のもと、研究者が自由に創造的な研究を行える環境を提供した。特に仁科は、「コペンハーゲン精神」を理研に持ち込み、自由な議論と知的交流を重視する研究文化を根付かせた。
結果、仁科の原子核物理学、朝永振一郎の量子電磁力学、鈴木梅太郎のビタミンB1発見、真島利行の合成染料開発、池田菊苗のグルタミン酸発見、長岡半太郎の原子模型提唱といった、多くの画期的な成果が生まれていく。これらの研究成果の一部は理研コンツェルンを通じて企業化され、日本の産業界に大きな影響を与えることになる。
理研のビジネスモデルは、科学と産業の融合による新たな価値創造の成功例として、創造的な組織を作り上げる上で参考になるかと思い、今回取り上げさせていただいた。
少しでも、この投稿が役立つことを願っています。






