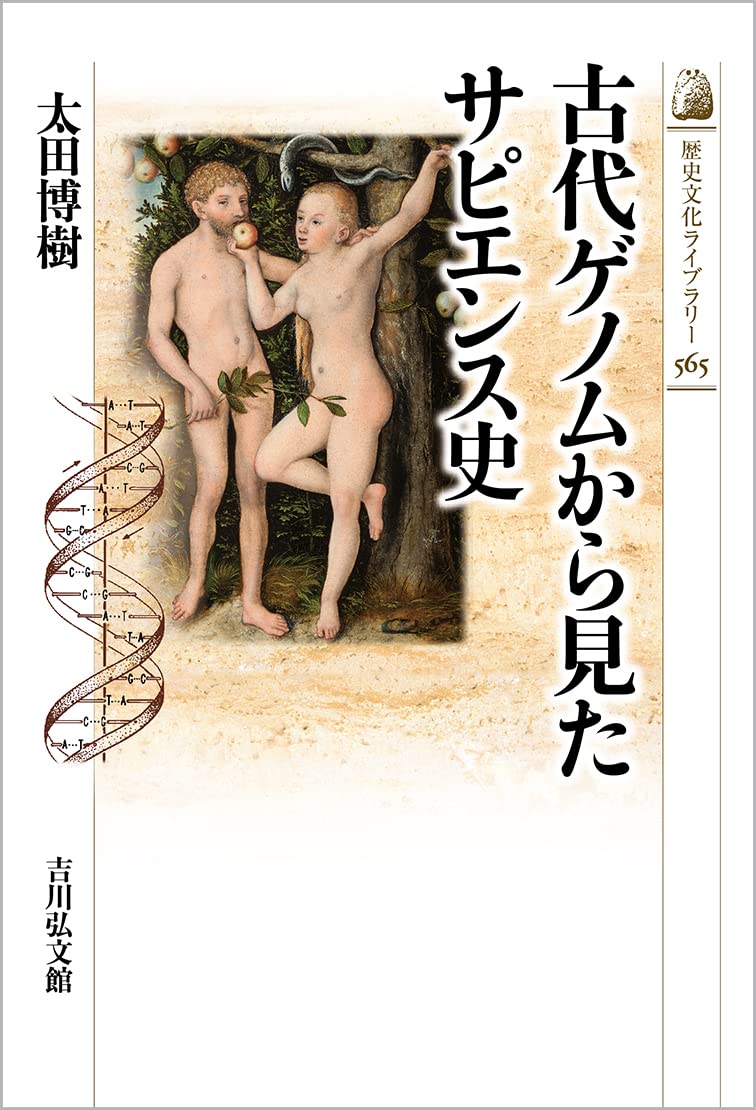【J#28】茶室の世界に触れて〜「はじめての茶室論」に参加して
世界茶会の岡田和弘さんと偶然Facebookのやり取りをしていたときに、たまたま一席「はじめての茶室論」が空いていると伺い、申し込むことができた。2013年6月2日(土)に行われたこのイベント。普段、裏千家のアバンギャルド茶会、近藤俊太郎さんから茶道を学んでいるが、本格的に茶室自体を学ぶのは初。東海大学の小沢朝江先生がどのように講義をするのか?期待しつつ参加してきた。
講義は、茶室の歴史から始まり、茶の湯の思想、空間要素、光と窓、素材と手法、そして茶室の個性を出すにはどういった工夫をこらしているか?という観点から説明し、あっという間に90分が過ぎ去ってしまった。
特に興味を持ったのが、茶室の空間に対する茶人の想い。茶室というのは、一期一会、関係性を重視、亭主とお客がお互いに敬うこと。そのためにどういった空間を設計すればいいのか?という点から空間が考えられている点。そこから、素の自分になれるような空間が必要であり、都市から離れたような雰囲気の演出が施されるようになる。例えば、下地窓やなぐり柱などわざと仕掛けることで都市の中にいても山里にいるような感覚を味わせるのである。

人間というのは、想像以上に周囲の環境や他人や自分の発する言葉から影響を受ける。場合によっては自分を見失ってしまう可能性がある。そこから離れ、リセットする時間を持つことの大切さを、恐らく戦国時代の武将は知っていて、茶室や茶道が盛んになったのだと感じる。

私自身、日常生活から一歩離れる時間を毎日早朝、ヨガを練習することでもつようにしている。ヨガは呼吸に意識を向け身体を動かすことで内面に(いわば内面の空間)に目を向ける。空間という意味では、雑踏とした外部から山里にいるような内部にいるような感覚の茶室と似ているかもしれない。
空間から考えるとこのようにヨガと茶室の考えは共通点があるということに気づかされる。素になる時間の大切さは、私自身もこれから大切にして行きたいと思う。